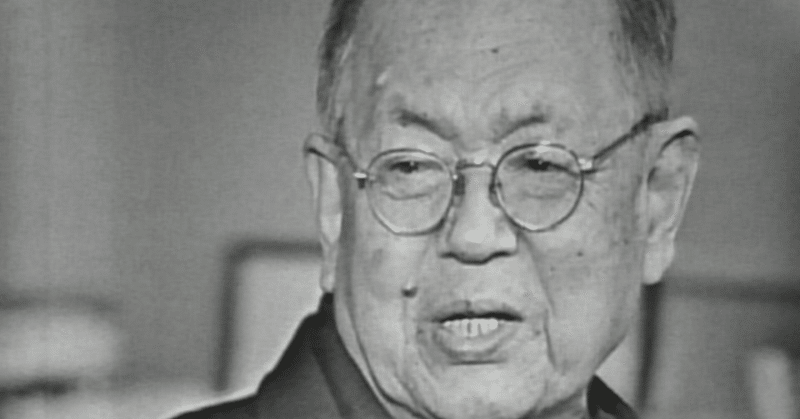
武者小路実篤、あるいはAnarchy in JP(1)(2004)
武者小路実篤、あるいはAnarchy in JP
Saven Satow
Aug. 31, 2004
さあ、俺も立ち上るかな
まあ、もう少し坐っていよう
武者小路実篤『さあ俺も』
第1章 武者小路と言文一致
「個人的なトラウマとその克服の物語が政治を動かしてしまうのが9・11後の世界である」最近の小説について、島田雅彦は、舞城王太郎やモブ・ノリオ、柳美里の最新作を例に、二〇〇四年八月二六日付『朝日新聞夕刊』の「『9・11後』とは」において、次のように述べている。
毎月の文芸誌を読んでいると、二十代、三十代の書き手の多くに共通のスタイルがあることに気付く。それはオノマトペとリフレインを多用した畳み掛けるようなリズムであり、メールの文面のように思い付きをそのまま言葉にした心内語中心の遠近法を欠いた描写なのである。
近代に入って以来、日本文学の小説家は、時代に応じて、新たな言文一致体を捜し求め続けている。「二十代、三十代の書き手の多くに共通のスタイル」も同様の動きである。けれども、この文体の特徴は決して新奇なものではない。それは私小説に典型的に見られる。彼らは、言葉遣いを別にすれば、近代文学の伝統をリフレインしているにすぎない。
最初にこうした文体を用いたのは、いわゆる私小説家ではない。武者小路実篤である。彼の文体が私小説の基準となり、定石になっている。「死んだものは生きている者にも大なる力を持ちうるものだ。生きているものは死んだ者に対してあまりに無力なのを残念に思う」(武者小路実篤)。
武者小路は、『お目出たき人』(一九一一)における次のような文体によって、文壇から一躍注目される。
自分はまだ、いわゆる女を知らない。
夢の中で女の裸を見ることがある。しかしその女は純粋の女ではなく中性である。
自分は今年二十六歳である。
自分は女に飢えている。
この『お目出度き人』や翌年に発表された『世間知らず』を宇野浩二と平野謙は私小説の淵源と指摘している。自然主義文学により非常に重苦しい閉塞状況に陥っていた文学界に、武者小路が登場し、個性の伸張と自己の肯定を主張する。”Maybe I'm a prehistoric monster by being an individual. It's highly likely. All I offer to others is their own individuality. Grab it!”(Johnny Rotten)
露悪主義に偏っていた文学に、「自分」を主語とした平易で、ペーソス溢れる彼の文体は衝撃を与える。それを芥川龍之介は「文壇の天窓を開け放って、爽やかな空気を入れた」と述懐している。作品中、「自分は女に飢えている」を何度も繰り返し、思いつきを単純明快に短いセンテンスで言語化している。自己を意欲的に肯定しつつも、ペーソスによってそれが鼻につかない。「哀歓《ペーソス》は扇情的《センチメンタル》な催涙反応と関係が深い。その主人公はある弱点のために孤立しているものとして現わされるが、この弱点は、われわれ自身の経験と同じ水準にあるため、われわれの同情心に訴えるのである」(ノースロップ・フライ『批評の解剖』)。
二葉亭四迷の『浮雲』に始まり島崎藤村の『破戒』に至り、一九世紀的な言文一致体が形成される。武者小路はそこから二〇世紀的な言文一致体を生み出している。前者が国民文学の文体であるとすれば、後者はポップ文学と呼ぶことができよう。武者小路は、雅号を用いずに作品を発表した最初の世代であり、ポップ文学者の先駆けである。
小説家は、日露戦争まで、軽蔑される職業である。長谷川辰之助が文学を志したいと打ち明けた際に、父親から「何をたわけたことを。くたばってしめえ」と罵られて、「二葉亭四迷」が誕生している。そんな彼も「文学は男子一生の事業にあらず」と公言し、小説家と見られることを嫌っている。
武者小路はそんな偏見や反対に直面していない。武者小路実世子爵の第八子は皇族・華族の子弟向けの教育機関である学習院に進み、文学に傾倒する。一九〇七年四月、東京帝国大学文科社会科を中退後、志賀直哉らと十四日会を組織し、一九〇八年四月には、著作集『荒野』を刊行して、文学に専念している。友人たちから「武者」と呼ばれた彼には陽のあたる場所を歩き続けた毛並みのよさに加えて、文学に対する屈折した思いがない。
武者小路の文学はしばしば中学生の作文と揶揄される。文体は単純明快であり、華麗な修飾語を散りばめた凝った文体でもない。けれども、スムーズで、明るさが大正期の人々にとって「モダン」を感じさせている。それは到来しつつある大衆社会にふさわしい。
武者小路が何を書こうが読者にとってそれはたいしたことではない。エドワード・G・サイデンステッカーは、『現代日本作家論』において、「かりに戦時中の発言のいくつかは、思想家としての冷静さを疑わしめるとしても、氏は明らかに個人としては立派な人である。問題はただ、藤村、武者小路の場合とも人生と芸術との混同が、小説と小説家との区別を困難にし、そこで小説をあるがままに眺めることが難しいといいたいのである。他の長所はともあれ、武者小路氏が小説家だとは私には思われない」と指摘している。これは完全に正しい。
武者小路の小説の主題は、切り口によっては、スリリングになりうる。しかし、彼は見事にそうしない。『若き日の思い出』や『棘まで美し』では、三角関係を主題にしながら、まるで精神性が弱い。夏目漱石の小説とは大違いだ。また、五幕の戯曲『その妹』では、戦争で盲目となった画家とその妹の葛藤に苦しむ姿を描いている。一九一五年のこの作品などフランク・ボーゼージ監督の名作『第七天国』(一九二七)を思い起こさせる。けれども、残念ながら、比較することさえ躊躇してしまう。劇団民芸などで上演され、さらに、原研吉監督により、一九五三年、『その妹』は佐田啓二主演で映画化されている。愛読者には、大切なのは文体であって、作品ではない。どんな主題であっても、彼自身の文体が彩りを加えており、それが魅力だからだ。
エッジが効いていないので、先鋭的な読者には物足りなさを覚えるだろう。その代わり、武者小路の小説は定型的でわかりやすく、誰でも安心して楽しめる。森鴎外や夏目漱石の高い教養に裏打ちされた文体と違い、すぐにでも書けそうに見える。それが武者小路文学の意義である。文学が文化だとすれば、読者層の幅の広さが不可欠である。文学は新奇さという先鋭さによって高度な読者を獲得する反面、底辺が縮小してしまう。武者小路が見ていたのは、文学にとって草の根の読者である。彼の文学は文学教育である。インタラクティヴな文学として、その文体から私小説が生まれ得たのである。行き詰ると、意識してようといまいと、日本文学は武者小路的な文体に回帰するようになる。
武者小路の代表作の『友情』と『愛と死』という恋愛小説は片山恭一の『世界の中心で、愛をさけぶ』と違いがないかのように見える。実際、『愛と死』は、石原裕次郎主演で、滝沢英輔監督によって『世界に賭ける恋』として一九五九年に映画化されている。しかし、片山に溢れる自己憐憫が武者小路にはない。基調はペーソスである。「自分は淋しさをやっとたえて来た。今後なお耐えなければならないのか、全く一人で。神よ助け給え」(『友情』)。 また、『愛と死』は、栗原小巻主演で、中村登監督により、一九七一年、原作通りのタイトルで再度映画化されている。『金色夜叉』(一九四八)のスクリプターを担当して映画と縁ができて以来、『その妹』と『愛と死』の他、『幸福な家族』が一九五九年に、『暁』が『いのちの朝』として一九六一年にそれぞれ映画化されている。
亀井勝一郎は武者小路の作品群を五期に分類している。しかし、ほとんどがペーソスの文学である。『幸福な家族』のような会話体の小説があったとしても、『お目出たき人』の類型である。主人公は恋が成就することもあれば、失恋することもある。けれども、たいてい、『若大将』シリーズの田沼雄一のごとく、裕福で、金銭や社会的地位に対する執着はない。理想家であり、友情に厚く、ちょっとぬけたところがある。このいささか間抜けさが武者小路において不可欠な要素である。彼はジュール・ルナールに近い。一九一九年に刊行した『幸福者』では、清廉で欲がなく、贅沢をせず、一文も持たず、集まってきた弟子たちに食を与えられながら、教えを説いている人物を描いている。また、一九四九年から連載を始めた『真理先生』で、画家志望なのに、石ばかり描きたがる馬鹿一を登場させ、とうとう『馬鹿一』という独立した小説まで書いている。
ぼくたちは、馬鹿一を訪れるときは、よく道ばたで雑草を折り取って持ってゆくのだ。馬鹿一は郊外に住んでいるから、馬鹿一の近くにはいくらでも草がある。その草を一本でたらめに取って、おみやげに持っていってやるのだ。
そして、
「どうだ、この美しさは。あんまり美しいので、きみが喜ぶと思って取ってきたのだ。」
と言うと、馬鹿一はすっかり喜んで、
「そうか、それはどうもありがとう。ほんとうにこれはすばらしい。さっそく写生しよう。どうもありがとう。ぼくは、今までにこの草を何度も見たが、まだこの草の美しさをじゅうぶん知ることができなかった。きみのおかげで、この草の美しさを知ることができるのは、ありがたい。」
そう言って、喜んで花びんにその草をさすのだ。そして、いろいろの角度から見て、
「なかなかこの美を見つけるのはむずかしい。よくきみに見つかったね。」なぞと言う。それが、すこしもひにくでなしに、大まじめなのだから驚く。そして、どうかすると、その雑草が美しく見えてくることがあるのはふしぎだ。
ときどき、ぼくたちは、馬鹿一は日本一のしあわせ者かもしれないと思うのだ。なにしろ悪意がないのだ。万事善意にとって、いつもうれしそうにしているのだ。
そして、いくら他人から悪口言われたって、にこにこしていて、
「きみたちにはわかるまい。きみたちでも十年勉強したら、ぼくのものがわかるようになるが、その暇がないから、わからないのだ。」なぞと、本気にそう思っているのだから、手がつけられない。
(『馬鹿一』)
武者小路の文体が日本文学の定型になったのはペーソスの文学を描いたからである。ペーソスは近代日本の最も主流の笑いである。ユーモアでもアイロニーでもウィットでもない。マンガには、新聞の四コママンガや田川水泡の『のらくろ』、藤子・F・不二雄の『ドラえもん』を含め、ペーソス・マンガの伝統があるだけでなく、それこそが日本マンガのプロトタイプである。代表的なペーソスのマンガ家として森田拳次と板井れんたろうがあげられる。ジョージ秋山は森田拳次、吾妻ひでおは板井れんたろうのアシスタントであり、彼らはその安定した基本をわずかに弄ることでラディカルな独自性を発揮している。
「哀感《ペーソス》の根本概念は、われわれと同等の人間を、彼が加わろうと努めている社会集団から排除する、ということである。洗練された哀感の文学の伝統の中心は、こうして孤立した精神の研究であり、一見してわれわれ自身と違うところのない人間が、内部の世界と外部の世界との対立、想像上の現実と社会の共同意志によって作られる現実との対立によって打ちくだかれる物語である」(フライ『批評の解剖』)。ペーソスの作品の主人公は家族や友人、恋人、世間から見直されるために、奮闘努力する。けれども、そこで逆にドジをふみ、ズッコケてしまう。彼──女性や人間以外の存在のこともある──にはかすかな笑いと共に哀愁が漂うが、それは「彼が加わろうと努めている社会集団から排除」されているからである。その姿は日本社会におけるわれわれ自身である。武者小路はこうしたペーソスを文学にしたため、原型となり得ている。「我らは過去の人間から受けとつたものに我らの精神と労働とを加味して未来の人間に渡すものである」(『我等は』)。
武者小路の最大の功績にはこの大衆社会的な言文一致の創始の他に、もう一つある。それは「新しき村」の創設である。そこにも、文体同様、ペーソスの哲学がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
