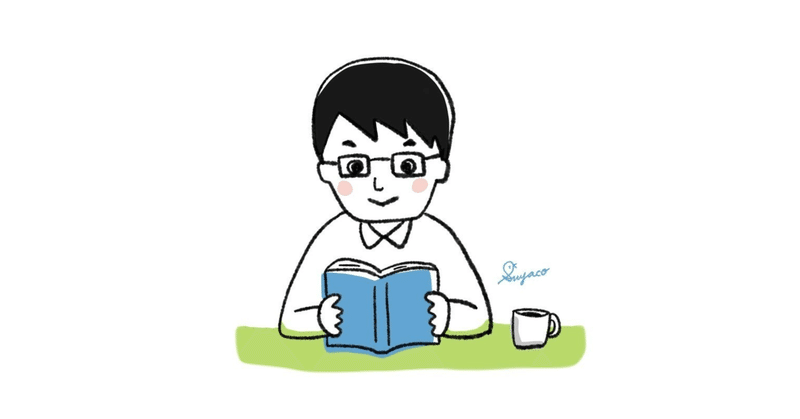
「ウイリアム・グラッサー 選択理論への歩み」-選択理論学習者には最重要な伝記本
選択理論がよくわかる本の紹介#8
「グラッサー博士の選択理論」を超える? 選択理論の全体像がわかる重要な本
選択理論とリアリティセラピーを学ぶ人にとって、この本は、4回、5回と、精読すべき、もっとも重要な本だと思います。他の本も同じでしょうが、この本は、特に、読むたびに新しい発見があるでしょう。ぜひ、細かいところまで、精読してください。
私にとっては、選択理論を客観視でき、「神は細部に宿る」ことを感じさせてくれる本でした。
著者のジム・ロイは、グラッサーとの5年間にわたるインタビューと、資料の渉猟を経て、この労作を書き上げました。この本の目的は、「グラッサーの理論の発端と進化を彼の私生活を通して注意深く研究する」ことです。
この本の最大の魅力は、ウィリアム・グラッサーの生い立ちから、リアリティセラピーという新しいカウンセリングを開発し、その基礎理論としての選択理論を開発し、精神医療だけでなく、矯正教育、学校教育、ビジネス分野、地域社会、公衆衛生(メンタルヘルス)へと適用分野を拡大し、展開していった、グラッサーの思想の発展と変遷、その経緯と内容、これらの全体像を、この1冊で、通して学ぶことができる、ということです。
①「選択理論とは何か」「リアリティセラピーとは何か」が、客観的なものとして、見えてくる
グラッサーの本は、私も、邦訳された本を中心にしか読めていませんが、1冊1冊が詳しく、細かく書かれすぎていて、「要するに、何が、なぜ言いたいのか、どういうことを言おうとしているのか」が飲みこめないところが出てきます。
冗長な書き方のところも多く、特に初期の本は、精読するモチベーションが続きません。「今日は、この辺でやめておこう」という選択をしてばかりです。
この本を読むまでは、肝心かなめの「選択理論とは何か」「リアリティセラピーとは何か」ということも、なにかぼんやりとした部分が残っていました。今でも、ぼんやりとした部分は残っていますが、相当、解消されたと思います。
② 大きな「ジグソーパズル」のコマが、次々と当てはまって「絵」が見えてくる
グラッサーの考え方や開発したものは、時代時代で、4期くらいに分かれて、変遷してきているのですが、なぜ、変遷したのか、変遷した内容がどういうことを意味しているのかなど、背景にあることが、グラッサーの書いたものだけを読んでいても、セミナーなどで話を聞いても、よく理解できません。
グラッサーの思想の全体を「ジグソーパズル」の大きな絵に例えると、この伝記本以前には、パズルの大きなコマが、ところどころ欠けているとか、そもそもパズルのコマがどんな形をしているのかが、よくわからず、「ジグソーパズル」の絵自体がぼんやりとしていました。
そして、これらの点に関して、この伝記本は、14章から成っていますが、それぞれの章が非常に要領よく、わかりやすくまとめられており、各章が大きなパズルのコマのようです。
③ グラッサーの生涯を、時系列的に、一気通貫で読める
読み物としても非常に面白く、あっという間に読めてしまいます。グラッサーの生涯を、時系列的に、一気通貫で読めます。
グラッサーの書いた重要な書籍についても、書かれた順に、また、必要に応じて繰り返して紹介されており、その内容の要約(要するに○○が書かれている)と、その本の意味や意義、位置づけ((その本がグラッサーの生涯の仕事の中で、どのような意味を持っているのか)が、わかりやすく理解できます。
すぐれた、リーダーズダイジェストの機能を持っているといえるでしょう。
④ 「パワーズのコントロール理論」の説明から、「外的コントロールとはどういう概念なのか」がわかった
マニアックな点になるかもしれませんが、私にとって、もっとも印象的だったことを挙げると、グラッサーの選択理論の開発のきっかけとなった「ウィリアム・パワーズのコントロール理論」について、第8章と第9章でくわしく取り上げられており、
・「ウィリアム・パワーズのコントロール理論」とは何だったのか
・「ウィリアム・パワーズのコントロール理論」における外的コントロールの概念
・「ウィリアム・パワーズのコントロール理論」と「グラッサーのコントロール理論(後の選択理論)」の力点の違い(パワーズが「人の行動を外側からコントロールするのは不可能であること」を証明したかった。一方、グラッサーは、人の行動がどのように内的に引き起こされるかという「行動の内的コントロールの理論」をつくって、それをリアリティセラピーの基礎理論にしたかった)
、がよくわかりました。
第8章と第9章を、何度も精読したことで、「内的コントロール心理学としての選択理論」、「外的コントロールとは本来どういう概念なのか」ということが理解できたように思えます。
⑤「選択理論」について、アハ体験が、何度もありました
この伝記本を丁寧に読んでいくと、上記のことも含めて、本の中の、細かな、ほんの1つのフレーズがヒントになって、「今までの学びの中で、もやが、かかっていたのが、晴れた」という体験(アハ体験)が、いくつもありました。
おおげさかもしれませんが、「神は細部に宿る」というのがこれかな、と思われるような体験です。
⑥「選択理論」「リアリティセラピー」、そして「グラッサー」に振り回されるな!
今回の記事のしめくくりに、
この本の「はじめに」の中で、グラッサーの言葉として、
・「わたしは昔のことを思い出して懐かしがったりするタイプではない」
・「今やっていることに強い関心がある。過ぎたことは本当にどうでもよい」
・「今いるところが大切で、どのようにしてそこに到達したかということは問題ではない」
また、第14章の最初に、
「私の頭の中では、選択理論は決して完成することはない」
という言葉が紹介されています。
グラッサーは、2013年になくなりましたが、もし、生きていれば、今頃は、さらに変化した選択理論を主張していた可能性もあります。
私は、選択理論を学んで、実践することを、趣味として、ライフワークのように楽しんでいますが、この伝記本を読みながら、次のような思いを抱くことがあります。
・「選択理論」は自分にとって、どのような意味があるのか?
・自分の「選択理論の理解」を自己評価し、より上質な理解に向けて、改善を続けよう。
・また、そのようにする意味があるのかについても、自己評価しよう。
・ただし、決して、「選択理論」「リアリティセラピー」、そして、「グラッサー」に振り回されるな!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
