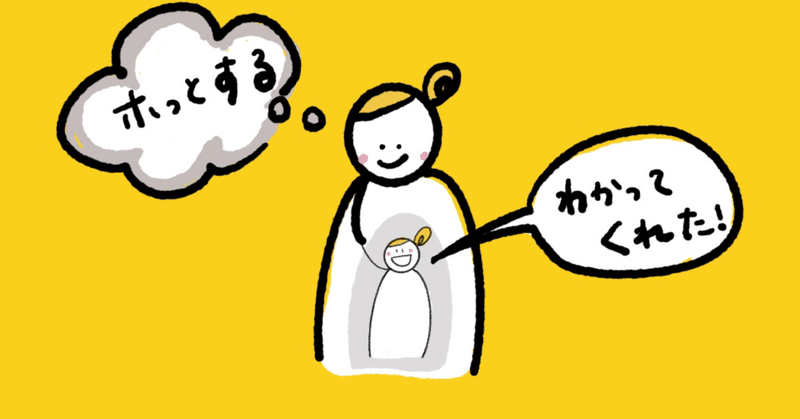
「リアリティ・セラピーの理論と実践 」-選択理論にもとづく本人のセルフコントロールを、カウンセラーが手助けする本
選択理論がわかる本の紹介#5
「リアリティセラピーの理論と実践」の秘密?
この本の原題は「Using Reality Therapy」で、「リアリティセラピーを使う」とか「リアリティセラピーの実践」という意味だと思います。
グラッサーが開発した心理カウンセリングであるリアリティセラピーについて、その実践やセミナー、トレーニングの第一人者であるロバート・ウォボルディングが書いた本で、ちょっと古い(1988年)ですが、リアリティセラピーの考え方や方法、注意点や事例など、くわしく、細かく、まとめられており、非常に参考になる本です。
ロールプレイなどを通してリアリティセラピーを勉強した人が、確認や整理、レベルアップに読むのに適しているでしょう。
ところで、「リアリティセラピー(現実療法)」は、名前からして、セラピー(癒やし)の方法とか、心理療法を思わせます。
また、この本は、「カウンセラーによる、リアリティセラピーのカウンセリングの考え方と方法」が内容の大半を占めています。
しかし、私(筆者)は、この本が、「技術の本」「セラピーの本」である以上に、もっと重要であると思っています。
実は、この本の最初の書名は「セルフコントロール」という書名でした。
そして、私は、この「セルフ・コントロール」という旧書名が、リアリティセラピーの本質というか、リアリティセラピーが「セラピー以上のもの」であることをよく表していると思います。
① 本人のセルフコントロールを手助けする方法が「リアリティセラピー」
この本の原書には、付表として「Summary Description of Reality Therapy」が付けられています。そこには「リアリティセラピーの定義」が書かれているのですが(邦訳の冒頭にも掲載されています)、私なりにわかりやすく翻訳してみますと、次のようになります。
「リアリティセラピーとは」
-リアリティセラピーの定義を求める人のために-
リアリティセラピーは、みなさんが自分で自分の人生をよりよくセルフコントロール(内的コントロール)できるように、手助けするための方法である。
リアリティセラピーは、みなさんが自分の願望と基本的欲求がなんであるかを明確にし、自分が満たしたいという願望が、現実的に達成できるかどうかを、自己評価する手助けをするものである。
リアリティセラピーは、みなさんが自分の行動を検証し、明確な判断基準(criteria)に照らして、自己評価する手助けをする。
そして、続いて、みなさんは、自分自身の人生をセルフコントロールして、実現可能性のある願望と基本的欲求を満たすことができるような前向きな計画を立てる。
その結果、みなさんは、自分の精神力が高まり、より自信に満ち、よりよい人間関係と、より効果的な自分の人生計画を得ることができよう。
このように、リアリティセラピーは、みなさんに、日々において、問題(逆境)に対処し、自分らしく成長し、自分の人生をより効果的にセルフコントロールすることができるセルフヘルプ(自助:自分で自分を助けること)のツールを提供する。
リアリティセラピーは、いくつかの原則に基づいている。
①みなさんには、自分の(選択した)行動に責任がある。(自分の行動は)社会や、遺伝や、過去の出来事のせいではない。
②みなさんは、変わることができ(自由に行動を選択することができ)、より効果的な人生を生きることができる。
③みなさんは、(願望と基本的欲求を満たすという)目的のために行動している。つまり、彫刻家が粘土で彫像を形作るように、みなさんは、自分の環境を、自分の内側にある手に入れたいイメージ写真にマッチさせるべく、行動している。
そして、自分がほしい結果は、継続的な努力と、ハードワークによって、達成可能なものとなる。
※( )内は筆者が追加
上の定義を読むと、「リアリティセラピーとは、本人が、自分の行動や、ひいては、自分の人生をセルフコントロールする方法」であり、同時に、「本人がセルフコントロールするのを他者(カウンセラーなど)が手助けする方法」であることがわかります。
② 「リアリティセラピー≒コーチング」といえるのでは?
上の文章の、
セルフコントロールをセルフコーチングに置換え、
リアリティセラピーをコーチングに置換え、
カウンセラーをコーチに置換えて読めば、
リアリティセラピーは、どちらかというと、「選択理論のカウンセリング」というより、「選択理論のコーチング」と言った方がいいのではないかとも、私には思えます。
③ さらに、「リアリティセラピー≒セルフコーチング」でもある?
そして、この本の「12.「質問」の意義とQ&A」の質問(5)には、次のような文章があります。
「(リアリティセラピーは)プロの援助者が、他者の効果的な援助をする前に、まず自分のセルフヘルプのために使うべき「生き方(人生)の方法」である。
もし、援助者自身が欲求を満たされていなければ、また、もし、援助者自身に欲求を満たすための知識とスキルがほとんどなければ、そのような援助者が他者を助けられる望みはほとんどないであろう」
(筆者が原文から翻訳)
④「うん? セルフ・リアリティセラピー?」
このように、リアリティセラピーは、援助者本人の「セルフヘルプ(セルフコントロール)の方法」「生き方の方法」として、まず活用されるべきであり、それによって、リアリティセラピーの知識と方法が身について、効果を上げられてはじめて、「他者のセルフヘルプ(セルフコントロール)の手助け」ができる、と考えられています。
ということは、援助者(カウンセラー)に限らず、リアリティセラピーは、誰が学んでも、セルフヘルプのツールとして、自分の願望や欲求を満たし、自分らしい生き方ができるということでもあります。
また、誰でも、自分の生活、日常のコミュニケーションにおいて、リアリティセラピーを使うことができれば、身の回りの人間関係をよくし、相手の願望実現や欲求充足の手助けもできるようになる、ということになります。
このような意味でのリアリティセラピーは、「セルフ・リアリティセラピー」と呼んだ方がいいのかもしれません。
⑤「選択理論を実践するためのトーク」としてのリアリティセラピー
ところで、選択理論とリアリティセラピーの関係については、「選択理論は線路」であり、リアリティセラピーは、「線路の上を走る電車」であるといわれます。
内的コントロール心理学としての選択理論の基本原理は、
「人は自分の行動を内的コントロールしている。そして、人がコントロールできるのは、自分の行動だけである」
でした。
また、選択理論は、「人間関係が良好であること」「満足できる人間関係が持てていること」を、私たちが幸せになるための絶対条件と考えています。
そして、それを実現するために、「相手(のシステム)を外側からコントロールすることはできない(相手を変えることはできない)」という考え方を徹底します。
これは、カウンセリングでいうと、「カウンセラーはクライアントを変えることはできない」となりますし、「カウンセラーはクライアントを外的コントロールしてはならない」ということになります。
このように考えてくると、リアリティセラピーは、カウンセラーがクライアントを外的コントロールせずに、クライアントのセルフコントロール(内的コントロール)を手助けするというカウンセリングの方法ということになります。
そして、カウンセラーだけでなく、誰でも、リアリティセラピーの方法を、自分の日常的な人間関係で活用できれば、「相手を外的コントロールせず、相手の内的コントロールを手助けする」ということ、つまりは、他者に対しても、選択理論が実践できること、になります。
このように、リアリティセラピーは、私たちが、それによって選択理論を実践することができ、お互いに幸せになっていけるための「日常的なコミュニケーションの方法」であるといえるでしょう。
筆者は、「リアリティセラピー」の呼び方を、選択理論を自分が実践するためのセルフトーク(自己対話)と、他者が選択理論を実践する手助けのための対人トークの両方をまとめて、「選択理論実践トーク」と呼んだ方がわかりやすいのではないかと思います。
「リアリティセラピー」は、その語感以上に、広くて大きな意義を持っていると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
