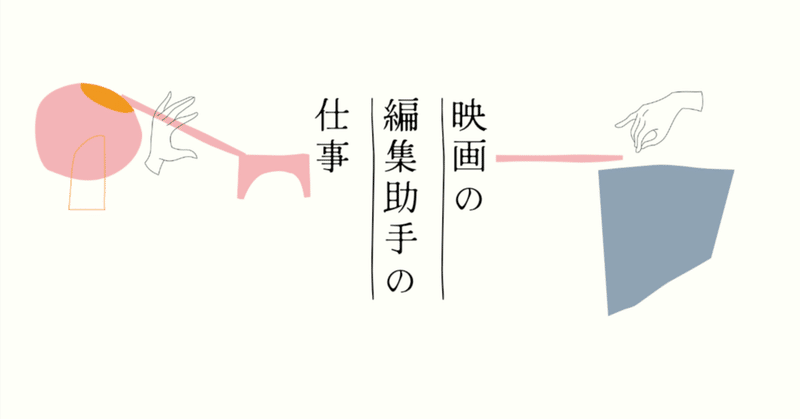
27.フィルムとデジタル
2004 年、私がフリーランスで編集助手を始めた年は、映画はフィルムで撮影していて、フィルムからテープにダビング(テレシネ)したものをパソコンに取り込んで編集していました。
編集が固まったら、パソコンから編集データを出し、元のフィルムを切り張りし、音の仕上げに進みました。
当時はまだ、映画館はほとんどがフィルム上映でした。

入ってすぐ、先輩がざっくり書いてくれたものです。ここに書かれているように、フィルムとデジタルが混在していた時期でした。
助手は、フィルムの技術を覚え、デジタルの技術を覚え、10年経ったらエディターになる、というのがその頃の常識でした。
それから20年経ち、「映画のエディターになるには、10 年下積みで編集助手を経験しなければならない」という時代ではなくなったように思います。
CM やテレビドラマの監督が映画を撮る時、いつも一緒にやっている編集マンを連れてきたり、監督自身が編集することが増えたからです。
もちろん、その人たちには映画の編集助手時代などありません。その場合でも、編集マンの下には映画をやってきた編集助手が付くことがほとんどです。
なぜなら、映画の編集部として育ってきた人でなければ分からないことが多い仕事だからです。
デジタル化が進み、なんとなく編集ができる時代になりました。一般の人でも「編集」はできます。
だから編集助手も、なんとなくできるようになったのかもしれません。
でも、私はなんとなくできればいいものではないと思っています。
編集は経験と知識の積み重ねです。
若いときにしかできない編集もありますが、本当にいい編集は、ちゃんとしたルールと経験に基づき、監督やスタッフの人たちと一緒に作っていくも
のだと思います。
そのやり取りを見るために助手を10 年やるのだと、技師になった今、実感しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
