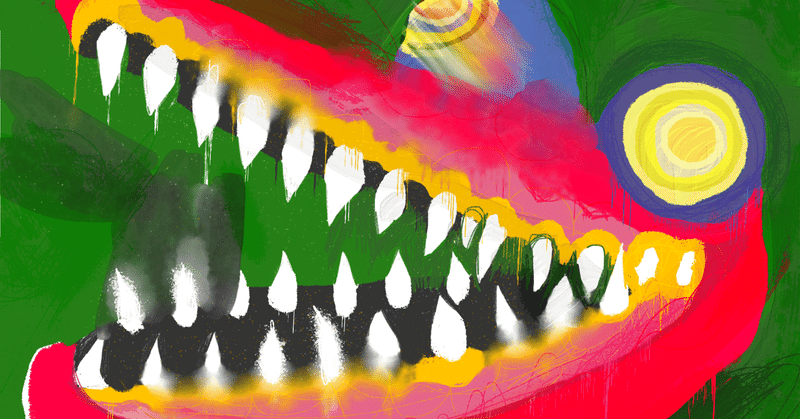
100ワニで選別される道徳的な人とそうでない人
白状するなら、私はこの漫画が苦手だった。いや憎んですらいたかもしれない。その理由が後ろ暗くて、誰かと共有したくて、初めてnoteを書いている―
最近、SNSは『100日間生きたワニ』という映画の話題で盛況だ。ただ、それは"炎上"とか"祭り"の類で、レビューが荒れたり、座席予約で遊ぶ人が現れたりと、完全におもちゃにされている。
こうした、匿名性を隠れ蓑にして石を投げる行為は卑劣だと思うし、製作者に関わった人々を可哀想だとも思う。
……思うのだが、私もまさに匿名性を隠れ蓑に正直に告白するなら、この騒ぎを見てほくそ笑んでいる自分に、やはり気付かされるのだ。いや、本当の私は、そもそも前段で書いたような規範的なことなど、真実感じられていないのかもしれない。
やはり、というのは一年ほど前、twitterに投稿されていた原作漫画の『100日後に死ぬワニ』が完結し、炎上したときにも、私は心のどこかでほくそ笑んでいた。
断っておくと、私には100ワニという作品を貶す意図など毛頭ない。むしろSNSという媒体をフルに活用した、ユニークな作品なんだろうと思う。
それに、開始当初は、むしろこの漫画の更新を日々楽しみにしていた。自分は、多くの人と同じように、この先にどんな展開が待ち受けているのか、ワニの身をハラハラと案じる読者の一人だと思っていた。
だが程なくして、自分の中の妙な感情に気が付いた。毎日この漫画を読み終える度、妙な苛立ちを感じるようになっていた。正確には、漫画と、そこに寄せられる多くのリプライに、だった。虫唾が走るような気分でさえあった。
何故かは、自分にも分からなかった。最初は成功した作者への妬みかと思った。けれど、他の話題のtwitter漫画には抱いたことのない感情だった。起伏のない展開に苛立ったのだろうか。けれど、私が居心地の悪さを感じるのは、リプライを眺めているときだった。
自分が薄暗い感情を抱くリプライの傾向を探ったところ、ワニを心配する無邪気なものばかりだった。単に浅はかな感想に嫌悪を感じるのかとも思ったが、全く違った。
そういったリプライを眺めているとき、私は苦虫を潰したような思いを感じていた。例えるなら、小学校の時に先生から誉められるクラスメイトを、したくもない拍手をしながら遠巻きに祝っていたときのような劣等感―
それで気付いた。そもそも私は、ワニの身を案じてなどいなかった。どころか、いつどのように彼に死の影が差すだろうか、という邪な好奇心で毎日更新を待ち望んでいた。たった4コマの中に何か不吉な予兆はないかと、毎日血眼になって探していた。
そんな自分にとって、純粋にワニの日々に一喜一憂するリプライは、どうしようもなく"正しかった"。しかもそれが大多数の人間の反応であることが、息苦しくてしかたなかった。
私は、あの漫画を見る度、道徳的劣等感を味合わっていた。それがたまらなく嫌だった。
それを認識した上でも、ワニを案ずる気持ちが、自分の心の中に、この道徳的空洞の中に、これっぽっちも見つからないことが空しくて、恐ろしかった。
思えば、これまで一度でも、心から道徳的であることができた瞬間が私には存在しただろうか。日常生活では、比較的優しい人間だなどと言われながら、私は、社会からつま弾きにされたり、失望されたりすることを避けようとしていただけだったかもしれない。
私が恐ろしかったのは、罪ではなく、ただ罰だったのかもしれない。私が受け入れられなかったのは、人を気付付けたり見捨てたりすることではなく、報いに伴う自分自身の痛みだけだったのかもしれない。
ワニの余命に心を痛める人々を見ていると、この世界には、そんな私が入り込む余地などどこにもないかのように思えた。
遠藤周作の"海と毒薬"で、第二次世界大戦中に捕虜を解剖し、非人道な人体実験の果てに殺してしまった医師、勝呂は独白する。
"俺が恐ろしいのはこれではない。自分の殺した人間の一部を見ても、ほとんどなにも感ぜず、なにも苦しまないこの不気味な心なのだ。"
100ワニのブームを通じて、このような不気味さを自分自身に感じた人はいないだろうか。炎上をほくそ笑んだり、果ては騒ぎに加担したりしている人の中にも、道徳的劣等感からくる居心地の悪さをどこかで感じてる人はいるのではないだろうか。
大多数は暇つぶしや空気に流されているだけだろうが、こういった後ろ暗さから目を背けることを動機としている人だっているのではないだろうか。自分が多数派だと確かめたくて、やっている人はいるのではないか。
だとしたら、私は世間の一層の下劣さに安堵するし、やはりほくそ笑んでしまう。やっぱり貴方たちも同じ穴の狢だったんだね、と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
