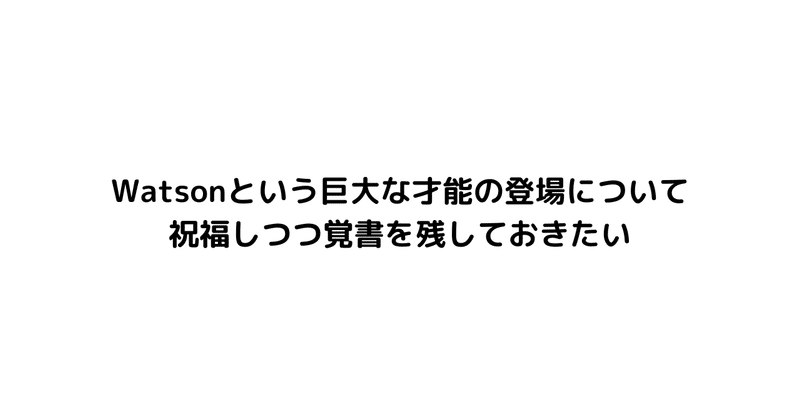
Watsonという巨大な才能の登場について祝福しつつ覚書を残しておきたい (text by 韻踏み夫)
せっかく始めたSCRAPTだが、さっそく二回目の更新まで空いてしまった。吉田雅史は自分の仕事にかかりっきりで山場を迎えているようで(がんばれ!)、私も私で、すでに情報公開されているが『ユリイカ』のフィメールラップ特集の原稿などに追われていた。
さて、ここ数か月ずっと、Watsonについて書かなくてはならないと思っていた。最近のWatsonは、破竹の勢いとはまさにこのこと、というような感じで快進撃を続けている。毎日のように客演曲が出ていた数日があったし、しかも毎回強烈なインパクトを残して、曲を食い散らかしている。彼が明らかに、ここ数年のうちで日本語ラップが生んだ最大の才能であるというような評価はすでに、シーン内ではゆるぎないものとなっているのではないだろうか。個人的には、その表現の独自性や刷新性といったことでは、KOHH以来の衝撃というか、切断点になるような予感がしている(KOHHがやばいと騒がれ始めたのも、ちょうど今から十年前ぐらいだったのではないだろうか)。KOHHについてならば、佐藤雄一「なぜ貧しいリリックのKOHHをなんども聴いてしまうのか?」(『ユリイカ』2016年6月号)が決定的なKOHH論として知られているけれど、そのようなWatson論が書かれることを私はすでに夢見ている。
WatsonもKOHHと同じように、きわめて最先端感がありながら、同時にきわめて「日本語ラップ」的であると思う。USのトレンドをその都度翻訳してゆくことにはきわめて大きな意義があるけれども、同時に、日本語ラップだからこそ可能で、USよりもオリジナル、というような作品を、つねに日本語ラップファンは待ち望んできた伝統があると思う。KOHHがそうだったように、Watsonもそういう一つの理想の形を体現していると思う。だからこその絶大な支持だと思う。
それで、とりあえずWatson論一歩手前というか、Watsonとは何なのだろうという文章をそろそろ誰かが書くべきだと思い、なんとなく彼について思っていることを、未完成なままではあるが、残しておこうと思った。
Watsonには誰の耳にも明らかなものとして、少なくとも三つの特徴をあげられると思う。一つはそのフロウで、彼の促音的というかスタッカート的というか、そういうフロウ。「せんぱいかっばてももらえっないお、か、ね」みたいな。「ZARA MENのジャ、ケ」みたいな。それがとてもクセになる。そしてもう一つの最大の特徴は、これもすでにさんざん指摘されているけれども、その言葉遊びであふれたリリックだろう。「reoccurring dream」からとりあえず抜粋してみると、「あと三年以上持つ弁当おかずとかない」「次買うICEはvvsそれかチョコミントかストロベリー」「四六時中ずっと触ってるちんちんでもやな事触れない」「音楽で稼いだ金で回してるmaryjaneとそれと乾燥機」「俺の友達野菜なら食べれないだけど巻いてるcannabis」といったところだろうか。いわゆる「オチをつける(パンチライン)」、「上手いことを言う」というような感覚が濃厚にある。そしてもう一つが、彼の素晴らしい強烈な声。赤井浩太が発明したらしい、いささかぎこちない造語を借りるなら、まさに「パンチヴォイス」ということになるだろう。
これらが生む、きわめて奇妙で独特な感触は日本語ラップではこれまでにほとんどなかったものであるように思われる。その謎を解き明かすのは批評の仕事だが、私はSCRAPTでは「批評からは一歩手前」の文章を書こうと思っているので、批評家としてではなく、いち日本語ラップリスナーとしての雑感を残しておきたい。
Watsonを考えるのに一つの大きなヒントになるなと思ったのが、彼が最大の影響を受けたと言う二人のラッパーの名前が明かされたことだ(https://www.youtube.com/watch?v=JF9K-ngdRX8)。それがKOHHとT-PABLOWとのことで、それを聞いて私は、シーンに突如現れた異物のようなオリジナルなスタイルのWatsonがどうやってできたのか、少しだけ垣間見えたような気分になり、とても腑に落ちたのだった。まずKOHHについては、二つのことが言える。一つは、時折WatsonはKOHHとすごくよく似た声を出す瞬間があること。両者ともに、さほど力を込めなくても、底にとても強い芯の通った、よく通る声をしていて、それは共通点だと思う。もう一つの共通点が重要と思われるのだが、それをここでは仮に「反詩情の詩情」とでも名付けてみたい。KOHHのあまりに平坦なリリックが、日本語ラップ史において衝撃的だったということは、語られつくしたことだ。その、文学的に瘦せこけたリリックが、逆にアートそのものになる、ということをKOHHはやっていたと言える。それは、廃墟を見たときに私たちが感じる一種の情感と似ているようなものであり、その意味でKOHHは「反詩情の詩情」だった。
対してWatsonは、KOHHとは異なり、むしろ言語的技巧をこそ褒められているラッパーである。しかし彼のラップには、たとえばTha Blue Herbに代表されるような文学的リリシズムの感触はなく、むしろ彼はどんなに内省的、ドラマチックな内容も、言語遊戯をそこに絡めることで、抒情性を自ら破壊、脱臼してゆくのだ。かつての絓秀実のような文芸批評には、ある種の文学的スカスカさ、痩せ細り、ジャンクさ、「雑」性といったものを肯定する態度があったが、そうしたフレームでWatsonを聴き、そのような方向性で評価することは十分に可能だと思う。そういう意味で、Watsonのリリックも「反詩情の詩情」と言うことができると思う。
そして、それを可能にしている彼の言語遊戯がどこに由来しているかと言えば、それがT-PABLOWということなのだろう、と私は解釈した。「音の上じゃ一生好き放題だから巻かれないよ長いもの」、「ぶっ飛ばされて教わってきたんだ礼儀と口のきき方」、「started from the bottom今じゃ上がってる右肩」(「Life Style」)みたいな歌詞。厳密に言葉遊びとまでは行っていないが、「長いものに巻かれる」、「右肩上がり」というような慣用句を一度分解し、倒置法にするという言語的な操作は、いわゆる「上手いことを言う」ラップの感覚に直結する技法だと言えるし、「~する〇〇と△△」というような言い回し(日本語ラップ的に一番有名なのは「巻くのはポリスとガンジャだけ」であろう)も、しばしば「上手いこと言う」のに使われる技法である。あるいは、「いくら積まれてもだせーオファーを蹴る代わりにかっけーヴァースを蹴る覚悟」(「Mobb Life」)、「変わらず追われる身/少年Aからスーパースター」(「Kawasaki Drift」)だと、明確にWatsonに繋がるような言語遊戯的パンチラインである。あるいは、「Ocean View」の冒頭、「ディナー運んでくるウェイターもしてるびっくり/タトゥーいれまくり若いのにいい羽振り/もしかして悪い仕事してる人たち?/いや違うよラッパー横に幼馴染」という、ボースティングの仕方。単にレストランで羽振りがいいということを歌うのではなくて、周囲に「悪い仕事してる人たち」に見られているけど実はそうではないという第三者目線と物語性を差しはさむことでユーモラスな香りが出てくるし(ユーモアとは子どもを見る大人目線で見ること、というのがフロイト的定義だった、はず)、「オチ」をつけているようなところも、Watsonに近いと思う。
いま上で「~する〇〇と△△」という言い回しについて触れたが、それはT-PABLOWが好むものであると同時に、Fuji Taitoにも共通している(周知のとおり、パブロとタイトは、高校生ラップ選手権の第一回大会で戦っており、二人の間にはドラマがある)。それは赤井浩太が「パンチヴォイスは止まらない」(『LUCKY STRIKE 02』)で論じている。「Nowadays」の「ベートーヴェン弾けねぇ引き金/薬より決める運命 回るルーレットと目/修羅場と韻踏んでも 上もっと上」というラインに注目しており、たしかにここは掛け言葉だらけである。実際Watsonは「T-STONEと曲やってたFuji Taito」(「kick it」)とネームドロップしており、Fuji Taitoを聴いていたことはたしかであるだろう。
あとここでもう一つ話しておけば、Watsonの特徴的な促音的というかスタッカート的なフロウがどこからやってきたのかということも問題となるはずだが、Fuji Taitoもそういうフロウを使っていたということは指摘できる。周知のクラシック「Crayon」を聞いてみればよい。フック「まっくらな~」「たっとえ何回~」という箇所が思い浮かぶし、「Lifeは映画でも目で見えてるものがすべてじゃないぜ」の箇所も、一文字一文字区切ったようなスタッカート的なフロウになっている。もちろん、ここではWatsonを日本語ラップ史のなかで考えるという風な趣旨で書いているので、本来ならばWatsonのフロウを考えるには、グライム/ドリル的なラップとの比較が不可欠であるように思われる。あそこには、変則的なドラムの位置に対応するためのフロウの試行錯誤が詰まっているはずで、Watsonのラップもそうだと思う。
非ブーンバップの、トラップ/ドリルのビートで、メロディ系ではなくスピット系のラップをするときの一つの最新系がWatsonであることはたしかで、それを支えるのが促音的なフロウであるだろう。このことについても脱線するが話しておきたい。私は最近、Leon Fanourakisがすごく重要だったのではないかと思うようになった。日本でトラップ以後、みんなラップにメロをつけるか、ミーゴス的三連フロウかの二択だったなか、倍速スピット系を貫いたことが、ここ最近のシーンに繋がっているような感覚があるからだ。だからLeon、benjazzy、ralph、夜猫族、Watsonなどを、現在のラップスキル最先端の領域としてマッピングする、というような大まかな見立てを提案してみたいのだが、どうか。
さて、話をKOHHとパブロの二源泉に戻せば、パブロの場合、彼の言語遊戯的リリックのセンスがすべて「スーパースター」性に収斂していくのに対して(このあいだの凱旋MC BATTLEでの圧巻のパフォーマンスを見よ)、Watsonはそうした充実性、超越性を絶えず攪乱しジャンク化し消尽してゆくような「反詩情の詩情」の感覚があるわけで、その「反詩情の詩情」はとてもKOHH的であり、だからやっぱり、彼はまさにKOHHとパブロをミックスさせていると言えると思う。
ところで、KOHHもパブロも、その作詞術のルーツを探ればキングギドラに行き着くというのが面白いと思う。KOHHが初めはKダブを聴いていたというのは有名な話だと思うし、BAD HOPが世に出る前にラップを教えていたのはKM-MARKITだったという証言がどこかでされていたはずである(出典失念、失礼)。そうでなくても、ZEEBRAのGRAND MASTERに2WINは所属していた。となると、Watsonに「日本語ラップ」感があるのも、遠くさかのぼれば、そうしたギドラ的押韻性を土台にした作詞術の延長線上にあるからだとも言えるはずだ。
とはいえ、ギドラ的なものにはユーモアの感覚は欠如している。Watson的ユーモアはもちろん濃厚にUS的な感覚があり、それは遠くさかのぼれば、ブルースの作詞法に淵源しており、たしかにWatsonの「反詩情の詩情」を端的に「ブルース的」と言いかえても、さほど問題はないとも思う。しかし、ここではそれをあえて日本語ラップ史的に系譜づけてみたいと思っていて、そうするなら、真っ先に思い浮かぶのはやはり漢である。漢が偉大なのは、「ストリート・ユーモア」とでも呼ぶべき感覚を体現していたからだ。おそらく日本で初めて、ストリート感覚とユーモア感覚を合体させたのが漢だったのではないだろうか(TOKONAもそうだったけれど)。だけど漢は、言語遊戯的にオチをつけるというような作詞術ではない。作詞術においてユーモラスだったラッパーとして思い浮かぶのは、AKLOとLowpassだ。特にLowpassの話術、ユーモア性というのは、なかなか後継者がいないよねという話を、昨年の「POP LIFE THE PODCAST」でも話したように思うが、ようやくWatsonに結実したともみなせるのではないだろうか(もちろん、Givvnはニヒルなユーモアだが、Watsonはストリート・ユーモアだ)。AKLOやLowpassが出てきた時代はいわゆる「スワッグ」期であり、スワッグ的言語感覚が遠くWatsonに流れているとも言えるかもしれない。その意味で、Young Hustleらに代表されるような、リリックが日常性を強く持ち卑近すぎることをたくさん歌うがためにユーモアがにじんでくる、というのもWatsonの歌詞に見られる特徴と共通している。
こうしてまとまらないことをずっとウダウダ考えながら、私はWatsonに強烈に引きつけられ、最近は特に毎日のように聞いている。明らかにWatsonは日本語ラップの新時代を切り開きつつあると思うし、それをリアルタイムで追えていることは素晴らしい体験だ。こないだツイートしたが、私は「Makuhari」の「21歳死ぬ気でやったがこの通りピンピン生きとった」という歌詞がものすごく好きだ。このみずみずしさ!たとえば「I woke up early on my born day; I'm 20, it's a blessin' /The essence of adolescence leaves my body, now I'm fresh……」というような、Nas「Life’s A Bitch」に歌われる、爽快で躍動する「生」の、「エラン・ヴィタール」(!)の感覚に似ていると思うからだ。偉大なラッパーはみんなそうして現れた。MACCHOも般若もSEEDAもANARCHYも、誰でも、みんな自らの「生」を精いっぱい表現して出てきた。Watsonも完全にそうだ。私たちはそういうレベルのラッパーの出現を目撃している。それを最大限に祝福したい気持ちだ。
韻踏み夫
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
