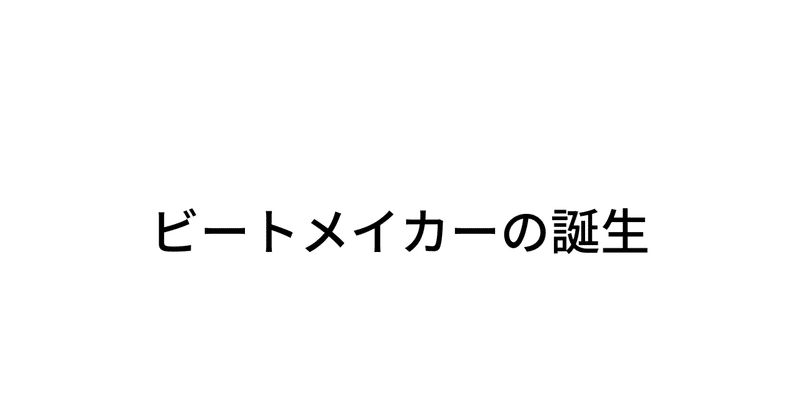
ビートメイカーの誕生 ―Grandmaster Flash・DJ Premier・PUNPEE― (text by 吉田雅史)
さて、肩の力を抜いて一発目の記事に向かっていきたい。SCRAPTで書いていきたいことはたくさんあるのだが、そのひとつは2022年10月に荘子it氏と韻踏み夫氏を招いて行った『ゼロから聴きたい日本のヒップホップ』@美学校の中で触れられたトピックを発展/深掘りすることだ(注1)。
その補足動画の中で「ビートメイカーの元祖とは?」という話をした。結論から言えば、グランドマスター・フラッシュが元祖というのが、私の考えだ。一般的に彼は、クール・ハークやアフリカ・バンバータと共に、ヒップホップのゴッドファーザーであり、三大「DJ」のひとりだ、とされている。確かに1970年代のヒップホップ黎明期の主役は何と言ってもDJであり、ヒップホップの誕生日とされている1973年8月11日にクール・ハークが二枚のレコードでループさせたブレイクビーツのグルーヴ自体が「ヒップホップの誕生」――マイルス・デイヴィス風に言うなら「Birth of Groove」〜グルーヴの誕生〜――だったわけだ。
意地悪な見方をすればクール・ハークの妹が服を買う金欲しさに兄貴を利用して開催したとも取れるこのパーティが誕生日となるなんて!実にヒップホップ的ではないか。
では「ビートメイカー」が誕生するのはいつのことだろう。DJがプレイするブレイクビーツのループの上でMCたちがラップを始めるという原風景から、ヒップホップのビートはテクノロジーの進歩や時代状況の変遷に伴い徐々に進化していく。当初ヒップホップはパーティの現場のものだったが、1979年にシュガーヒルギャングの「Rapper's Delight」が初のヒップホップのレコードとしてリリースされるのを皮切りに、少なくとも楽曲ベースにおいては、現場でしか経験できない文化ではなく、複製技術時代の芸術作品=商品として流通するようになる。
その際にビートを担ったのは、バンドだ。DJがプレイする既存のレコードの上でMCがラップする様子を「楽曲」としてリリースするわけにはいかないのだから、レコードに録音された演奏を生バンドがプレイし直すこととなる。いわば人力二枚使い、あるいは人力サンプラーのようにして即席のバンドは延々と四小節のループをプレイした。例えば「Rapper's Delight」はシックの「Good Times」(1979)のイントロを延々と「人力」で繰り返し演奏したものがバックトラックとなっている。スタジオに呼び出されたベーシストのチップ・シアリンは「Good Times」のベースラインを「15分間ぶっ続け、ミスなしで」演奏させられたことを回想している(注2)。彼はその非人間的な演奏と引き換えに70ドルを手にし、このレコードは全世界で500万枚以上を売り上げることになる。
ドイツではクラフトワークが『マン・マシーン』(1978)をリリースし、日本ではYMOがグルーヴを捨てた機械仕掛けのビートを追求し始めた翌年に、ニューヨークではヒップホップが人間にロボットであることを強いる演奏――サンプラーのように正確無比に演奏の揺らぎ込みのグルーヴをN回ループせよ!――で本格的に商業化の一歩を踏み出したというわけだ。
シュガーヒル・レコードやエンジョイ・レコードの作品群が牽引するこうした牧歌的な「バンド時代」が1980年代の初頭しばらく続く。だが1980年代の中盤に差し掛かる辺り、例えばランDMCのファーストアルバム『RUN D.M.C』(1984)を聴けば、ビートの様相が一変しているのが分かるはずだ。このアルバムで使用されているOberheim社のDMXを始めとして、1980年にはあのRoland社のTR-808も含めたドラムマシンが発売され、数年のうちにビートはバンド中心からドラムマシン時代へと突入することになる。
その端緒を遡っていくと、1980年にリリースされたとある記録音源にたどり着くわけだ。Bozo Meko Recordsと題された得体の知れないレーベルからいわゆるブート盤としてリリースされた「Flash It To The Beat」は、当時のシーンの生々しさを余すところなく捉えた貴重な音源だ。1979年の12月、ブロンクスリバー・コミュニティセンターで開催されたパーティ。グランドマスターフラッシュと五人のMCたちのパフォーマンスは、幸運なことにカセットに録音されていた!その一部を「Flash It To The Beat」と名付けたこの音源は、文字通りビートを刻むフラッシュの姿がフォーカスされている。
リンク先はフルのライヴ音源だが、ブート盤のレコードに記録されているのはちょうど2分すぎからの部分だ。「One, two, three and」というイントロに続きMCたちが「Listen to this, just listen to this」と煽りのラインを開始すると共に聞こえてくるのは、出力レベルがデカ過ぎるがゆえに歪んで、さらにカセットテープの自然なコンプレッションがかかったと思しき、実にラフでラグドでロウな――PMDが1996年に喝破したように――、つまり愛おしいキックとスネアのサウンドだ。この潰れたキックとスネアこそが、フラッシュ自身がリズムマシンを手で叩くことで刻まれたビートだった。フラッシュは二台のターンテーブルから一旦身を剥がし、ビートを刻むためだけに生まれたその機材に身を委ねた。まさにこの瞬間、ビートメイカーが誕生したのだ。
Thomas Organ Company社から1966〜1968年の間に発売されたVOX Percussion King Model V829は、鍵盤の伴奏としてのリズムを発信するための機材だった。これは当時の楽器演奏者のアシスタントとして需要され、リズムボックスと呼ばれた。音声合成によるドラムのサウンドを詰め込んだ魔法の箱。マーシャルアンプのヘッドのようなデカいボディに並べられたのは、小さな押しづらそうなボタンたち。これをチマチマと叩くことで魔法の箱から出力されるサウンドは、キックとスネア、そしてボンゴやシンバルのチープなシミュラークルだ。
けれどもそれは、実にヒップホップ的な価値転倒を呼び込んだ。チープなドラムサウンドは録音環境によってさらに劣化することで――このショウのライヴレコーディング環境がたまたまもたらした奇跡――、極上の歪みとローファイさを前景化させ、後世で何度もサンプリングされるほどのポテンシャルを勝ち取ったということだ。
「Flash It To The Beat」をサンプリングネタ検索サイトwhosampledで検索してみよう。その100件以上ある検索結果からは、フューリアス・ファイヴのラップのフレーズが引用されているケースが多いことも分かるが、同時に、これを「ネタ」として採用した様々なビートメーカーたちがリストアップされる。それらを数珠つなぎにすることでいくつかの系譜を立ち上げることができるわけだが、ここではそのうち二人を挙げたい。
一人目は他でもないリビングレジェントたるビートメイカー、DJプレミアだ。彼のことを話出すと止まらなくなるので、プレミア論は別の機会に譲ることにする。ここでは「Flash It To The Beat」のラフ、ラグド&ロウなキックとスネアをサンプリングしたギャングスター『Moments Of Truth』(1998)に収録の「You Know My Steez」に着目する。ビートの構造はシンプルだ。材料はドラムとウワネタ、それだけだ。
まずドラムについては、フラッシュがVOXを叩いたキックとスネアをサンプリング、そこにハットを足した三音でいつものプレミアらしいコンプレッサーの効いた打ち込みのドラムがリズムを刻む。ドラムマシンの音色を、それが使われたレコードからサンプリングすることは稀だ。TR-808の音色でドラムを組みたければ、実機かクローンのソフトウェアを使えばいいからだ。だがDJプレミアがフラッシュがVOXを叩いた音をサンプリングしたという事実は、単にVOXを使うだけでは再現できないラグド&ロウな音色がブート盤のレコードに刻まれていたことを証明している。
そしてウワネタは、ソウルシンガーであるジョー・サイモン「Drowning In The Sea Of Love」(1972)のギターフレーズをチョップしてーー切り刻んでーー再構成したものだ。ギャングスターの前作『Hard To Earn』(1994)辺りからDJプレミアはドラムのチョップを前景化させ始める。サンプラーのサンプリングタイムが長くなることでビートメイカーたちはブレイクビーツをそのまま小節単位でループさせることができるようになる。だがやがてサンプリングタイムの制限があった時代に逆戻りするような形で、ビートメイカーの「自我」が芽生える。単音のキックやスネアに分解してドラムパターンを打ち込みで組み上げることによって、ビートメイカー個々のグルーヴを響かせ始めるのだ。かつてマミーDは、このパラダイムシフトのきっかけはATCQの『Midnight Marauders』(1993)なのだと指摘した(注3)。そしてドラムのみならず、上部構造であるウワネタにまでチョップの手法が大々的に適用されたのが『Moments Of Truth』だった。「You Know My Steez」のイントロでグールーが宣言しているように、二人は「時代と共に制作方法――ライムとビートのスタイル――をアップデートしていくが、それでも変わらずグールーとプレミアであり続ける」のだ。
なんと言えばいいのか、何かを並べ直して新しい組み合わせを探るという行為には、ある種の素朴な愉しみがある。過去から未来の方へ一定の方向へ順列で流れている演奏の時間をぶった切って、並び替え、ループさせること。すでに目の前にある素材から、予想だにしなかったアウトプットを引き出すこと。大げさに言えば魔法。「遊び」のように適当に切り刻み並び替えてMPCのパッドを叩きまくり色々やっていたらドープなものができてしまった!という感覚。例えばノトーリアスB.I.G.の「Unbelievable」(1994)やバンピーナックルズ「Part of My Life」(1999)を聴けばその感覚が伝わるかもしれない。
ビートメイカーたちによる音楽を通して時間軸を操るという感覚は、DJ特有の全能感にも通じるものがある。パーティの現場のDJがカリスマティックな存在であるのは、様々な時代のレコードに刻まれた音楽の時間軸を自由に操りつなげることで、その場のリアルタイムの時間を支配するからだ。かつてグランドマスターフラッシュが「clock theory」と名付け方法論化したのは、ある楽曲の時間軸Aに別の曲の時間軸Bをフレーズ単位で挿入する技法だった。だから言い換えれば、そのDJたちの全能感を引き継ぎ、より解像度高く精緻な時間操作を代行する機械がサンプラーなのだ。
AにBをブッこむ。このとき、AとBの関係性が薄いほど、距離が離れていればいるほど、組み上がったビートの魅力は増す。具体的にはAに対して音楽ジャンルが異なり、制作時期が異なり、鳴っている楽器が異なり、音色が異なり、リズムが異なり、音質が異なるようなBを接続すること。「Flash It To The Beat」というレコードに、そのようなまなざしを向けたビートメイカーが、PUNPEEだった。Norikiyoの「終わらない歌(REMIX)」(2017)は、Aである「Flash It To The Beat」のドラムと煽りのループから始まり、THE BLUE HEARTSの「終わらない歌」がBとして接続される、理想的で半端ない距離感の一曲となっている。
THE BLUE HEARTSの公式リミックス企画である本曲でPUNPEEが得意のポップセンスを最大限に発揮し提示するのは、90年代ライクなメロウでソウルフルなブーンバップスタイルのビートだ。メインのドラムネタとして選ばれたのは、数々のヒップホップクラシックでサンプリングされているメルヴィン・ブリスの「Synthetic Substitution」(1973)だ。『Ultimate Breaks & Beats』シリーズにも収録されビートメイカーを志すなら一度は使うだろう定番ブレイクで、もちろんDJプレミアも例外ではなく、ギャングスターの「Code Of The Street」(1994)で使用している。
しかしここで注目したいのは「Substition」のドラムが入ってくる前の1分間にわたるイントロ部分だ。「Flash It To The Beat」のドラムと煽りのフレーズは一旦フェードアウトするが、今度はウワモノのエレピのコード弾きと「just clap you hands to the beat box」というフレーズとドラムをバックにPUNPEEが次のような短いヴァースを披露する。
終わってなかったんだ ほら過去から
ゆっくりこっちに走って来てんじゃん
息切らした青臭いガキが今追いついて
キー君 Let’s go
THE BLUE HEARTSからの影響を言葉にしてきたNorikiyoだが、「青臭いガキ」だった当時の自分自身と対峙することになるのもまた、時空を超えるサンプリングの効果だろう。そして曲のイントロの後半ではさらにヒロトとマーシーが歌うコーラスのアカペラが挿入されるのだが、ここで左チャンネルからビートを支えるのもまた「Flash It To The Beat」のグランドマスターフラッシュのVOXによるキックとスネアなのだ。グランドマスターフラッシュというビートメイカーが誕生したのは1979年12月だったが、その翌年にはフラッシュより五歳下で高校生だった甲本ヒロトも地元岡山で最初のバンド、ラウンドアバウトに参加しようとしていた。グランドマスターフラッシュと甲本ヒロトの邂逅を後ろからニヤニヤ眺めるPUNPEEは、最高の形でビートメイカーの「魔法」の使い方を示してくれている。
それにしてもなぜPUNPEEは「Flash It To The Beat」をこの曲でサンプリングしたのだろう。
それはきっと、「始まり」を告げたかったからだ。若きNorikiyoとTHE BLUE HEARTSの出会いという「始まり」があったように、自らがコミットするヒップホップという文化のひとつの始まり、そして自らの肩書きであるビートメイカーの始まりがあったことを。PUNPEEはここで、サンプリングを通して歴史を超えどこまでも語り継がれ引用され続ける「終わらない歌」に始まりがあったことをリマインドしている。だから「終わらない歌」とは、フラッシュ・DJプレミア・PUNPEEと如何様にも接続され系譜付けられ伸張していく、ビートメイカーたちが織りなす物語の別名でもある。
▪️
肩の力を抜いたつもりが幾分リキんでしまった感があるが、このようなビートメイカーたちが織りなす物語については、今後も適宜探っていきたい。
吉田雅史
注1:美学校で行われた「基礎教養シリーズ〜ゼロから聴きたい日本のヒップホップ〜」は下記URL先のpeatixリンクよりアーカイブ公開中です。
注2:https://www.tcelectronic.com/artists/artist.html?artistId=chip-shearin
注3:『Front』誌1998年4月号 P.27
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
