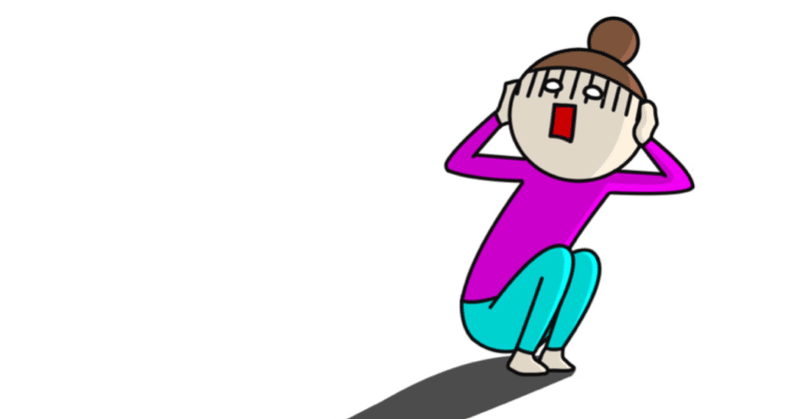
不登校の理由が伝えられない子供と、理由を知りたい親の葛藤
こんにちは😊
Prism校長のきよこです。
新年度になり、ちまたでは、入学式やクラス替えにドキドキの子供たち。
揺れる時期ですね😊
学校に行きにくくなっている子供さんのお母さんから相談をいただきました。
その子は、年度末くらいから学校に行きにくくなったそうです。コロナの影響で、学校の様子も様変わりし、学校も変化を余儀なくされている様子。大人もついていくのに必死なのに、子供たちなんて、尚更ですよね😅
ただ、学校の在り方の方向性としては、より厳しくなっているという印象。
休憩時間は、あまり話してはダメ。外で遊ぶ時も、マスクが必要。給食は、うちの地域では、グレーのついたてをして、みんな前を向いて食べるそうです。
話は厳禁。お互いに、目を光らせる感じが、ちょっと怖い😅
確かに、少し、息苦しさを感じることがあって、当然ですねw
「みんな、頑張ってるねんから当然や!」

という言葉を、たまに耳にします😊
そうですね。ここは、力を合わせるのがとても大事。好き勝手していい!というわけではない。だけど、「これは嫌だなぁ〜。」という感覚を抑え込むのは違うと思うのです。
人は、「これは、嫌だなぁ〜」というマイナスな感情から、改善点を見出し、社会が発展してきたのだと思うのです。
だから、一度決めたルールを頑なに守るのではなく、疑問点を話し合い、問題点を抽出して、新しいルールを考えてみる。

ルールだからと決めてしまわずに、その目的は?本当に必要なのか?を考えることって大事ですよね。これが、今、求められているクリティカルシンキングというものになると思います。
結果、いい解決策が浮かばなくても、過程を考えることがとても大事なのです。
さて、話を戻しますと、今、学校に行きにくくなっている子は、何かしらの違和感を感じていて、このまま学校に行ってていいのか?という疑問と対峙しているのかもしれません。
けれども、そこまで!ハッキリと認識できる年齢でもないことが多く、「なんか、行けない…」「行きたいけど行けない」「朝が起きられない」「行きたくない」「体の調子が悪くなる」そんな、色々な形でサインが出てきます。
でも、私たち大人は、子供に理由を求めます。

私も、何度も理由を聞きました。
でも、お子様の状態にもよりますが、私の経験では小学6年生〜中学生になってからでないと、言葉で伝えるのは難しいと感じています。
もし、子どもが学校に行きにくくなったら、他の世界も見せてあげて欲しいのです😊
人間の成長には幅があります。私は、20歳の頃に看護学校の実習で学んだことを30歳代で本当の意味で理解したと感じたことがあります。
その時に、理解ができなくても、その体験は必ずその人の中にあって、必要な時に学びとして開花します。
不登校も同じです。この体験をただ否定するのではなく、この体験はがこの子のどんな成長に繋がるのかを楽しみにしてみてください😊
大丈夫!必ず、繋がります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
