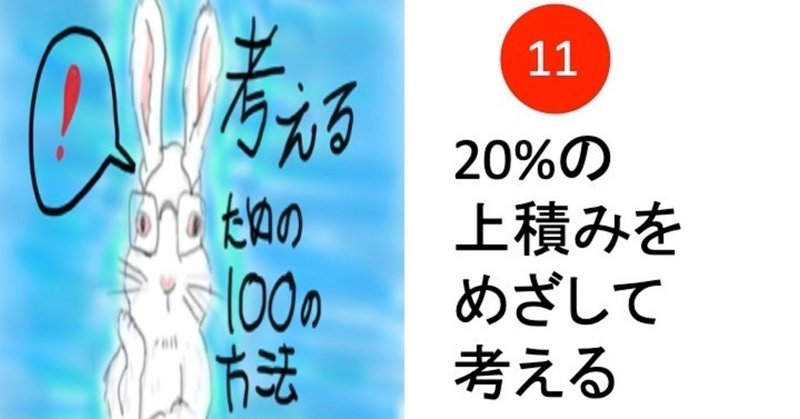
11 20%の上積みをめざして考える
「考える」という作業の多くは、その考えに対して評価を下す人間を意識しながら行われます。ということは、自分の頭のなかだけで考えを進めるのではなく、その人が何を考えているのかということを察しながら進める必要があります。
教授は、なぜ別のテーマではなく、このテーマを期末レポートとして課したのだろうか。新人研修の目的は何だろうか。この課題は、どういう位置づけになるのだろうか。得意先の社内構造において、この提案は各部門にどのような影響を与えるのだろうか、などなど。このように想像力を駆使することで、与えられた課題の多くについて、解決の糸口が見えてくるはずです。
ただ、それは、相手が求める(だろう)という答えを寸分違わず用意する、ということではありません。学校のテストならそれでも満点がもらえるかもしれませんが、ビジネスの場ではさらに上を行く必要があるでしょう。上司や得意先が満足する提案を行うのは当たり前、そこからどれだけ上積みできるかが、腕の見せ所というわけです。
だからといって、無理をして、できもしないプランをひねり出したりする必要はありません。だいたい20%くらいの上積みするようなつもりで考えると無理が生じないで、相手にも「考えているな」ということが伝わるはず。
まずは20%、それをクリアしたらさらに20%、というぐあいに、少しずつ上積みしていくイメージを持ち続けましょう。 求められた水準より100%アップのアイデアというと、上積みというよりも「意外感」の方が強いですが、こうなると、インパクトがあります。
具体例で考えてみましょう。大学で「大学とは何を学ぶところか」という基礎的なメッセージをもっと高校生に知らせていこうという話が持ち上がりました。広報担当者が高校を回っているときに、そうした当たり前の情報が、意外にも高校生にも先生にも不足しているという声があったというのです。それを聞いて、ちょっと驚きました。それは、自分で探すことではないかと思ったのです。
ただ、もう少し詳しく聞いてみますと、納得できる点もあります。昔のように法学部、経済学部と分かりやすい学部ばかりなら、高校生も見当がつきますし、先生も教えることができるでしょう。ところが、いまは時代の変化が早い。いちばん変わりにくい法学にしても、法を取り巻く考え方、新しい分野における法的整備、企業活動における法的思考の重要性など大きく変わっています。それに対応して、大学が法学を教えるときも、その内容は多様になりました。よく分からずに偏差値だけで学部を選んで入学してみると「自分に合わない」ということもあるでしょう。
文科系に限っても、情報、心理学、社会学、国際関係の分野などで新しいアプローチが増えています。経済学においても、研究内容は千差万別です。ともかくパンフレットを作ろうという話になったとき、私は高校生に向けて、彼らを主人公にした大学選びの物語はできないだろうかと思いました。各学問の説明は、妥協することなく、厳密でありながら、高校生が引き込まれるストーリー仕立てにしよう。といっても、こういう内容だと、プロダクションに依頼といっても執筆者が見つからずに難しいわけです。
自分で書くかということで、企画のラフ案を作りました。広報担当者のみなさんは、「おっ」という感じで受けとめてくれました。各学問の教科書を読み比べながら書いた小冊子は、幸いに話題になり、マスコミでも取り上げられました(下記参照)。高校の進路指導の先生たちから100部単位でまとめて送って欲しいという要請が多かったのは嬉しいことです。アイデアは、まあまあの最低水準でなく、20%以上の上積みを狙う。それは大変でも、結構楽しいことでもあります。
大学進学を考えるガクブック https://www.tku.ac.jp/exam/gakubook.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
