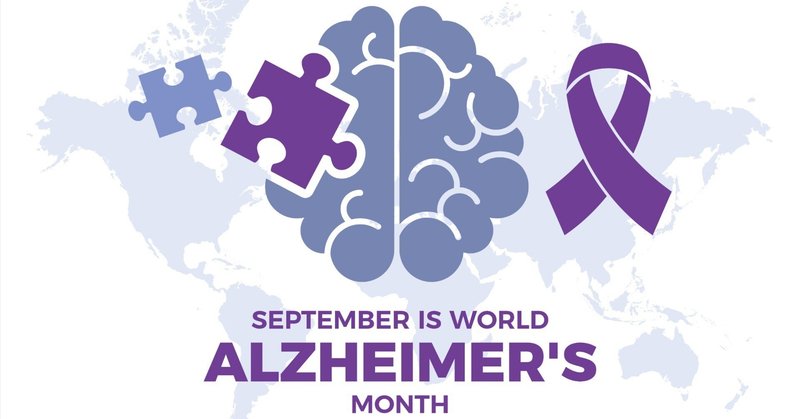
アルツハイマー病研究最前線に関する書籍2つ
人類の寿命が長くなるにつれ、認知症を患う人の数も増加していることは周知の事実。人々の感心も高く、治療薬の開発も切に望まれている。来る9月はアルツハイマー病の周知月間だが、タイミングを図ったかのように2冊の書籍が刊行。幸い、どちらも発売前に出版社よりご恵贈いただいていたので、合わせて紹介したい。
間もなく、8月24日に刊行予定なのが『アルツハイマー病征服』(下山進著、角川文庫)。アルツハイマー病の治療薬開発には多数の人々が関わる。患者さんやそのご家族、治療にあたる医師、病気のメカニズムを探求する基礎研究者、薬の開発に関わる企業の研究者、そしてその効果を調べる治験に参加する方々……。下山さんはこれらの多数の方々に丁寧な取材をして、物語を紡いでいる。本書は2021年1月に書き下ろされた書籍の文庫版だが、なんと、新たに400字×80枚が加筆された。
単行本の方は、「アリセプト」という認知症薬で世界を席巻した日本の製薬企業エーザイが開発に関わった「アデュカヌマブ」という抗体薬の臨床試験が混迷したところで終わっていたが、そこに新たな矢として「レカネマブ」という別の抗体薬が開発され、米国FDAより今年1月に迅速承認、7月にフル承認を取得したことまでが文庫版には加わっている。日進月歩の世界だ。
どちらの抗体薬もターゲットにしているのは「アミロイドβ」という分子である。100年以上前にアロイス・アルツハイマー博士が、記憶障害、言語障害、予測不可能な行動により入院した女性患者アウグステ・Dが亡くなった後に、その脳を解剖してみると、多数の異常な凝集体(アミロイド斑あるいは老人斑と呼ばれる)と、線維のもつれ(神経原線維変化と呼ばれる)を発見した。この神経病理の結果、アミロイドβ分子が凝集するのを防ぐことによって、アルツハイマー型認知症を防ぐことができるのではないか、という仮説のもとにこれらの抗体薬は開発されてきた。
エーザイによる説明では、「臨床試験の結果、2週間1度、レカネマブの点滴を1年半続けた人では、偽薬の投与を受けた方に比して、症状の進行を27%緩やかにすることができ、認知症の進行を約7か月半遅らせる効果がある」とされる。ちなみに、商品名の「LEQEMBI(レケンビ)」の言われは、レカネマブの生みの親として知られるスウェーデンのウプサラ大学のLars Lannfelt先生をリスペクトして「LE」の音を取り、「健美」と組み合わせたものだと聞いている。
根拠となる臨床研究の論文は、世界多機関の連携によるもので、一番最後に国立精神・神経医療研究センターならびに東大の岩坪威先生のお名前がある。
本書は創薬開発がどのような仕組みで行われるのか、製薬企業間の交渉などもとても丁寧に説明してあるので、単行本の頃より東北大学の医学部生向けに「大隅推し本」として取り上げている。
一方、8月17日にみすず書房から『アルツハイマー病研究、失敗の構造』という単行本が出版された。こちらは米国のカール・ヘラップという研究者が一般向けに書き下ろした書籍の和訳で、翻訳者の梶山あゆみ氏は、『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』(デビッド・シンクレア著、東洋経済新報社)や、『脳の地図を書き換える: 神経科学の冒険』(デイビッド・イーグルマン、早川書房)の翻訳も手掛けられた方。
こちらの原著者は、そもそもアルツハイマー病の「アミロイド仮説」に研究が集中している現状に疑問を呈しており(とくに流行りの研究に皆が飛びつくのは、COVID-19の場合も同様、動きの早い米国や中国ならではなのだが)、アルツハイマー型認知症の定義がどのように拡大されてきたのか、というところから振り返る。もともとは稀な若年性の認知症の一型であったものが、いまやほとんどの認知症がアルツハイマー病と呼ばれるような時代になった。また、アミロイド仮説の根幹を成しているのは、遺伝的な要因があはっきりしている家族性のケースであり、圧倒的多くの「孤発性」の場合、その原因は明瞭ではない。認知症の進行するプロセスはきわめて複雑であり、アミロイドの蓄積だけが原因ではないことや(線維のもつれの主成分であるタウの蓄積や、その他、老化に伴う脳内のプチ炎症など、より全般的な問題もある)、治療薬の効果を症状の改善ではなく、アミロイドの蓄積で判断することの是非については、確かに一聴に値するだろう。
ただし、へラップ博士自身、認知症の研究者であるため、自説への愛着が強い点は否めない(研究者にとっては、自分の研究成果こそが自分の子どものように一番、可愛いのだ)。へラップ博士は、老化した神経細胞が暴走して、再度、細胞分裂を開始しようとして破綻する(本来、神経細胞は生まれた後、分裂しない)こと、その結果として周囲に炎症を巻き起こすことが本質的に重要だと考えている。
マウスの脳にアミロイドを沈着させても、記憶は悪くなるものの、ヒトの認知症のような複合的な症状は示さないことや、抗体でアミロイドを除去すると、ヒトと異なり記憶がバッチリ改善すること、アミロイドが脳に沈着していても症状が出ない方や、アミロイドが沈着していなくても、認知症を発症する方がいることは、アミロイド仮説一択ではリスキーであることを示唆している。原著タイトル『How Not to Study a Disease: The Story of Alzheimer's』に対して、日本語タイトルの『〜、失敗の構造』は、いささか強すぎる印象もあるのだが……。
日本ではちょうど明日、8月21日に厚生労働省の会議によりレカネマブが認可されるかどうかが判断される。
【追記】(2023.8.22)
昨日夜の報道にて、日本でもレカネマブが認可された。薬価がどうなるかは今後の議論だが、米国より低価格にするとのこと。とはいえ、年間200万〜300万円前後というのは大きな負担。
報道関係では、現時点でこちらのNHKの記事が詳しくまとまっていてお勧め。
【追記】(2023.8.27)
『アルツハイマー病征服』で触れられているのだが、エーザイはエレンベスタットという低分子薬についても開発していた。アミロイドβが切り出される酵素を標的とした阻害薬という意味では同じ仮説に立脚しているが、低分子薬は薬価が抑えられるという点ではメリットがある。だが、残念ながら、エレンベスタットは2019年に、治験の第III層の途中で、効果が認められないということで打ち切りとなった。
折しも、専門家向きの医学雑誌ではあるが、『BRAIN and NERVE』(医学書院)の8月号の特集が「アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか」となっていて、臨床家数名が寄稿している。エーザイもタウ抗体薬の開発も行っており、タウの蓄積を下げた場合のアミロイドβの阻害効果に期待している。さらなる多様な研究の進展を期待したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
