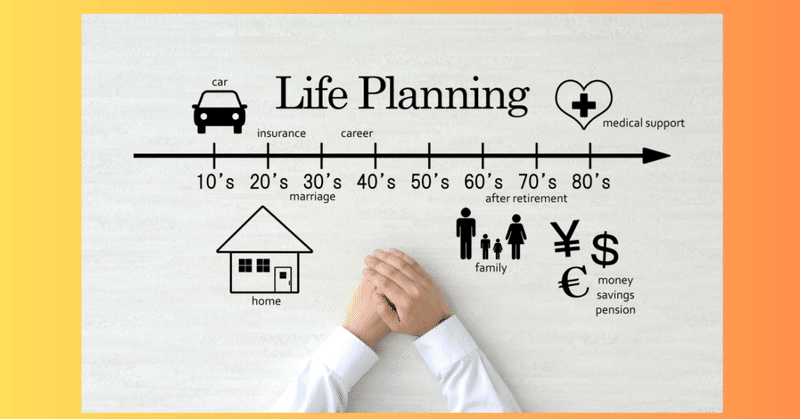
人口減少はもう止められない
トレンドはもはや変えられない!
人口減少、特に労働力人口の減少を食い止める為に少子化対策が叫ばれて久しいですが、近年の著しい人口減少ペースを見て、岸田内閣は「異次元の少子化対策」を最重要課題に掲げ、児童手当や給付金など子育て世代への支援に対する予算を厚くし、人口減少のトレンドを何とか「増加」に変えようと苦慮しながら、様々な施策を打ち出しています。
一方、政治家、特に地方選挙の候補者の政策を聞くと、「子育て世代の手厚い支援で人口を増加させます」といった類いの政策主張をよく耳にします。
しかし日本中で少子化の弊害が目に見えるようになって、やっと社会の空気が「少子化対策」に舵を切り出しはしたものの、「人口を増やす」ことはもはや幻想でしかなく、少なくとも21世紀中に日本の人口が増加に転じることは難しいでしょう。
最近、個別の自治体で人口が増加した好事例みたいなものが取上げられることもよくありますが、これは結果的に他の自治体と少ない人口を奪いあっているだけで日本全体としての人口減少のトレンドは今後も続いて行きます。もはや日本の人口減少のトレンドは変えられないのです。
20年間放置された少子化対策ー団塊ジュニア世代の出産適齢期からの退場
しかし、この少子化や人口減少問題は、東日本大震災やリーマンショックとは違って、突然降って湧いた問題ではありません。もう、ずっと以前からわかっていて問題視されていた事なのです。
2003年には、「少子化社会対策基本法」が成立しています。そして、その前文では、次の様に述べられています。
『我が国における急速な少子化の進展は、平均寿命の伸長による高齢者の増加とあいまって、我が国の人口構造にひずみを生じさせ、二十一世紀の国民生活に、深刻かつ多大な影響をもたらす。我らは、紛れもなく、有史以来の未曾(ぞ)有の事態に直面している。
しかしながら、我らはともすれば高齢社会に対する対応にのみ目を奪われ、少子化という、社会の根幹を揺るがしかねない事態に対する国民の意識や社会の対応は、著しく遅れている。少子化は、社会における様々なシステムや人々の価値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立った不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。急速な少子化という現実を前にして、我らに残された時間は、極めて少ない。<以下略>』(太字筆者)
このように、すでに、20年前に、ここまで危機意識に満ちた言葉で、事の重大さが訴えられていたのです。然るに、その間、「何もなされなかった」と言えば、言い過ぎでしょうが、少なくとも、少子化の流れを堰き止めるような有効な対策は取られなかったと言えるでしょう。
この法律施行当時は、日本の人口構成の2番目のボリュームゾーンである「団塊ジュニア世代」が30歳前後の時期でした。まさに日本女性の出産が一番多い25歳~35歳の年齢層です。約800万人近くがいるこの世代こそ、日本の少子化を止め、人口減少規模を緩慢なものにする最後の世代であったのです。それゆえ、少子化対策の最後のチャンスと捉えられ、その効果が期待されていたのです。
しかしこの世代が20歳台、30歳台の時期は経済的に日本は失われた20年に苦しみ、東日本大震災などの度重なる災害やリーマンショックによる派遣切の嵐を経験してきました。すなわち、ライフスタイルの変化や価値観の変化もあったにせよ、それ以上に、社会的・経済的影響により、予想された第三次ベビーブームは起こせなかったのです。それから20年以上が経ち、彼等彼女等も50歳前後になり、生物学上の出産適齢期を過ぎようとしています。この後の世代は、年々人口が減って行き、子供を産み育てる母親の数『大きな分母』は縮小していきます。それゆえ、出生率が少々上がったとしても、もはや人口減少は止める事はできないのです。
今後も引き続き政策的な少子化対策は必要であります。しかし、その意義はもはや「激変緩和措置」としてしかありません。もはや、私達は人口減少は止めることができないものとして、新しい社会システムの構築と新しい意識の醸成に努力し、未来の設計図を描く必要があるのではないでしょうか。
前回、人口減少問題が老後設計に影を落とすと書きました。
今の30代、40代、50代の人達が設計すべき老後の時代-これから30年は、今までの延長上の社会ではありません。人口減少という社会の激変下で、新しい様々なリスクも発生してくるはずです。これに耐えうる老後設計、これを作り上げて行くには、並大抵なことではありませんが、従来の発想から脱却した、新しい「働き方」、新しい「暮らし方」を模索することが必要になってきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
