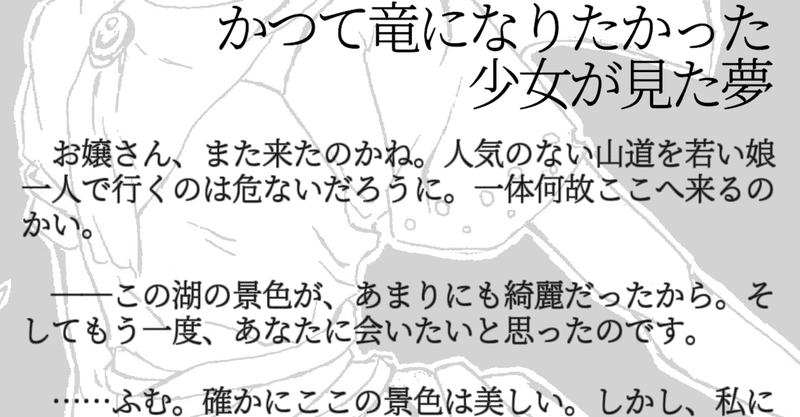
かつて竜になりたかった少女が見た夢
※再掲載。8000字程度。
〈プロローグ〉
お嬢さん、また来たのかね。人気のない山道を若い娘一人で行くのは危ないだろうに。一体何故ここへ来るのかい。
――この湖の景色が、あまりにも綺麗だったから。そしてもう一度、あなたに会いたいと思ったのです。
……ふむ。確かにここの景色は美しい。しかし、私に会いたいと思うのは、おかしな理由だね。人間にはよく嫌われているから。何せ見ての通り、私は竜だ。私たちは人間に害を及ぼす存在として認識されている。なのにどうして私に会いたいと思うのか……。
そんな風に言われると、思い出してしまうよ。過去に君のような娘が、私に会いに、ここに来た日があったことを。記憶が綻びて、彼女の顔も名前も、はっきりとは思い出せないが、今思うと、本当に君にそっくりだったような気がするよ。ここに来たついでに、お嬢さん。この長生きな竜の話をひとつ聞いていってはくれないか。
〈起〉
あの少女に初めて出会った頃は、今よりも、もっと自然が豊かだった。まだ山の切り崩しも少なかったし、人間の文化の発展も緩やかで、人と自然とが上手く住み分けられていた。とはいえ、文明がこれから発展していく予兆もあったがね。そのことに関して、私自身は、先のことを憂いながらも、時代が進む流れに身を任せるように暮らしていた。人が山を崩して手に入れたとはいえ、葡萄畑は美しく、私のお気に入りでもあった。
あの日、私は湖の底で居眠りをしていたのだが、湖の近くで生き物の気配を感じ、目を覚ました。たとえ眠っていようとも、ここは我が城。どんなに小さな生き物の息遣いでも、竜は感じ取ることができる。私はしばらく感覚を研ぎ澄ませていた。
しばらくして、詩(うた)が聞こえてきた。……可愛らしい声だ。高い声が幼なさを表していたが、それが返って愛しく感じられた。乾いた心に光を当てられたような気がしたのだ。
一体誰が詠っているのだろう。人間から憎まれている立場としては、するべきではなかったのに、私はつい湖から顔を出してしまった。
……予想した通り、年端もゆかぬ娘が水辺に佇んでいた。一目見ただけで、彼女には人間の子供が持つあどけなさ、無垢さをまだ備えていることが分かった。そして失われていない純真さを、私は予想以上に好ましく受け取った。これが私と彼女の出会いだ。
彼女は私を見て驚き、詩を止めた。しかし意外なことに、私を恐れてはいなかった。……私はもう少し、彼女の声を聞きたい気分だった。
「もう詩は終いかね」
やや間があって、娘はもう一度詠い始めた。やはり可愛らしい……そして、美しい。私は水辺に身体を預け、彼女の声に聞き入った。 娘は一頻りその詩を披露してくれた。詠い終わってから、私はあまりの気持ちの良さにまどろみかけていた頭を持ち上げた。
「良い詩だ。ありがとう、お嬢さん」
彼女は小さい頭を下げて、行ってしまった。私はもうこれで、二度とこの詩を聞くことはなく、彼女に会うこともないだろうと思い、残念に思っていた。
しかしこの予想は私を裏切った。数日が経ち、物思いに耽る私のところに、またあの詩が湖の底へと降ってきた。顔を出すと、やはりあの少女が詠っている。私は嬉しくなった。
それからは、彼女はよく私の住む湖へと遊びに来てくれるようになった。私は娘に尋ねたことがある。どうしてこんなところにわざわざ来るのかと。
すると彼女は答えてくれた。
「最初は、帰り道が分からなくて迷っていたの。そしたら偶然、この湖に出て、景色がとても綺麗で……。思わず詩を口ずさんだら、あなたに会った。竜は怖くて恐ろしいものだと聞かされていたのに、あなたはとても穏やかで優しく、気高い生き物だった。図々しいかもしれないけれど、私、もっとあなたと話をしてみたいと思ったの」
彼女は私に名前を尋ねたことがある。しかし竜の掟上、私には名前が存在しなかった。
「お嬢さん、竜は自分だけの名前に縛られない存在だ。我々は種族で成り立っているのだから」
「でも、名前がないと不便なのよ。無いのなら、私があなたに、名前をつけてもいいかしら」
「ふむ、そうだな……。掟関係なく、私的に君が私の名を呼びたいというのなら……君が呼びたいように呼びなさい」
「ありがとう! えっと、まず私の名前はね……」
彼女は嬉しそうだった。日を追うごとに、少しずつ、彼女が住んでいる街のことや、人間たちのこと、自分自身のことについて、彼女は私に話してくれるようになった。あの詩についても教えてくれた。
「この詩は、お母様から教えてもらったの。お母様はお婆様から、お婆様は、そのまたお婆様から……」
「じゃあ、君はその美しい詩を代々受け継いでいっているという訳だね」
「ええ。私の祖先を遡っていくと、昔はここから遠い東に住んでいたそうよ。きっとご先祖様はこの詩と一緒に、ここまで旅してきたんだわ」
私と彼女が話す間、ここには穏やかな時間が流れていた。どんな生き物からも遠ざけられ、寂しさによって頑なになっていた私の心を、彼女が癒してくれた。
もう少し彼女が話してくれたことについて、詳しく話そうか。
彼女が私のために何か食べ物を持ってきてくれることが度々あった。秋になると、地元で収穫された葡萄を分けてもらったこともある。私が愛している風景から生まれた果物はとても甘く、瑞々しいものとなっていた。
「ふむ。良い実が成ったな。人々が毎日世話をした賜物だ」
「これでワインを造るのよ。まだ私は飲めないのだけれど、とても美味しいものができるのですって。私も早く大きくなって、飲んでみたいわ」
「その言葉に嘘はないだろう。楽しみにしていると良い」
彼女はよく笑って話していたが、いつも明るい彼女の表情ににも暗い影を落とす時は稀にあった。それは自分の妹の病気について話す時だ。
「私の妹、生まれた時から身体が弱くて。お医者様でも治せないって、お父さんとお母さんが話しているのを聞いてしまったの。でも、お医者様には治せなくても、神様なら治せるかもしれないと思って、寝る前に毎日祈っているのだけれど……」
「妹思いだな、君は。会ったことはないが、君たち姉妹は、きっとそっくりなのだろうね」
「妹が元気だった頃は、よく一緒に遊んだり、喧嘩したりもしたわ。でも今は、具合が悪くなるかもしれないって、あまり外に出させてもらえなくなってしまって」
彼女は悲しそうに、少し俯いていた。私はそれを見て少し考えてしまった。彼女の妹が元気になる術に、心当たりがない訳ではない。しかし、その方法を教えることに関しては、あまり乗り気ではなかった。結局その日は何も言わずに、彼女を見送った。
〈承〉
その頃、人間の世界では不穏な影がちらついていた。人間という生き物は、お互いに争わないと生きていけないものらしい。度々戦をしては、領地や人々を奪い、また奪われて嘆く姿を、私は幾度も目にした。それはもう、人間の性、というものなのだろう。竜には竜の掟、人には人の掟があるものだ。私はそう考え、いつも人間たちの争いごとを、遠くから眺めていた。
……私がこのように彼らを一歩引いた目線で見ていたのにも、一応の理由がある。それは我々の生存理由にも関わることだ。
お嬢さんもあの街に住んでいるなら、大人たちにこんな話を聞かされたことがあるだろう。山を必要以上に荒らしてはいけない。特に山深くにある湖には決して行ってはならない。そこには古くから白い竜が住んでいる。竜は特別な力を備えていて、その鱗を煎じて飲んだものは、どんな願いでも叶えられるという。しかし彼は獰猛な性格である故に、近づく生き物には皆容赦なく襲い掛かるだろう。
……そこがここの湖であることは、君も知っての通りだと思うがね。
よくある話だ。少なくともここ最近、五百年程では。それより以前は、人も竜も、もっと上手いことやっていた。人々は我々を敬い、我々は人々を助け、お互いに愛し合っていた……少なくとも私は、そう考えている。
だが、自らの文明を発達させていくにつれて、人々は我々がどのような存在であったのか忘れてしまった。今となっては、我々の持つ強大な力だけを誇張し、信じることに決めてしまったようだった。我々は、人間たちの選択に落胆した。このまま人間たちとの関係を続けていても、いずれは何かのきっかけで、諍いが起こる未来が見えている。……我々は姿を消すことにした。衝突を避けるために、我々は人間たちに、必要以上に介入しないことを掟とした。そして、我々にとっても、さすれば人間にとっても、寂しい平和が訪れたのだ。
私は悩んだ。本来ならば、我々は人間に肩入れすべきではない。しかし同時に、私自身の感情では、あの少女を助けてやりたいと思っていた。
次に娘が来た時、私は意を決して彼女に尋ねた。
「君の妹の具合はどうかね」
「……あまり良くないみたい。最近はベッドで横になっていることが多いの」
「そうかね」
私は助けてやりたいという気持ちの方が大きくなっていた。
「今度の満月の夜が明けたら、またここに来ると良い。きっと君にとって良いことがあるだろうから」
「良いことって、一体何かしら」
「来たらその時、種を明かしてみせよう」
「……分かったわ。じゃあ、楽しみにしているわね」
彼女は本当に楽しみにしているようだったよ。何故なら、満月の次の日が来るまでの間、私のところにやってきては、種明かしをせがんでいたからね。そんな時私はいつも、その日になったら分かると言って、秘密を守り通していた。
……冬の満月の夜。その日は雲一つなく、空気は冷たく澄み渡っていた。私は準備を整えてその時を迎えた。
人間たちには忘れられていることだが、我々は脱皮をする。私の場合は一年に一度。この満月の夜が、その時だったという訳だ。
この時期になると、私はいつも神経質になる。古い皮を綺麗に脱ぎ捨てられなければ、身体に違和感を抱えたまま生活することになるし、飛ぶのにも支障が出る。また、竜にとって脱皮することは、一種の験を担ぐ行為を担っていた。上手く皮を脱ぐことができれば、次の脱皮の時期までは心穏やかに過ごせる。ここは急がず、丁寧に仕事を終えねばならない。
根気良く取り組み続けたおかげか、滞りなく事は終わった。一年を共に過ごした私の殻が、入り江に静かに横たわっていた。
次の日の昼過ぎ、彼女は来た。私は新しく生まれ変わった身体の調子を、確かめ終わった頃だった。
「やあ、お嬢さん。来たのかね」
彼女は私の抜け殻を見て驚いていたようだった。そして皮を脱いだことによって、以前にも増して白く輝いている私を見て、目を細めていた。
「真っ白……いえ、白というより、白銀かしら。綺麗ね」
彼女が震えるような溜息をついていた様子が、今でも私の中に鮮明に残っている。
「お嬢さんにお願いがある。そこに置いてある抜け殻の、目に当たる部分の鱗を取って欲しいのだ。良いかね」
「ええ」
彼女は頷いて、目の鱗を取ろうとした。小さな手で押すと、鱗はまるで待っていたかのように外れて、少女の腕の中に落ちた。彼女は両腕で抱えながら、私に向き直った。
「ありがとう。……実はそれを君にやりたかったのだ。受け取っておくれ」
「どうして私にこれを……」
「竜の瞳の鱗は、君の願いを叶えてくれる。鱗を煎じて飲みなさい。妹の回復を祈りながら、毎日一ヶ月飲み続ければ、きっと君の妹の病は、すっかり良くなるよ」
それを聞くと、彼女はたちまち笑顔になった。私も嬉しかった。彼女の喜ぶ顔を見られたのだから。
お嬢さん、黙って聞いてくれてありがとう。昔のことをこんなに長く話してしまうなんて、私はきっと、誰かに自分の話を聞いて欲しいと、どこかで思っていたのかもしれない。そして自分自身の心の整理のためにも、話さなければならないと感じていたのだろう。……もう少し続きを話しても、構わないだろうか。
〈転〉
とうとう、戦の影が足下に迫ってきていた。真夜中、人間に見つからないように空を飛んでいると、街に明かりが灯されているのが分かる。静かな夜の時代は終わり、街の空気が張り詰めているのが遠くからでも見通せた。
あれから一週間、彼女は私の湖を訪れていない。いつもなら、三日に一度は顔を合わせているというのに。彼女が来ない一日は、時間が経つのが遅く感じられた。彼女に出会った以前と以後で、私の中にある時の流れ方が変わってしまったようだった。
このような状況では仕方がないだろう。何せ、いつ敵が襲ってくるのかも分からないのだから。私は彼女が再び笑顔で尋ねてくることを願うしかなかった。そうだ、今度彼女に会った時、元気になったらぜひ一度君の妹の顔も見させてくれと、言ってみようか……。
それからまた、しばらく退屈な日が続いた。その間に幾度か街でいざこざがあったようで、騒ぎの声が私の下にも飛んできた。私は森の奥深くで動かずに、神経を尖らせて様子を窺っていた。
次に彼女が来た時、私は笑った顔が見たかったのに、彼女は泣いていた。その理由を知るために、私は彼女が落ち着くまで黙ったまま、側で見守り、寄り添うことにした。
やがて彼女は口を開いた。
「街で、戦いがあったの。知らない男の人たちがやってきて、街の人と喧嘩し始めた。お母さんたちと子供たちは、みんな怖がってたわ。それから、怒った男の人たちの誰かが、葡萄畑に火を点けようとして。私……私、どうしよう」
私はただ頷いて聞いてやった。幼い少女の顔が真っ白になっているのは、見ていて痛々しい。彼女は張り詰めた緊張の糸が切れたかのように、突然がっくりと膝を突いた。
「私、みんなを助けたい。怪我した人たちを治したいし、葡萄畑も守りたい。戦いなんてやめて欲しい。でも、妹のことだって……」
「……戦は、終わらんよ。終わらせることは、できない」
「なら、力が欲しい! この戦いを終わらせる力が! そうすればきっと、何もかも上手くいくわ!」
彼女は吼えた。悲しい叫びだった。そして私は、非情だと分かっていながらも、冷たい答えを返さなければならなかった。
「……戦いを終わらせようとすることも、力を欲しようとすること、全ての願いを叶えようなど、今の君には過ぎた願いだ」
「ねえ、お願い、助けてよ……」
「……掟に反する」
泣きながら彼女は行ってしまった。しばらくの間、私は物思いに耽らなければならなかった。
その後彼女は、自ら私の下を尋ねなくなった。なんとなく気が塞いでいた。日に日に嫌な予感が、心臓を通して血管中を巡っているようだった。
あの日、電流が体中を走り抜けたような感覚で、私は飛び起きた。その瞬間、頭のなかで最悪な答えが閃光のように迸り出た。私は急いで元凶の下へ風を切り裂き飛翔した。
街が怒りと恐怖に燃えている。
「ああ、なんと愚かな」
私は誰にという訳でもなく呟いたつもりだった。しかし、愚かなのは私だった。
葡萄畑は焼き払われ、レンガの家々は瓦礫となり、石畳は打ち砕かれていた。その間に人々がまばらに倒れ、あるいは逃げ惑っている。
あの娘は……娘は。
……いや、続けさせてくれ。あの娘は……もはや人ではなくなっていた。指先からは鋭く尖った爪が生え、皮膚の一部は艶やかな鱗を纏い、背には翼が生えていた。竜のようで……しかし、彼女は竜ではない。
彼女が竜に成りきれたのは下半身のみだった。上半身は未だ人のまま、かつて美しかった髪は逆立ち、麗しかった肌はくすみ、優しかった目は獣のように攣り上がっていた。彼女は怒りに支配され、自我を失っている。そして彼女が守りたいと思っていたものさえ、自らの力で傷つけていた。
私は悟った。彼女は願ったのだ。我が鱗を捧げ、力が欲しいと。自分の周囲を不幸にする全ての障害を排除できる、竜のような力を授けよと。
私は娘を、悲しい性を持つ人間として生まれた娘を、愛おしく思った。
だが、感情とは裏腹に、私は役目を果たさなければならない。こうなったつけを自らの身を持って払わなければならない。
「娘よ。人間は神には成れぬのだ」
もう彼女に言葉は届かないことを私は知っていた。私は自らの炎によって、娘に裁決を下した。
竜ほどの力を手に入れて、全ての望みを叶えようとするなど、例えそれが誰かを護りたいという純粋な思いであれ、人間という身ではしてはならない願いだ。彼女は神の怒りに触れ、呪われてしまった。娘が禁じられた願いによって罰を受けるなら、私自身もこの災厄をもたらした責任を負わねばならない。
我が炎に包まれて、娘は燃え上がった。その熱さと苦しみのあまり、もがき苦しみながら。終わりのない怒り、悲しみ、そして救いを求めて、彼女は壮絶に身をくねらせていた。やがて炎の中でうごめくものは塵さえもいなくなり、炎で焼き焦がした跡には灰さえも残らなかった。私は呪いを受けた彼女が存在した証を全て消して、街を後にした。
〈結〉
それから、私は再び退屈な日常を取り戻した。人間に比べれば、死とは無縁に思える身であるというのに、竜の暮らしというものは、人間よりも遥かに生を全うしていないものだということを、私は思い知った。
彼女は竜の力強さから来る美しさに憧れていたが、私は人間のように、か弱きものほど、矛盾を抱えて生きるものほど美しいと思う。愛おしいと思う。互いに支えあっていても、時には無常にも倒れ伏す儚さ、生き急ぐからこそ閃く命の輝き、己が弱き故に知る優しさ。そして未熟ゆえに高ぶらせることのできる怒りと悲しみ。ああ、私には持つことのできないものだ。
私は彼女の、人間らしさが羨ましかったのだな……。
私は長く生き過ぎた。生涯の道の半ばで、あれほど大切だと思った彼女の名も、彼女が付けてくれた私の名もどこかに置き忘れて、ここまで生きてきてしまった。重大で残酷な失態だよ。どうやら竜の本能は、私個人の意思を尊重することを決して許さないようだ。私は変わり果てた娘の姿を見た時、本当なら絶望するべきだった。人間のように悲しみに溺れてしまえば良かった。
しかし実際のところは、私は人間よりも、遥かに冷酷で、残忍だった。理性で愛するものを殺せるのだから。
……ああ、お嬢さん、最後まで話を聞いてくれてありがとう。誰かにこんなに話を聞いてもらったのは久しぶりだよ。
――あなたはそれから、ここにずっと一人でいるのですか。
恐ろしい竜が住んでいるというのを知っていて、ここに近づくものはほとんどおらんよ。力試しや興味本位で来る者がいても、結局は私の姿を目にした途端、恐怖におののき逃げ帰る。私もあれから、湖の底に引き篭もっていることも多い。また悲しみを増やしたくはないし、なんだかとても疲れるようになってしまってな。
――では、どうして私の前に、あなたは姿を現したのですか。
……どうしてだろう。あえて答えるなら、直感か。信じるべきではないということは分かっているのに、私は私を、もう一度信じてみたくなったのかもしれない。なんとなく、君の気配が、あの娘と似ているような気がして。彼女に会えるような気がして。
ああ。お嬢さん、できることなら、どうかその唇で、彼女の詩を詠って欲しい。綻びて忘れてしまった記憶を、その声で紡ぎ直して欲しい。
――私はあなたの忘れた詩を知っています。何故ならば、彼の娘と同じ血を引く者だから……。
頼む。詠っておくれ……。
――……。
――過去を思い
明日に祈る
ただひとつ
平和を永久にと
我が営みの成果を分け与える喜びを
君の慈しみを授かる喜びを
我が君よ
いつの世も 我と共にあれ
我と永久の輪を結びたまえ
君に祈りよ届きたまえ
我が思い叶うならば
我は君に詩を贈ろう
我が君と共に
今日を喜びあうために……
おお……あの詩だ。もう一度この詩が聞けるとは、まるで夢のようだ。……少し疲れた。このまま私が眠るまで、詩を詠っていてはもらえないだろうか。久しぶりに心が少し晴れた気がするよ。お嬢さん……ありがとう。
〈エピローグ〉
……。
――エテルネ……。眠ったまま、聞いていて。
……。
――私は竜と共に生き、命を渡り歴史を繋ぐ人々の末裔。メルは……あなたの娘は、あなたを責めてなどいなかったと聞かされています。あなたは自分が傷ついていることすら気づいていないのでしょうけれど……悲しみにくれたあなたの姿を知ったら、メルはきっと心を痛めることでしょう。
――あなたの意思とそれを許さない掟に、もがき苦しむ必要は、もうありません。苦悩から解き放たれ、その心に負った傷を癒すため、今は深く眠ると良い、エテルネ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
