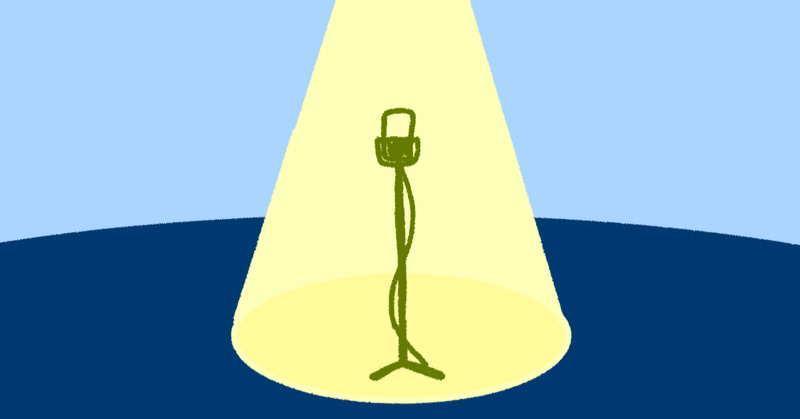
(お)笑いと男子校
第19回M-1グランプリ決勝セカンドラウンド。ファーストラウンドを1位通過したコンビ「さや香」は、1票も得ることなく敗退した。実際、さや香のネタはほとんどウケていなかった。スベッていたというより、何がしたいのか伝わらなかった。
審査員7人は皆「令和ロマン」か「ヤーレンズ」を選び、4票を勝ち取った「令和ロマン」が優勝した。芸歴6年でのM-1優勝という偉業達成の瞬間に、誰もが圧倒されたことと思う。
テレビの残り中継時間は30秒ほど。そんな中、審査員の1人、山田邦子がこう言った。
さや香の最後のネタ、全然良くなかった
会場は爆笑に包まれる。「みんな思ってたことをよく言った」とばかりに。
この発言がなければ、さや香の二本目のネタについて話すことは、少し難しくなっていたように思う。腫れ物のような扱いをされていてもおかしくなかったと思う。さや香の二本目のネタは、山田邦子によって「バカにしても良いモノ」へと昇華された。
山田邦子が行ったのは、さや香に対するイジリである。お笑いに限らず、「イジリ」は笑いの少なくない割合を占めていると思う。
さや香が実際どう思ったかは知らないが、「イジられる」側にとって、「イジリ」はどう見えるのかを考えてみたい。
第一に、「痛いところつくんじゃない」という、恥ずかしい気持ちになるかもしれない。普通の反応だと思う。みんな空気を読んでスルーしていたのに、それをほじくり返すようなことをされて、わざわざ恥をかかせないでくれと思うのが、普通の反応な気がする。
第二に、「ありがとう」という感謝を抱くこともあり得る。さや香の例でいえば、彼らは決勝でわけのわからないネタをするという結構な失態をしたわけだが、イジられることによって完全な腫れ物扱いからは逃れることができる。何も言われないよりは、馬鹿にされて笑われた方がマシだ。この記事によると、これはお笑いでよくある技法らしい。
イジリは相手の痛いところをつく攻撃的な側面もあれば、相手の気まずさを緩和させる回復的な側面もある。相反する効果を持つ技法なので、イジリをする人は相手との関係や気持ちやどんな聴衆がいるのかなど、結構いろんなことに気をつけてやらないといけないと思う。イジリは高度技術。
イジリには気まずさを緩和する効果がある。さらに、「自分は相手に正直に向き合っている」というメッセージを伝えることができる。たとえば、文化祭の出し物としてダンスをやった友人が大失敗したとしよう。これに対して後から「ダンスすごく良かったね〜!」と言うのはあまりにも白々しく思える。こんなことを言われても、「いや大失敗したんだよ、見えすいたお世辞はやめろ」と思わないだろうか。それに対して、「半年練習した割に下手だったな」と伝えれば、言われた側は「こいつは思ったことを正直に言ってるな」とは思うだろう(この発言に怒るか悲しむかはおいておいて)。
このように、イジリには①気まずさを緩和し②相手に正直に向き合っていると伝達するというプラスの効果がある。
イジリによって相手の気まずさを緩和させるという手法は、男子校的な文化によく見られる傾向だと思っている(自分は中高男子校出身です)。男子校には、相手の失敗を正面から受け止めるのではなく、斜めから笑うことによって、失態を犯した人を迎えいれるような文化があると思っている。男子校や男子校的な文化を持つ集団では、誰かが何か失態を犯した時に、同情や慰めではなく、イジリや相手を馬鹿にした笑いによって気まずさを取り返すことが多いように思える。
その背景には、「同情や慰めは『女性的な』行為であり、男同士のコミュニケーションは面白さや笑いによって行われるべきだ」といった規範があるのかもしれない。あるいは、単に男子校の生徒は適切な同情や慰めの仕方を知らない、というだけなのかもしれない。
失敗した人を認めてあげるのであれば、イジリよりも同情や慰めといった手段の方が優れている。感情的なコミュニケーションを排除するホモソ男子校コミュニケーションはなくなるべきだ!
こんな安直なことを考える人がいたら、なくなるべきはコミュニケーションの取り方を相手によって考えられないその姿勢だと思う。
確かに、イジリによって笑いの対象にされ、自分の失敗が馬鹿にされるのは、いつもいい気持ちかと言われたらそんなことはない。普通にうざいこともある。しかし、失敗をしたこっちの感情を3倍くらいに増幅して同情してくる胡散臭いやつよりも、ゲラゲラ笑われて馬鹿にするやつの方が正直で信頼できる。イジリも同情もコミュニケーションの手段でしかないので、自分のできる方を全ての人に押し付けるのではなく、相手との関係や状況に応じて適切な方を選んで使えるのが、真のコミュ強である。
結論、山田邦子はすごい。
よろしければぜひ
