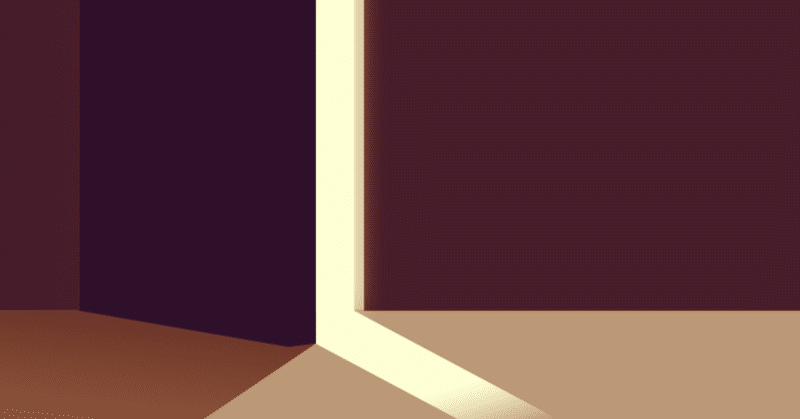
認知症介護小説「その人の世界」vol.9『暴力人間ですか』
その女の子は突然泣き出してしまった。
「私もう、ここを辞めようと思っているんです」
トイレでの出来事だった。
その少し前、私はお尻のあたりに何やら生ぬるい違和をおぼえ、座っていることができなかった。濡れたような感触は焦燥感に姿を変えて私の脚を操り、気づけば私は広い建物の廊下を歩いていた。
「キクさん、座って」
私の腕を後ろから掴んで言ったのは若そうに見える男性だった。
「やめて」
男性の手を振りほどこうとして私が肘を回すと、男性は私の脇を抱え込んだ。
「そんなに歩いたら転ぶから」
「転ばない。大きなお世話」
男性を振りきろうと私は足を速めた。すると男性は後ろにまわり、私の腰に鼻を近づけた。
「ああ、分かった」
「何が」
返事もせずに男性は私の腕を引くと、引き戸の奥に私を押し込んだ。
「何するのっ」
私の声を聞いているのかいないのか、男性は言った。
「はい、キクさん。座るよー」
いきなり後ろから私のズボンと下着を下ろすと、男性は力づくで私を坐らせた。それが便器だと気づくのに、坐ってからしばらくかかった。
「やめてっ」
下半身があらわになった私は、それを隠そうと必死でズボンに手をかけた。すると男性はその手を掴んでから、私の浮いた腰を便器に押しつけた。
「動かないで」
男性が声の音量を上げた時、私の背すじは凍りついた。殺される、と思った。
「誰かーっ。誰か来てーっ。警察を呼んでーっ」
死にもの狂いで私が腕を振り回していると、そこへ現れたのは若い女の子だった。
「大丈夫ですか?」
女の子の存在に男性が気づいた。
「ちょっと手伝ってっ。動いちゃってすごいから、押さえて立ち上がらないようにしてっ」
「はっ、はいっ」
女の子は両手で私の手を包み込むようにつないだ。強引に押さえつけることはなく、温めるような握り方だった。女の子は腰をかがめて私と目線を合わせると、言葉を丁寧に区切りながらゆっくりと言った。
「キクさん、ごめんなさいね。ちょっとだけ、私とこうして、手をつないで頂けますか。怖いですよね。すぐに終わりますからね。お洋服が汚れているので、取り替えています。きれいになったら、出られますからね。ごめんなさいね」
女の子の言葉から事情を理解したわけではなかった。ただ、殺されるわけではなさそうだということは何となく分かった。
「ああ終わった。もう、引っかかれちゃったよー。すげえ暴力行為激しい。じゃあ、後はよろしく」
男性がため息をつきながら姿を消すと、私は隣にしゃがんだ女の子とトイレに残された。
「どうして……」
安堵なのか、混乱なのか、怒りなのか、今の自分を支配しているものの正体がよく分からなかった。ただ、この声のふるえを受け止めてくれそうな女の子の存在が救いだった。
「もう少し、坐っていますか? 私は、いない方がいいですね」
女の子が申し訳なさそうに語尾を弱めた。私は言った。
「いてちょうだい。あなたがいてくれて良かった。本当に良かった」
私が顔を上げた時、目に映ったのは深く俯いた女の子の姿だった。
「ありがとうございます……」
女の子の声は潤んでいた。泣いていると分かった。
「私もう、ここを辞めようと思っているんです」
肩をふるわせて泣き出した女の子を私はじっと見つめていた。黙っていることが許されない空気が横たわっていた。
「よく分からないけど……何かあったのね」
私が言うと、女の子は俯いたままこっくりと頷いた。
「私、何をやっても怒られてばかりなんです。何をやっても時間がかかるから……」
「時間がかかるのは、丁寧ということじゃないの?」
「余計なことをするなと言われます。皆さんのお話しをよく聞こうと思っているだけなんですけど……」
女の子は鼻水をすすった。私は俯く彼女の黒々とした髪に視線を下ろしていた。若さゆえの悩みなのだろう。私にもあった、こんな頃が。
その時、私の心の鍵が“かちゃり”と音を立て、薄く開いたドアの隙間から春風が吹き込むような感覚をおぼえた。
「時間をかけてはいけないこともあるのかもしれないわね。でも、あなたが間違っているわけではないのよ。あなたは正しいの」
女の子が微かに顔を上げた。私は続けた。
「じゃあ、あなたにあれこれ言う人が間違っているのかと言うと、それも違うのよ。私の夫はね、警察官だったの。警察官の妻って、人が思うよりずっと大変なのよ。どんなに小さなことでも、悪いことはできないわ。いつも人のお手本となるような振る舞いをしなくてはいけないの。それはね、警察官の妻という立場がそうさせるの。違う人と結婚していたらそんなふうには思わなかったでしょうね。
それだけ、人っていうのは立場とか環境に左右されるものなの。あなたにあれこれ言う人には、その人の立場とか環境での憲法があるわけ。それを信じていると、何が正しくて何が間違っているのか分からなくなってしまうのよ。その憲法を変えるのはとても大変なことね。私の夫もよくそう言っていたわ。組織には魔物がすんでいるんですって。一人で立ち向かうには到底かなわないって。だから若い頃の夫はじっと耐えて、おかしいと思ったことを決して忘れないようにしていたのね。そしていつか必ず、自分にチャンスがやってくる。その時が魔物に立ち向かい、憲法を変える時だって。よくそう言っていた。そして夫は署長になったのよ。
ものごとにはね、その時にはどうにもならないことがあるの。だからそういう時は、目の前のことを一生懸命にやることよ。自分が正しいと思ったことをね。そして、あなたにあれこれ言う人が言ったことをよく聞きなさい。あなたにとって耳の痛いことでも、有難いことなのよ。正しいことも、間違ったことも言われるでしょうね。でも、それが正しいかどうかよりも、その人がどうしてそういうことを言うのかが大事なの。
あなた自身があなたの考えをしっかり持って、人の言うことを誠実に受け止めていれば、必ず道は開ける。あなたにはそれができるわ。あなたなら大丈夫。だからあなたは、やりたいと思ったことを今はやればいいのよ。人を幸せにするには、まずは自分が幸せでなくてはね。幸せの水がめが満たされていないと、人に分け与えることなんかできないのよ。だからあなたは、自分がやりたいと思うことを、やりたい人と、やりたい場所で、すればいいの。どんな時でも、あなたのことを見ている人が必ずいるから。
いい、認められるというのは、それそのものに大きな意味があるわけではないのよ。大事なのは、誰に認められるかということなのよ。認められたいと思う大切な人を見つけなさい。あなたはいつでも幸せになれるし、幸せになる権利がある。それはあなたが決めることなのよ」
夢中でしゃべっていた。とめどなく言葉があふれた。そうだ、同じことを息子にも繰り返し言って聞かせてきたのだ。
小さく開いていた心のドアはいつしか開け放たれ、その先には懐かしい景色が広がっていた。ネクタイを締めた若き日の夫の姿があった。少し曲がったネクタイを私が締め直すと、夫は顔をしかめて笑った。この人の妻であることが、私の誇りだった。
「ありがとう……ございます……」
女の子の顎からは、雪どけを迎えたつららのように涙がこぼれた。その涙の純真さに胸を打たれた私は目頭を押さえた。
「私は、あなたがいてくれて良かった。そう思っているのは私だけではないと思うわ。若いからできることもあれば、できないこともある。でも、輝けるということに年は関係ないのよ。あなたの笑顔があると、まわりが明るく見えるわ」
「キクさん……」
女の子は顔を上げ、私と視線を合わせた。
「私、がんばります」
そう言って、女の子は晴れやかな笑顔をつくった。ああ良かった、と私は胸を撫で下ろした。
そこで、ずっと気になっていたことを口にした。
「ところで……」
「はい」
「パンツ、履いてもいい?」
女の子が私の股を見下ろすと、私たちは同時に笑い声を上げた。
※この物語は、介護施設を舞台に書かれたフィクションです。
【あとがき】
「立たないで」「坐って」などの行動を抑制する言葉は『魔の3ロック』のひとつ、スピーチロックと言われるものです。抑制というとフィジカルロック(縛る、閉じ込めるなどの物理的な抑制)のイメージが強いため、介護現場ではスピーチロックが軽視される傾向にあり、ドラッグロック(薬物による抑制)にも罪悪感が伴わないケースがあります。それらを受ける人の世界から見た時、同じ扱いを自分が受けたいと思うでしょうか。その人の言動には必ず理由があります。「暴力行為あり」とレッテルを貼る前に、理由を探ることが大切なのですね。
今回は少し長くなってしまいました。すべてのけなげな介護職の方々へ、心を込めてエールを送ります。ご利用者は見ています、そして分かっています。けなげなあなたのことを。
悲しみや苦しみ、切なさ、喜び、そしてきらめきは誰もが持ち合わせ、それは認知症であってもなくても同じです。より深い理解を得るため、物語の力を私は知っています。
※この作品は、2016年2月に書かれたものです。
私の作品と出逢ってくださった方が、自分の世界をより愛しく感じられますように。
