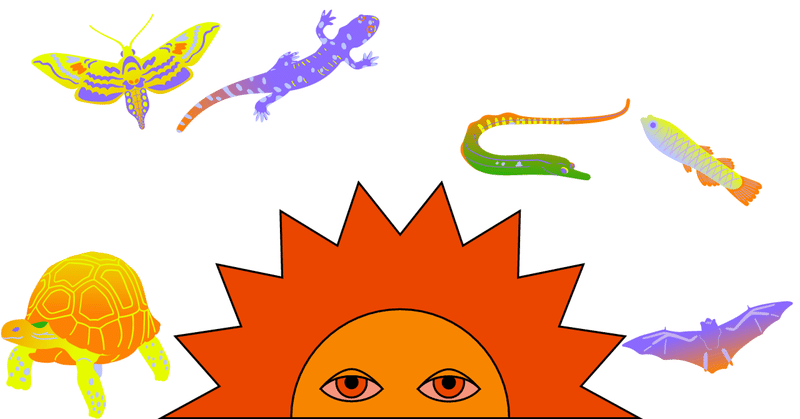
ベイトソンの生きた世界観③ サイバネティクスによる認識論の定式化
では、ベイトソンの世界観はいったいどのような点でこれまでのものと異なるのかを見ておきたい。それは、バーマンによる次のサイバネティクスによる認識論の定式化によって簡潔にまとめられている。
サイバネティクスによる認識論の定式化
(1)相互に作用しあう諸部分がひとつの全体をなし、その相互作用をスタ
ートさせるものが「違い」であること。
(2)これらの「違い」が、物質と空間と時間に属するものではなく、特定
の場に位置づけることができないということ。
(3)「違い」や、「違い」の変換形(「違い」がコード化されたもの)が
閉じた円環に沿って、もしくは経路のネットワークを複雑に進みなが
ら、伝達されること。このシステムは円環状もしくはより複雑であ
る。
(4)システム内で生じる出来事の多くが、それ自身のエネルギー源を持つ
こと。つまり、反応を引き起こす部分から衝撃力が与えられるのでは
なく、反応する側にその出来事を支える自前のエネルギーが用意され
ているのである。
バーマンはさらに「ベイトソンの世界観に内在する倫理観がもっとも明確に現れるのは、ベイトソンが自分の認識論を生物に適用するときである」と述べ、以下のような直接に倫理観にかかわる4つのテーマを掲げている。
(1)あらゆる生物は恒常的(ホメオスタティック)である。つまり、諸変
数を最大化しようとするのではなく最適化しようとするのである。
(2)我々が<精神>の単位として見てきたものは、実は進化における生存
の単位にほかならない。
(3)耽溺(addiction)と順化(acclimation)は生理学的に見て根本的に異
なっている。
(4)種の多様性は種の一様性よりも好ましい。
この4つのテーマのうち、(1)と(2)は循環性と不完全性というサイバネティクスのテーマの言いかえである。バーマンは、「デカルト的パラダイムによれば、(中略)意識は物質に還元可能なものとして捉えられ、つきつめて考えれば精神などというものはどこにもないということになってしまう」のに対し、ベイトソンの考え方においては、暗黙知を含んだ<精神>を持つあらゆるシステムを構成する情報の経路の、複雑きわまりない組合せ(そのなかには社会・自然環境も含まれることは言うまでもない)という人間システムの透過性をできるだけ高めることが目標となっている」としたうえで、「この目標を成し遂げたからといって、自我、すなわち実に見える弧が消滅してしまうことにはならない。むしろそれによって、自我がコンテクストのなかに位置づけられ、より大きな<自己>の小さな一部分として捉えられるようになるのだ」ととらえている。
さらにバーマンは環境へのかかわりについても次のように書いている。
叡智とは、ベイトソンによれば、循環性を認識し意識の支配力の限界を悟ることである。部分は決して全体を知ることはできない。部分にできるのは——叡智の声が響けば——全体に奉仕することだけである。
ではこうした考え方は、(1)とどうつながるのか。それはこういうことだ。情報が循環する回路も生物と同じように恒常性を持つシステムであり、そのシステム内のひとつの変数だけを——たとえば「精神」「意識」「目的合理性」などと呼ばれる変数を——最大化させようとすれば、システムは暴走状態に陥ってしまい、自らと自らのまわりの環境を破壊してしまうであろう、ということである。生物のシステムも本来的にそうした構造になっている。
(中略)合理的意識、利益、権力、技術、国民総生産、これら大きければ大きいほどいいと我々は思い込んでいる。だがサイバネティクス的に見れば、そうした考え方は自己破壊的であり、愚かというほかない。目的ということに我々がとらわれるほど、自己というもののサイバネティクス的本質が見えにくくなる、とベイトソンは指摘している。サイバネティクスは、「安定」と「変化」の本質について鋭い洞察をもたらしてくれる。変化というものが実は、安定を維持する過程の一部にほかならないことを教えてくれるのだ。これに対し、目的的行動、言いかえれば最大化をめざす行動は、循環性と複雑性を見えにくくしてしまい、行きつくところは漸進的変化——すなわち「暴走」である。
ここでのバーマンの説明は、外見的には環境問題へのアプローチとして同じように見えても、その意識がデカルト的な二元論的世界観の場合にはサイバネティクス的本質が見えなくなって「暴走」に走り、環境問題の解決にはならないと指摘しているのである。なぜなら、「西洋の個人主義は<精神>をはじめから混同してしまっている」からだというのだ。
サイバネティクス理論において、「回路」とはひとりの個人ではなく、その個人が埋め込まれた関係のネットワークである。むろん生きた有機体はすべてベイトソンの言う<精神>の規準を満たすが、あらゆる<精神>はつねにより大きな<精神>の一部であり、またそのなかにより小さな<精神>を内包している。(中略) 西洋の個人主義は、<精神>と下位<精神>をはじめから混同してしまっている。すなわち、人間個人の精神のみを唯一の精神として捉え、その唯一の精神が好きな変数を勝手に最大化してよいのだ、より大きな単位の恒常性などは無視してよいのだ、と思い込んでいるのである。これとは逆に、ベイトソンの倫理学は関係から出発する。さまざまな経路から成るネットワークを認識することから出発するのである。
バーマンは(3)の「耽溺と順化は生理学的に見て根本的に異なっている」の説明では、時代をとらえて次のような見解をあげている。
これは、恒常性を持つシステムが乱されたときに生じる事態を問題にしたものである。(中略)そもそも1600年以降の西洋の生活様式全体が、ひとつの大きな耽溺だったと言うことができる。これに対し、本書ですでに論じた過去の歴史から例をとれば、たとえばヘルメス的伝統は自己修復のフィードバックを持っていた。合理的意識、特に環境を支配しようとする側面は、つねに抑制されていた。言いかえれば、最適化されていた。それは、聖なる調和という理念のもとにつくられたシステムのなかの一変化にすぎなかったのである。だが科学革命の到来とともに、このたったひとるの変数を最大化しようとする流れが生まれた。それは聖なるコンテクストの外に引き出され、ほんの数世紀後には、かつては倒錯と思われていたものが正常とみなされるようになった。限りない拡張という理念が、フランス啓蒙主義と自由競争の経済理論に支えられて、道理にかなった理念と考えられるようになり、ますます多量の「薬」を求める欲求が、異常どころか物事の自然な秩序の一部とみなされるようになったのである。そしていま我々は、まったく耽溺状態に陥っていて、我々自身の自然のシステムを破壊しているまさにその変数を最大化させることに腐心している。このような時代に全体論的思考が出現したことは、自己修復的フィードバックの大きなプロセスのひとつの現れと考えてよいのかもしれない。
現在、私たちが時代のなかで見たり(あるいは行っている)全体論的思考の出現が、「自己修復的フィードバックの大きなプロセスのひとつの現れ」かもしれないというバーマンの考え方は、まさにベイトソン的であるといえるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
