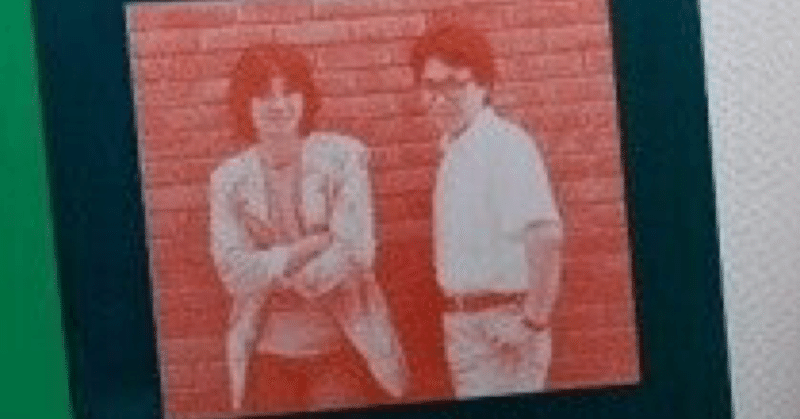
象さんのポット
不条理漫才の元祖、ボケツッコミを明確に分けないフリートークのようなスタイルの源流とも言える象さんのポット。今改めて観るとその掛け合いのシュールさナンセンスな空気感は現在の東京漫才の礎を築いていると思うと同時にその喋りの異物感はまだ時代が追いついてないと言えるとも感じます。
ネタ作りも担当していたとしゆきさんが主に会話の始まりというかきっかけのエピソードめいた小噺のようなものを唐突に淡々と話始めて、それに対して相方のひとしさんがその話を受けての一言コメントとその話をフリにしてさらに不条理を発展させるようなエピソードを当たり前のように話します。これを交互に行い続ける事で混沌を丁寧に積み上げていきゆっくりと聞き手を不可思議な世界へとどんどん没入させていきます。
スローテンポでありながらマイペース過ぎるテンポでもなく、どこか形式的な標準語を当時の若者だったとしても違和が残るようなイントネーションとシンコペーションでおかしみを増幅させ続けながら掛け合っていく手捌きは既存の漫才だと捉えて観るとコント的で、かと言ってコントだと思って観ると漫才の引き込み方になってるという、そのちょうど間の細かい位置にバランスを保ちながら立っていたと思います。
特にひとしさんの受けの上手さが際立っていて、としゆきさんの若干不安定な言葉の繋ぎ方でリードしてゆくのを破綻するギリギリのところで落として成立させる手腕がプロフェッショナルだと感じます。2人でおぎやはぎの矢作さんのリードと受けのツッコミを分担して空気感としてひとつにまとめあげる作業をしているような感じです。つまりそれは小木さんのような確固たる自分の進行スピードがあるタイプがいないという事でもあり、そこが象さんのポットの浮遊感の正体だとも感じます。
ひとしさんはサンドウィッチマンの伊達さんのオフのツッコミにも似ていると言われ、単純に声が近いのだと思うのですが語尾をもう少し強めて舞台映えするような所作や型を入れていくとさらに近くなるのではないでしょうか。逆を言えばこの時代のベースをズラしたテンポのツッコミ方は今だとスタンダードの中の球種のひとつになっている事が確認できる材料だと思います。
としゆきさんのネタ以外の部分での話し方を聞くと、思い出し気味というか言語より先に自分のリズムがあってそこに喋りを合わせていく事でメロディライン的なものを発生させているような感じです。ただそれで突っ走るわけでは無いので対峙した相手や空間にコミュニケーションを測りながらその返しの中での尺の限界値を引き伸ばすように話します。
これは井上陽水さんのやり方にも近いのですが、としゆきさんは先立ってコメントを入れてからオチまで引っ張る形式を取らずに、その素に近いような状態から思考をスタートさせているようなところがあります。松本人志さんがトークでボケるためにその発想をテンポの中に落とし込むのとは真逆の、会話の中で沸き立つ発想の方にテンポを寄せるようなニュアンスになっています。そしてそれがグダグダになりきる前に切り上げているところがテクニカルだと感じます。象さんのポットの漫才はわざとグダつかせているのではなく、寸前でグダつくかつかないかの所でキープしてそれをパッケージングしていた事に凄みがあります。
これがアンガールズやエルシャラカーニとかだとグダつかせる事が笑いのポイントになっています。象さんのポットはそのペーソスを淵の手前で漫才に仕上げるという難しい事を成し遂げていたと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
