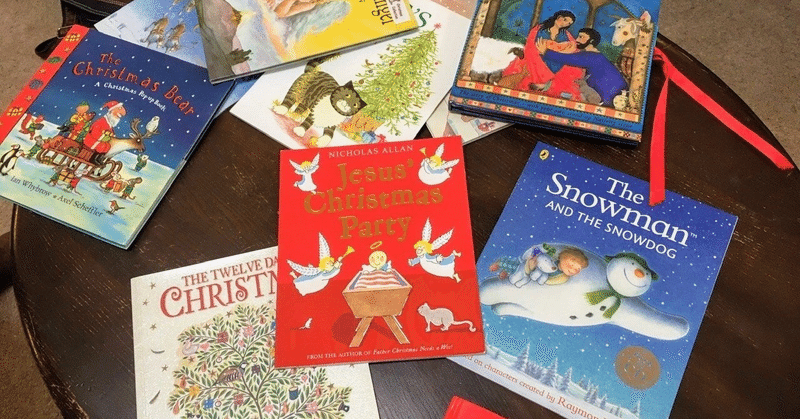
なつかしい絵本
紀行番組の一場面にはっとした。見覚えがある。あの噴水は実家の近くの公園だ。急に懐かしくなり、今もそこに住んでいる妹に電話をかけてみた。
「お兄ちゃん? 久しぶりね」スマホの向こうの声が落ちついたトーンで応える。妹は母が老いてからの子で10歳近く齢が離れている。私とちがって家族皆から可愛がられて育った。
「さっきテレビで見たんだけどあの公園ぜんぜん変わっていないよな」
幼いころよく遊んでやった場所だ。
「そう。ドラマのロケとかでたまにカメラ持った人が来ているみたいよ」
母が入院していた病院から近かったので車椅子で散歩したこともあったという。そろそろ命日ではなかったか。
「ああお母さんの年忌法要ね。忘れているわけではないけど。このご時世でしょう。お彼岸のお墓参りはちゃんと行っているわよ」
そのとき私は奇妙な錯覚にとらわれた。電話の向こうにいるのは妹ではなく亡き母ではなかろうか。それほど声音も言い回しも似ていたのだ。いつのまにか私を追い越して、手のかかる子どもをうまくたしなめる口調を身につけている。
「あのさ、一度そっちに行ってもいいかな」
二十代で一人暮らしを始めて以来実家から足が遠のいていた。電車に乗れば1時間あまりだが、ずいぶん敷居が高くなっていた。数日後、とうとう重い腰を上げた。
意外にも実家で私の物はきれいに保存されていた。本、CD、アルバムなどが本棚にぎっしりと並んでいる。
「持って帰ってもらえるとありがたいんだけど」あまり期待していない口ぶりだが、本当はすぐにでも片づけたい様子が見てとれた。とはいえ私にとっても実家は無料の倉庫だ。
「うちは狭苦しい賃貸アパートだからな。ここ以上に『ちいさいおうち』というわけだ」私は手にとったバージニア・リー・バートンの有名な絵本の埃をなぞりながらおどけてみせた。
「あら失礼ね。誰のせいで狭くなっていると思うの」
そうだ。ここはもう私の家ではなくなっている。私の蔵書は居候させてもらっているのだ。『ちいさいおうち』が『ちいさいおうち』であり続けてもそこの住人は住み変わっているのだ。
「この本ロングセラーだろ。今でも面白いと思うよ。タカシはもう読まないかな」確か甥っ子はそんな名前だったっけ。父に買ってもらった絵本はさほど汚れていない。この黄色い表紙は『せいめいのれきし』だ。大好きだった恐竜が出てくる。子どもたちにぜひ読み継がれて欲しい。
「『せいめいのれきし』は、2015年に改訂版が出たのよ。地質学とか天文学の研究成果を反映させたり先住民族に配慮したりで原文が修正されたの。だから惑星から降格した冥王星は消されているのよ」
何でそんなに詳しいんだときくと、ボランティアで近所の小学生相手に読み聞かせをやっているからという答えだった。絵本についてひと通りの研修を受けたらしい。
「だったら改訂される前の版はもう無価値だというのかい。そんなことはないだろう」
私は思い出す。これを初めて読んだときのわくわく感とぼんやりとした違和感。ここに登場する生き物たち、生活、人生のどれもが本当は自分たちのものとはいいきれないのだが、そのことにはあえて踏み込んでいかない方が良さそうな感じ。そりゃしょうがないよ。アメリカ人が書いたアメリカの話だもの、と言ってしまえば身のフタもない。もう一つの違和感とは、「せいめい」の話がなぜか途中から生活とか人生とかに変わっていくところだった。英語のlifeにそういう意味があるので、不自然ではない。けれども「せいめい」を額面どおりに生物とか進化の話として受け取ってしまうと、どうしてそっちに話が行くのだろうと思ってしまう。
あのころは夢をみていた。いつか私たちの暮らしがそこに合流して、公園にあるような木々や花にかこまれた煉瓦の家にすむ日がくると。高度経済成長期のアメリカの物質文明をどんどん取り入れていた戦後史の夢見る一幕である。つまりこれは日本にとっても一つの「れきし」なのだ。
私にとっては父に買ってもらった大切な一冊であった。妹は、母と再婚相手のあいだにできた子だ。私は新しい家庭の空気になじめないものを感じていた。畳だった部屋は板張りになり、座卓は椅子とテーブルになった。そういう時代だったのだが。
「荷物、処分するよ。長い間すまなかったな」
あらためて見る妹の顔は母にそっくりだった。
「お兄ちゃんたら。孫のタカシはまだ赤ちゃんですよ」
2021年4月「本」応募作
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
