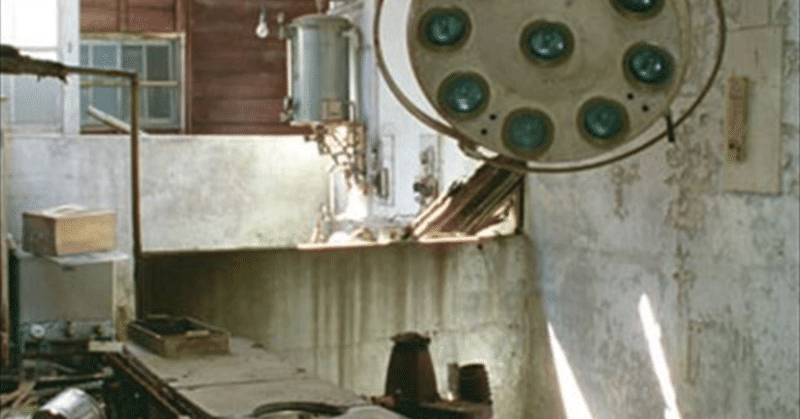
生きるとは死と隣り合わせなのだと今回の件で人類はまた学び直さなければならない。
『リスクを適切に恐れるというのは、かくも難しいことなのか——世界は今、百年に一度の災禍に見舞われている。このパンデミックについて、さまざまな「専門家」が、それぞれの立場から数多くの発言をなし、錯綜し矛盾する情報の渦のなかで、人々は右往左往させられている。誰もが例外なく生活世界の変容を経験し、時にはその生活基盤を失う脅威にさらされ、戸惑いながらもそれを受容したり、あらがったりしている。感染への不安と恐怖は、過去においても排除や隔離といった振る舞いを引き起こしたことがある。今回も、感染者やリスクの高い行動をする人々を過剰にバッシングする「自粛警察」と呼ばれる人々の行動が報道されたりもしている。以下では、アルコール依存や薬物依存の人々が排除の憂き目にあってきた歴史にも触れつつ、そうした行動の背景にある「感染への恐怖」について考える。戦争、飢餓、大恐慌……社会全体を覆う種々の災禍の中でも、伝染する病(疫病)は際立って特殊な地位にある。古くより幾度となく疫病の波に襲われ、ある意味では経験豊かなはずの西欧諸国が、経済を犠牲にしてまでロックダウンという「ハードな施策」に踏み切ったことも、今回の事態の受け止められ方の深刻さを示している。~ペストは後世になって、ネズミ(ノミ)が媒介となって拡大していたことがわかるのだが、何を媒介とするにせよ、人から人へと伝染し、なおかつ死に至る(可能性のある)病は、常に最大限の恐怖の的となる。その最終地点は人類の滅亡だからだ。『監獄の誕生』のミシェル・フーコーによれば、西欧世界がこうした大規模な疫病に対して取った対策は、伝統的には大きく二つしかない。「排除(追放)」と「隔離(閉じ込め)」である。~19世紀にパスツールやコッホらの尽力で病原菌の存在が指摘され、公衆衛生学が発達を遂げると、身体や場所を「清潔に保つ」という新たな手法が登場する。それまでは、手の上に目に見えない雑菌が存在するなど、人は想像さえしなかったのだ。この転換は、疫病対策が、個人・集団といった人間(の移動)レベルでの阻止から、よりミクロな細菌レベルでの阻止へと移り変わったことを意味していた。ところが、今回の新型コロナに関しては、まるで時の流れが逆行しているように見える。国内でも、2020年2月に横浜港に帰港した豪華客船は「隔離」の象徴となり、4月に全国に発令された緊急事態宣言は、人々に強い外出自粛を説いた。つまり人の移動レベルでの阻止という、古いメソッドが採られたのである。この逆行はいかにして起こったのだろうか。鍵になるのは「感染の恐れ」である。~こうしたどこか優生学的な学説は、無論現在では明確に否定されている。しかし当時の西欧は進化論と遺伝研究の流行期を迎えており、それゆえ大きな影響力を持ちえたのだった。同じような時期に、イタリアの犯罪人類学者ロンブローゾは、犯罪は遺伝する(犯罪者の子は犯罪者になる)との学説を発表し、凶悪犯の断種(去勢)までを主張していた。ある病が拡大を見せることと、それが伝染病であることとは、別々の二つのことであるはずだ。だが上記の例で見たように、特にその原因やメカニズムが不明な時期には、両者の混同はしばしば見られる。感染への恐怖や、拡大への社会的不安がそうさせるのである。話を現代へと戻そう。欧米諸国が次々とロックダウンに踏み切ったのは——もともとマスクをつける習慣がなかったのを差し引いて考えても——消毒液による殺菌などの、衛生状態を清潔に保つ方法が、さしたる効果を上げなかったことが直接の引き金だっただろう。ただ、さらに一歩踏み込んで述べるならば、より根本的な原因はこの病の未知性にある。今回「専門家」たちが相矛盾することを語り、各国政府の対応が後手に回るといった現象がしばしば見られたのは、端的に言えばこれが未知の病だったからだ。データの蓄積がないのである。過去のデータの積み上げを基に未来予測を行うのは、実証的な科学の基本的態度であり、今日ではビッグデータを用いた分析が華々しくなされている。しかしそれは裏返して言えば、統計データに頼りすぎた現代社会が、全く新しいケースに対しては無力化しているということでもあった。データとエビデンスを偏重するこの現代社会は、既知のものに対しては強いが、未知なるものに対して脆弱な、弾力性の弱い社会になってしまっているのである。未知なるものへの恐怖とは、すなわち、その振る舞いが予測困難なものへの恐怖である。社会学者アンソニー・ギデンズは『モダニティと自己アイデンティティ』の中で、近代以降の「逸脱」は社会的コントロールの観点から再定義されたと述べたが、これは言い換えれば、予測不能な動きを見せコントロールが難しいものに、「リスク」のレッテルが貼られ、人々の不安や回避行動、ひいては社会的排除を引き起こしていく傾向を指していた。~19世紀末にデジェネレッサンス概念を用いた精神科医マニャンは、「原則として遺伝的に変質した者に責任はないが、彼らは社会や人類に対する責任を負っている。なぜなら有害だからだ」といった奇妙な論理でもって、社会的弱者への非難を正当化していった。ひるがえって、現代の新型コロナ患者も、どこか似たような境遇に置かれていないだろうか。多くの人が正当に「患者」として扱われる一方で、感染者が自宅に投石を受けたケースもあった。また強い自粛ムードの中、「外出する人々」や「マスクをしていない人々」への非難は、どこか過剰なものになっていないだろうか。これらも元を正せば、病と病者との混同という誤謬に由来するものである。他人を感染させる恐れがある、つまり周囲に害悪を及ぼすリスクがゼロではないという理由で、それは恐怖の対象となっていく。しかし、病に罹患することに責任はない。ウィルスや病原菌にとって、人体はただの箱舟に過ぎないからだ。ごく例外的な、明確な悪意があるケースを除き、その責任は問われるべきではない。伝染する病が再び、人の移動レベルでの感染阻止という古いモデルで捉えられつつある。またそれに付随して、社会的弱者に対する新たな偏見や差別、社会的排除が生み出されつつある。しかも、もしそれが(時には誤ることもある)「科学」の説明を根拠に、また「正義」を振りかざしつつ行われるとすれば——我々はいま、歴史のあやまちを繰り返そうとしていると言わざるを得ない。感染不安の渦中にあって、リスクを適切に恐れるというのは、難しいことかもしれない。だがそれでも我々は、決してその努力を断念してはならないのである。』
ヒトは誰かの所為にして安心を得たがる。安心を脅かす恐怖がヒトをヒトデナシにしてゆく。死への恐怖を延命治療というベールで覆い誰にでも確実に訪れる死の恐怖をできるだけ遠ざけてきた。生きるとは死と隣り合わせなのだと今回の件で人類はまた学び直さなければならない。
新型コロナの「自粛警察」が抱いている「恐怖」の構造
アルコール、ドラッグの歴史から考える
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72493
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
