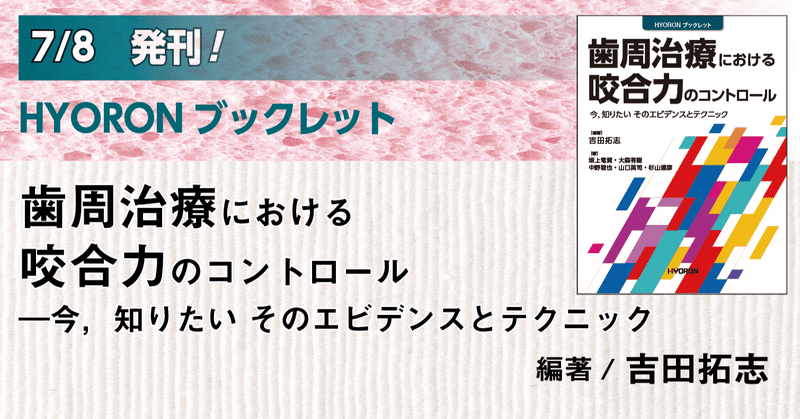
吉田拓志編著:『歯周治療における咬合力のコントロール―今,知りたい そのエビデンスとテクニック』より―はじめに
吉田拓志先生編著『歯周治療における咬合力のコントロール―今,知りたい そのエビデンスとテクニック』(HYORONブックレット)を7月8日に発刊します!
発刊に先駆けて「はじめに」をウェブ版として公開します.
吉田拓志/東京都大田区
とある歯科医師が「大臼歯のバランシングコンタクトと早期接触が原因で,ガイドとなる犬歯に動揺が生じた.これは大臼歯の咬合調整が必要な症例である.これは誰もが知っている常識だ」と語った.確かにそんな症例もあるだろうが,その治療にエビデンスはあるのだろうか.
そもそも動揺といっても原因はいくつかあるわけで,歯周炎による支持骨量の低下であれば歯周炎の治療,外傷性咬合による歯根膜腔の拡大があるなら動揺歯の咬合治療を行うべきであろう.「バランシングコンタクトや早期接触が歯周病に悪影響になるのは常識だから,咬合調整するべきだ」ということが,短絡的にまかり通っているようにも感じる.“誰もが知っている常識”が“エビデンスに基づいたこと”ではないことも,あるのではないか.
歯周病と咬合性外傷については,Glickmanが提唱した(1963,1965)「咬合性外傷は骨縁下ポケットを伴うくさび状骨欠損が1歯または複数歯に見られる場合の重要な病因である」という学説が日本において広まり,いまだに多くの歯科医師がこれを正しい認識としている.
そこで本書では,われわれが学生時代や勤務医時代に教科書や有名な先生から学んだ事項を“常識”とせず,第Ⅰ章ではその常識のエビデンス,特に咬合性外傷の研究の歴史から,現時点での信頼性の高い研究を整理,解説していただいた.
それを受けて第Ⅱ章では,5人の臨床家の一口腔単位の実症例を参照しながら,咬合力をコントロールするテクニックを解説している.また,各症例においては歯周治療だけではなく,インプラント,義歯,矯正,歯周補綴などのさまざまなアプローチをしており,補綴設計を含めた治療計画の立案や治療のプロセスにもバリエーションがあるので,ぜひ注目していただきたい.
過度の咬合力やそれを惹起する咬合様式が,かならずしも歯周組織の破壊をもたらすわけではないので,歯周治療に咬合治療がかならずしも必要ではない,ともいえる.しかしながら,すでに歯周病の進行が認められ,その進行が咬合力によって明らかに増悪しているときにどのようにアプローチすればよいのか,悩むことが多いと思われる.そのようなとき,本書がその臨床対応の手助けになれば幸いである.
2020年6月
編著者 吉田拓志
関連リンク
◆歯周治療における咬合力のコントロール
※シエン社でのご購入はこちらから
月刊『日本歯科評論』のSNS
LINE公式アカウント / Facebook / Instagram / Twitter
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
