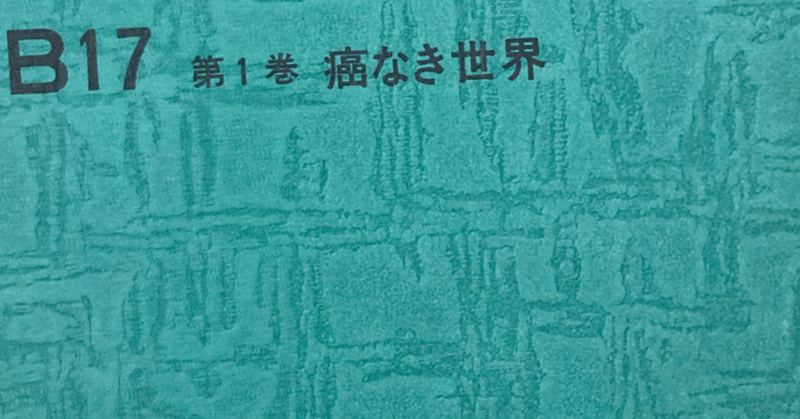
癌を抑制する栄養素を日常生活に取り戻す~「B17 癌なき世界」1章まとめ
「B17 第1巻 癌なき世界」(1979年初版発行 著者:G・エドワード・グリフィン 訳者:渡辺正雄、河内正男、小笠原治夫 監修:河内省一 ノーベル書房)の1章を紹介します。
1章 ウォーターゲート事件の症候群 抜粋
アメリカ人の”四人に一人”はその生涯のうちに癌にかかるだろう。しかし、人類にとって治しにくい悲惨な癌が、現存(※ブログ主註:原著初版当時1974年)の科学知識の範囲で完全に制御できることを、順を追って解説するのがこの本の目的である。
癌は壊血病やペラグラ(皮膚病)と同じように、必要不可欠な「特殊成分」が現代の文明食に欠けているために、発病したり、悪化していく病気であり、一種の栄養欠乏症なのである。また、癌を根本的に抑えつけるためには、ある「特殊成分」を含んでいる食物を日常生活に取り戻すことが必要である。
この本ですすめる特殊成分を濃縮してつくった特効薬は、残念ながらアメリカでは医薬品として認可されていない。FDA(米食品医薬品局)当局、アメリカ癌協会、アメリカ医師会では、たしかな根拠もなく、「インチキ」だと決めてしまった。しかも、あらゆる手段を使って、市民の真実を知る権利を妨害してきたのである。ビタミン理論を応用して患者の生命を助けようと努力する医師までも、容赦なく告訴するとおどかしてきた。
癌で死ぬ人以上に癌関係で生計を立てている人数は多い。こんな矛盾が、簡単なB17療法で解決できることになれば、巨大な医薬品業界や政治的な産業は一夜にしてつぶれてしまうだろう。
B17に対しての最もひどい中傷は、1953年に「カリフォルニア州医学」4月特集号として、カリフォルニア州医師会癌委員会が出した「B17は、癌を治すような働きの証拠を少しも示さないし、また、癌細胞に対してはっきりした制癌力ももっていない」とするにせ科学的報告書(以下カリフォルニア・レポート)。報告書に直接携わったのはアイアン・マクドナルド博士とヘンリー・ガーランド博士。癌委員会の構成メンバーは両博士とほか7人いるが、いずれもB17の実験には直接手を出していない。どこかで発表されたデータを勝手に評価しただけだった。
当時はまた、癌への懸念から業績不振に陥っていたタバコ製造業界がアメリカ医師会に多額の研究費を提供していた時期とも一致し、両博士は「喫煙は肺癌とまったく関係がない」と主張し続けた代表的医師であった。
マクドナルド博士は寝タバコが原因で焼死。ガーランド博士は肺癌で死亡した後の1963年、カリフォルニア・レポートには、薬効の鍵と言える基礎研究において、正反対の結論が出ていたのに、両博士がB17に肯定的な報告は無視し、否定的な報告を採用していたことがわかった。
また、複数の医師による対腫瘍効果を示した臨床例も無視し「B17が癌細胞に対して有効な毒性を与えた証拠は一つも観察されなかった」と断言していた。しかも当時のB17の投与量は現在考えられている適量の五十分の一、一回の投薬量はわずか五十~百ミリグラムだった。
1974年現在、B17を一週間から十日間で合計五十~七十グラム投薬すると、癌患者の容態は必ずよくなってくる。
カリフォルニア・レポート同様B17の薬効を否定したレベルが高い機関の発表は次の通り。
▽スタンフォード大学、1953年のプロジェクト▽国立癌研究所、1960年のテスト▽カリフォルニア大学バークレー分校、1961年の研究▽バークレーのダイアブロ研究所、1962年の研究▽モントリオールのマックギル大学、1965年の研究
五つの特徴として、多くは刊行物になっていない。多くの実験は腫瘍の大きさがどれくらい減ったかを測定している。人間の癌にB17を応用して腫瘍の大きさの減少ではなく、人命の延長に成功したかどうかによって、癌治療法の真の効用をつかまなくてはならない。
マックノートン財団のB17の第一次臨床テストのFDA認可申請が通った際、政治的影響力をもつ某大物が、FDAを電話で叱りつけ、試験を中止させた模様である。
FDAが「アミグダリンに毒性がないことを証明するはっきりとした資料が欠如している。人間の長期投薬テストをすることは危険と考える」との声明への三つの疑問点
①B17が無毒なのは周知の事実。何百年も議論の対象になっていない。
②新薬審査申請書の一部資料は人体での例証の歴史を示す。
③毒性問題はFDAが自ら承認している現代主流派の医薬や制癌剤の一切に、いつでも含まれている問題である。
これまでにFDAが認可した多くの制癌療法こそ、激しい毒成分が含まれており、B17だけが毒性問題で試験を拒否されることは、屁理屈の最たるものである。
<1章への個人的感想>
※1章のタイトルは、「ウォーターゲート事件は政府高官の噓八百に大勢の国民が気付いた」ことに由来します。著者G・エドワード・グリフィン氏は1974年の執筆当時(※ブログ主註:ニクソン引責辞任の年です)、ニクソン大統領側の盗聴事件としてとらえ、「政府高官の嘘がばれても、崇高な目的推進のために必要な処置と言い逃れするであろう」と書いています。
しかし、私自身は馬渕睦夫元ウクライナ大使がおっしゃる通り、所属記者がピューリッツアー賞を受賞したワシントンポストとFBIが組んだニクソン大統領追い落とし事件であり、スピロ・アグニュー副大統領の追い落としまで狙った共和党はめこみ事件とみています。
ただ、政府機関より大きな政治力が働いたという意味では、今でもこのタイトルに違和感はありません。
※本書の最初の挿入写真は、カリフォルニア・レポートに直接携わったアイアン・マクドナルド博士とヘンリー・ガーランド博士の顔写真です。B17研究や臨床に携わった人ではなく、「B17は癌に無効」報告の基となっている人が巻頭を飾っているのです。
カリフォルニア・レポート紹介の中で、腫瘍の大きさではなく、人命の延長で判定すべきというもっともな意見もありました。
「新版 どうせ死ぬなら『がん』がいい」(中村仁一、近藤誠共著 2018年宝島社新書発刊)の中で中村医師が「抗がん剤の認可基準というのが『画像診断でがんの面積が半分(最近は長さで決めるようになり、その場合は長径が7割)になった4週間続く患者が、2割いたらOK』ですからね。8割は縮小効果すらなくても認可されちゃうなんて、どうなんですかね」と疑問を呈しています。
カリフォルニア・レポートでは、マクドナルド、ガーランド両博士が「本質的薬効ではないが、(B17を投与した)患者の状態を再検討してみると、患者の気分がよくなり、食欲も増し、痛みも薄らいだ。」と渋々付け加えているそうです。
しかし、患者、家族にとって、一部の患者への一時的な癌細胞の縮小より人命の延長やQOL(生活の質)の向上の方が優ることは論を待ちません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
