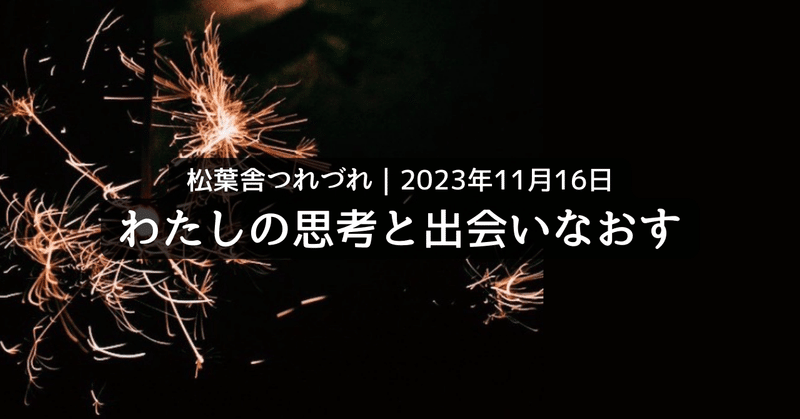
わたしの思考と出会いなおす|松葉舎つれづれ|2023年11月16日
ヴァイオリニストの本郷幸子さんが、先日ひらいた松葉舎ゼミに参加したさいの感想を寄せてくれた。
人に敢えて言うほどでもない。でもだれかとこのことを話してみたい。でも言ったら変だと思われるかもしれない。そういうものごとが、自分の心に時折さざなみのように起こる。そのさざなみを臆することなく隠さずに感じ続けられるような場だった。昔の自分はここにいたら救われただろうな。孤独だった。
「人に敢えて言うほど『でも』ない。『でも』だれかとこのことを話してみたい。『でも』言ったら変だと思われるかもしれない」。なんども繰り返される『でも』には、自分の思いや考えをひとに打ち明けるさいの迷いやためらいがありのままに表れている。
ダンサー/振付家の岩渕貞太さんをゲストにお招きした先日のゼミでは「言葉に触れるからだ」というテーマを軸としつつも、そのテーマに沿って一本道に言葉を紡ぐのではなく、流れの中で浮かび上がってくるときどきの思考をすくいとって、それに身をゆだねるように話を展開していたのだけど、そこで醸されていた空気感が『でも』といって固まりがちな心をほぐしてくれたという旨を本郷さんの言葉で書き綴ってくださっていて、松葉舎という場所が、そのようにして「行き場をなくしていた思考(*1)」 をすくう場所であって欲しいと願っているぼくには、感無量の言葉だった。
そんなあたたかな喜びを胸に感じつつこの言葉を反芻しているうちに、ぼくはいつの間にか、自分と常識、あるいは世間との関係を再考しはじめていた。
***
小さなころから世間の常識に馴染めなかったぼくは、学問の常識批判の精神にすくわれた恩があるのだけど、ついにはそうした学問的世界の常識にも安住できなくなり、松葉舎というあらたな探求の場をひらくにいたった。
その経緯については以前「自分のことばとからだで考える」と題した note に書いたのだけど、いま思うとこの文章を書いていたときのぼくには、自分のことを世間から外れた存在として捉える感覚があったように思う。自分は世間の常識になじめない、それは自分が世間から浮きたっているからだ、と。
だけど本郷さんの文章に触れて、それは違うのではないかと思うようになった(とまでは言えないのだけど、少なくともそれは事実の一面でしかないと思うようになった)。
常識に馴染めないと思っているのは、なにもぼくだけではない。本当は、誰しもが常識とのあいだに摩擦を抱え、悩んでいる。常識はこうだと言うけれど、わたしはそうではないと思っている。そして、本当は「だれかとこのことを話してみたい。『でも』言ったら変だと思われるかもしれない」。そうして逡巡しているうちに、わたしの中にたしかにあったはずの思いや考えは「人に敢えて言うほど『でも』ない」ものとして、そっと胸の奥にしまい込まれていく。
ひとの心の片隅には、そうしてしまい込まれ、忘れさられていった、数え切れないほどの思考が山積みになっているのかもしれない。
世間の常識というものは、必ずしも、世間の「大多数」の思考の平均値としてあるわけではない。むしろ、少なからぬ人がそこに違和感を抱き、馴染めないと思いつつも、そこから外れると「変だと思われるかもしれない」という恐れから、仕方なしにそれに付き合っている。だから世間の常識は、世間の総意とイコールではないし、場合によってはマジョリティの意見ですらないのかもしれない。
にも関わらず、常識に対する一人ひとりの違和感が胸のうちに隠されているために、その常識がどれほど人びとの思いから掛け離れているのかもまた、見えなくなっている。そうして世間の常識が、まるで世間の総意であるかのような顔をしてまかり通ることになる。ぼくたちは、みずから生みだしたみずからの望まない常識に捕らわれているのかもしれない。
***
だから、常識に対する違和感はしっかりと口にしていかなければならない——などと言いたい訳ではない。
ただ、こうしたことを考えているうちに、これまで自分と対立するもののように思われていた世間が、にわかに、たがいに手を差し伸べあって連帯すべき隣人であるかのように思いなおされてきた。世間の常識に馴染めないことは、かならずしも世間から浮きたっていることを意味しない。だれしもが世間の常識に違和感を抱きつつも、世間の一員として生きている。そしてぼくもまた、そうして世間を生きている一人なのだと。ぼくはようやく、はぐれてしまっていた世間——正確に言えば、はぐれたと勝手に思い込んでいた世間——とふたたび巡り会えたような気がしている。
それとともに、松葉舎がもつ社会的な役割についても、認識が変化してきた。これまで松葉舎のことを、ぼくと同じように世間からはぐれてしまった変わり者のための場所だと思っていたのだけど、そうではないのだと。一部の変わり者だけではなく、世間を生きている多くのひとが、人知れず、世間の常識に対して違和を感じている。感じていながらも、そこから生じた思考を、そっと心の片隅にしまい込み、そのうちにそれを忘れて、自分自身とはぐれてしまっている。
谷川俊太郎の「私はあらゆるおとなの中に、抑圧された子どもが生きつづけていて、それを解放することがおとな自身の解放につながると思っています」(『詩を書く』)という言葉を思いだす。
常識に抑えられながらも、ときおり心の奥底から「さざなみのように」浮かび上がってくる思考。それを、常識に抗おうという強い意志をもって口にする必要はない。だけど松葉舎は「そのさざなみを臆することなく隠さずに感じ続けられる」場所であり続けたい。そうして、はぐれてしまったわたしの思考と出会いなおすための場所として、これからは松葉舎を守り続けていきたいと思う。
***
最後に、尼ヶ崎彬によるピナ・バウシュへの評をここに置いておきたい。
廃屋の前を通り過ぎようとしていたら壁の割れ目に気づき、ふと覗いてみると、自分そっくりの人間が見覚えのない服装をして泣いているのが見えたとしよう。自分の意識は「あれは私ではない」と判断しているけれども身体の奥で「あれは私だ」という呟きが聞こえる。泣いている理由などわからないと理性は言うけれども、記憶の底に思い当たるものがあるような感触がある。そして向こうが泣いているのにこちらが泣いていないことに、なぜか後ろめたい思いさえしてくる。しだいに壁の向こうにいるのは「もう一人の私」であり、しかも向こうのほうが本当の人生、本当の身体であり、こちらにあるのは間違えた人生、偽造された身体であるような気がしてくる。なぜ自分は泣けないのか。それはこの身体がヴァーチャルな身体にすぎないからではないか。自分は人生が人生であるために必要なものをどこかに捨ててきたのではないか、身体が身体であるために欠かせないものを抑圧してきたのではないか。そんなことを考えているうちに忘れていたものを思い出したような、見えない束縛から解放されたような気がしてくる。そしていつの間にか眼から涙がこぼれている。ピナ・バウシュを見るとは譬えて言えばこのような経験である。それは身体が身体をみるということが戦慄的な経験でありうることを八〇年代の日本の観客に教えたのである。
ぼくはピナ・バウシュの振りつけた舞台を生で観たことはない。ただ、一度Youtubeでその踊りを目にして以来、一気にその世界に引き込まれてしまっていた。ふだんのぼくは、どれだけ素晴らしい絵画や踊りであっても、生でみないことにはその良さを実感できないのだけど、ピナ・バウシュは数少ない例外だった。そのことは、ぼくにとっての長らくの謎だったのだけど、尼ヶ崎さんの文章を読んで疑問は氷解したのだった。ぼくは、ぼく自身に出会いたがっている。ぼくがピナ・バウシュを好きなのも、松葉舎を主宰しているのも、根っこは繋がっているようだ。
*1 松葉舎に通ってくれている川尻優さんが「行き場をなくしたもの」への愛おしさを動機として服を作っている。その言葉にあやかって、ここでは「行き場をなくした思考」という言葉をつかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
