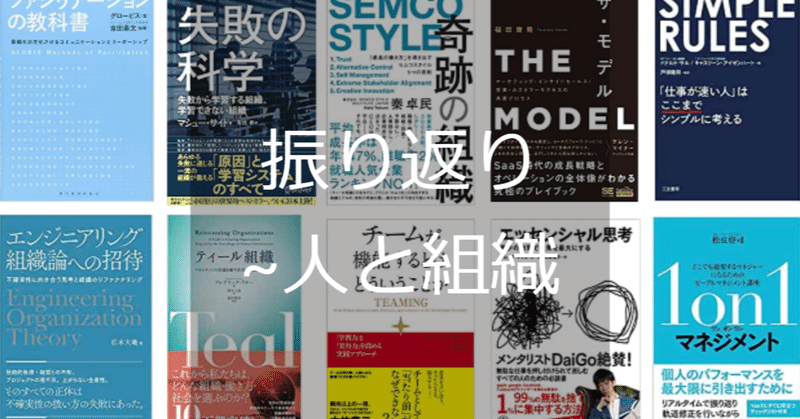
2020年の振り返り【インプット編】
今年は「人と組織を科学する」をテーマと掲げたわりには、積読が増えるばかりでインプットが圧倒的に足りていないな…という反省です。
セムコスタイル(SEMCO STYLE)との出会い
2020年を象徴する取り組みがSEMCO STYLEでした。自社への仕組みの導入も着手し、2021年が本格始動な感じです
オランダで研究機関が立ち上がり、日本法人は2年前。各地でのノウハウを蓄積し、アップデートしながら、各国の法人に対して実験を行なっている…というイメージです。(フレームワーク自体は完成しているので、用法と容量に関して実験中な印象)
セムコ社の事例紹介の『奇跡の経営』に対して、『奇跡の組織』なので、夢物語はあくまでも一例。思想や理想ではなく、組織変革のプロセスとフレームワークを学べます。
ティールっぽい文脈がふんだんに用いられているので、ティールがしっくりくる企業にはある程度、理解しやすいかもしれません。
ティール組織も、オーディオブックで流しましたが、これを読んで自社に展開できるイメージは掴めなかったですね。なので、ティール組織では、概念を掴む、要素を理解する位置付けでしょうか。
自主経営(セルフマネジメント)って結局なにか
ティール組織の全体性、存在目的についてはイメージが湧くのですが、セルフマネジメントが難しかった。そこで、自主経営(セルフマネジメント)組織の本を手に取ってみました。
・セルフマネジメントが正解ではなく、階層型(トップダウン型)組織との併用も視野に入れた発想が前提にあるとよさそう
・チームコーチ、フレームワークなど、セルフマネジメント型組織を徹底するには、組織の学習が欠かせない(コーチング、ファシリテーションスキルも要るなぁ…)
・全員がひとしく能力を持つわけではないので、後ろからサポートする体制や、理解し合える組織風土って大事かも
というような気づきを得ました。
セルフマネジメントについては、別でnoteに書いてみたので、よかったらどうぞ。
サブスクリプションビジネスとセールスプロセスを考えた
仕事編の振り返りで詳細に触れましたが、「サブスクビジネスってなんだ?」ってことを考えた1年でした。
サブスクリプションサービスに特化した管理システムZuoraを立ち上げた人が著者でした。「顧客中心」がキーワードで、Netflixなどの動画配信サービスやTimesなどのカーシェアなどの理解も深まります。
「財務/管理会計の考え方もこう変わる」というのも触れられているので、バックオフィス視点でのメリットも理解できました。なので、業務管理、数字管理の観点から見れるようにもなるので、オススメです。
Salesforceが推奨している営業プロセス。THE MODELでググれば、Salesforceの記事が出てきます。顧客中心のサブスクリプションサービスにおいては、上流から下流までのつながり、双方向の情報連携が重要。KPI設計の例などもあるので、あたらしくサブスクのビジネスを立ち上げたり、サブスク化するにあたって営業プロセスを見直すときに役立つと思います。(THE MODELを共通言語にしたら強くなりそう)
会議進行のフレームワークを獲得した本
今年は会議を行う回数が増え、特に、ファシリテータとして立ち回る機会が増えました。耐えられない空気を生んじゃうときや、「何の成果もありませんでした」で終わったこともあり、なんとかしようと思って手にとった本。
懇切丁寧に、準備から会議の招集、会議中の武器までも提供してくれています。僕は、準備と会議招集の段取りを中心に学びました。
・会議の位置付け、目的、ゴールを明確にする
・参加者の属性(どんな情報を持っているか)を想像する
・意見やアイディアを求める場合は「問い」を作っておく
・沈黙には動じない。
・その場で予定通りに決めなくても良い。(延期、再設定もOK)
物語でファシリテーションをイメージしたいのであれば、以下の本がオススメ。
僕は、オーディオブックを入口に読みました。物語形式は、オーディオブックとの相性が最適ですね。
組織を学ぶためにちゃんと読んでアウトプットしたい本
「人と組織を科学する」という自分自身のテーマにもっとも近いのが「学習する組織」かなと思っています。ただこの本、かなり読み応えがありまして、なかなか前に進まない…読んでは休み、読んでは休みを繰り返しております。
全体の1/5程度の進捗ですが、「組織が学習するとは、共通の言語を習得すること」というフレーズが刺さりました。組織が直面する問題や課題をいかにして認識し、理解できるかは、表現する側と受け取る側のどちらもが理解できる言葉が必要だからです。
知識の共有には、『共通の言語』が欠かせない。専門性が高く、複雑な理論になればなるほどに、共通の言語は欠かせない。なぜなら、簡単な言葉では表現できないからだ。
— Shinya@情シスからHRへ挑戦 (@REPWORLDS) December 29, 2020
『あ、それって、量子力学的な事象に近いよね』って言葉が伝わるには、量子力学に関する知見が前提に必要だから。
自分のツイートで、他の本を読んでの気づきですが、つながりつつあります。
もう1つ、学習する組織風土の醸成に欠かせないのは、失敗に対する向き合い方でしょうか。
マインドセットの獲得や、バイアスの学習も必要だなぁと。こういう知識って、各組織はどうやってインストールしてるのでしょうか。
【読書メモ】学習する組織とは?
— Shinya@情シスからHRへ挑戦 (@REPWORLDS) September 13, 2020
・失敗から学ぶというシステム
・失敗をシェアしても非難されない組織風土
・失敗を受け入れる個人のマインドセット#失敗の科学https://t.co/vz5WuSWZyr
感想のツイートも載せておきます。
人類最強の力である「チームの機能を高める!」を目指したい
昨年から引き続き…ではありますが、エイミー・エドモンドソン氏の著書に触れておきたいと思います。
あらゆる専門性を持った人同士が、即席で組成されたチームで、どうやってパフォーマンスを発揮するのか?めちゃくちゃ関心の高いテーマです。
・学習する組織風土の獲得
・心理的安全性の成熟
・失敗からの学習
・境界を超える動きの活性化
・リーダーシップ
このあたりが、僕の中で落としたワードですが、必要性はわかっても、どうやって組織として使っていくのかが見えていません。
結局、リーダーシップやマネジメントの在り方だよねーってするなら、以下の著書が僕のバイブルなので、推薦したい。。。
総括
常に新しい考えに触れながら、定期的にアウトプットや実践をしないと体系的に落とし込めない。( noteを書きながら、痛烈に反省した)
やっぱり、人や組織って面白い。人には興味無いけれど、人類やそれが集まって動く組織っていうものに興味がある感じです。
自分の興味や関心(自己満足)を高めつつ、パフォーマンスを上げていかないと、会社から必要とされなくなる不安も湧いてきました。なので、役に立つレベルまで落とし込むのが、喫緊の課題かもしれません。
