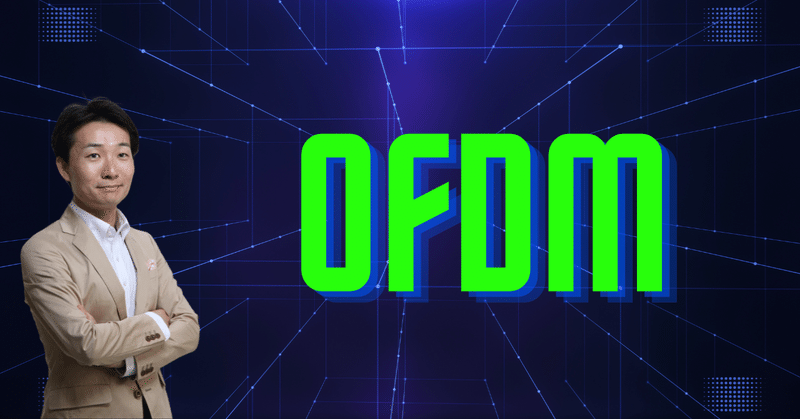
【Wi-Fiの仕組み】高密度に効率よくデータを送る優れた仕組み「OFDM」
はい、こんにちは。前回記事からの続きです。サイバーセキュリティにおいて重要なテーマの一つである「無線LAN」の仕組みについてシリーズ記事でご紹介します。
前回は、IEEE802.11a以降に採用されている変調方式「OFDM」を知る上で前提となる知識として、周波数、サブキャリア、位相という3つの単語についてお話ししました。個人的には、位相という概念がちょっと新鮮でした!

さて、今回は、「OFDM」の話の続きです。OFDMは、「直交周波数分割多重」という長い名前なのですが、先に「周波数分割多重」とは何か?を見ていくことにしましょう。その上で、直交周波数分割多重について解説します。
難しいことはとにかく分解して理解していく作戦です!
では行ってみよう!
別々の周波数帯で信号を流す「周波数分割多重」
はい、では「周波数分割多重」(FDM)を先に知ることにしましょう。いかにも難しそうな単語ですね。
この「周波数分割多重」とは、「キャリア波の周波数帯域を複数のサブキャリアに分割して、それぞれのサブキャリアで別の信号を送る」ことです。
うん、イメージが湧かない…。例えましょう。
異なるレーンがある高速道路をイメージしてください。それぞれの車(信号)は自分のレーン(周波数帯域)を走り、互いに干渉せずに目的地に進むことができます。こんな感じでしょうか。

このようにして、周波数分割多重は、複数の信号をそれぞれ周波数帯を通して同時に送ることができます。周波数帯を仲良く分けあうのですね。
ラジオ放送では、異なる局が異なる周波数で放送を行い、リスナーはチューナーを使って特定の周波数を選んで聞きますね。これもFDMです。え、ラジオのチューナーを合わせたことがない?本当ですか?

なるほど、このように見ていくと、FDMは、そんなに難しい概念でもないですね。さわりだけですからね。
直交するってどういうこと?
FDMがなんとなく分かりました。でも、FDMですと、サブキャリアの周波数帯の間隔を十分に開ける必要があります。その周波数帯の信号の伝達量を大きくできないので、効率はよくありません。
一方、OFDMでは、隣り合うキャリア波の位相を90度ずらします。これが、直交です(位相は前回学びましたね!)。

これによって、間隔を十分にあけず、高密度に無駄を少なく周波数帯を利用することができます。
例えれば、アクロバットチームで、狭いエリアに個々の選手が飛び回っていても、上手にぶつからないにできているって感じですかね~。
ちなみに、この理屈をもっときちんと理解したかったのですが、フーリエ変換など難しいキーワード満載なので、これくらいにさせてください~。
はい、本日はここまで。本日は、OFDMについてお話ししました!次回は、3番手の規格「IEEE802.11g」に行きますか!
では!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
