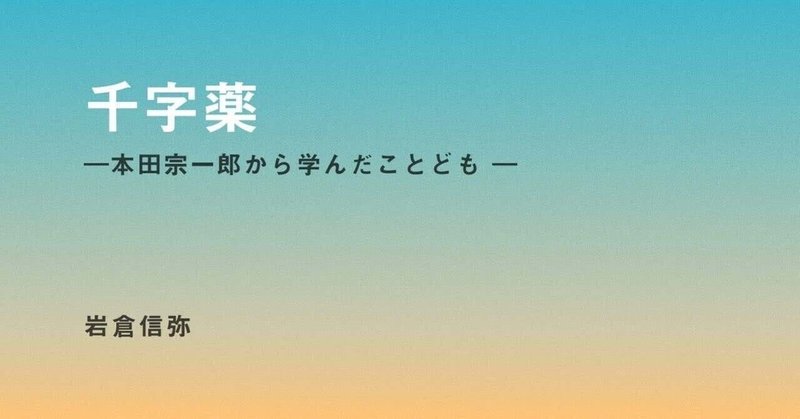
第204話.全体と部分
1995年
6代目「ホンダアコード」の開発を通じて、世界各地域の要望と生産効率の整合、そしてホンダらしい技術を備えたアコードのあり方を、世界のホンダマンの総智を結集して構想を重ねていった。
同一ジャンルでありながら、地域ごとに最も適合したそれぞれに違った車を、どうすればつくり出せるかと検討を進めた。その結果、当たり前のことだが、その車が必要とされる地域に住み、そこの文化を理解する人たちによって、つくり出されるべきだとの考えに至った。
こうした考えをもとに、4代目~5代目にかけてのアコードシリーズは、日米欧の研究所が率先し、地域ごとの「ベストファミリーカー」のあり方を模索してきた。車づくりの「基本コンセプト」は、それを必要とする人々の暮らしや文化を抜きに考えられない。
世界各地の人々と「車」との関係を、本当に良いものにしたいなら、それぞれの文化を大切にするのは当然のこと。さまざまな人のあいだで生まれる「場」が各々異なるように、世界の各地で、「車」と「人」とのあいだに生まれる「場」も、いろいろと違ってくるはずである。
このように考え、ながらく「お客さん本意」にと重ねてきた試行錯誤が、6代目アコードを開発するための考え方や手法を醸造したと言える。
こうした考えのもと、6代目アコード用に開発されたオハイオ生産のV6エンジンは日本に運びこまれ、狭山工場でつくっている日本の初代オデッセイに搭載されることになった。またインスパイアー系の車は、オハイオ生産のV6エンジンを搭載、オハイオ工場で生産され、日本に輸入されることになる。
加えて、この6代目アコードのプラットホームは、アメリカ専用の「ミニバン」を生み出し、それを生産するためのカナダ工場までつくってしまった。さらにそれを、日本にも輸入して売るのだと言う。
「ローカル」を進めていたら「グローバル」になった。日米欧の、現地研究所でデザインされた三つのアコードは、私にとって、それぞれに「地域らしく」、しかも、揃って「ホンダらしく」映る。宣伝の連中が知恵を絞って「グローカライゼイション」という新語までつくってくれた。
「部分が集まっても、全部にはなるが、全体にはならない」と誰かが言っていた。アコードはその名の通り、全体(世界)と部分(地域)をみごと調和(ACCORD)させ、世界の「一体化」に、一歩踏み出そうとしている。私の、最後の大仕事はこうして終わった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
