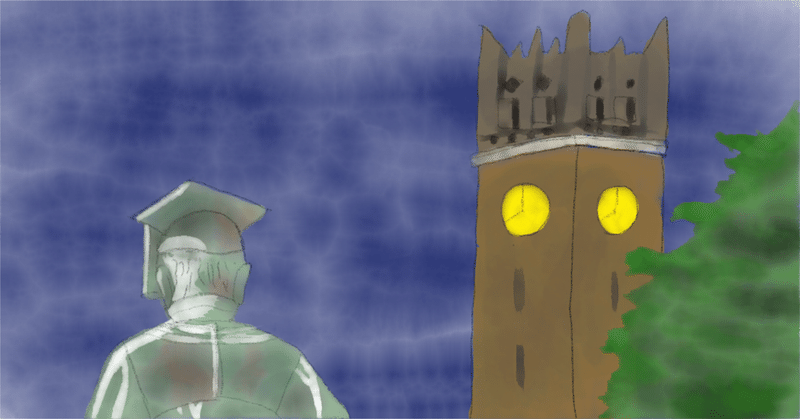
心の悲鳴と「写真論」
2022年9月27日(火)晴れ
1日中、何の予定もない休日があったら何をするか?
睡眠は5時間ぐらいでいいから、朝、まだ陽が低いうちに目を覚まして筋トレと家事をする。家の中が整ったら、中華料理店においしいランチを食べに行く。ビールかグラスワインを1杯飲む。それから、東京都写真美術館をゆっくり観てまわる。母校の図書館にこもって本を読む。青春の味がするつけ麺を食べたら家に帰って、Unityの教科書をなぞって、Blenderで3Dモデリングをして、少しだけ絵を描いて寝る。
誰にも会わなくていいし、誰とも話さなくていい。ただ、寝る前に少しでも夫と顔を合わせて、そして隣で眠れたらとてもいい。
自由な時間に身をすべらせると、自分のことが少し理解できたような気持ちになる。生活の中で、人生の中で一番何を大事にしたいのか。そんなことを。
・・・
私の9月27日は、そんな1日だった。文句なしの、自由な日。
東京都写真美術館のショップで見かけたスーザン・ソンタグの『写真論』が面白そうで、数時間後に早速図書館で読んだ。最近、絵画の芸術性についてはその端緒を掴んだような気がしているが、それに伴って「芸術作品に位置づけられる写真とは、どのようなものか?」という問いが頭をもたげるようになったのだ。
描き手の思念が一筆一筆に乗って生み出される絵画と比べると、写真というものは随分あっさりとした表現方法のように思える。誰もがスマホで気軽に高画質の写真を撮り、アプリを使えば簡単に思い通りの色味に編集できるこの時代は特にそうだ。写真において、芸術作品とそうではないものの境目はどこなのか。芸術作品と評されるものがあった時に、それは絵画と並べて語ってよいものなのか。
『写真論』は、デジタルカメラも生まれていない1977年の本だが、今に通じる考察が散りばめられている。私がもやもやと抱いていた問いに対しても、彼女なりの解をいくつか得た。まだ整理するまでに至っていないが、面白かった箇所をいくつか引用する。
写真は絵画やデッサンと同じように世界についてのひとつの解釈なのである。
写真は絵画のようには完全にその主題を超越することができないという点がその本質にあるからである。また写真はある意味ではモダニストの絵画の究極的な目標である、見えるものそれ自体を超越するということもできない。
写真はすすんで郷愁をかきたてる。写真術は挽歌の芸術、たそがれの芸術なのである。写真に撮られたものはたいがい、写真に撮られたということで哀愁を帯びる。(中略)美しい被写体も年をとり、朽ちて、今は存在しないがために、哀感の対象となるのである。(中略)写真を撮ることは他人の(あるいは物の)死の運命、はかなさや無常に参入するということである。
カメラは経験を小型化し、歴史を光景に変えてしまう。写真は同情を生み出しもするが、同じく同情を切りつめ、情緒を引き離しもする。
写真が芸術ーー主観性を要求し、嘘をつくことができ、美的喜びを与えるーーと呼びうる作品を生み出すにしても、写真はそもそも芸術形式などではまったくない。それは言語のように、それによって(なかでも)芸術作品が作られるメディアである。
絵画と写真は、和解するためには適当な領土分割に達すればよいというような、映像の制作・複製の潜在的に競合する二つの制度ではない。写真は別の秩序の企図である。写真はそれ自体は芸術形式ではないが、その主題をすべて芸術作品に変える特別の能力をもっている。
写真が芸術として合法化されるために、作家としての写真家の観念と、同一の写真家が撮った写真はすべてひとつの作品群を構成するという観念を養わなければならない。
・・・
どうせ写真を撮るのであれば、「SNS映え」とかそういうことではなく、誰かに何かを伝えるための作品を撮ってみたいと思う。非言語のコミュニケーション。今月、私はそれにどっぷりと浸かり、今までにない刺激を得た。まるで、筋トレによって普段使うことのない筋肉を動かしたかのように。私の心の一部が、筋肉痛を起こして小さな悲鳴をあげる。それは確実に、うれしい悲鳴なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
