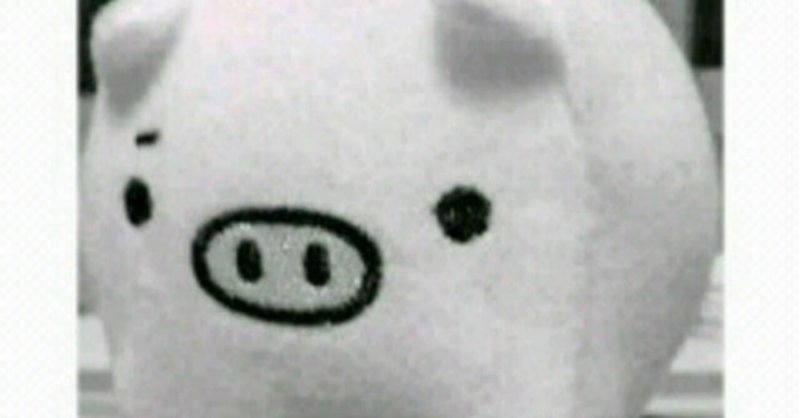
[Column] 踊る共通テスト (後編)
前編からのつづき
~英語を民間試験で代用するのはもっと無茶~
“英語を民間試験で”が無茶だったワケ
「記述式」と同時に議論され、そして同時に導入断念にいたったのが、「共通テストの英語試験を民間の英語能力検定などで代用する」というものである。これは、英語の問題を大学入試センターが作成しなくなるということを意味していたため、まさに方針の大転換であり、2018年あたりからそういった情報が報道されるたびに、われわれ塾業界、とりわけ大学受験対策をメインに据えている大手予備校などは、混乱の極みの中で右往左往せざるを得なかった。
そして結局、全部が白紙に戻ったわけだが、そもそもなぜ、英語は民間の検定を活用しようなどという話になったのか。
受験の機会均等が担保されない
センター試験が共通テストに変わる直前の時期、当初の報道では、英検・TOEIC・TOEFLなどから各自で選択・受検し、CEFR(セファール)なる国際基準に照らしてウンヌンカンヌンと言われていたのだが、しかし、こんな乱暴な話もない。まったく異なった別々の検定の結果を、1つの物差しで測定しようというのだから。
それでも、意図は理解できる。センター試験は受験機会が年に1回の一発勝負で、しかも、実施時期の問題から、たいてい寒波による大雪で交通機関がマヒする。地域によっては大雪で受験会場までたどり着けず、開始時間をずらして実施するなど、もはや恒例行事である。
英語を民間試験にゆだねる意図は、受験回数を1回に限定せずに済むことにあった。高校3年生の1年間で複数回受検した検定の中で、もっとも好成績だったものを自身の成果として採用できる仕組みになるはずだったのだ。しかし、これも教育の機会均等という観点から非常に不公平を生むとして批判された。
英検にしてもTOEICにしても、地域によって実施会場の数に差があるし、複数回受検が可能ということは、それだけ“受験料”がかかるのである。センター試験や共通テストそのものにも受験料が発生するのに、さらに出費を求めるのというのはいただけない。たった数千円ではあるのだが、問題はその複数回の数千円が、生徒ごと、家庭ごとに異なることにある。
ただでさえ、大学受験にかかる費用は年々増加している。それらへの支援体制が整っていない中での施行は極めて困難なのである。
[筆者補足]
なおかつ、英語だけ民間にゆだね、受験機会を増やしたところで、ほかの教科・科目は相変わらず一発勝負なのですから、これはそもそも論理矛盾をきたしていると言わざるを得ません。
Speaking の測定は極めて恣意的
さらにもうひとつ、「英語の4技能」についての議論がある。英語の4技能とは、「読む Reading 」「書く Writing 」「聞く Listening」「話す Speaking 」の4つの能力を差し、「話す」をさらに「会話」と「発表・表現」に分類して、これらを総称して4技能 5領域という。
2021年からの中学校の教科書改訂においてもそうだが、ちかごろ何かと「使える英語」がクローズアップされており、4技能の中でもとくに「Speaking」が重要視されるようになってきている。
言わんとすることは理解できるのだ。中学・高校と6年間も英語を勉強するのに、誰一人として自在に話せるようにならないのはどういうわけか、と筆者自身そう思う。
[筆者補足]
ちなみに筆者の母は昭和27年の生まれなのですが、自分が学校に通っていた時分からすでに50年以上が経っているのに、いまだに日本人が英語をしゃべれない現状に対して怒り狂っています。
旧来のセンター試験で測ることができる能力は、基本的にリーディングのみである。途中からリスニングが追加されたが、残りの領域については放置されているではないか、これはいかん、ということで、4技能すべからく総合的に評価するために、すでにある民間の試験を導入しようという議論になったわけである。
だがこれも、記述式問題を導入するか否かの議論と同様で、採点が公平にならないのである。
なにしろ共通テストの受験者数はおよそ55万人。いざ導入となったら日本全国津々浦々、いたるところでスピーキングの面接試験をすることになるわけだが、そんなことができるわけがない。スピーキングテストの評価方法として古典的なものに、自身の声をテープに録音して採点機関に送るというのがあるが、これには本人認証をどうするかの問題も発生する。ともあれ、どんな手法であろうと採点者が複数の人間になった時点で、公平性は担保できなくなる。
まして評価するのが「話す」能力である。英検の面接を受験した人なら知っていることだが、面接の評価項目に「 Attitude 」というのがある。英検のHPによると、「 Attitude 」とは「積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲や態度」だそうだが、これこそ評価基準のあいまいさにおいて最たるものである。
[筆者注]
いま流行りのAIを活用すればよいという意見もありますが、当然ながらAIにもできることとできないことがあります。機械による判定は、あれもなかなかいい加減なもので、まだまだ評価方法として充分であるとは言えません。評価方法が確立されていないという時点で、導入は時期尚早と結論づけざるをえないのです。
共通テストは大学進学希望者のレベルを測るための、全国一斉のテストである。全国一斉に実施しようとする時点で、はじめからできることに制限があるのだ。これまでのセンター試験からして、当日のアクシデントは枚挙に暇がない。このうえさらに混乱を招く要素など必要ない。
要するに“利権”か
これは少し穿った見方をしすぎであるかもしれないが、筆者はこの報道を聞いた瞬間、まっさきに“利権”という言葉が頭をよぎった。
小中学校の教科書に指定されるかどうかで、巨大な金額が動くのと同様で、英語の民間試験を導入する場合、共通テストの英語の成績として利用できる検定に指定されることによって、検定の主催者側には莫大な利益が見込める。
[筆者補足]
こういった検定を主宰している組織は、たいていが公益法人や非営利団体だったりするのですが、そんなことは表面上の話にすぎません。
問題冊子の印刷、採点システムの開発、広告・宣伝といった実働の部分では、ごくふつうに民間企業が活動しているわけで、「検定は営利目的ではない」などという主張があったとしても、そんなものは“おためごかし”に過ぎないと思うわけです。
なにしろその検定を受けなければ、さらに自分の求める級やスコアが取れなければ、大学に進学すらできないのである。すでに述べたとおり受験料の問題があるわけだが、実際に導入されるとなると、受験生は受けられるだけ受けることになるであろうことは、想像に難くない。
ゆえに今回、導入そのものが白紙に戻った背景には、教育の機会均等の確保やら地域格差・経済格差といった、わりと高尚な指摘がされるなか、その水面下では英語検定の主催者間に指名獲得に向けた激烈な利権争いがあり、どこかの一人勝ちを避けるために、いわゆる“痛み分け”になったという、非常に俗っぽい理由があるのではないかと想像したりもするのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
