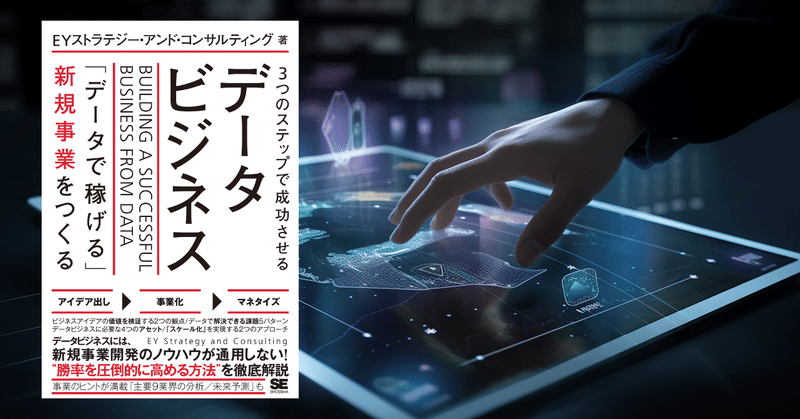
新規事業は、難しい。データを使うとなると、もっと難しい!(でも、やり方はある)
「第2の事業の柱を――」
「社内のデータを使って何か新しいビジネスを――」
そんな声が社内で上がっていませんか?
いまや、新規事業にはデータ活用が不可欠。
ただ、データを使うとなると、
一般的な新規事業立ち上げのノウハウが通用しません。
データはすぐ陳腐化する、
データそのものはお金にならない、など理由はさまざま。
実際、データビジネス(データを使った新規事業)に挑戦した
各社では、どんなことが起きているのでしょうか?
架空の「あるある話」を見ていきましょう。
(2023年6月21日刊『3つのステップで成功させるデータビジネス』より抜粋)
〈A社の場合〉ビジネスアイデアが思いつきの域を出ない……
製造機器を製造・販売するA社では、社長の号令のもと組織横断で人が集められ、新規事業部門として、社内のあらゆるデータを活かしたデータビジネスを検討せよ、という指示が下った。社内のデータとは、顧客に提供する製造機器の稼働状況や顧客の利用状況、販売先となる顧客の属性や、製造機器の利用用途などだ。
新規事業部門では、社長の指示を受けてまずは営業部門、生産部門、保守部門、顧客サポート部門などがそれぞれ持つデータを一斉に棚卸しすることにした。
当初、各部門からは「何に使うのか分からないと、データを特定しようがない」など、抵抗があった。だが社長の指示であることと、A社としてもデータを活用した新規ビジネスを打ち出していかないと、この先のビジネスが厳しいということを粘り強く説明し、「各部門にあるデータはとにかく出してくれ」と新規事業部門からお願いをした。
その甲斐あって、社内にかなりの量のデータがあることが分かった。ある程度、棚卸しができた段階で、新規事業部門内では、「社内のこれらのデータが一体何に使えるのか」という話になりディスカッションしたが、アイデアはどれも思いつきの域を出ず、また、「そもそも社長がどんなデータビジネスをしたいのか、という点が明確でない」といった議論にも発展してしまっていた。これは、「自由な発想で新たなデータビジネスを検討したい」と考えていた社長が望んだ事態ではない。
その様子を見ていた他の部門は、自分たちが苦労して棚卸しをしたデータが結局、有効な使い道も見いだせないままとなり、データビジネスの検討が遅々として進まない状況を目の当たりにして、「結局、棚卸しのし損だった」と白けきっていた。
さらに、社長からは思いつきのアイデアしか出せないと呆れられ、新規事業部門は明確な方向性を示さない社長に不満を抱え、結果、A社のデータビジネス検討は頓挫してしまった――。
〈D社の場合〉アイデアはいいんだけど稼げそうにない……
IoTデバイスを製造するD社は、業界内でシェアトップの地位を築いていたが、近年はシェア2位の競合が低価格戦略で急激にシェアを伸ばしつつあることに加え、IoTデバイス市場も成熟期から衰退期に差し掛かっていることから、「デバイスで収集したデータを活かすデータビジネスの展開」を基本方針に新規事業開発の取り組みを推進していた。
主要事業部から人員を集め組成された新規事業開発チームを中心に、まずは取り扱っているデバイスからとれるデータの項目などを棚卸しし、様々なデバイスから取得できるデータをそれぞれ掛け合わせることで、把握できる事項の整理が進められた。
各データの整理結果をもとに、新規事業開発チーム内で数週間かけてアイディエーションを実施し、合計100件にも及ぶアイデアリストが作成された。
その後、具体的なサービス化の検討に向けて有望なアイデアの絞り込みを複数回実施し、「ウェアラブル+空間センサーによる居住者の心身状態の可視化」というアイデアをまず検討してみることになった。
新規事業開発チームでは、このアイデアを活かしたビジネスモデルの策定が始まった。
チーム内での討議を経て、居住者の心身状態の可視化による診断・スコアリングサービスや健康増進支援サービスなどのビジネスモデル案を検討した。
検討期間は十分に設け、いずれのビジネスモデル案も、検討に検討を重ねて出したものではあった。が、どれも、新規事業開発チームメンバーに「大きなビジネスになる予感」を感じさせるものではなかった。
「アイデアは良いんだけど……。このモデルだと次の収益の柱にはなりそうにないね」。報告を受けた役員の発言に、新規事業開発チームメンバーは小さくうなずくしかなかった。
こうして、D社のデータビジネス開発検討は暗礁に乗り上げることになった――。
〈F社の場合〉同じことを大手にやられてしまった……
F社は、データビジネスとして「小売と仕入れ先メーカーとのマッチングサービス」を推進していた。これは、小売向けにF社が提供していたITソリューションより収集されるデータをもとに、商品の売れ行きなどを分析し、適切な仕入れ先メーカーのレコメンドからマッチングまで提供するサービスである。
F社は、自社が取得できるデータと分析技術を活かし、「店舗別の売れ行きから、より売れそうな商品とそれを扱うメーカーをレコメンドするサービス」を企画した。事前のPoC(Proof of Concept、コンセプトの検証)では小売事業者からの評判も良く、無事社内の稟議も通り、サービスの立ち上げへと至った。
ただ、F社はマッチングサービスの供給側であるメーカーとのリレーションが弱かったため、メーカーの利用企業数が思うように伸びなかった。結果、サービス立ち上げ当初は、小売事業者にマッチングさせるメーカーが少ない状態が続いていた。
危機感を持ったF社は、その後精力的な営業活動を続け、サービス開始から約半年でメーカー数は当初目標としていた100社を超えた。メーカーの数が増えることで、サービスの売りであったレコメンド機能も効果を発揮し、小売事業者からも評価する声が聞こえるようになった。
しかし、軌道に乗る兆しが見えたこのタイミングで状況は一変した。Z商社がF社と類似のサービスを立ち上げたのだ。
「自分たちには先行者利益があり、Z社も追いつけないはずだ」というF社の予想と裏腹に、Z社のマッチングサービスは、立ち上げから1カ月もたたないうちにメーカー数が100社を突破してしまった。
Z社は、既存事業で培ったメーカーとのリレーションを活かし、立ち上げ前の段階からすでに多数のメーカーから参加を取り付けていたのだ。
「このままではZ商社に顧客をとられてしまう。しかし、メーカー開拓で追いつくことは現実的でない。であれば、サービスの機能で戦うしかない」と考えたF社は、さっそくレコメンド機能の強化へと乗り出した。これまでは仕入れるべき商品のみレコメンドしていて、どの程度の量を仕入れるべきかまでは対応できていなかった。
すぐさまF社は、機能を追加したが状況は好転しなかった。
実は、Z商社が展開するマッチングサービスにも、F社と同様の最適仕入れ量のレコメンド機能が実装されたのだ。しかも、F社とZ商社の両方のサービスを使う小売事業者によると、Z商社の機能の方が精度が高いというではないか。
その後もZ商社のサービスは順調に成長を進め、Z商社の参入から約3カ月後、F社のサービスを利用する小売事業者数はついに減少へと転じてしまった。
その後、様々な策を講じるが一向に状況は改善せず、サービス展開から約2年がたったタイミングで、ついにF社のサービスは経営層により撤退が決定された――。
〈G社の場合〉巨額出資を受けたスタートアップに追い越された……
G社は、社内の新規事業立ち上げ企画を通じ、「ダイナミックプライシングサービス関連事業」を立ち上げることになった。3年後には日本中の小売店舗で、このサービスが導入されることを想定した事業計画を策定した。
新サービスの立ち上げにあたり、これまでデータビジネスを企画してきたメンバーに加え、他部署からも社員が異動する形で新組織を設けて推進することになった。
立ち上げのための準備は、試行錯誤の連続だった。ユーザーとなる顧客の開拓はもちろん、ダイナミックプライシングの精度を高めるためのデータを所有する企業との交渉も、限られた社員で精力的に行った。
しかし、G社が新組織を立ち上げてから3カ月目に、同様の他社のダイナミックプライシングサービスを紹介するCMが流れ始めた。しかも、そのCMは、有名芸能人を起用するなど、潤沢な予算をかけていることが容易に想像できた。
サービスの運営元の企業を調べると、設立3年目のスタートアップであることが分かった。さらに驚くべきことに、そのスタートアップは数カ月前に、G社のライバル企業をはじめ、複数の大手企業からの出資を受けており、潤沢な手元資金があることが分かった。豪華なCMを打つ予算があるのも納得である。また、魅力的な給与水準で、外部から優秀な社員を中途採用で多数獲得できていることも分かった。
ライバル企業である小売企業は、このスタートアップのサービスを活用して、すでにダイナミックプライシングを全国の店舗に導入しているようだった。自前で新規サービスを立ち上げるのではなく、有望なスタートアップと資本・業務提携をして素早く事業展開する、というのがライバル企業の戦略だ。
なかなかサービスが軌道に乗らなかったG社は、他社が先行して開始してしまったことが分かり、事業立ち上げを断念せざるを得なかった――。
〈I社の場合〉競合との戦いに終わりが見えない……
数年前、広告関連企業I社は、「次世代の広告サービスを」というスローガンのもと、4大媒体やネット広告に代わる次世代の広告販促サービスを模索し、「店頭サイネージを用いた広告サービス」というアイデアに注目した。
これは、小売店舗内にデジタルサイネージを設置し、来店者に対する広告を流す、いわば小売店舗を広告出稿媒体として活用する広告サービスである。単に広告を流すだけでなく、サイネージに設置したAIカメラで来店者の反応を分析し、小売店のアプリとも連動したキャンペーンを行うなど、データを存分に活かすものだ。当時はまだコンセプトレベルのサービスであり、実際に国内で収益化に成功していた事業者はいなかった。
「うまく展開することができれば先行者利益を確保できる」とI社は考え、このサービスの展開を決めた。
それから数年、店頭広告サービスは2桁億の売上を創出する事業にまで成長していたが、しかし状況はI社にとって決して満足いくものではなかった。
サービスの展開当初は、広告販促を出稿できる店舗を増やさねばならず、サイネージの調達や設置の費用については、媒体面を確保するための投資として、持ち出しでの対応を余儀なくされた。しかし、これはある種の先行投資であり、実際に媒体面が開拓できていた当初は、順調にメーカーからの広告出稿の依頼も増え、売上規模はだんだんと増していった。
ここからは投資回収、と意気込んでいた矢先、I社に大きな試練が訪れた。サービス開始当初は、サイネージ店頭広告サービスの収益性に半信半疑の企業も多かった。ところが、I社が収益化を実現できそうになると、同業他社に限らず、異業種からも様々な事業者がこの事業に参入してきたのだ。
競合との競争は熾烈を極めた。競合の多くは、I社のサービス以上の出稿を確保するために、無料でサイネージを設置するどころか、逆に「サイネージ設置料」を小売事業者に支払う形をとりだしたのだ。
多くの小売事業者がI社のサービスからの乗り換えを始めたため、I社もこれに対応せざるを得ず、同じくサイネージ設置料の提供を開始した。
すると今度は、別の競合事業者がサイネージ設置の見返りとして、各店舗が来店施策として行う割引クーポンの原資を提供し始めた。I社は設置料と同様、これにも対応せざるを得ず、既存設置店へのクーポン原資の提供を開始した。
このように、店舗出面を確保するための苛烈な販促合戦に陥り、I社のサービスは2桁億の売上で頭打ちとなり、競合対策のためのコストがかさみ、未だに赤字であった。
そして、何よりもI社を悩ませた問題は、この競争に終わりが見えないことだった。いつ終わるとも分からない競合との販促合戦に巻き込まれており、その先に黒字化、収益化できるか分からない「出口が見えない投資」が続いている。
黒字化の目途が立たない中で、大型投資を続けるわけにはいかない。しかし、一度投資をやめてしまえば、たちまち市場シェアを失い、撤退を余儀なくされるだろう。「出口の見えない競争の継続か、撤退か」。重要な判断の岐路にI社は立たされていた――。
以上、5つの架空の事例をご紹介しました。
いずれも、よくありそうな話ではないですか?
『3つのステップで成功させるデータビジネス』では、
「ビジネスアイデアが思いつきの域を出ない」
「競合との戦いに終わりが見えない」
といった課題を乗り越えるための
具体的なフレームワークやステップを提供します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
