
葦津珍彦「時の流れ」を読み解く(1)「時局展望」第1回「神器と大嘗祭の規定なき新しき皇室典範の成立」
コラム「時の流れ」について
戦後神社界・神道界を代表する言論人である葦津珍彦は多作の人であり、厖大な数の論著をものした。その内容も近現代神社史・神道史を中心に、明治憲法制定史や明治維新史、ロシア革命史、西郷隆盛などの人物論、韓国論から戦後憲法論など非常に幅広い。
葦津の多作と議論の幅広さを象徴するものとして、葦津が神社新報で執筆を続けたコラム「時の流れ」があげられる。
「時の流れ」は神社新報の準社説的な位置にあったコラムで、昭和22年1月の神社新報第29号に「時局展望」とのタイトルで始まった連載のコラムを改称したものである。「時局展望」は一時「週間展望」とも名乗りながら連載され、昭和33年より「時の流れ」となり、途中「時局通信」に名をかえたり、葦津の神社新報社の退社に伴う休載を挟みながら、昭和54年までの長期にわたって連載された。昭和22年の「時局展望」連載開始以来、実に33年、記事数は約1500篇にもおよぶとされる。
葦津の回想によると、「時の流れ」は元神宮奉斎会専務理事で、神社本庁事務総長・神社新報社社長の宮川宗徳が葦津に要請して始まったものだそうだ。宮川は、占領下のこと、神社人・神道人は国内外の情勢についてこれまで以上に新しい知識が必要であるが、神社新報の社説や論説には自然と表現・筆致の限界もあるだろうから、自由に時評を書き、読者に問題提起しててもらいたいと葦津にリクエストしたという。
「時の流れ」と神道ジャーナリズム
こうしたこともあり、「時の流れ」は神社界・神道界の業界通信の枠にはまったく当てはまらず、内は時々の政権の政策や政党・派閥の対立といった政論から経済情勢、あるいは左翼運動などの社会情勢、さらに流行りの文化からマスコミ論、また外は米ソの超大国をはじめとする世界情勢、ことにヨーロッパやアジア、アフリカの情勢まで幅広く論じている。
だからといって、このコラムが葦津の興味や関心を思うがままに書き散らしたエッセイではないことはいうまでもない。
繰り返しになるが、「時の流れ」は占領下での神社界・神道界の一つの言論運動の展開という宮川の要請をうけてはじまったものであり、対米軍闘争や反共闘争、あるいは戦後の精神文化や風潮との鋭い対決姿勢を維持する戦闘的な論陣をはった。
無論、それは「反動」といわれるような戦前回帰を目指す論調とは異なる。再軍備反対論や日米安保批判など、時に葦津自身も悩み、あるいは批判にさらされながら、戦後を生きる神社人・神道人として思索を続け、独自の見解を提起することもあった。
その上で、葦津みずから「神道ジャーナリズム」「神道ジャーナリスト」というように、国内外の様々な情勢を神社界・神道界の見地に立って独自に追及し、分析・批判し、世に問うていく、ジャーナリズムとしての達成がそこにはあり、とりとめもなく目につくもの流行りのものを論じたようなものではなかった。
他方、こうした神道ジャーナリストとしての葦津の言論はあまり回顧されてこなかったように思われる。それは葦津の思想・言論の33年分を等閑視するものといえる。
これより昭和22年の連載第1回から昭和54年の連載終了まで、「時の流れ」(「時局展望」「時局通信」なども含む)を一篇ずつ読み解き、ジャーナリストとして葦津が何を見て、何を訴えていたのか、振り返ってみたい。
「時局展望」(昭和22年1月20日)第1回
後に「時の流れ」となるコラム「時局展望」の第1回は、昭和22年1月20日発行の神社新報第29号の1面に掲載された。論題は「神器と大嘗祭の規定なき新しき皇室典範の成立」。署名は「葦津生」。言うまでもなく、この「生」とは手紙などで自分の名前の後に付す「拝」などと同意である。
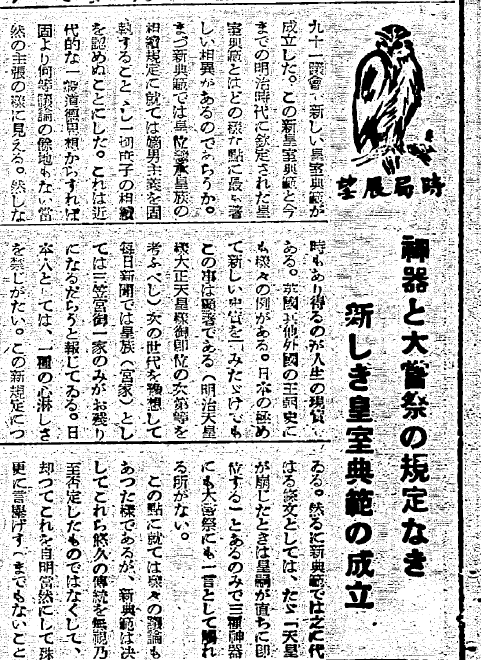
昭和22年1月20日発行神社新報コラム「時局展望」
本コラムでは昭和22年1月16日に制定された新しい皇室典範(新典範)について論じている。
葦津はまず第一に、新典範において皇位継承が庶子相続を一切認めない嫡男主義を採用しているところに着目し、嫡男主義は理想ではあるが現実的にはそれが難しく、「万世無窮、一系連綿の皇統の御隆昌を冀ふ日本人にとつては、一抹の憂念なきを得ぬのではないか」としている。さらに葦津は、
養子は固よりのこと女帝も認めぬ、庶子も認めぬ制度である。
として、新典範における皇位継承の嫡男主義の厳格さに疑問を投げかけ、とりようによっては旧皇室典範(旧典範)でも認められていなかった養子や女性天皇について容認するかのようなことを記していることは注目したい。
また、葦津は、このままでは時の経過により宮家は三笠宮御一家のみがお残りになるだろうという毎日新聞の記事を紹介しているが、これは皇族が減少した現在の姿を見通していたといえる。
続いて葦津は、旧典範には皇位継承においては神器の相承と大嘗祭の執行が明記されながら、新典範には「第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」とだけあることについて分析と解説を試みている。
葦津はいう、
新典範は決してこれら悠久の伝統(神器の継承や大嘗祭の執行─引用者註)を無視乃至否定したものではなくして、却つてこれを自明当然にして殊更に言挙げするまでもないこととして成文化を省略したものと解したい。
と。
新情勢において、ただただ否定的言辞を繰り返すのではなく、そこからいかに<真>を見出していくかという葦津の姿勢は尊敬すべきものがある。
その上で葦津は、こうした新典範の規定の解釈は、戦後憲法において皇位が「国民統合の象徴」とされたことからも自明であるとする。つまり「国民統合の象徴」とは歴史的伝統とは離れて考えられないものであるところ、皇位継承における神器の相承と大嘗祭は歴史的伝統のなかでもっとも根源的なものであり、あえて新典範に神器の相承と大嘗祭の執行について明記されておらずとも、皇位継承にあたりそれらが行われることはいうまでもない、というのである。
戦後憲法における「国民統合の象徴」の文言についての葦津の理解は、後に神道神学者上田賢治が実践・応用神学として象徴天皇の意義について理論化していくことになるが、いずれにせよ葦津の先見性や先駆的な議論をよくあらわす連載第一回であることはいうまでもないだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
