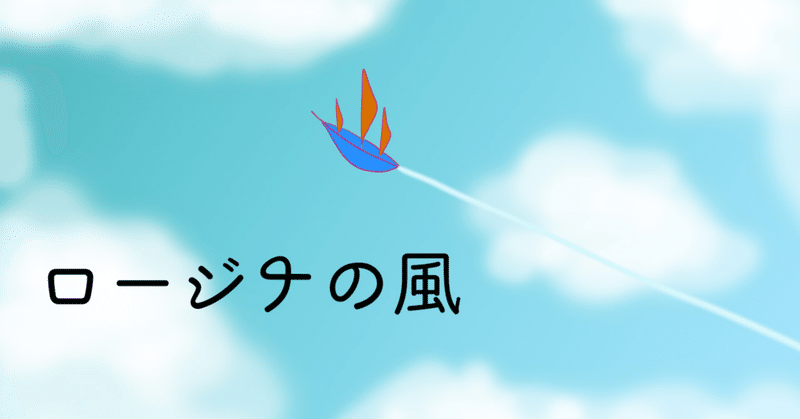
ロージナの風:武装行儀見習いアリアズナの冒険 #185
第十二章 逢着:19
海から遡上してくる川風は穏やかだった。
凪いだ海洋の水分を含むせいなのだろうか。
風が運んで来る香気は甘く優しく、ロージナの海にも宿るわたつみの慈愛が、スキッパーの鼻にも確かに感じ取れた。
プルタブ川に落ち込む丘陵の斜面は、そこを谷と言っても良いのかと迷うほどに傾斜が緩やかだった。
それはここからそう遠くはない下流で、この川が海に躍り出る落差百メートルを超える瀑布の事を思えば、長閑すぎる地形にも思えた。
試みにブルタブ川の源流から下流までを、星の一生に例えればどうなるだろう。
河口の滝の荒々しさは、誕生からずっと穏やかに星系を営んできた太陽がその死を迎えるにあたり。
超新星爆発を起こして、己が命の咆哮を叫び上げる様に似ていると言えようか。
対して山地に端を発する複数の源流は、清冽ながら不確定な幾筋もの小さな急流からなる。
そうした川の始まりは、星間物質が重力で引かれあって集まり、やがて熱と光を得て誕生する星の始まりに似ていたろうか。
流域に広がる丘陵の斜面はどうだろう。
なだらかな稜線に沿う自然林の間に形良くレイアウトされた畑と人家は、そこで暮らす人々の幸福を伺わせる品の良い佇まいを見せていた。
中流域の景観は、星系が抱く惑星の一つにもし生命が生まれたとしたなら、その在り様に相応しい。
その景色は多様に進化する生命を見守る太陽が、丁度中年期に差し掛かろうかという、穏やかで充実した日々が続く時期に相当するだろうか。
好事家なら試みに切り取って、額装してみたくなるような絵画的風景は、プルタブ川の澄んだ青がアクセントを足して見せていた。
スキッパーはそうした美しい景観の中、青く澄む川の右岸を、何の感慨も抱かずにトコトコ独りで駆けていた。
アートと言えば肖像画と彫刻に傾倒しているスキッパーだった。
風景画にはまったく興味が無かったのだ。
そんな自分が風景画の構図に当てはまる、うってつけな一点景としてそこにあることを、夢にも思わないスキッパーだった。
石畳の遊歩道はよく整備されていたが、あろうことか犬への配慮がまったく欠けていた。
スキッパーは力を込めないトロットで足を運んでいたが、肉球へ当たる路面の感触が不愉快でたまらなかった。
スキッパーは厄介事をちゃっちゃっと片付けて、肉球触りが心地よい木製の甲板上に、一刻も早く戻りたいものだと嘆息した。
ディアナとアリアズナが元老院暫定統治機構の強行偵察班に捕まった時点で、スキッパーは速やかにその身を隠した。
人間相手の戦闘だからと言って勿論臆するところは無かったが、如何せん多勢に無勢であった。
そこで内心じくちたるものがある事を認めつつ、無理はせずいったん戦線から身を引き、反撃の機会を伺うことに腹を決めたのだった。
けっして戦いから逃げたわけではない。
スキッパーはピグレット号から降下の後、自分の保護下においた二人の少女については、知的にも肉体的にも物の役に立たないと考えていた。
ありていに言ってスキッパーは、アリアズナとディアナをはなっから戦力外と見なしていた。
自分の任務が二人の安全を最優先にすることであると仮定すれば、無益な交戦は絶対に避けるべきだった。
そうとなれば論理的帰結として、この場で戦術的後退を選択することは、歴戦の古参兵が取るべき最良の判断だったろう。
誇り高き甲板犬であるスキッパーとしては『保護者たる責任を果たし得なかったことについて慙愧の念に堪えぬ』と言うのが正直なところだった。
堪え難きを堪え忍び難きを忍んで、襲撃者に覚られぬよう一行の様子を偵察監視するスキッパーだった。
敵の指揮官の言動と辛うじて嗅ぎ取れる匂いからすると、当面少女たちに危害が加えられる可能性は低いと見て取れたのは僥倖だった。
元よりいささか知恵の足りない少女たちではあったがそのひとり。
ディアナが無謀にも敵に対して近接戦闘を仕掛けたのには心底魂消た。
これが本職の戦闘であればまさに瞬殺であったろう。
幸いディアナは殺されずに済んだが、敵の指揮官はスペンサー甲板長に勝るとも劣らない凶暴な女だった。
彼女は歴戦の甲板犬が思わず尻尾を股に巻き込むほどに獰猛だった。
しかし話振りを聞く限り、頭のねじが飛んだメスゴリラと言う訳ではなかろう。
そうは思った。
いやしくも士官を拝命している以上、捕虜を法に適ったやり方で処遇する知性はあるに違いない。
スキッパーは彼女が強行偵察班の隊長である可能性にはあえて目を瞑った。
もしそうであるならば最早スキッパーの手に負える相手ではないからだ。
彼女を知性あるメスゴリラと仮定できるのであれば、偵察監視の目を解いても心配はあるまい。
スキッパーは早鐘のように鳴る心臓のドキドキに急き立てられ、戦術的撤退を正当化する屁理屈をでっちあげた。
スキッパーはびっしょり汗ばんだ肉球を芝草で拭うと、速やかに戦線から離脱した。
ブラウニング艦長であれば、艦から降下した少女たちを救出するために、既に何らかの手を打っているに違いない。
加えて首輪から下げているお守り袋には、アリーが降下後の経緯と現状を書き留めたレポートが入っている。
スキッパーはブラウニング艦長に対し、ホモサピにしては有能な奴とそこそこ高い評価を与えていた。
そうである以上、少女たちを奪還するためには、彼女にアリーレポートを渡すことが最良の選択であると結論付けたのだった。
一度考えがまとまれば、即断即決を信条とするスキッパーに迷いはなかった。
『だから、この行動は断じて敵前逃亡ではない』
少女たちを見捨てたのではなく奪還要請のため敵中突破を図るのだ。
下腹に巻き込まれたシッポと、口中に溢れる唾液にグルグル鳴り始めたお腹の調子はいかんともし難い。
だがしかし、スキッパーは自信を持ってそう吠え切ることができると胸を張った。
スキッパーはこうして見事に、臆病犬とそしられそうな自分の状況判断を、自分自身に対して合理化して見せた。
スキッパーは、川岸まで出たところでいったん立ち止まると、空を振り仰いで鼻をひくひく動かし降り注ぐ陽の光に目を瞬かせる。
そうして風に乗って流れてくる誰かの言葉に耳をすますかのように、首を傾げてしばしの間いっさいの動きを止めた。
静かなひと時が過ぎ、スキッパーはいきなりくしゃみを一つした。
そして何事かを了解したかのような迷いの無い足取りで、そのまま目の前に掛かる面影橋を渡った。
スキッパーは、辿り着かねばならないゴールを目指して鼻面をブルタブ川上流に向け、己が義務を果たすべく従容とその右岸を走り出す。
スキッパーにとってはあくまで、危険な敵中突破の状況開始だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
