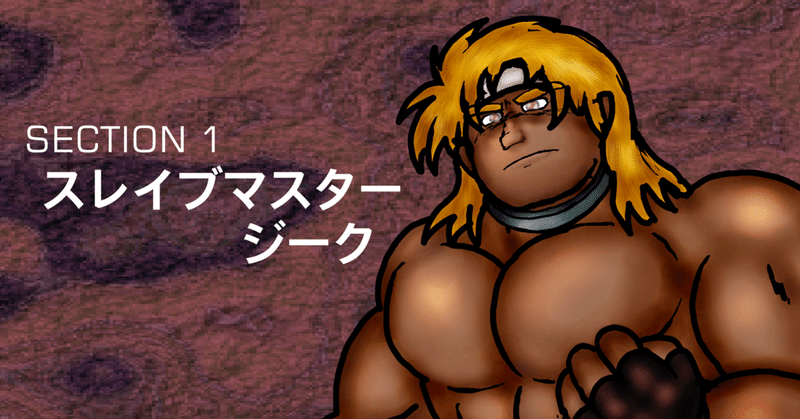
6.「あまり気が進まないなぁ…」
手ぶらでかえってきたタルトたちに、リキュアとナギは落胆を隠せなかった。いや、落胆ではない…スレイブマスター・ジークという最悪に近い敵の出現にショックを受けたのであろう。元隷属の鎖の神官であるリキュアはジークのことを少なからず知っていたし、実はナギにしてもジークとは何度かしゃべったことがあった。ジークという悲劇の勇者のことは、二人ともかなりの同情と強敵であるという危機意識の点では共通していた。
唯一の救いはクーガーやレムスが無事だったことである。楽観していた作戦で、ここまでの危機があったのである。リンクスを救うどころか、クーガーたちが捕まったり殺されていたとしてもおかしくないのである。リキュアもナギも、命の恩人ともいえるジャッキーに感謝しっぱなしである。
もっともジャッキーとしてもこんな美人に感謝されるのはいやではない。それに格闘家であるナギもジャッキーとはかなり気があうらしく、楽しげに話をしている。こうなると必然的に…パーティーを組まないかという話になってくる。
「ねぇ、ジャッキー、よかったらあたしたちといっしょに旅をしない?あんただったら大歓迎よ!」
「そうだな、俺も気に入ったよ。よかったら来ないか?」
「…いや…俺…さすがに…」
ジャッキーはちょっとどうしたものかと悩んでいるようである。ジャッキーとしてみればリキュアやナギ、それからクーガーと仲間になるのは感覚的にはいやではない。年齢も…女性陣はちょっと高めだが、男性陣は同じくらいである。話題も合うし楽しそうである。しかし…いくつかの問題で相容れるのだろうか …
ジャッキーの悩みというのは、リキュアやタルトが帝国人であるということだった。既にお話したとおり、はるばる中原からやってきたジャッキーにしてみれば、帝国人というのは付き合いにくい相手である。現在の中原はサクロニアと同じように帝国に敗北した状態である。半植民地状態…といってもいい。ジャッキーはいろいろな事情もあって…主には灰色の予言者の言葉にしたがって、だが…この帝都に来たのだが、本来ならレジスタンスをやっていてもおかしくはないのである。
それを考えると、もしこの二人の帝国人を含むパーティーが「親帝国」のスタンスとすれば(帝都にいるパーティーなのだからそう考えるのが普通である)決定的なところで絶対に相容れないということになってしまうのである。
さらに大きな問題は、ジャッキー自身の目的のことだった。目の前の連中は、たしかに悪い奴らではなさそうに思える。しかしジャッキーには大きな目的があった。彼の故郷である中原から失われた伝説の神器『黄帝の剣』である。
『黄帝の剣』というのは、中原に伝わる伝説的英雄『黄帝軒轅氏』の剣である。進化の力を持っていたという文化英雄、黄帝は中原世界に最初に国家を作ったという。その剣こそが『黄帝の剣』だった。
炎や風のようなわかりやすい力と違い、黄帝の力である『進化のルーン力』は、そのあまりの異様な力と危険性のため、黄帝の子孫である軒轅氏族によって守られ、隠されていた。しかし…
先年の帝国軍による中原攻略によってその剣は奪われ、持ち去られたのである。黄帝の剣の喪失は、中原の魔力バランスを崩壊させ、戦乱と天変地異に襲われていた。それだけではない…
奪われた黄帝の剣は、帝国のサクロニア攻略に使用されたということすら、ジャッキーは知っていた。さすがにそれがどのような運命をもたらしたのかについては、十分な情報があるわけではなかったが、ともかく今のジャッキーには、目の前の帝国人らしい連中とパーティーを組むところまでは、とても踏み切れなかった。彼には彼の目的と運命があるのだ。
まさか目の前の連中が、彼の目的『黄帝の剣』と闘い、そのもたらした悲劇を知っていたなど、想像もできなかったのである。
「そうか、また会えたらいいな」
「ジャッキーのおにいさん、またね」
ジャッキーは手を降って別れを告げる。また会えたら…そしてジャッキーの道はこの先何度も彼らと交差することになるのだったが…
* * *
こういう具合でジャッキーと別れたタルト達だったが、リンクスの問題については全く目処が立たなかった。せっかく見つけたリンクスをスレイブマスター・ジークが連れ去ってしまったのだから話が簡単にいかないのは当然である。恐らく…いくらスレイブマスター・ジークが恐ろしい力を(体力とかそういう問題とは別に、魔力もすごそうである)もっているとしても、それほど遠くまでテレポートはできないだろう。(自分でテレポートが出来るタルトやリキュアにはそれがどれほど大変なものかよくわかるのである。)恐らくはまだこの帝都のどこかに隠れているはずだ…というのが一番素直な予想である。
しかし、見つけ出すといっても並大抵のことではないし、仮に見つけ出したとしてもジークを捕まえるとか、リンクスを取り戻すというのは至難の技である。ジークにせよリンクスにせよ…普通の神将では手も足も出ないほどの強さだったし、(自分が「普通の神将」であるリキュアがそう感じるのだから間違いない。)見方によればリンクスは人質なのである。しかし…時間を置けば置くほどまた手がかりがなくなってしまうわけで、何か手を打たないと最悪の事態になってしまうだろう。と言っても …
何が困ったといって、ジークを見つけるために必要な人手が足りないということなのである。たった5名のこのパーティーでは、広い帝都の中をたった一人の人間を…それも大至急探すのは至難の技である。そういうのが専門であるわけでもない彼らだから余計大変なのである。せめて誰かこの帝都で頼りになるつてがあれば、という気になるのも無理はないのだが …
散々考えたのだが、彼らに思い付くあてというのは一つしかなかった。
「しかたねぇなぁ…奥の手を出すか…」
「なんだタルト?奥の手っていうのは?」
「いるじゃねぇか、一人だけ大物の知り合いが帝都に…」
「…最高神官様ね…どうかしら…」
「あ…そうだな…たしかに…」
タルトが思い付いたつて…「最高神官様」というのは、他ならぬクレイ・クレソンズのことである。帝国最高神官クレイ・クレソンズ…この帝国でもっとも高位の神官の一人である彼は…タルト達の知り合いだったのである
* * *
今では盗賊冒険者そのものであるタルトだが、実は帝国の大貴族ユーレックス家の一員だった。「だった」という過去形なのは、彼はずっと昔にある事件を契機に、ユーレックスの名を捨て、冒険者となったからである。当然そんな過去はトラウマとして、何度も彼の前に立ちふさがったのだが、リキュアやセミーノフ、そして何より亡きランドセイバーの助けで乗り越えてきた。
そういうタルトであるから、帝国で最も力ある存在である「帝国最高神官」にも、貴族として面識があってもおかしくはない。が、その中でも大地の最高神官クレイは特別だった。タルト達がクレイを知っているというのは…ただの知り合いとか、昔一度名刺交換をしたことがあるとか、その程度のレベルではない。何度かいっしょに冒険をしたことだってあるし、命懸けでお互いを助けたことだってある。そう…タルトとクレイの関係は、冒険者仲間というのが正確な表現だったのである。
しかし、今タルト達が「しかたねぇ」と言ったというところで判るとは思うのだが…正直な話、あまりタルト達はクレイに頼りたくないと思っているのは事実だった。別に仲が悪いとかそういう訳ではない。タルトの冒険人生で、喧嘩別れに近い元仲間がいることを考えれば格段に仲がいいと思うし、たまには連絡のやり取りもある。(といってもたいていはタルトが一方的にクレイのところを訪ねるのだが…)それではなぜあまりクレイに頼りたくないと思っているのかというと …
タルト個人の見解では、クレイはどうしようもないほど頼りなかったからである。
クレイという若者は…一応帝国では戦いをつかさどる神将の最高位、「最高神官」という役職に就いているのだが、直接会うとどうみても気の弱い戦士としか言いようがない。
決断とかそういったリーダーシップを取る事はまれだったし、戦い振りを見てもどうも安心感がない。たしかに戦闘能力だけ考えるとずば抜けて…ほぼ最強の戦士と確実に言うことが出来るのだが…どういう訳か安心感がまったく感じられないのである。少なくとも…彼らが知っているクレイはそうだった。
もっともこれはクレイの生い立ちや…それから今おかれている立場、そしてその力と考え合わせると、無理もない…といわざるをえない部分が多い。いや、正直な話タルトの本音でも、「クレイはかわいそうな奴だ」と思っているくらいである。
* * *
クレイ・クレソンズ…本名は恐らく違うだろう…彼もまたリンクスと同じく元剣闘士奴隷だった。
剣闘士としての実力はどうだったのか、タルトはよく知らない。ただ、クレイは見た限り背も高いし、ほれぼれするくらい逞しい肉体を誇っていたし、ちょっとベビーフェイスなルックスと不思議な緑色の髪の毛も印象的である。人気の方はまずまずだっただろう。しかし…とにかくクレイは剣闘士「奴隷」だったのである。
さっきも話に出たとおり、剣闘士というのは魔法によって自我を奪われた戦闘マシンである。見世物として戦わされるために悪魔の鎖で肉体の自由を奪われてしまった彼は、体を(これも魔法で)鍛えられた上、ただコロシアムの中での戦いの日々を送っていた。その彼は…ある日魔法実験の犠牲者に選ばれたのである。
さっきも話したリンクスや、そして恐らくタルト達の難敵ジークも含めてそうなのだが、どうも剣闘士奴隷というのは魔法実験の犠牲にもってこいらしい。元々魔法的な技術で創り上げられたタフな肉体がさまざまな危険な実験にちょうどよいのだろう。とにかく …クレイは帝国を支える宗教結社の一つ、「聖母教会」の魔法実験の犠牲者となったのである。もう100年も前のことである。
聖母教会とそれに協力する帝国魔道士の手でクレイは特別な力を持つ戦士として目覚めさせられた。氷河のルーン…すべてのものを凍てつかせる強大な力を持つルーン力をその身に宿すことになったのである。もちろん彼自身がそんな事を望んだわけはない。ただ彼は…心を取り戻したときには人間ではなくなっていた、というだけのことなのである。ただ、彼が目覚めたのは剣闘士だったころから100年の歳月が経っていた。魔法実験の副作用で100年間氷漬けで眠り続けていたのである。
こういうわけで…目覚めて、突然に氷河のルーン力を持つことになったクレイはそのまま帝国の守護神として最高神官に祭り上げられた。とにかく彼にしてみれば「突然」の自分の肉体や地位の変化にびっくりするのも当然である。100年の歳月だろうがなんだろうが眠っていた彼には関係はない。それどころか…ようやく人間の心を取り戻したばかりの彼なのだから、そもそもクレイという「人間」が何であるかですら…動揺無しには受け入れることができなかったのである。これは…いくらなんでもかわいそうな話というしかない。
こういう訳でクレイは、自分が何者か、なぜ今の自分があるのか、自分の歩まされた道は何だったのか…というもっとも基本的なことで戸惑いながら今まで何度もタルト達と冒険などをしてきたのである。「帝国最高神官」などという肩書きや、無限に近い強大な力など彼にとっては訳の判らないものでしかない。というところまではタルトだって、他の全員も…重々理解し、同情くらいはしているのであるが …
いざ、クレイに応援を求めるとか…仲間となるとすると話は別である。
* * *
とにかくこういう具合で内向的で、そのくせ人百倍くらいパワーがあって …時々剣闘士丸出しの獣みたいな暴走をして…となると、タルトから見ていささか面倒なのである。100歳以上という年齢効果は眠っていたんだから何の足しにもなっていないのは当たり前だし、とてつもない戦闘能力は喉から手が出るくらい欲しいのだが、それよりも先にリンクスとジークを見つける知恵も欲しいのである。こういう時にはクレイ「猊下」はぜんぜん頼りにならない。単にいっしょに悩んでしまって…ぜんぜん結果が出ないような気がしてしまうのである。
「あまり気が進まないなぁ…クレイはなぁ…」
「わかるわよ。でも他に頼る人、いるの?」
「…いないな。こまったな…」
困惑した表情を浮かべてタルトはリキュアに答える。リキュアだって他に名案があるわけはない。とにかく今までの経験上クレイに相談すると、「よい結果は出ない上に、騒ぎが大きくなる」という折り紙付きなのであるから、もはや破れかぶれと同義語である。
最後に決定を下したのはナギだった。
「仕方ない。他にツテもないんだからクレイに声をかけてみよう。久しぶりに会って、他にも話しておかないといけないこともあるし…」
「そうか…そうだな」
タルトはナギの言葉の意味が痛いほどわかった。クレイに、イックスの死闘の結末とセイバーの最期だけは…話しておかないといけないと、わかっていたからである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
