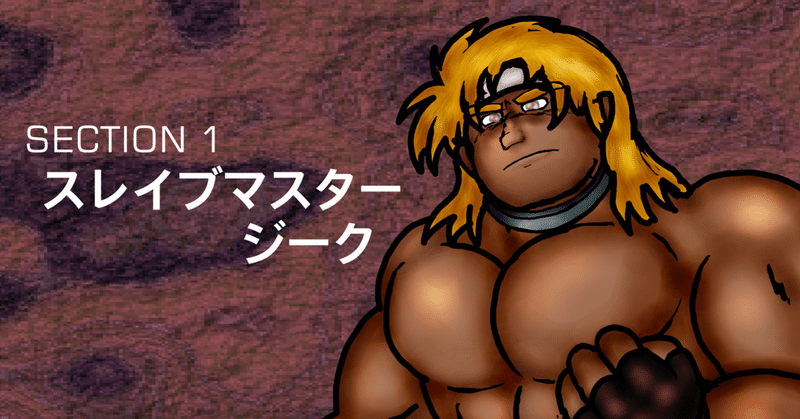
10.「今のレムスくらいだったよな…」
帝国女神神殿での乱闘の後、ナギたちは宿屋へ戻って今後の対策を練っていた。クレイは大神殿で他の帝国最高神官や神将たちと、今回の件に関しての連絡調整会議をしなければならなかったので、先にナギたちだけでの帰還…というわけである。
一番頭を悩ませたのは、クーガーやレムスのことである。今回の闘いでは幸いまだ若いクーガーやレムスは矢面に立たずに済んでいたが、いつまでもこの幸運が続くわけはない。第一この間の「リンクスの偽死体争奪戦」では、レムスとクーガーが危なかったのである。あの時は幸い通りすがりのジャッキーとかいう武闘家が助けてくれたので良かったが、このままスレイブマスター・ジークを追いかければ、ただでは済まないことは容易に想像がつく。
命かけのバトルで疲れ切ったクーガーは、クレイの屋敷の狼犬マグに抱かれて流石に眠っている。その横でレムスは真っ赤になってリキュアやタルトに抗議していた。
「イヤです!僕は絶対に降りません!」
レムスは頑として退かないようだった。彼はイックスでの孤独な戦いのときに、同年代のリンクスが親身になって彼を支えてくれたことを忘れたくないのである。というか、レムスはリンクスがいなければ生きていなかっただろうとすら思っていた。だからリンクスの解放は、レムスが絶対に手放してはいけない、いわば心の支えとして信じていたのである。
しかしいくらレムスが5年の歳月で少しは強くなったと言っても、とてもあのスレイブマスター・ジークに太刀打ちできるとは、タルトやリキュアには思えない。いや、本音を言うとタルト自身あの恐るべきスレイブマスターには勝てる気がしないのである。とてもでないがレムスやクーガーを同行して、奴らを追撃することなどできるとは思えなかった。タルトですらこうであるから、クーガーの母親であるリキュアに至っては猛反対である。
「無理よタルト、子供連れて奴らと戦うなんてありえないわ。万一のことがあったらどうするのよ!」
「それじゃリンクスくんを見捨てるんですか?!」
「そんなこと言ってないわよレムス!私とタルトが追いかけるわ!」
「僕だってもう大人です!十分戦えます!」
「まだとても無理よ二人には!この街で待っていればいいじゃない。知り合いに預かってもらえるわよ!」
絶対反対のリキュアは、もう一人の大人であるナギからもなにか言ってもらおうと視線を向けた。ところがナギの見解はいささか違っていた。
「リキュア、俺は…レムスとクーガーを連れてゆくしかないと思う」
「!!ナギ!?」
リキュアはナギの意外すぎる意見に、目を怒らせた。しかしナギはその視線を押し返すように言葉を続けた。
「よく考えろよ…まさかクーガーをこの街に残す気か?世界に唯一人の…人間と鋼鉄精霊の子なんだぞ?」
「!!」
ナギの爆弾発言は、リキュアやタルトにコップの水を浴びせかけたような衝撃を与えた。
「そ、それは…」
「俺は正直、この帝国という国を信じていない。いや、帝国だけでなく、国とかそういう連中を、だ」
「…」
「リンクスだってクレイだって、巨大な組織の陰謀の犠牲者だ。エビックヒーローだなんだって、雲を掴むようなものを狙ってああいう連中が好き勝手している。そんなとんでもない奴らの真ん中に、クーガーやレムスを置いてゆくなんて危なすぎる。」
「ナギっ!」
「いいかリキュア、わかっているはずだ!クーガーは…この子は奴らの言う、エビックヒーローに一番近いんだぞ!」
ナギの恐ろしい宣告に、リキュアは蒼白になった。彼女にもナギの論理が正しいことがわかっていたのである。クーガーは、ランドセイバーの忘れ形見は、生まれたその時から、平凡な一生を送ることなどできるはずはないのである。世界で唯一人の鋼の精霊と人間の子…
「わかっている…わかっているのよ、ナギ…」
ナギの非情とも言える指摘に、リキュアは泣きそうな顔になって答える。できる事ならばクーガーに、平凡な一生を送ってほしい…母親としての望みである。栄光や地位、名声など、なんの意味もない。
しかし恐るべき陰謀と魔道が渦巻いているこの世界では、十分な力がないと生き抜くことすら難しいのだ。特に…今は…
だから彼女やタルトは、クーガーに生き抜くための力を伝えようと、今まで必死に手元で育ててきたのである。
じっとナギの言葉を聞いていたタルトは、頭をかきながらリキュアに、そしてレムスに言った。
「まあ考えてみれば俺もリキュアも、多分ナギも、冒険を出る羽目になったのは今のレムスくらいだったよな…」
「タルト…」
「その年でいきなり上方世界っていうのはちょっとハードだけど、まあ俺たち無しで帝都に放り出すよりましか…」
タルトにせよリキュアにせよ、冒険に出るきっかけとなった事件に出くわしたのは、今のレムスより若い時だった。いや、レムスだってあの時はまだまだ半人前だったが、五年前の絶望的なイックス戦役をくぐり抜けているのである。今ならもうタルト達と肩を並べて闘う資格はある。そして…そのソファーで大きな狼を枕に眠るクーガーだって…
クーガーは鋼の精霊の魂を持つ子なのである。
「しゃーねーな、クレイが帰ってきたら言ってみるか。絶対猛反対しそうな気がするんだけど…」
タルトは渋々ながら、この面倒な役回りを引き受けることにしたのである。
* * *
クレイが戻ってくるといよいよ本格的なジーク追撃戦の相談会が始まった。戻ってきたときのクレイの表情は…まああまり芳しいものではないのは予想通りで、どうせあのじいさん(つまり天空の最高神官殿だが)とおばさん(これまた海の最高神官)の二人にねちねちといびられたのだろう。と、言っても今回は天空の最高神官タラントラス殿は肝心なときに不在という失態をさらしたのだから、クレイはあまりひどい目にあったとは思えないのだが…それでもやはりあの二人と遣り合うのはかなり疲れるものらしい。
「ジークは間違いなく上方世界に…リンクスを連れて…逃げたみたいだ。早急に追撃するつもりだ。」
クレイが一同にそう宣言すると、全員はうなずいたが…いささか困惑を隠せない様子だった。微妙な困惑の表情を見て取ったクレイは少し首をかしげる。
「?どうしたんだ?」
「上方世界っていうと、神々の住んでいるところだよな?クレイ。」
「…ああ、タルト、前にお前も行ったとは思うが」
「問題は…あの広い上方世界のどこに彼奴等が行ったのかってことだよな」
「…あ、ああ。確かに…」
クレイはタルトの指摘にちょっとあわてた。非常に間のぬけた話なのだが、この瞬間までクレイは…「ジークを追って上方世界にいったそのあと」をまるで考えていなかったのだ。
「…当ても無くさまようってわけにはいかないな…さすがに…」
「ああ。そうだな…何か良い案はないかな?みんな…」
クレイが全員の顔を見渡すと、一行は再び首をかしげて思案に入った。上方世界の地理…というものが断片的にしか判っていない以上、あまり無謀な作戦は危険である。可能な限りジークの目的や行きそうなところを調べておきたい…という気もする。
もちろんあまり時間をかけると、ジークの後を追うということができなくなるということもあるので、最小限度の調査で追撃を開始しなければならないのであるが… だからといって無計画、無防備でゆくのは愚の骨頂である。
* * *
ナギやタルトが「上方世界追撃作戦」に慎重になっているのは、上方世界の特殊な…魔法的な環境の問題があったのである。上方世界というのは神々の領域である、というのはさっきも述べた。この魔法力的に高次元な領域においての旅行ではなかなか難しい問題がある。最大の問題は…魔力が回復しにくい、というものだ。
時間が地上と違った感覚で流れる上方世界では、普通の人間ではなかなか魔法力が回復しない。もちろんその代わりに一度かけた魔法はなかなか消えない、という便利なところもあるのだが、いずれにせよこういう問題は上方世界にゆく冒険者の悩みの一つである。
一番よい解決策は、ある特殊な儀式呪文によって上方世界でも多少魔力が回復するようにすることなのだが、これはかなり難しい問題があって…部族の英雄とかそういう少数の連中しか使うことはできない。つまり支持者の支援を受けて、地上世界から魔力を供給してもらうという方法だった。帝国最高神官クレイならそれも可能なのだが、ただの村の青年拳法家であるナギなどにはどうやっても不可能である。
こうなると一番現実的なのは…あらかじめ魔法の物品や御札などを準備して、出来るだけ魔法力を使わずに済ますようにするという方法になる。こういう準備にかなりの時間が必要なのである。
それにもう一つ…これはクレイよりもナギやタルトが思案していたのだが… どうしてもジークの目的が判らない、ということがあった。スレイブマスター・ジーク…今まで集めた数々の噂では、隷属の鎖の神官戦士であり驚いたことに元剣闘士奴隷だということだった。どう考えても剣闘士が同じ剣闘士を調教する、ということ自体何か妙なものがある。もちろん腹いせ、とかそういうものもありえるのだが…それにしてもジークの場合どこか挙動がおかしい。まるでリンクスを溺愛しているように見えるからなのである。そのくせ…リンクスをいたぶって喜んでいるようにもみえるし(ジークにSMの気があるのかもしれないか)…
いや、それだけならまだしも…それならそれでなぜジークは今回リンクスを連れて、わざわざ帝国女神神殿でクレイを待ち伏せしたり、これまたわざわざ上方世界へと逃げたりしたのだろうか?何か目的やなにかがあったりするのだろうか?
「どうも気になるんだ、クレイ。たとえば…」
「たとえば?」
「ジークの行動は…隷属の鎖教団の命令なんだろうか?」
「?そうじゃないのか?あいつは隷属の鎖教団の神官戦士なんだろう?」
「それは…そうなんだが…」
ナギは納得できないような表情でうめいた。いくら考えても…ジークのあの行動が隷属の鎖教団の命令によるとは思えないのだ。そう…リンクスを溺愛しているようにしかみえないジークのあの様子は…何かおかしいのである。それに今、隷属の鎖教団の連中がわざわざ帝国に喧嘩を売るようなそんなことをしでかすのだろうか?奴隷商人である彼らにとって、最も上得意なのは帝国なのである。
どうしても納得できないナギは思い切ってクレイに提案した。
「あのさ、ちょっと相談なんだけど…」
「?」
「追撃をする前に、一度隷属の鎖の本部に行ってみたいんだ。どうだろう?」
「鎖の都へ、か?!」
クレイは露骨にいやそうな表情をする。ジークやリンクスと同じように元剣闘士であるクレイは、隷属の鎖教団に対して敵対感情をはっきりと持っている。そんな状態で隷属の鎖の本拠地「鎖の都」にでかければ、とても我慢ができずキレてしまいそうで…というわけであろう。
「鎖の都に行ったとしても、素直に情報を教えてくれるのか?」
「それは判らない。ただ、大方のことは判ると思うな。」
ナギは自信ありげに言う。ナギの思考の中には…もしジークが隷属の鎖の命令で動いているのなら、隷属の鎖連中は何もしゃべらないだろうし…逆に勝手な行動をしているのなら何か漏らすだろう…という考えがある。それだけでかなりの情報である、というわけである。
結局クレイはナギの強い意見に説得された。しぶしぶクレイはうなずくと言った。
「飛行呪文でゆけば…1週間だな。いろいろ準備もあるだろうし …出来るだけ早く頼む。」
「そうだな、今回はタルトとリキュアさんとで行くよ。その間にクレイはレムスとクーガーのおもりをしてくれ。今のうちに色々教えてやってほしい。特に上方世界での振舞い方とかを…」
「…えっ?…まさか上方世界にこの子達を連れてゆく気なのか?」
驚くクレイだったが、これは昨夜ナギとタルト、リキュア達で何度も話し合った既定路線である。クレイは完全に押し切られるような形で、レムスとクーガーを預かることになってしまったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
