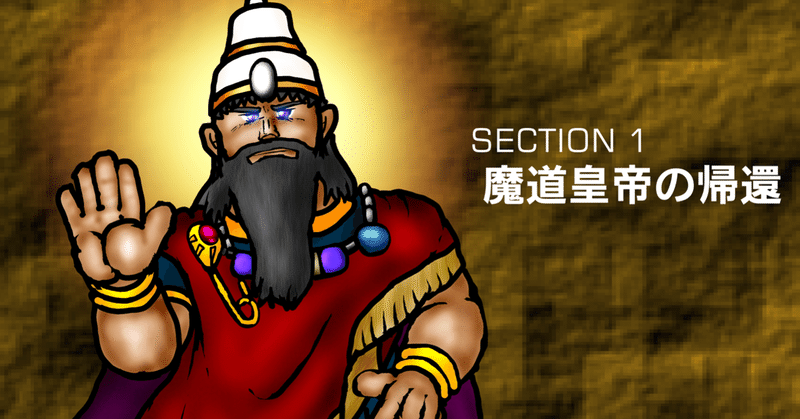
6.「そんなことだと思ったわ」
クレイが見た、信じられないもの … 味方である聖母教会の大女祭を暗殺しようとした烈の姿 … この異常な光景を彼はすぐには仲間に話すことは出来なかった。何かの間違いではないか … そういう気がしてならなかったからである。
しかしこの問題はそのまま何も手を打たないでいいものではなかった。悩んだ挙げ句、クレイはレムス達に事の顛末を告げざるを得なかった。
「ほ、本当ですか!?クレイ様!」
「まさか、烈さんが!?」
ヴィドやレムスは半分怒ったような表情でクレイに問い詰める。クレイはどう答えたらいいのかわからず、重苦しい表情でうなずくだけである。
「信じられませんよ。あの烈君が … 」
ヴィドはショックで腰を抜かしそうな様子だった。ヴィドと烈といえば大体パーティーに参加したのも同時期だし、現実主義であるところも似ている。おしゃべりなヴィドと寡黙な烈だったが、互いに不思議と馬が合うようだった。とにかくこの中では誰よりもヴィドがこの事件に衝撃を受けているようだった。
ヴィドやレムスだけでなく、ナギやリキュア、クーガーにとってもこの事件はショックだったらしい。ほとんどが皆黙り込んで、クレイを恨めしそうな目でにらむのである。別にクレイの責任とかそう言うわけでは決してないのだが、やはりそうなってしまうところがパーティーリーダーの辛いところであろう。
唯一いつもとかわらなかったのはジークである。ジークと烈といえば、正直言ってつい先日まで反ジーク派の筆頭だったレムスすら危ぶむほど「本当に」仲が悪かった。だいたい烈はジークがいる所には絶対といっていいほど姿を現さないし、例え現したとしても必ず … 全く隙を見せない。いつでも戦える態勢なのである。逆にジークはといえばジークで、全くそんなことを気にしていないというか、そもそも烈の存在そのものに気が付いているのか不安になるほど悠然としているのである。レムスの想像なのだが … ジークは烈のことに全く興味が無いとしか思えないありさまだった。
そんな普段の状況が判っているだけに、さすがのレムスもジークに「もっと深刻そうな顔をしてくださいよっ!」とか … 無茶な要求はする気もなかった。ただ、こういう事態であることだけは … せめて認識するのが当然だと思ってしまうのだが …
そんな具合でいらいらしてしまったレムスは思わずジークに半分噛み付くようにいった。
「ジーク、なにかアイデアとかないんですか?」
「?アイデア?」
「烈さんが僕たちの敵にまわったんですよ!なにをぼぅっとしているんですか」
わずかに小首をかしげて答えるジークに、レムスはやっぱりという表情をした。やっぱりジークは事態を全く認識してない … レムスはだんだんヒステリックになって(いつものことなのだが)ジークに噛み付き始めた。どうもレムスはこういう行き場の無い感情を手当たり次第ジークにぶつけてしまうらしい。(誰の責任というわけでもないし、そもそも烈が敵に回ったということ自体はっきりしないことなのだが)
クレイはクレイでまるで「ぼうっとしている」と非難されているのはクレイ自身であるかのようにすまなさそうな表情をするし、いつもなら「それは証拠がありませんよ」とかいってなだめ役に回るヴィドも今回にかぎってはパニックだし … このパーティーの恒例の紛糾状態が全くいつもと同じように持ち上がり始めたのだった。いつもならこのまま何の結論も出ずに2、3時間はもめるところなのである。
ところが …
* * *
「皇帝に会う。」
「??」
ジークがぼそりと … 本当に唐突にこんなことをいったのである。レムスもクレイもヴィドも、前後の脈絡が全く見えない。「烈が敵に回った。どうするんだジーク!」→「皇帝に会う」では、少なくともレムスには全く見当外れな答えに聞こえた。
「聞いているんですか!」
「? … だから皇帝に会う。」
ジークは切れそうになっているレムスをかえって不思議そうに見た。その目はあたかも何かにおいのようなものを嗅ぎ付けている獣そのものの目だった。少なくとも傍で見ているクレイにはジークが何かを感じとっていることだけは確信持てた。それも … クレイが感じている何かと同じだった …
「レムス。俺もジークに賛成だ。」
「クレイさんも?!どうなっているんだよ … 」
クレイとジークという巨体レスラーコンビがそろって訳の判らないことを言い出したとでもいうように、レムスは露骨に渋い顔をする。いや、レムスだけではない。脈絡の無いことは嫌がるヴィドもはっきりと不振そうな表情をしている。口下手なクレイはどう説明をしたらいいものか困惑してしまう。ましてやジークは始めから説明しようという意図もないようだった。
ところがリキュアはどうやら脳筋コンビの意図がわかったらしい。
「そうね、あたしも賛成だわレムス。」
「 … よく判るように説明してくださいませんか?」
「だって、こういう異常な事態が起きているのは、結局のところ皇帝陛下があの馬鹿でかい天空城をひっさげてお帰りになってからでしょう?皇帝に直談判するっていうのは、安直だけど的外れじゃ無いわ」
「!」
レムスは意外な(というほどでもないが)リキュアの意見に逆にびっくりしたようだった。確かにいわれてみれば彼女のいう通りである。皇帝が御帰還遊ばされてから「帝都の閉鎖」とか「謎の行動をする烈」とか、奇妙な事件が相次いでいるのである。
「それはまあ判りますがね … 相手が知らぬ存ぜぬといってくるとそれっきりじゃないですか?残念ですけど今まで見た限りでは、単に会いにいって成功した試しなんか無いですよ。特にうちのパーティーじゃねぇ … 」
ヴィドはあくまで懐疑的である。ただ様子を伺いに行くだけならあまり効果は期待できない。少なくともこのパーティーではしらを切る相手から情報を聞き出すほどの能力は丸でない … ということをヴィドはいやというほど知っている。一番苦労させられている彼だから、それがどれほど(このパーティーで)難しいことなのかよく判る。
「それはそうだわ。でも手掛かりはそれしかないわ。むしろ『単に会いに行く』以上の情報を探り出す方法を考えておきましょうよ。」
「そうですねぇ … それしかないでしょうね … 」
ヴィドもしぶしぶ同意した。たしかに彼女のいう通り、今のところ他にこのパーティーに使えそうな「手掛かり」というのは存在しないのである。魔法で調べるとか、現場の遺留品から手掛かりを探すとか、そういう高等な技は全く持って不可能な彼らである以上、ストレートな「直談判」以外には手段はない。それならば … ヴィドやリキュアが最大限度情報を引っ張り出せるように下準備をするしかないのである。
今一つすっきりしないような顔をしているヴィドやレムスに、クレイは安心させるようにうなずいた。というわけで、ようやくにして「皇帝陛下に会いに行こう」作戦は決定されたのである。
* * *
「リキュア … うまく行くかな?」
「そうねぁ … あの場ではそう言ったんだけど、ヴィドの気持ちもわかるのよねぇ」
クレイ達の計画がようやくまとまったあとでも全員が気ままな時を過ごすというわけではない。リキュアとタルトはいろいろ明日以降の準備ということで相談をする羽目になっていた。特に殴り合いよりも情報収拾がメインということになれば、忍び担当であるタルトは必然的に忙しくなるのである。
「昔みたいに、ただにこやかにおしゃべりしていても駄目だわ、タルト。セイバーみたいな人がいるわけじゃないんだから。」
リキュアはもう5年も前に死んだはずのセイバーの名を持ち出した。彼女にしてみればたった一人の旦那だし、何かにつけ思い出してしまうのは仕方が無い。(タルトにしてもそうなのだから … )それにセイバーみたいなしっかりした舵取り役が居ない現パーティーは何かにつけ迷走をしてしまうのだから、彼女にしてみれば不安極まり無いことだろう。
といっても死んでしまった仲間を懐かしんでも仕方が無い。セイバーのように何でもない雑談から相手の状況や貴重な情報を引っ張り出せるすご腕の仲間が居ないのは残念だが、居ないなら居ないなりに … 少々強引でも他のルートから情報を見つけ出すしかないのである。
「俺はクレイ達が警備の目を引き付けている間に、周囲をうろついてみるつもりなんだが、サポート頼めるかい?」
「そんなことだと思ったわ。いいわよ、タルト。」
リキュアは笑顔でOKする。全くこの二人は … もし二人が全くのシングルならきっとすてきな恋人同士になっていたことだろう。それほどまでに息が合う二人だった。リキュアの旦那ランドセイバーが無くなって以来、セイバーの思い出と忘れ形見クーガーを二人は守ってきたのである。
しかしリキュアにはセイバーの思い出はあまりにも大切過ぎたし、一児の母でもある。タルトはタルトで彼が追い続ける大切な人、帝国最強の神将ジャコビーがいる。二人はいつまでも本当に仲のいい親友 … そうあり続けることだろう。馬鹿な奴等 … 本当に馬鹿な二人かも知れないが、それで二人は満足だった。
それにしてもタルトの計画は考えようによっては危険極まり無いものである。得体の知れない(といっては言い過ぎかもしれないが)帝国皇帝イサリオスの城の中を偵察するというのだから、どういう事故が起きても驚くにはあたらない。リキュアがいくらサポートするといっても最後に頼りになるのは自身の能力と運だけである。それをいとも簡単に「やる」と言ってのけるタルトもすごいし、そんなタルトに「いいわよ」というリキュアもとんでもない。二人とも互いの技量に絶対の信頼をおいているのだろう。「出来ないことは始めから言い出さない」「言い出したことは必ずやり遂げる」という無言の信頼 … それが二人の間に自然のうちに成り立っているのだ。
必勝の自身と信念をもってタルトはうなずいた。そんなタルトをリキュアはほほ笑み、うなずき返したのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
