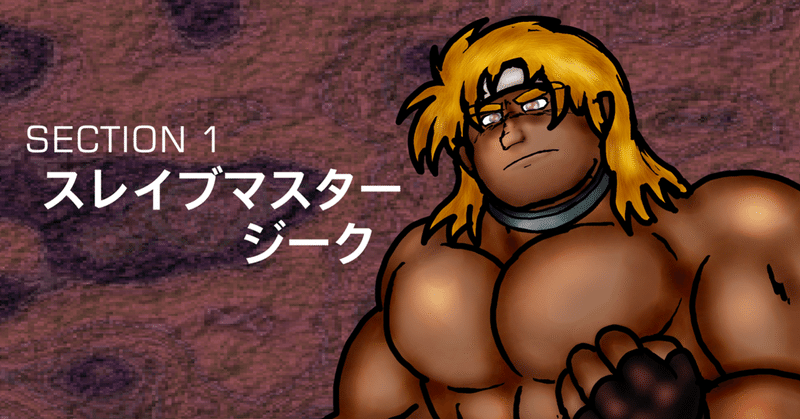
7.「セイバーは…死んだよ」
クレイの屋敷というのは、帝都では一番上流の貴族たちがすむ「新帝都」の一角にあった。石造りのその建物は…正直言うと「帝国最高神官」という仰々しい肩書きから見るとあきれるほど小さい。庭の方だってもっと豪華な広い屋敷なら帝都にはいくらでもある。ただ、きちんと刈り込まれた芝や手入れの行き届いた庭木がごてごてした装飾の多い帝都の町並みのなかで独特の清涼感をもたらしていた。
タルト達はうじゃうじゃと…文字どおりうじゃうじゃと、という感じなのだがクレイの自宅の前に列を成してあらわれた。人口も多いこの帝都だが、タルト達のような「ごちゃまぜパーティー」が列を成してこの高級街に出現すると、なんとなく妙な違和感がある。個人個人はけっこうまともなのだが、徒党を組むと何か「ごちゃごちゃ」という感じがする。体格のいいナギからはじまって、まだちび助のクーガーまで集まるとそういう感じはいや増すのだろう。
それにもう一つ原因はクレイの家にこういう集団が押し寄せるというのは、そもそもきわめて珍しいことなのである。
最高神官とはいえ元剣闘士だったクレイは、帝国の貴族や実力者の中ではどうしても浮いた存在になってしまう。いくら「最高神官だ、なんだ」って奉られていても、周囲の連中は決して彼のことを温かく迎えてくれるわけではない。言ってしまえば「奴隷という獣」が最高神官という肩書きがついただけという、考えれば考えるほど腹立たしい見られ方をしていた。
確かにクレイは…これは残念なことなのだが…洗練された高雅な趣味とかそういうものには縁が無い。体力お兄ちゃんというところは丸出しだったし、血が頭に上りやすいという側面もある。こういう部分が帝国の首脳陣を始めとする社交界の方々には「所詮剣闘士、人間じゃない」という見られ方をさせる原因となっていることは否めない。(実際、ある首脳などは「クレイ殿には奴隷女でもあてがっておけばいいのだ」と公言してはばからないのであるのだから、ひどいものである。)クレイはクレイでこんな仕打ちを受ければ誰でもそうするとおもうが、与えられた小さな自宅に引きこもって、誰にも会おうとはしなくなってしまった。もちろん貴族の方々もクレイにわざわざ会いにゆこうなどしないわけで …まさに悪循環である。
こういう理由でクレイ・クレソンズ邸はこんなにぎやかな連中が訪れるのは久しぶりだったのである。
* * *
クレイはいつものようにテラスに座って庭を眺めていた。執事であるジョルジオが極めてきちんとした性格をしているので、庭の状態はすこぶるいい。このジョルジオという執事は、一応帝国の某お偉方からクレイにつかわされた監視役だった。といっても、クレイがそれを知っているということは、もうぜんぜんその役目を果たしていないのは明らかである。さすがに2年もクレイの世話をしていると、いつしか情が移ってしまったのだろう。今では逆にクレイに帝国や世界の情勢などを話したり、相談相手になったり…とにかくクレイにとっては唯一人の親身になってくれる人だった。
「だんな様、そろそろ寒うございますよ。晩御飯にいたしますか?」
「あ…ああ、わかったよ。そうするよ。」
台所のジョルジオの声に、クレイは振り向いた。ジョルジオ自慢の白身魚の料理のかぐわしい香りがクレイの鼻をくすぐる。体格から予想されるとおり、クレイは普通の人の2倍以上は食べるし、ジョルジオの特製料理は全く味覚に鈍感な(これも剣闘士時代のなごりだろう)クレイでも「すばらしいんだ」と実感することが出来るほどのものである。
クレイはのそりと…文字どおり熊のようにのそりと、という感じでテラスの椅子から立ち上がると、食堂へとむかった。ジョルジオはせっかくの力作の料理が冷めてしまうと半日くらいは機嫌が悪い。それはそれで…別段たいした問題でもないのだが、クレイ自身の空腹感もあっていつもよりはちょっと早めに食堂へといくことにしたのである。
ところが食堂へゆく廊下にでたところで、クレイはジョルジオのちょっと緊張したような声を聞いた。
「はい、いや、だんな様ですか?」
「ああ。会わせてくれよ。いるんだろ?」
「どなた様ですか?だんな様のお友達ですか?」
ジョルジオの声はかなり露骨に「不信」という意識をあらわしていた。大体クレイの家をここしばらく訪れる相手というのはろくな相手がいない。普通はクレイの「帝国最高神官」という肩書きを利用しようとしてやってくる馬鹿ものどもである。こういう相手はジョルジオが普通はあしらってくれる。
ところが玄関の傍まで来たクレイは…その声に妙な聞き覚えがあることを思い出した。どうも昔聞いたような…なつかしい声 …
けんもほろろにその客を追い払おうとするジョルジオに、クレイは慌てて玄関口へと飛び出した。
「ジョルジオ!ちょっとまった!」
「だんな様!」
「クレイっ!久しぶりだなっ!」
「久しぶりじゃない、クレイ。驚いたわ!」
玄関口にいた客人はにぎやかそうな5人組だった。過半数はクレイの知った顔である。タルト、ナギ、レディー・リキュア、レムス…あの、懐かしい昔の仲間たち …
妙に嬉しそうにクレイは彼らを部屋に招き入れた。クレイが今まで感じたことのない不思議な感情…懐かしさが彼の心を占めていたからである。
「ジョルジオ!すまないが今夜はこの人たちと食事をする。準備してくれないか?」
「はいはい、だんな様。ちょっと待っていてくださいね。」
めったに笑わないクレイがこんな笑顔を見せるのをみて、ジョルジオも大体のことを理解したらしい。半分仕方ないという表情なのだが、後半分はクレイが嬉しそうに笑うのがうれしいらしい。軽い足取りで彼は台所へと戻っていったのである。
* * *
というわけで、クレイはタルト達を応接間に引っ張っていった。応接間といってもたいした調度品があるわけではないが、ある程度の人数を捌くには他に部屋が無い。簡単な食事くらいは出来るように部屋にはテーブルやソファーがちゃんと置かれている。
「へぇ、結構いい家じゃないか!」
「まあ…借り物なんだけど…」
「官舎」なのであるから当然この家はクレイの所有物ではない。いい家といわれてもちょっと困ってしまうのだが、そういわれると悪い気はしないものである。クレイはちょっと嬉しそうにナギの顔を見た。
応接間に入るドアを開けると、整然とした家具が並んでいるのが目に入ってくる。簡素だがさっぱりとした家具は、ごてごてした帝国風の屋敷が多いこの街では不思議なインパクトを与える。まあ、これだけの人数を収容するとなると、こんな小さな屋敷ではそれでも難しいといえるのだが …
ところが部屋に入ると家具のほかに妙な黒い生物が寝転がっているのに気がついた。ソファーの上に堂々と…ごろりんと寝転がっているのである。これでは客人が座るところが無い。クレイは困ったような表情をした。
「あっちゃー…」
「なんなんだ?これ?」
ソファーの上を指差したナギに、クレイはますます困ったような…そしてすまないような表情を示した。ナギは小首をかしげ、片手でその寝転がっている物体をさわってみた。丸まって寝転がっているため頭はよく見えないのだが、ごわごわしている感触が、確かに獣のようである。ただ、獣にしてみれば相当大きい。熊とはいわないが、それに近い体長である。
ナギに触られてその獣はむくりと首をもたげた。同時にその獣の全貌が明らかになる。そいつは、巨大な犬だったのである。思わずナギは声を上げた。
「おまえ、すごいでかい犬を飼っているんだな…」
「いや、その…飼っているんじゃないんだけど…」
「野良犬か?そりゃえらいものを…」
「…住んでいるんだ…俺の家に…」
「住んでいる?」
クレイは頭を掻いてナギに弁明した。あまりに巨大なこの犬が、勝手に家にやってきて、そのまま居座ってしまったこと。それもただの犬じゃない …
そこまでクレイが説明をしたときに、巨大な犬は「口を開いた」のである。そう、まさしくこいつはしゃべったのである。
「クレイ、友達か?」
「…しゃべった…」
「まさか…」
「だろ?…住んでいるんだ。」
「俺はマグだ。」
この巨大なしゃべる犬…マグという名らしい…に、しばしタルト達は唖然として物を言うことができなかったのは言うまでもない。
* * *
巨大な御犬様はしぶしぶ客人たちにソファーを譲って、自身は床に堂々と寝そべった。おそるおそるタルト達はソファーに座ると、ちらちらと巨大な犬のほうをみながら話しはじめた。住人であるクレイは…これまたマグに遠慮するように席についている。料理を運んできた執事のジョルジオはそれほどでもないみたいなのだが …
目を丸くしてタルトやリキュアはクレイに言う。
「たまげたなぁ…すごい犬じゃないか。」
「犬というより、狼じゃないの?」
「よく判らない。そうかもしれない…」
確かにリキュアの指摘は可能性がある。マグの顔は、そこらに番犬として飼われている犬よりもずっと野生っぽかったし、毛並みの方も黒っぽい銀色で…たしかに犬というより狼だろう。ただ、いずれにせよ人語を解するというのは、それはそれでえらく珍しい狼なのだが…ただの狼ではなく精霊狼というわけである。
まあ、そういう具合でスタートした再会だったのだが、話は自然と近況報告にうつりはじめる。そう、そもそも今回は雑談をしに来たのではなくリンクスの話を相談しに来たのである。
クレイは昔の仲間…セミーノフたちのことを思い出してタルトに尋ねる。
「セミーノフは元気か?」
「ああ。あいつは元気だ。ルンナと結婚して、な。子どもまで居るよ。」
「そうか、子どもまで居るのか…そうだ、ドランは?」
「よく判らないんだ。音沙汰が無い…」
「そうか…」
イックスのスナイパーのセミーノフ…あのどこか余裕の無い感のある青年が結局結婚したというのである。それも相手がルンナ…元聖母教会の女祭だった気の強い少女だというのだ。最初は喧嘩ばかりしていた二人が、結局引っ付いたのである。面白いとしか言いようが無い。それからクレイと同じように元剣闘士だった、灰色の勇者神官戦士ドラン…彼はイックスでの戦いの後、行方が判らなかった。ただ、めったなことでは死なない奴だとは思うので、タルトはあまり心配はしていなかった。
セミーノフが話題に上ると必然的に相棒だったセイバーの消息が出てくるのは当たり前である。しかしタルトにしてみれば、それは辛い話題になる。ランドセイバーはもういない…リキュアと、タルト達と、そして忘れ形見のクーガーを残して、永遠に戻ることの無い旅に去ってしまったのだ。
「えっと、そういえばあの探偵の鋼鉄精霊…あいつはどうしている?」
クレイがランドセイバーのことを言いだすと、タルトは表情を暗くした。
どういう形でクレイにこの事実を告げるべきなのか、タルトは一瞬迷った。うそをつくとかそういうつもりはないのだが、クレイがどういう反応をするのか、急にタルトは不安になったからだった。
ショックでクレイがひっくり返るのならいい…泣いてくれるならどれだけいいだろう…しかしタルトはどうしてもクレイがセイバーの死に涙してくれるということが、その瞬間想像できなくなってしまったのである。
あれだけいろいろ…クレイの事を心配し、あれやこれやと気をもんでいたランドセイバー…ところがその時、タルトにはクレイがセイバーのことをあまり記憶に残していないように感じたのである。いや、まるで忘れてしまったのではないか…そうでなければ、セイバーを名でなく「あの探偵」と呼ぶことは考えられなかった。まるで記憶の一部が崩壊し、失われたような、そんな恐怖すら感じられるクレイの言葉だった。
タルトはリキュアやナギを…目で助けを求めるように見た。しかし二人も同じ事を考えているかのようにうつむいていた。仕方なくタルトは言った。
「セイバーは…死んだよ。」
「そうか。」
クレイは何もそれ以上聞こうとはしなかった。クレイのアイスグリーンの瞳が何を意味しているのかタルトは知りたいと思ったが、いつものように神秘的な光をたたえたクレイの瞳は、タルトには何も語らなかったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
