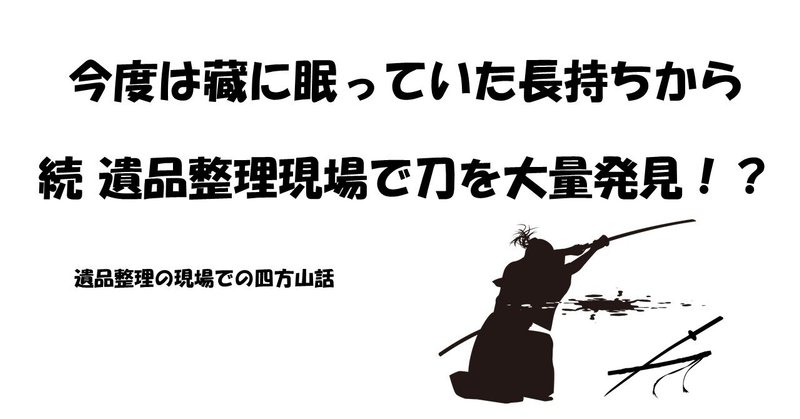
続 遺品整理現場で刀を大量発見?! 藏に眠っていた大量の刀
遺品整理現場での四方山話
以前にお手伝いさせて頂いた遺品整理の現場でのお話し。とても大きなお宅で庭には蔵があったご自宅なのですが、お客様は遠方の為、当事務所に全て一任頂いての作業となりました。
一日では分別や貴重品の捜索が終わらないので日にちを分けて作業を行っていた時のこと、蔵の整理をしていたスタッフから「谷さ~ん、刀が出てきました」との声が。
蔵の二階部分は電気もなく、風通しも悪いなかスタッフが頑張ってくれていたのですが、蔵の二階部分には長持ちが4つほど置かれており、昔の布団などいろいろな生活雑貨が納められていたのですが、そのうちのひとつから刀が数本出てきました。
刀が出てきた場合にまず確認するのが登録証の有無です。登録証があれば教育委員会で名義変更を行い引き続き所持することができますが、登録証自体が紙製で発見した時点で既に登録証が無くなっていることも珍しくはありません。
今回の刀も登録証らしきものがついているのが一振りあるだけで、その他の刀には登録証はついていませんでした。
スタッフから発見の報告をもらってすぐに長持ちの中も再度捜索しましたが長持ち内にも落ちていません。
こうなってくると、まずは警察署(発見地を管轄する)へ発見届けを行い、その後警察署から発行される届出済証を持って教育委員会への審査に持ち込むこととなります。
普段は遺品整理の貴重品と供に依頼者の方へ刀をお渡しして発見届け等の手続きの説明をして完了となるのですが、今回は依頼者の方は遠方であることと、警察署から発見者である当事務所が発見届けを代わりに行っても良いとの返事がありましたので、依頼者の方に代わって警察署へ行くことに。
遺品整理で刀を発見することは良くあるのですが、「発見届」を依頼者に代わって行うのは初めてだったりします。
ちょっとわくわくしながら警察署へ刀を運ぶのですが、運ぶ際にも注意が必要です。
いきなり刀を車に積み込んで運んでしまうと何かの際に警察に呼び止められて車のチェックを行われたりすると「この刀はなんだーー!」ってなってしまいますよね。
ですので、万が一に備えて事前に持ち込む警察署(通常は生活安全課)の担当者の方に連絡を入れて「今から持っていきます~」の連絡を入れておけばもし、職務質問などで刀が出てきても「警察の指示に従って運んでいます」と言えるからセーフ!ってなるわけです。
もちろん、いくら事前に連絡を入れてあるからといってあきらかに「刀」ってわかるような形では持ち運ばずに布で包むなりして運びましょうね。
そしていよいよ「発見届」の手続きとなるのですが、事前に依頼者の方と警察署にて一振り以外は破棄するということで話しが纏まっていましたので、実際には「発見届」とは別に任意に提出して、所有権は放棄、そして破棄への承諾といった書類を別途作成していきます。
それらの書類を作成するにあたり、刃渡りや刀の種類(太刀や軍刀など)、銘の有無などを確認するのですが、警察署にはちゃんと刀の柄の部分を外す道具があるんですね(笑)

あの時代劇などで、柄の部分をコンコン叩いてから手首を叩きながら刀身と柄を分ける作業をこの目で見るとは思いませんでした。
今回持ち込んだ刀はひとつが太刀、その外が典礼用と思われるサーベル、そして軍刀が数本といった感じです。
警察署の方は書類作成上で色々調べることもあるらしく、軍刀と太刀では吊るす際の刃の向きが上下反対になるなど色々と面白い話しを聞きながら書類を作成していきました。

(柄にかたつむり(蝸牛)が描かれていてちょっと可愛い)

(軍刀やサーベル、太刀もあり)

(こういう画像は需要があるのですかね?)
軍刀は美術品としての価値がないとなると教育委員会で登録ができない可能性もありますが、ご依頼者の意向としては思い出の品として刃を潰してでも所持していきたいとのことですので、遺品整理専門の行政書士として、ちょっと手続き頑張ってみますかね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
