
Puma Blue "In Praise of Shadows"
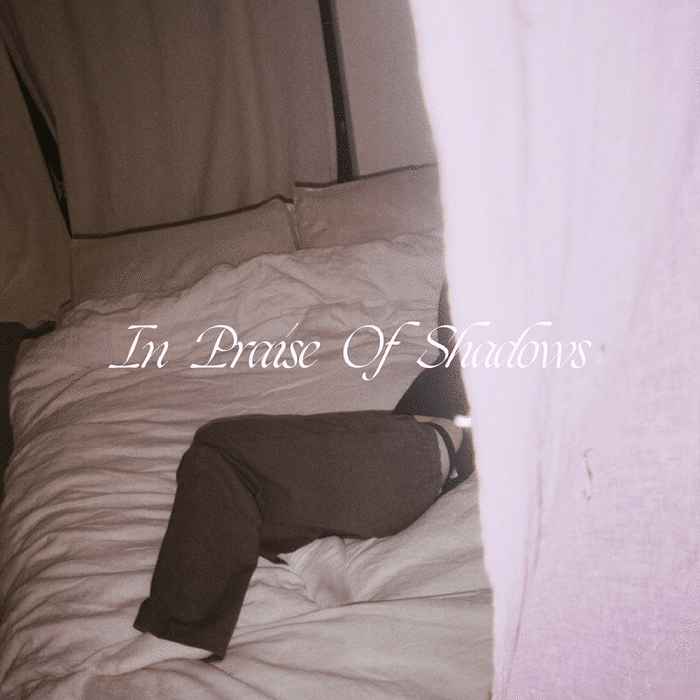
イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライターによる初フルレンス。
最近は自宅で音楽を聴くためのまとまった時間が取りづらいので、通勤中に音楽を聴くことの方が多くなった。エレベーターで、電車で、大通りの歩道で。そのため周囲の騒音をシャットアウトできるくらいに音量や音圧のある音楽をリピートしがちになっている。時間や場所を選ばずにその魅力を享受できる、非常に便利な音楽を。しかしながら、この Puma Blue のデビュー作はそういった便利さとは真逆を行っている。全編通じてひどく繊細で、騒音に負けて取りこぼしてしまいそうになる音があまりにも多すぎる。なので必然的に今作を聴くシチュエーションは限られてくる。自分の場合は仕事から家に帰り、子供の世話を一通り済ませたあと、風呂に入ってから床に就くまでの1時間程度。その間に自室にこもり、十分に気持ちを落ち着かせてからリスニングに臨む。そうせざるを得ない。そうしなければ今作に収められている魔的な魅力を十分に掴み取ることはできない。結果として、今作は自分を徹底的にひとりきりにさせるアルバムなのである。
音楽性は R&B 。その中でも Frank Ocean や Rhye 、The Internet あたりを連想させる、アンビエントの感触が強い類のもの。ではそれら先達との差異は何かと言うと、彼の方がさらに、何なら聴き手側が心配になるほどに憂いの色が濃い。例えば上のリードトラック "Velvet Leaves" を聴いてみよう。起伏の抑えられたメロディ。肩の力が抜けきった、ほとんど溜め息に近いボーカル。ささやかなエレキギターのストローク。そしてよくよく注意しておかないと気付かない程度のストリングス。それらが絡み合って濃密なムードを醸し出し、今生の別れに直面したかのような悲しみが訥々と綴られる。終盤に向かうにつれて音が膨張して迫力を増していくが、臨界点を越えての爆発にまでは至らず、次第に萎み、そのまま霧消してしまう。まるで自分が抱え込んでいる悲しみに終わりがなく、延々とループの中でさ迷い続けていることを暗示しているかのようだ。しかもこの曲はまだ盛り上がりがある方で、他のリード曲は憂鬱の度合いがなお深く、場面によっては内省を通り越して閉塞的な印象すらある。変調されたボーカルが嗚咽にも似た痛切さを孕んで響く "Snowflower" 、一睡もできないまま夜と朝の隙間に佇むときのような朧朧とした雰囲気の "Silk Print" 、軽快なリズムやサックスの音色に少しばかりの安堵を覚えつつ、表題通り緩やかに麻酔の淵に落ちていく "Opiate" 。まあ揃いも揃って濃青一色なのだ。
それで、彼の持つ音楽性は R&B だと先に書いたが、それと同時にフォーク的な要素もかなり強く感じるのが今作のもうひとつの特徴だと思う。彼はシンガーであり、プロデューサーであり、マルチインストゥルメンタリストでもあるとのこと。なのでここではほぼすべての演奏を自身でやってのけているのだと思うが、決して技術をひけらかしたりはせず、あくまでも淡々としたプレイで、必要最小限の音数に絞り込むアレンジを意識している。それもあってか、リズムの作りやミキシングにこそエレクトロニックな感触が表れてはいるものの、曲の構造的にはギターと歌のみの弾き語りでも十分に成立するであろう、至って真っ当なシンガーソングライターのスタイルが基盤にあるのだ。YouTube にあるいくつかの過去のライブ映像も見てみたが、そこでの彼はサックス奏者を含めたバンド編成を従え、エレクトロよりもジャズのテイストを前面に出し、彼自身もギターを弾きながらメンバー各自の息遣いを大事にした演奏を展開していた。その様子からも伺えるのが、基本的には彼がサウンドデザインの先鋭性よりもオーソドックスな歌の良質さを志向しているということだ。ただこのアルバムにおいてはほとんどの楽曲が、夜更けのベッドルームでさらさらとデモ音源を録るくらいのテンションの歌ばかり。しかしそれは決して気を抜いているわけではない。むしろ力を抑えて歌う方が、些細なタッチの違いで曲のニュアンスを大きく変えてしまう危険性があることを、彼は重々理解しているはずだ。ここでの彼は憂鬱をドラマチックに拡大解釈せず、脱臭もせず、できる限り自身の体温に近い生々しさを保ちながら、慎重に憂鬱を取り扱い、そこにきめ細かな美しさを宿している。
そういったフォークの側面を加味した上で今作を聴くと、自分の脳裏に浮かんできたのは R&B 勢ではなく、Vincent Gallo だった。Vincent Gallo はもちろん俳優や映画監督として広く世に知られているが、ミュージシャンとしてもマイペースに活動しており、2000年代初頭には2枚のアルバム作品を発表している。そのうちの1枚である "When" 。自宅をスタジオ化し、長い時間をかけて多くのビンテージ機材を収集したが、実際に曲中で使うのは必要最小限。Gallo 自身の生演奏とサンプリングを組み合わせながら、柔和な音の中に憐憫の色をうっすらと滲ませ、無音の隙間に豊かな情感を忍ばせた傑作である。実際には Puma Blue 自身は D'Angelo や Jeff Buckley からの影響を公言しているようだが、今作の持つ雰囲気はその "When" と重なる部分が随分と多いように、自分には感じられる。音数を削げば削ぐほど、メロディを抑制すればするほど、まるで表面張力ギリギリで踏み止まっているコップの水のごとく、歌の中に注ぎ込まれたエモーションはかえって危うい存在感を増して響く。そういった "歌うこと" に対する意識が、Gallo と Puma Blue の両者には深く共通しているのではないかと思う。
アルバム表題の "In Praise of Shadows" は和訳すれば "陰翳礼讃" となる。これは谷崎潤一郎の随筆から引用したものだそう。西洋の文化を取り入れ、利便性を追求し、生活が豊かになっていく一方で、日本の文化が本来持つ "もののあはれ" の風情、物と物の隙間にある陰翳の美しさを忘れてしまってはいないか、という趣旨。まあ Puma Blue は英国出身だが、今の時代に国境や人種がどうのこうのの話はナンセンスだろう。ともかく、この作品には影のみが持ち得る脆弱さ、遣る瀬無さ、そして官能的な美しさがある。1作目にして彼はすでに陰翳の真髄を掴んでいる。眠れずに不安定な夜を過ごし、心が千切れそうになっていたとしても、そこに確かな美意識を貫き、表現へと昇華している。物理的な波長の穏やかさとは裏腹に、ある種の激しい衝動をも見出せる。なんとも聴きこみ甲斐のあるデビュー作だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
