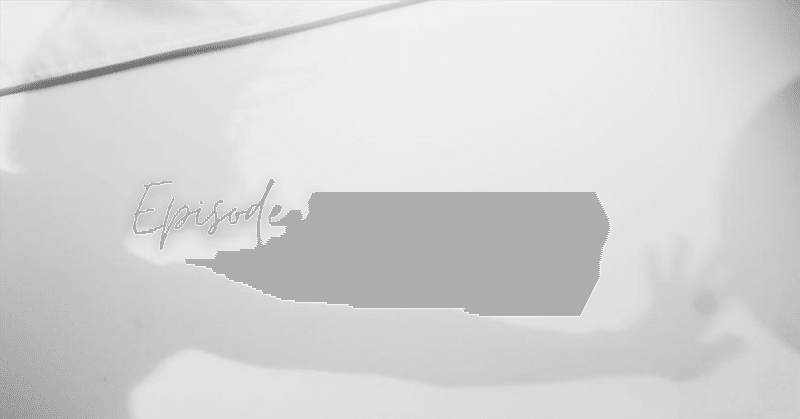
Beside|Ep.2 空っぽの部屋
Beside-あなたと私のためのベットサイドストーリー
いつもとなんら変わらないはずの仕事始めに
見知らぬ青年を家に連れて帰るとしたら
あなたはどう冷静でいられる?
chap.1
「おじゃまします…」
「何も用意がないけど、とりあえず先にシャワーどうぞ」
ホビに半ば強引に説得され、勢いで家に連れてきたものの、この状況はどう理解したらいいのだろうか。
ーいや、何やってんの自分
「はい、これホビに借りた服。あと、濡れた服は洗濯機入れておいて?乾燥回せば明日には乾くと思う。それと…」
「あのっ…ほんとにありがとうございます。見ず知らずの僕を…」
「いや、私もあんまり状況が飲み込めてないんだけど、とりあえず風邪ひくから入ってきな?」
ホビは何回も来たことあるお客さんだから大丈夫と言っていたけど、何がどう大丈夫なのかということは今は深く考えてはいけない、否、まともに考えられるキャパシティは私にはなさそうだ。年下の青年を、飲み屋で助け、家に保護しているというこの状況自体を、冷静に整理できるアラサー女子がいるなら、心から尊敬する。
ーいや、何やってんの自分(二回目)
つまるところわたしは動揺していて、それをどうやって隠そうかと無駄な足掻きをしている。いや、やめよう、とりあえず何も考えてはいけない。そうだ、三毛猫を拾ったことにすればいいじゃないか。びしょ濡れの三毛猫を放っておけないのは万国に共通のよくある話だ。それが、たまたま、今日にかぎって、私に起きているだけだ。
「猫っていうことにしよう猫に。」
「おねえさん、猫飼ってるんですか?」
「わ、びっくりした。いや、飼ってないよ。実家の隣の隣の家の話で…」
シャワー先にいただきましたと、礼儀正しい。新年から無一文で女性にお酒をぶっかけられるような人には見えないのだが。彼は本当に何者なんだろう。いや、ダメだ、やめよう。今何も考えないことにしたばかりじゃないか。目をほとんど閉じるくらい細めれば、三毛猫に見えなくもない。
「あの、改めて、ジミンと申します。アミさん、本当にありがとうございます。」
「うん、長生きしてればこんな日もあるよね。そっちの部屋のベット好きに使って?ずっと空いてるから」
「…ずっと?」
「そう、昔必要になって用意したんだけど要らなくなったんだ。」
ーまさか、この部屋がこんな風に活躍する日が来るなんてね
都内2LDK分譲マンション。ハードワークの会社にも電車で4駅の好立地。この家に住んで5年目になるが、あの部屋が空っぽになってからも5年が経つ。そう、おおよそ30年くらい生きていると、色々あるものだよ。初めから2LDKにひとりで住んでみたかったのかなとか、売る時に売りやすいからかなとか、色々推測してくれて構わない。
「ジミンくん…でいいのかな?呼び方。」
「あ、僕、ホソギヒョンより2つくらい下です。なので、呼び捨てしてください。」
「あ、うん、わかった。ちょうどよかったよ、部屋が空いてて。」
「僕もヌナって呼んでいいですか」
「私はなんでも構わないよ。」
今日はきっと、前々から起こることが決まっていた”びっくりするような日”、だったに違いない。明日からはまた何の変わり映えもない日々がやってきて、会社に行き、仕事をこなし、へとへとになってビールを飲んで、寝るんだ。そうやってこの5年間ここで暮らしてきたんだから、きっと明日には何事もなかったかのように元に戻っているはずだ。そうだ、きっとそうだ。
「明日、私は朝から仕事に行くけど、必要なものあったら使ってくれてかまわないし、マンションオートロックだから、そのまま出て、ホビにでも声かけておいてくれ」
「はい、ありがとうございます。」
こんな状況で、初めて会ったのに、どうしてジミンにこんなに、安心してるんだろう。それともこの状況に頭がもう付いていってないのかな。どちらにせよ、ジミンも疲れているだろうから、今日は早く寝るのがいいに決まっている。
「ジミナ…疲れた顔してるな…色々あったんだな。機会があればまた話そう?今日は早く寝なね。おやすみ。」
「ヌナ!おやすみなさい!」
おやすみ、なんて何年ぶりだろう。
なんだろう、今夜は、よく眠れそうだ。
chap.2
ーヌナ…か。初めて呼ばれたな
「聞いてんのか?おいっ!アミ!」
ユンギの声で我に帰った。すまん、全く聞いてなかったみたいだ。
「お前な、会議中もずっとボサっとしてたろ?何やってんだよ全く…」
「ゴメン。でも許せユンギよ。私も感情のある人間だったようだ」
「…何言ってんだ?」
昨晩は何事もなく、寧ろいつもよりぐっすり眠れた。ジミンの服は乾燥機で綺麗に乾いていた。服を畳んで、コーヒーを飲んで、普通に出勤している。全て完璧だ。だから、どうしたって考えてしまう。本当に起きたことだったのか?あの部屋を朝から開ける勇気はなかったから、もしかしたら夢だったのかなとか。
「来週からの新しいメンバーが挨拶に来てるんだよ。早くその締まりのない顔どーにかしろ。」
「なっ…生まれてこの方この顔ですがね」
「そうか?入社当時はもう少し締まってたぞ」
「ユンギよ…相変わらずお前はセクハラで訴えられたいようだな」
「いいから5秒で準備しろよ…」
テヒョンとジョングク。来週からこのグループに配属される2人は育成の一環でジョブローテーションを実施中である。ここは2番目の部署だ。
「声かけずらいな…とっても」
「そうですね…。でも頼れるコンビだってナムジュニヒョンが言ってました。」
「ほんと?」
「はい…」
配属挨拶に来たのに、メンターがこの調子なら、不安になるのは当然のことである。
「すまん、気付くのが遅くなった。どうも、ユンギです。ジョングク氏のチームのリーダー兼グループマネージャーです。よろしく。」
「アミです。テヒョンくんの入るチームのリーダーです。よろしくね。」
先ほどまでの小競り合いはどこへいったのか、ビジネスモードの2人は息がぴったりで、この短い自己紹介ですら長年のチームワークのようなものを感じ、テヒョンとジョングクは密かに感動した。
(すごいな…噂通り、息ピッタリ…)
「よろしくお願いします!」
chap.3
その後、性懲りも無く残業しそうになるユンギを無理やりデスクから引き剥がし、新年会兼、歓迎会を実施する運びとなった。乾杯のグラス音と琥珀色の炭酸水は何度でも生き返らせてくれる、私の中の何か、明日への希望みたいなものを。互いの飲み物をカチンと合わせるという儀式めいた行動は世界中に散見されるが、一体誰が始めたんだろうか。ユンギなら乾杯の歴史にもくわしいかもしれない。
「まぁ慣れるまで少し大変だけど、活躍を期待してるよ!」
「ボスたちはみんな話しやすいし、楽しく仕事できる環境だと思う」
テヒョンはジョングクの2つ年上で、ナムよりも年下だというから、ユンギと私はいつの間にか”中堅どころ”となってきたらしい。私はいつまでもフレッシュな新卒のつもりで働いていますけど、何か?
「アミさんとユンギヒョンは同期とお聞きしました。さすが、お二人とも息がぴったりですね」
「息がぴったり?どこが?」
「ジョングガ?見間違いでは?」
(ほらまた…!)
週半ばの飲み会は、良い時間でお開きとなった。今日1日の我が身の為体を全て飲み干し、フレッシュな新人2人のエネルギーにあてられて、そして何か重要なことがあった気がするが、それも今は忘れることができていた。少なくともこの瞬間はそれで良いと思えた。帰り道、路線の違うテヒョンとジョングクと別れる。新しいメンバーというのは新しい風を連れてくるものだ。それが突風だろうが、竜巻だろうが、微風だろうが、少しくらい変化を期待してもバチは当たらないだろう。
「いいチームになるといいな」
「あぁ」
駅に向かっていると、ユンギがふと足を止めた。
「なぁ、アミ、お前さ…」
「ん?」
「お前、今日一日何考えてたんだ?会議中もぼーっとしたりして、らしくなかった。」
「えっ」
「その、まだ引きずってんのか?あの時のこと。」
ーユンギのやつ、よく覚えてるな
あの部屋が要らなくなったのはちょうど5年前の年明けだった。
「それは…全然引きずってない。何年前の話だと思ってんだ。それに今日の件とは関係ない。」
「そうか。なら、いい。」
ー引きずってないといえば嘘になるか
あの時から私の心はポッカリ穴が空いたまま、何にも呼応することなく、ただ空っぽだ。まるであの部屋みたいに。このマンションは気に入っているけれど、そろそろ引っ越してもよい頃だ。築年数も浅いし、買値で売れる可能性もある。そうして新しい家を買って、新しい場所で、新しい生活をすればいいじゃないか。それをしていないのだから、引きずっていると言われても何も否定はできない。でも、どちらかと言えば、何もしたくないんだ。今は、何も。
「今日、思ったより遅くなっちまったな。送ろうか?」
時間でいえば、昨日より早い。それに、いつものピーク期なんかより全然健全な時間帯である。
「大丈夫だよ。いつもより早いし。ユンギヤこそゆっくり休んでよ。最近遅いじゃん、毎日」
「ん、そうだな」
「ちょっと、痩せた?無理、してない?」
「母さんみたいなこと言うなよ」
「まだ同い年のアラサーですが何か?」
「ハハ。今日は、早く帰って寝るよ」
入社からほぼ毎日見てきた同期が、なんだか少し違う人に見えた。急に不安になって、ユンギの顔にそっと触れてみる。大丈夫、暖かい。ユンギが少し切なそうに笑った。そうだった、こういう表情のユンギは、びっくりするほど綺麗なんだった。本当に仕事しないで寝てよと言って、私はそっと手を離した。
chap.4
駅の改札を出て、商店街を抜けて、家までは少し坂道になっている。少し高いところにある眺めが好きなんだ。遠くまで見渡せるほうが、少しだけ安心できるから。それだけ人生は何がどんなタイミングでやってくるかわからない。未来がわからなすぎて、不安で夜眠れない子供がいるというが、私はそのタイプに近い子供だった。昨日びしょ濡れのジミンに会って、5年ぶりに誰かがあの部屋を使ったのは、何か意味のあるタイミングだったのだろうか。そういえば、ちゃんと家に帰れたんだろうか。彼女と仲直りできているといいけれど、路頭に迷ってないだろうか。また今度話そう、なんて言ってしまったけど、またいつか会えるのだろうか。会えたらいいなと思うけど、何を話したかったのかはわからない。帰ったらあの部屋はまた空っぽに戻っているんだろう。その時に少しまた、切なくなるんだろう。そんな自分が想像できて、情けない。
ーただいま
「おかえり!」
…ん?どうしておかえりって…
「ヌナ!おかえり!」
「ジミナっ?!」
「ヌナ、やっと帰ってきた…おかえりなさい!」
待っているのはいつも通りの空っぽの部屋のはずだったのに。
部屋を照らす 太陽みたいに暖かい笑顔。
予想もしなかったことが 一つずつ始まっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
