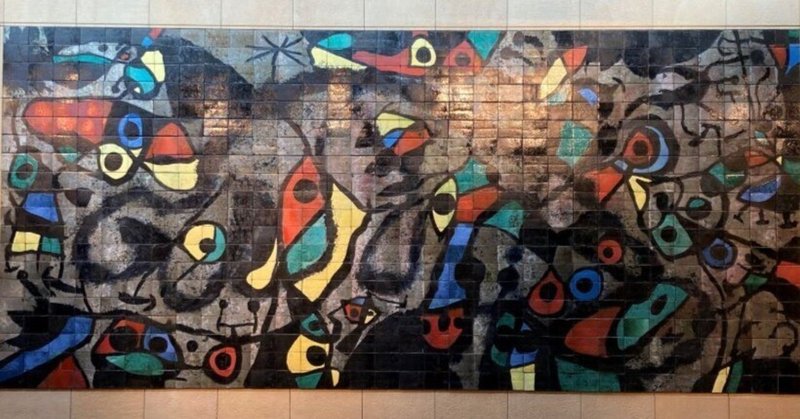
1000日チャレンジ 833日目 国立国際美術館「ホーム・スイート・ホーム」
ゴールまで167日
★BMI:24.1
★先日、国立国際美術館(大阪)で開催中の「ホーム・スイート・ホーム」を観たので、記録として残しておきたい。
「ホーム・スイート・ホーム」
◎概要
【会期】2023年6月24日(土)– 9月10日(日)
【主催】国立国際美術館
【協賛】公益財団法人ダイキン工業現代美術振興財団
【助成】一般財団法人安藤忠雄文化財団
(以下、公式web siteより引用)
「私たちにとって「ホーム」とはどのような意味をもち、どのような存在なのでしょうか?国立国際美術館では国内外で活動する現代美術作家たちによる特別展「ホーム・スイート・ホーム」展を開催します。
2020年初頭に登場した新型コロナ感染症拡大は、私たちの生活に大きな変化をもたらしました。いわゆるビフォアコロナ期には普通であった行動も、「不要不急」という言葉によって制限されました。本年5月8日をもって5類感染症に移行たことで、コロナ対策は一定の区切りがつけられましたが、かつての生活に完全に戻ったとは言えないのではないでしょうか。
こうして生活様式が変化する中で、感染症拡大の初期には予防の観点から「ステイホーム」という言葉が頻繁に使われるようになりました。この「ホーム」には、私たちが過ごす物質的な家、また家に集う集合体である家族、故郷そして祖国の意味もあります。私たちが留まることを求められたホームですが、パンデミック期以前に比べて長い時間を過ごす上で、またウィルス感染という病により生と死が身近になる中、「ホーム」が含む意味に対して意識的、無意識的に思いをめぐらす機会も増えたのではないでしょうか。パンデミック以前から世界各地における難民問題はありましたが、昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻も多数の新たな難民を生み出し、祖国・故郷というホームの別義に含まれる意味を私たちにも突きつけました。
本展「ホーム・スイート・ホーム」では、歴史、記憶、アイデンティティ、私たちの居場所、役割等をキーワードに表現された作品群から、私たちにとっての「ホーム」--家そして家族とは何か、私たちが所属する地域、社会の変容、普遍性を浮かび上がらせることを試みます。
タイトルの「ホーム・スイート・ホーム」は、愛しい我が家などとも訳せられ用いられてきました。ビターな社会が続く中で、私たちのホーム・スイート・ホームを見つめ直します。」
◎マリア・ファーラ「下関海峡でおぼれる両親を救う」(2017年)(オオタファインアーツ蔵)
※マリア・ファーラ;Maria Farrar
「1988年にフィリピンで、イギリス人の父親とフィリピン人の母親とのあいだに生まれる。幼少期を下関市で過ごしたあと、15歳よりロンドンに移りロンドン大学スレード美術学校で修士課程を修了後、現在もロンドンで制作を行う。ファーラの絵画に描かれるのは、日常生活の中から彼女が見聞もしくは想像する女性の姿、また記憶に残る生活の様子、興味のある動物の姿や食べ物である。そこには自身が大きな影響を受けた日本文化からの影響、またフィリピン女性コミュニティに見た異国で力強く生きる女性たちの姿を見ることもできる。」(展覧会web siteより引用)

◎アンドロ・ウェクア「無題」(2017年)(Courtesy of the artist, Gladstone Gallery and Take Ninagawa蔵)
※アンドロ・ウェクア;Andro Wekua
「1977年、現在のジョージア・スフミに生まれる。95年からはスイスに移住し、現在はベルリンを拠点に制作を行なっている。
ウェクアは、コラージュ、絵画、彫刻、インスタレーション、映像など、様々なメディアを駆使して作品を発表している。特にアッサンブラージュ的な視覚効果を獲得しつつ、個人的、政治的な記憶の断片をステージ化し、個人的な世界を夢想的に構築する作品で知られている。」(展覧会web siteより引用)

◎潘逸舟「植物」(2022年)(水彩、紙;作家蔵)
※潘逸舟 Ishu Han
「1987年中国・上海生まれ、幼少時に青森に移住。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了後、現在は東京を拠点に活動している。
潘は、中国で生まれ日本で育ったというアイデンティティを出発点に、社会と個の関係のなかで生じる疑問や戸惑いを自らの身体や周囲にある日用品を用いた映像作品やインスタレーション、写真、絵画など様々なメディアで表現している。」(展覧会web siteより引用)

※すべて初めましての作家さんだった。「ホーム」とはどのような意味?がテーマだが、一見、つながりのない作品群のように思えた。しかし、個々の作家にとっての「ホーム」とは何なのか?と考えると、なるほどという展示もあった。まあ、あまりテーマにとらわれず、様々なオリジンの作家たちの作品を楽しむことができた。
https://www.nmao.go.jp/events/event/20230624_homesweethome/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
