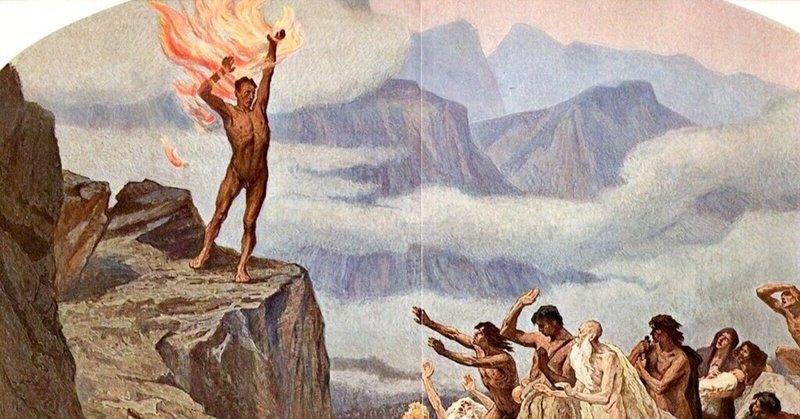
特攻文学としての《ゴジラ-1.0》|第11回|井上義和・坂元希美
(構成:坂元希美)
⑪まだまだある特攻文学映画 《インデペンデンス・デイ》《アルマゲドン》
Brave Storyが祖国を立ち上げる
★ネタバレ注意★
映画《ゴジラ-1.0》《インデペンデンス・デイ》《アルマゲドン》のネタバレが含まれていますので、知りたくないという方はこの先、ご遠慮ください。そして、ぜひ作品鑑賞後にまた読みにいらしてください。
《インデペンデンス・デイ》
人類絶滅の危機に命のタスキはどうなる?
坂元 今回はハリウッド映画から有名な2作品を「特攻文学の要素あり」として、取り上げます。
まずは1996年に公開された《インデペンデンス・デイ》。監督は“人類滅亡の危機といえばこの人”、ローランド・エメリッヒで、アカデミー賞の視覚効果賞を受賞しています。あらすじは割愛しますが、圧倒的な力を持つ宇宙からの侵略者(外敵)に立ち向かう人類(アメリカ)のお話です。
井上 壮大なスケールの物語なのですが、侵略から撃退まで、たった3日間の出来事です。3日目の7月4日、つまり人類による総攻撃の日は、奇しくもアメリカ独立記念日(Independence Day)。もうこの設定だけで、祖国立ち上げを「やり直す」、建国神話の「再演」の期待が高まりますね(笑)。
さて、主要な登場人物は、それぞれクセがありますよね。大なり小なりのマイナスを背負っています。それぞれが、思い通りにいかない人生を生きている。
坂元 ホイットモア大統領(ビル・プルマン)は湾岸戦争で空の英雄と言われた元パイロットだが、現在は支持率低下に悩む。妻と娘あり。デイヴィッド・レヴィンソン(ジェフ・ゴールドブラム)はMIT卒の秀才なのにケーブルテレビ局勤め、あまりに野心がないと妻に去られて3年経つが未練たっぷり。空軍パイロットのスティーブン・ヒラー大尉(ウィル・スミス)は宇宙飛行士を夢見るもNASAから「お祈り手紙」が届いてしまった。ラッセル・ケイス(ランディ・クエイド)は、ベトナム戦争では戦闘機パイロットとして戦った帰還兵で、アルコール依存症かつ「宇宙人に誘拐された」妄想もあって、仕事ではミスをするし周りからバカにされる、子どもたちからも呆れられる始末。今は軽飛行機で農薬散布の仕事をしている。これが皮肉の効いた設定だということに、今回見直してやっと気がつきました(笑)。
スティーブンは同僚からLoser(負け犬)と言われますけれど、全員が何かしらLoser要素を持っているんですよね。
井上 何もなければ交わらないであろう人々が、突然の侵略で、否応なく戦争状態に巻き込まれていきます。圧倒的な宇宙人の攻撃は、世界中をたった1日で壊滅寸前に追い詰め、これまで自国内で大きな戦闘を経験したことのないアメリカも同じ状況になる。追い詰められた大統領は自国内での核兵器使用に踏み切りますが、相手にはかすり傷ひとつ与えることはできずに、いたずらに兵力を消耗していきます。
坂元 一方、ケーブルテレビ局の技術者であるデイヴィッドはすごくいい仕事をします。物語の序盤、宇宙船が発する信号パターンから敵の侵略意図に気づき、元妻(大統領首席補佐官)のツテでホワイトハウスに入り込んで、大統領に直接伝えることに成功します。さらに終盤には、敵の弱点を突いて反転攻勢の機会を作り出す、というアイデアを提案して、その重要な任務に自ら志願する。これは民間の力を借りる部分になりますね。
井上 アメリカが世界に誇る軍事力は、宇宙人の圧倒的な攻撃の前に、脆くも崩れ去りました。なにしろ最終決戦兵器である核兵器が無力なのだから、どうしようもない。そうなると、軍を統括する国防長官も手詰まりとなります。
絶望的な状況のなか、敵の宇宙船に入り込んでコンピュータ・ウイルスに感染させる、という民間技術者(デイヴィッド)のアイデアを採用したのは、大統領の判断でした。敵のシールドが解除されるわずかな時間に、世界各国の空軍がタイミングをあわせて総攻撃をおこなう、という一か八かの大反攻作戦です。
この時点で、既存の政府や軍隊の枠組みから、離れるのですよね。作戦に後ろ向きな国防長官を、大統領は解任しました。そして、各国の空軍パイロットに直接(!)、モールス信号で(!)、作戦参加を呼びかけます。通信衛星が無力化されても、短波とモールス符号という原始的な通信手段によって、国境を越えた伝言が可能だったのです。

坂元 しかし、総攻撃に必要な戦闘機はなんとか確保できたものの、それを操縦できるパイロットが足りない。それで、元空軍パイロットだった大統領をはじめ、たまたま居合わせた避難民たちのなかで操縦経験のある者がかき集められます。そのなかには、あのアルコール依存症のラッセルも含まれていた。――「そのための伏線だったのか!」となる(笑)。
まさに文字通りの総力戦、という盛り上げ方ですが、無理がありすぎるのでは……。
井上 これも神話的な構成だと思います。政府も軍も機能しなくなったとき、各国の空軍パイロットとも連携し、大統領と元帰還兵が一緒に編隊を組んで戦うことに大きな意味があります。
もしも、残存するアメリカ空軍のみで自国の大統領の命令によって最終決戦に臨むのであれば感動は半減しますし、人類の独立記念日(インデペンデンス・デイ)にはならない。やはり「上から」の命令や強制ではなく、政府や軍隊の枠組みを超えて、「下から」自発的に参加するというところが肝要になるのではないでしょうか。
坂元 この作戦は世界各地で同時に実施され、日本の航空自衛隊も三沢基地から出撃するようでした。その際に大統領の演説が人々を奮い立たせ、祖国を立ち上げるものになります。
今から1時間足らずで世界各国の戦闘機が、共に人類史上最大の空中戦を開始する。
人類(mankind)という言葉は今日、新しい意味となる。
些細な違いにこだわっている場合ではない。人類共通の利益のために団結するのだ。
今日が7月4日なのは、運命だ。再び自由のために戦おうではないか。圧政や弾圧、迫害に抗うためではなく、絶滅に抗うために。われわれが生きる権利のために、生存するために戦おう。勝利したその時こそ、7月4日はアメリカの祝日ではなく、世界が独立宣言した日となる――
われわれは黙して引き下がりはしない!
われわれは戦わずして消え去りはしない!
われわれは生きていく! 生き延びる!
諸君、ともに独立記念日を祝おうではないか!
われわれ=人類なので、祖国は地球ということになりますね。
ちなみに「われわれは黙して引き下がりはしない!」の原文“We will not go quietly into the night!”がすごく詩的だなあと思ったので調べると、ウェールズの作家、ディラン・トマスの詩“Do not go gentle into that good night”から借用したようです。欧米では演説などに詩や故事を挟むことが多いので、ホイットモア大統領も教養を滲ませつつ、祖国(地球)への想像力をかきたて、命のタスキを繋ごう! と呼びかけました。

(写真はブルーエンジェルス機)
井上 あの演説には、アメリカ人でない私も、泣きそうになりました(笑)。文学的教養がなくても大丈夫です。祖国の想像力にスイッチが入り、「よーし、いっちょやってやるか」となります。
ちなみに、青森の三沢基地の空自パイロットたちは、おそらく総理大臣の防衛出動命令を待たずに(首都圏は壊滅=「内閣総辞職ビーム」状態か)、この全人類の反攻作戦への参加に踏み切ります。攻撃目標は自国の領空に居座る敵であり、自衛にとって必要最小限の武力行使なので、「専守防衛」的には問題ありません(笑)。
ダメおやじが決行した特攻
井上 そして、この作戦で宇宙船に特攻した者が一人だけいます。日頃酒浸りで、社会にも家庭にも居場所のなかったラッセル・ケイスです。彼はなんとか酒を抜いて作戦に参加、コックピットには愛する子どもたちの写真を貼り付けました。
当初の作戦では特攻は想定されていません。しかし自機のミサイル発射装置が不具合だったため、ギリギリの判断で自発的に特攻したのです。それが敵に致命的な打撃を与え、結果として人類の勝利をもたらしました。
坂元 ラッセルがミサイルを発射できないことに気づいて特攻を決意したとき、子どもたちの写真を見つめながら「頼みがある。子どもたちに愛していると伝えてくれ」と司令部に言い残しました。まさに、「死を覚悟したとき=未来が見えたとき」に、彼は「父になった」のですね。
そして、過去に自分を拉致して苦しめたエイリアンへの仕返しだ! と叫びながら突っ込んでいきます。ここは、国家の命令によってベトナムで戦って命からがら帰還したのに社会から疎外され続けたことへの意趣返しのように感じました。
井上 たしかに。ゴジラが「どこにも居場所のない戦死者(への負い目)」の象徴だったように、彼にとっての宇宙人=エイリアンは「どこにも居場所のないベトナム帰還兵(の恨み)」の象徴なのかもしれません。
そうだとすれば、家庭からも社会からも疎外されてきた、居場所のない帰還兵は、特攻によって、我が子にとってだけでなく祖国(人類)の子孫たちにとっても、勇敢な父祖たらんとした、ということになります。壮絶な一発逆転です。
一方、正規の空軍パイロットであるスティーブンは、軍人としてやるべき行動をきちんとやり、その中で自分だけが宇宙人の戦闘機と交戦して勝ち残り、ついでに宇宙人を捕獲して連れて帰ってきたことから「人類最大の作戦」において最も重要で危険な任務に志願する。
でも、彼もまた少しはみ出し者で、本当はNASAの宇宙飛行士になりたいし、出世の邪魔になるとわかっていても子持ちでストリッパーの恋人ジャスミンと同棲し、結婚を考えていました。そして、作戦前に急いで結婚する。これは恋人の子どもの父親となることを意味します。やはり「死を覚悟したとき=未来が見えたとき」に、スティーブンもまた「父になる」のですね。

坂元 子持ちのストリッパーと付き合っていることについて、スティーブンは同僚から「おまえ、そんなことじゃ出世できないぞ」と言われていましたよね。結婚はしたいけれど、何となくズルズル引き延ばしてきた。ジャスミンは避難中に出会った大統領夫人に「彼がこの子の父親になってくれればいいなと思うんだけどね」と話していましたから、私はなんとなく「震災婚」みたいなものではないかしら、とも思いましたけれど。
井上 つまり、危機的な状況下でこそ「家族として」のつながりが強く意識される、と。恋人のジャスミンはそうかもしれないですね。より近くにいてほしい、より確かな支えがほしい、ということでしょう。
スティーブンの作戦前の結婚と「父になる」は、それとは、ちょっと違うような気がします。今から危険な任務に赴くわけですから、そばで家族を支えてやることはできません。それでも、大切な家族の未来のためと思えばこそ、命がけのミッションにコミットできる。
出世は自分の将来のためでしたが、使命は大切な人たちの未来のためなのです。
《アルマゲドン》
身代わりによる英雄の物語
坂元 2作目は第5回でも取り上げた《アルマゲドン》(1998)。製作者の製作のジェリー・ブラッカイマーは《トップガン》や《パイレーツ・オブ・カリビアン》などの大ヒット作品だけでなく、《パール・ハーバー》《ブラックホーク・ダウン》《ホース・ソルジャー》といったバリバリの戦争映画も手がけている人です。
《インデペンデンス・デイ》は宇宙人による侵略というはっきりした敵がいましたが、この作品の相手は小惑星、つまり自然災害なのですよね。だから、対策を練る時間が少々あって、交渉もしなくていい。うまくいけば宇宙空間で小惑星を破壊し、地球にはほとんどダメージを与えずに済みます。しかし、うまくいかなくて……というストーリー展開ですね。
井上 この作品でも実際に行動するのはアメリカ政府に業務を委託された民間企業の荒くれ男どもです。石油採掘の技術で小惑星を掘削して核爆弾を埋め込む、という危険な任務です。
任務の最終段階で核爆弾の遠隔操作ができなくなり、地球を守るためには、誰かが小惑星にとどまって起爆スイッチを手動で押さなければならない。
ここでもまた「地球のために誰かが死ななければならない」問題が発生します。誰が死ぬのか、あるいは、自らの命をどう使うか。《アルマゲドン》では、娘の恋人AJがその役となるクジを引きますが、土壇場でハリーが強引に入れ替わって残りました。自分が身代わりとなり、若者に命のタスキをつなぎ、未来を託す。
こうした身代わり特攻のパターンは、百田尚樹の『永遠の0』(2006)でも見られましたね。『永遠の0』と他の作品との関係はいろいろ指摘されていますが、私は《アルマゲドン》は重要な先行作品に位置づけられると思います。百田氏が実際に参考にしたかどうかはともかく、全米が泣いた映画作品と、全日本が泣いた創作特攻文学との間に、感動の構造の共通性があってもまったくおかしくない、ということです。
鍵になるのは「Brave」?
坂元 ハリウッド映画なので、両作品とも作戦が成功した後には皆で抱き合って大喜びとなります。もちろん、宇宙人も小惑星も、「原ゴジラ」シリーズのように敬礼する相手ではないので構わないのですけれど。
ただ、その成功のために自発的に選択し、納得の上で行動したとはいえ犠牲者が出ている。お祭り騒ぎの中で、悲しい顔をしている遺族がいるわけですよ。

《インデペンデンス・デイ》では、ラッセルの息子に“What your father did was very brave”(君のお父さんは本当に勇敢だった)と、そっと声をかける人がいる。
《アルマゲドン》は、恋人は帰還したけれども父を失ったグレースに、“Requesting permission to shake the hand of the daughter... of the bravest man I've ever met”(私の知る限り最も勇敢な人の娘さんですね、握手させていただいてもよろしいでしょうか)と軍人が話しかける。
その時、どちらもbraveという単語を使っています。
braveとは何でしょう。私が外国の人とがんサバイバー関連の話をする時に、誰かのエピソードに「それはso braveだ」とか「braveにも、こういう決断をした」など、無意識に使っていました。いわゆる「勇敢な」という意味ですけれども、両作品のせりふをチェックしていて、他にもcourageousなどがあるのに、なぜ「brave」なんだろう? と思ったんです。
それで、Online Etymology Dictionary(オンライン語源辞典)を調べてみると、中世ラテン語のbravus「熾烈な、悪党」が語源だとされています。「勇敢」の中に蛮勇のような、褒め言葉だけれども少し「正しくない」ニュアンスがあるような感じです。
おそらく自ら死を選ぶという本来ならやってはいけない行動が、その状況においてはあまりにも正しく、あまりにも皆のためになる行動なので、野蛮な勇気というようなイメージがあるのかなと考えられます。
その意味で、《インデペンデンス・デイ》のラッセルも、《アルマゲドン》のハリーもbraveなヒーローだった。アメリカ的特攻文学は、Brave Storyと言えるのではないでしょうか。
誰かのために命をなげうつ行為がbraveであるとすれば、戦死は本質的にはbraveではないですよね。
井上 じつに興味深い指摘だと思います。職務で命令によってやる行為と、職務や命令を逸脱して、自由意志でやる行為がある場合に、braveは後者に対して言えるわけですね。軍隊の一員として作戦行動に参加して、その中で一生懸命戦っても、それはbraveではない。しかし、命令や義務を超えて、例えば仲間のために自分の判断で身体を張ったら、それはbraveだと。義務を超えた自由さというのがbraveの条件なのかもしれませんね。
坂元 志願してやること、自発的な行動ですね。
井上 今までの議論ともつながってきますね。祖国が立ち上がる必要条件は、政府の号令や軍隊の命令によってではなく、人びとが自発的に行動することでした。未来のため、他者のために、義務を超えた自由意志で自分を投げ出すbraveこそが、祖国の基礎にはある、と。
《アルマゲドン》では、核爆弾の遠隔操作が駄目になるまでは、アメリカ合衆国政府から与えられた任務としてやっている。そこまではbraveではなく、忠実に任務を遂行している。けれども、小惑星上で誰かが手動で起爆させるしかないとわかったところで、本来の任務から逸脱していきます。小惑星に残ってボタンを押すというのは、braveの領域に属します。
坂元 すると、残るはずだったAJもbraveだったのでしょうか。
井上 いや、braveはハリーだけです。振り返ってみると、そうするための手続きを踏んでいることに気づきます。
まず、誰が残るかを、クジで決めましたよね。クジを引いたAJは、自らの生死を確率に委ねました。つまり自発的に残る決断をしたのではないから、まだbraveではない。クジ引きをする前に、みんなが「俺が行くよ」「俺が英雄になるよ」と言うのだけれども、埒があかないから公平にクジで決めることになって、そこでいったんbraveは消えてしまうのです。

ハリーが宇宙船の外まで付き添って行ってAJを船内に押し戻したときにbraveが発生した。《アルマゲドン》は、このbraveを一人に限定するために、まず全員に「俺が英雄になる」と言わせてから、クジ引きによってbraveを一回消しているのです。
坂元 そうか、「俺が英雄になる」ために起こす行動は「未来のため」ではないですね。
井上 英雄になるためにやると言うことは、「不純なbrave」なんですよ。
坂元 不純なbrave! 英雄になりたいからというのは、僭称の祖国の担い手みたいなものですものね(連載第8回)。正統性は自分で付与することができない。「誰かがやらねばならない」切迫した状況下「他に誰もやる人がいない」というギリギリの必然性のなかで、命懸けの覚悟をもって発揮される自発性においてこそ、正統性が宿る、と。
井上 ハリーがAJの身代わりになったのは、英雄になりたいからではなく、娘のため、つまり未来のためで、命のタスキをAJに託したわけです。未来のために自分の命を使うのが、純粋なbraveです。
制度や組織が機能しなくなったときに、さまざまな立場の人が命令ではなく、未来のために志願して何かを守ろうとするときに祖国が立ち上がるのがbrave storyだといえるでしょう。アメリカの作品ではたいてい民間主導というより、大統領や組織のリーダーが自発的な力、brave的なものを引き出す演説をしますよね。
坂元 「犠牲者が出たらどうするんですか」に対しては「これは命令ではありません」「みなさん、自分で決めて志願しましたよね」ということで、犠牲者が出たとしても、それはbraveによるものであって、命令による死ではない。おそらく補償などにも応じない。
井上 そう。自由意志によって選択したのですからね。この場合、与えられるべきは補償ではなくて、「最高の名誉」です。名誉を担保するのは、犠牲者の追悼と顕彰です。
《インデペンデンス・デイ》における「人類最大の作戦」も全員が進んで参加しているので、braveとして賞賛されこそすれ、その死には誰も責めを負いません。命令による犠牲者は出ていないはずなのですから。
海神作戦にしても、仮に犠牲者が出たとしても責任を取る人はいないし、その必要もないのですよ。もちろん、それで国が救われたわけですから、政府から感謝状とお見舞金は出てしかるべきだと思いますが。
坂元 braveは美談にすり替わることが可能ともいえますね。《ゴジラ-1.0》では、敷島はゴジラへの特攻から生還しますが、その行動自体はbraveだったでしょうか。
井上 美談というとなんだか矮小化されますが(笑)、日本では「祖国」と同じく「名誉」についても、言葉の使い方を忘れてしまったのではないでしょうか。
敷島の行動は、作戦上の任務を超えるものなので、braveでしょうね。しかし、braveを名誉として社会的に位置づけないと、その後の人生はあまり幸せになれないかもしれません。つまり、ゴジラを倒して帰還したときは拍手喝采で迎えられるけれど、そうした熱狂は持続しませんから、次第に「特攻崩れ」「軍国主義の亡霊」などと腫れ物のように扱われ、疎外感を抱きながらひっそりと暮らしていくのではないか、と。
坂元 「Brave story」は、それを受容する社会的文脈についても考えさせられますね。特攻文学の要素がある作品にとっては、重要な概念になるかもしれません。
次回は、命のタスキリレーの中継者としてbraveな行動をした人物、あるいは勇敢な父祖となった人たちに対し「与えられるべきは補償ではなくて、『最高の名誉』です。名誉を担保するのは、犠牲者の追悼と顕彰」だとしたら、どのような方法で与えられ、効果を発揮するのか。
アメリカ映画の《ラスト・フル・メジャー 知られざる英雄の真実》を取り上げて考察します。
◎著者プロフィール
井上義和:1973年長野県松本市生まれ。帝京大学共通教育センター教授。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程退学。京都大学助手、関西国際大学を経て、現職。専門は教育社会学、歴史社会学。
坂元希美:1972年京都府京都市生まれ。甲南大学文学部英文科卒、関西大学社会学部社会学研究科修士課程修了、京都大学大学院教育学研究科中退。作家アシスタントや業界専門誌、紙を経て、現在はフリーのライターとしてウェブメディアを中心に活動中。がんサバイバー。
