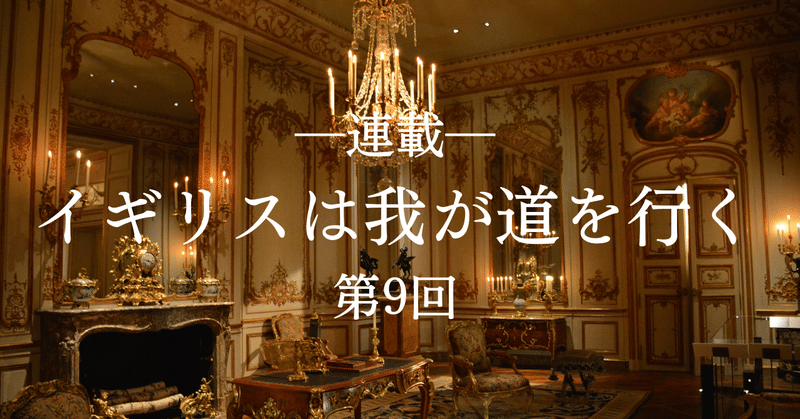
第9回 ジョージ五世と、首相になれなかった貴族ジョージ・カーゾン|本田毅彦(京都女子大学教授)
EU離脱、首相の交代、王室の関係など、なにかと気になる国、イギリスの「これから」を、歴史を紐解きながら考えていく連載『イギリスは我が道を行く』。筆者は、『インド植民地官僚 ―大英帝国の超エリートたち』(講談社)などの著書があり、大英帝国史の専門家でもある京都女子大学文学部教授の本田毅彦氏。
※強調部分には関連映像リンクが貼ってあります。そちらの映像もぜひご覧下さい。
誰が、どのようにして首相に任命されるのかについて、日本社会とイギリス社会を比べてみると、両国はともに民主主義国家であって、議院内閣制を採用しているので、本質的には同じだが(衆議院/下院の多数派を率いる政党の指導者が、首相になる)、実際の手順は少々異なっている。
日本では、国会の議決によって首相が指名され、それに基づいて天皇が任命し、新たな首相が組閣を行う。イギリスでは、選挙などを通じて議会の多数派に変動が生じた場合、新たな多数派の指導者が国王から宮殿に招かれ、首相となり、組閣を行うことを要請される。
従って、現在もなおイギリスでは、国王の意思が働く余地があるようにも見えるが、現実には、国王が議会の多数派の意思に反するような人選を行えば、それは憲法違反である。ただし20世紀に入ってからも、多数派の指導者が誰なのかが不明確だったために、国王の意思が作用する形で任命が行われた、と考えられる例が存在する。
今回は、そうした例の一つとして、1923年にジョージ五世(1865年生れ、1936年歿)が行った首相の任命を取り上げたい。君主であるジョージ五世と、彼によって首相に任命されなかった貴族政治家ジョージ・カーゾン(1859年生れ、1925年歿)の間には、個人的な関係に還元できない、王族と貴族の間の興味深い葛藤が存在した、と考えられるからである。第一次世界大戦を契機とする、近代社会の劇的な変化に直面した両者は、そうした変化の後、政治的リーダーシップのあるべき姿について、互いに異なる思いを抱くようになっていた。ジョージ五世は、伝統的エリートは民意によりそうべきだ、と考えるようになり、他方、カーゾンはなおも、伝統的エリートは民意を導く使命(ノブレス・オブリージユ)を帯びている、と信じ続けていた。
凡庸な王子と、野心的な貴族青年
ジョージ五世とカーゾンは、共にヴィクトリア女王時代に生まれ、成長した。両者は生まれた瞬間から、当時のイギリス社会の最上層に属していたため、幼い頃から王族・貴族の社交生活の中で実際に接触する機会もあっただろう。
ジョージ五世は、アルバート王太子(後のエドワード七世)とアレクサンドラ王太子妃の間に次男として生まれた。従って、王位継承順位は兄のアルバート=ヴィクターの次であり、本人も、自分が王位を継ぐ可能性はそれほど高くない、と考えていた。王子としての教育は、イギリスが海洋帝国であることをアルバート王太子が強く意識していたために、兄と共に、海軍将校を目指す形で行われた(ただし兄は、その中途で帝王学の研鑽へシフトした)。また、やはり父の意向に基づいて、兄と共にジョージ五世は、訓練航海の形でイギリス帝国各地を訪問した(日本にも立ち寄って明治天皇と面談している)。
しかし、アルバート=ヴィクターが1892年に病死したため、急遽、ジョージ五世は帝王学の研鑽を開始する。ちなみに、海軍兵学校での彼の成績は終始凡庸であり、本人もそれを認めていた。しかし同時に、政治的バランス感覚の優れた、また、見通しの良い人物だった、と思われる。
他方、カーゾンは、イングランド中部にあるダービシャー州のケドルストンを所領とする、ノルマン征服以来の貴族家系の継嗣だった。ただしカーゾン家は途方もない金持ちではなく、そのことが、カーゾンの上昇志向に火をつけた、と考えられる。つまり、学校で優秀な成績を挙げて自らの知的能力を証明し、イギリス帝国内の統治官のポストを得て功績を挙げ、やがては指導的な政治家となることを目指すようになった。
従ってジョージ五世とカーゾンは、それぞれ、王族、貴族としての立場からではあったが、「イギリス帝国」を、自らのキャリアを形成するための場所として強く意識する、という点で共通していた。そして、そのような二人が深く執着することになる政策課題が、やがて現れる。すなわち、イギリス帝国の基軸である英領インドにおいて、大規模な政治儀礼を成功させる、という使命である。
1903年インペリアル・ダーバーでのカーゾンの政略
1901年のヴィクトリア女王の死はイギリス帝国全域にインパクトを与えたが、とりわけ英領インド帝国が受けたそれは、大きなものだった。当時、カーゾンは、念願だった英領インド帝国の副王・総督の地位に就いており、この、ヴィクトリア女王の死去という事態に機敏に反応した。カーゾンは、女王の死を、英領インド帝国の政治心理的基盤を固めるための千載一遇のチャンスだ、と考えていた。他方、ヴィクトリア女王の孫であり、彼女の死を受けて王太子になったジョージ五世も、やがては自分がインド皇帝になることを肝に銘じており、従って、インド統治の将来像に関して、並々ならぬ関心を抱いていた。
昨今のイギリスの歴史学界において、代表的な歴史家の一人としてみなされているデイヴィッド・キャナダインは、カーゾンのことを、「卓抜な、政治的インプレサリオ(興行主)だった」と評している。そのカーゾンが企画し、実行した政治儀礼の中でも、最も大規模で、かつ成功を収めたものの一つが、1903年インペリアル・ダーバーだった。インド社会で伝統的に行われてきた君主たちの即位儀礼を大胆に焼き直した上で、ヴィクトリア女王に代わってエドワード七世がイギリス国王=インド皇帝となったことをインド社会全体に向けて宣言し、インドの藩王たち、そして英領インド軍の兵士たちに、新たな国王=皇帝への忠誠を誓わせることが、その趣旨だった。そしてカーゾンは、こうした儀礼に、英領インド軍の軍事演習、スポーツ大会、インドの伝統文化の展覧会などを組み合わせ、また、映画などのマス・メディアを活用して、その効果を高めることを狙っていた。
ただし、準備の過程で、この壮大なイベントの主役は、そもそも誰なのか、という問題が浮上した。即位の時点で既に高齢になっていたエドワード七世は体調不良であり、インド訪問は望めなかった。それゆえ、カーゾンは、副王である自分が儀礼を主宰するべきだ、と主張した。しかし、イギリス君主制と英領インド帝国の絆を重視する王太子ジョージ五世は、自身がこのイベントに参加することを切望していた。これに対してカーゾンは、ジョージ五世が来印すれば、式典において副王と王太子の序列(precedence)に関わる混乱が生じる、と唱え、結局、ジョージ五世の参加を阻止した。
1911年インペリアル・ダーバーでのジョージ五世のリベンジ
インペリアル・ダーバーを成功させ、栄光の絶頂に達したはずのカーゾンだったが、好事魔多し、と言うべきか、英領インド軍司令官キッチナーとの政争に敗れ、失脚する。さらに、カーゾンが発意したベンガル州分割が彼の離任後に実施され、それを悪意ある「分割統治」だとみなしたインド人たちにより、インド・ナショナリズム運動が一気に活性化した。
そのような中、エドワード七世が1910年に死去し、再度のインペリアル・ダーバーが1911年に行われることになった。父王の後を継いでイギリス国王=インド皇帝に即位したジョージ五世にとっては、言わば「復讐戦」の機会であり、彼は、この政治イベントを通じて、イギリス君主制とインド社会の和解を達成することを狙った。
式典での主要な儀礼がほぼ終わった段階で、ジョージ五世は大観衆に向かって突如スピーチを始めた。その内容は驚くべきものであった。ベンガル州分割の撤廃と、帝国の首都をカルカッタからデリーへ移すことが告げられたのだ。前者は、ヒンドゥー教徒の多いナショナリズム運動指導者たちの怒りを鎮めようとするものであり、後者は、イスラム諸王朝の都であったデリーへ遷都することで、ムスリムたちの歓心を買おうとするものだった。大胆な二正面作戦だったが、これにより、イギリス君主制に対するインド社会の好感度は一気に回復した。
なぜジョージ五世はデリーへの遷都を決断したのか
実は、ジョージ五世のこうした戦術は、カーゾンの残した先例に倣うものだった。1903年ダーバーに際してカーゾンは、ダーバーが単なる政治儀礼にとどまり、インド社会への実質的な「プレゼント」を伴うのでなければ、効果は望めない、と考え、インド社会の全住民に関わる、塩税の引き下げを式典の場で発表することを狙った。しかし、イギリス本国政府により、その実施を阻まれている(この30年後、マハトマ・ガンディーが、やはり塩税を焦点化し、大衆動員に成功する)。つまり、ベンガル州分割の撤廃と、デリーへの遷都は、ジョージ五世流の、インド社会への「プレゼント」だったわけである。
しかし、イギリスは本質的に海洋帝国であったから、英領インドの統治に関しても、いつでも撤収することが可能なように、三つの海港都市(カルカッタ、ボンベイ、マドラス)に張り付く形で支配を行ってきていた。これに対してデリーは、北インドの軍事的/政治的/経済的な要衝であり、インド亜大陸を支配する国家にとって、そこに首都を置くことは全く合理的だった。しかしイギリス人たちにとっては、内陸部への遷都は大きなリスクを伴うことになる。それにも関わらず、デリーへの遷都、そしてニュー・デリーの建設を行うことを、ジョージ五世が命じたのはなぜだったのか?
ニュー・デリーの建設は巨大なプロジェクトであり、多大の資金と時間を要したが、ジョージ五世の目の黒いうちに完遂した。そしてジョージ五世は、自らの像を、新都を見晴るかす位置に据え付けさせた。ただし、ジョージ五世の死後わずか十年で、英領インド帝国は瓦解することになる。
イギリス人たちは、インドにおける自分たちの帝国の命運が、それほど長くはないかもしれないことを当初から認識していた(インドに土着化する意思もなかった、ということになる)。そして彼らの中には、自分たちがインドを離れる際に、どれほどの遺産を伝えることができるのかを、インドにおける自分たちの支配の歴史的意義を測る尺度にしようとする者も、少なからずいた。今や、グローバル・サウスのリーダーになろうとするインド共和国にとって、ニュー・デリーは、それにふさわしい、壮麗で、しかも緑に富んだ首都として機能している。ジョージ五世は、ニュー・デリーを、英領インド帝国から、その後継国家への最高の「置き土産」にすることを意識していたのかもしれない。
カーゾンの首相任命を忌避するジョージ五世
1911年ダーバーを通じて、イギリス国王=インド皇帝への英領インド軍兵士たちからの忠誠心を再確認したジョージ五世は、その3年後に、第一次世界大戦に臨むことになった。開戦当初、志願制を採っていたイギリスの陸上兵力には限りがあったが、そうした中での、インド軍兵士たちの各戦線での活躍はイギリスにとって救いの綱であり、それを可能にしたジョージ五世の功績は大きかった。
大戦中、ジョージ五世は、イギリス国家の統合の維持にも顕著な貢献をした。また、時宜に適った首相の任命を行い、彼らとの協調を図った。大戦終結後には、イギリスでも社会主義的傾向の高まりが見られたが、これに関しても、君主としての立場から巧妙に対応している。
それに対してカーゾンは、インドでの失脚後、政界での逼塞を余儀なくされていた。しかし第一次世界大戦が始まると、国際政治の状況に通暁しているカーゾンの手腕への期待が高まった。ロイド=ジョージ首相からの誘いに応じて少数精鋭の戦時内閣のメンバーとなり、首相のサポート役に徹した。また、大戦後の国際政治の地殻変動の中で、的確にイギリス帝国を導くことができるのはまさに自分のような人間だ、との自負に導かれながら、外務大臣のポストに就いた。
そうした中、1923年、首相ボナー=ローが病気のために退陣することになった。しかし、この時点では、保守党内で、誰がボナー=ローの後を継いで次のリーダーになるべきなのか(次期首相になるべきか)が明確でなかった。国王ジョージ五世は、保守党所属で首相職を経験したことのあるバルフォアの意見を重視した、とされる。そしてジョージ五世とバルフォアは、カーゾンの性格を好まない点で(カーゾンを、自信過剰、自意識過剰で攻撃的だ、とみなす者は多かった)、一致していた。ジョージ五世は、「これからの時代は、貴族が首相になるべきではない」とのバルフォアの見解を受け入れ(カーゾンは、1908年以後、貴族として上院議員になっていた)、ボールドウィンに組閣を要請した。
王族の運命、貴族の運命
第一次世界大戦は、それまでのヨーロッパ近代社会のありようを大きく転換させた。それをもたらしたのは総力戦体制であり、その結果、いずれの交戦国でも社会の民主化が進んだ(革命に至った国も、多かった)。逆の見方をすれば、諸社会の伝統的な特権層にとっては、その存在意義自体が問われる時代の到来だった。そして、イギリス君主制は民主化に対応しえたが、イギリス貴族たちは退勢を挽回できなかった。こうした帰結には、貴族層の若年世代の多くが大戦中に将校として従軍し、前線で戦死したために、跡継ぎが失われるケースが多かったことも作用していた。
これは、ある面では皮肉な成り行きだった。イギリスの王族は、近世以降にドイツからやって来た、言わば新参の支配者だった。それに対してイギリスの貴族たちは、その多くが、ノルマン征服以来の、イギリス社会の土着の支配者たちだったから、である。そして王族、貴族ともに、口にこそ出さないが(出すこともあったが)、互いに対してそのようなイメージを持っていた。カーゾンがジョージ五世に向けて示した、やや不遜な態度も、そこに由来していた。
共に伝統的支配層に属するジョージ五世とカーゾンにとって、第一次世界大戦から与えられた難事は、民主主義/国民主義の進展に、どのように対応するか、だった。ジョージ五世は、それに「仕える」ことを選んだ。その結果、イギリス君主制は、とりあえず現在も話題に溢れ、イギリス社会から忘れ去られてはいない。これに対してカーゾンは、彼の目から見れば政治的に未熟な民主主義社会を、上から目線でリードし続けようとした。その結果、人々から時代錯誤とみなされ、物笑いのタネにすらされた。カーゾンの世代以降、世襲貴族たちは政治的権力者の地位から徐々に撤退し(その一部は、現在も上院議員の地位を保持しているが)、彼らの先祖が築き、子孫に伝えたが、現在はナショナル・トラストが所有し、一般に公開されるようになったカントリー・ハウスの一画で、歴史的遺産の管理人として、静かに暮らす者が多い。
