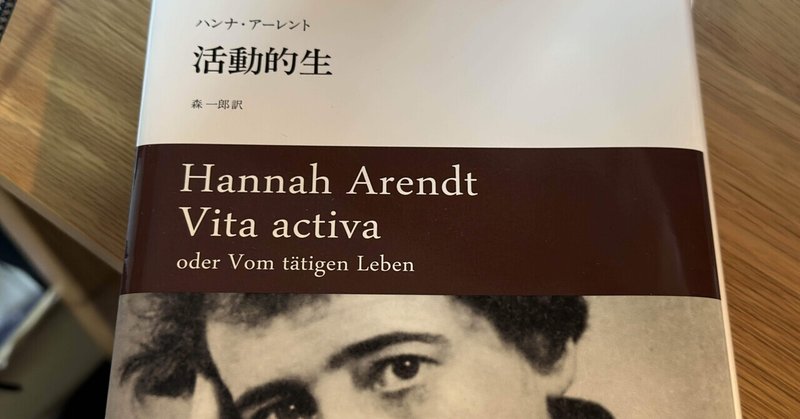
「赦す」という行為—アーレントの『活動的生』を読む
人間事象の領域の内部で赦しが何をなしうるかを最初に見てとり発見したのは、おそらくナザレのイエスであった。(中略)
目下の文脈で決定的なのは、「律法学者とパリサイ人」に反対してイエスの唱えた見解が、次のようなものであったことである。曰く、罪を許す力をもつのは、神だけではない。いやそれどころか、人間たちの間でのこの能力は、とりたてて神の慈悲深さに帰着させられるべき——あたかも、人間同士が許し合うのではなく、神が、人間という媒介を用いつつ、人間を許すかのごとく——ではなく、逆に、赦しの力は、相互共存している人間たちによってこそ動員されねばならない。そうしてこそ、神が人間たちを赦すこともありうるのだ、と。
ハンナ・アーレント(Hannah Arendt、1906 - 1975)は、ドイツ出身のアメリカ合衆国の政治哲学者、思想家である。1924年の秋、マールブルク大学でハイデッガーと出会い、アーレントは哲学に没頭する。その後、フライブルク大学のフッサールのもとで一学期間を過ごした後、ハイデルベルク大学に赴き、ヤスパースの指導を受ける。博士論文は『アウグスティヌスの愛の概念』。1951年に『全体主義の起源』を著し、全体主義について分析した。その後も、みずから経験した全体主義およびそれを生み出すにいたった西欧の政治思想を考察。1963年にニューヨーカー誌に『エルサレムのアイヒマン-悪の陳腐さについての報告』を発表し、大論争を巻き起こした。
1958年に発表した『人間の条件(活動的生)』では、人間の活動的生活を「労働」「制作」「行為」の3つに分類し、古代ギリシアのポリス共同体において行われていた活動的営みこそ「行為」であり、人間が人間性(唯一無比性)を保てるものは「行為」しかないと考えた。従って人間は、単に生命維持だけを目的とする「労働する動物(アニマル・ラボランス)」や、物質的・制度的な対象物を生み出すだけの「制作する人間(ホモ・ファーベル)」に堕してはならないと説く。
冒頭の引用部分は『活動的生』の第5章「行為」の中の一文である。人間の「行為」がなぜそれほどに特別なのか。一言で言えば、それは「新しいことを始める」という「出生性(natality)」に由来している。アーレントによれば、新しく何かを始めたり、逆に中断することができるのは人間だけである。自然や有機物、さまざまな生命体は、果てしない循環運動の中にあり、そこには始まりも終わりもない。その中で、まったく予想がつかない新しいことを始めたり、循環運動を断ち切るような中断をするのは、その「予測不可能性」を本質とする人間の「行為」だけである。
アーレントは、その「行為」の中でも「赦し」と「約束」という行為に注目する。「約束」は複数の人間が互いに共同体や国家を成り立たせ、未来に安定をもたらそうとする契約行為である。この「約束=契約」については社会契約論などで哲学において大いに論じられてきた。しかし「赦し」とは何か。これは主に宗教的分野で論じられてきて、哲学では真面目に取り上げられてこなかった、とアーレントは指摘する。人は「赦す」ことによって、過去の鎖を断ち切るのだという。これも一種の「出生性」であり、過去に誰かが犯した悪事に対する「復讐」という連鎖を断ち切る行為であるのだ、と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
