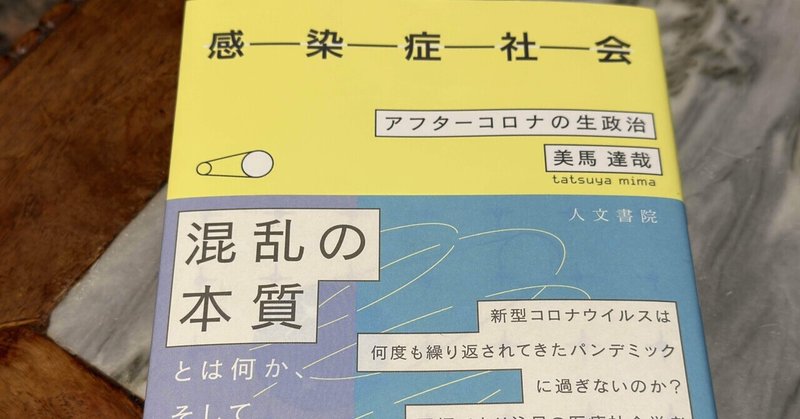
コロナ禍における「ミアスマ」の役割——美馬達哉氏『感染症社会:アフターコロナの生政治』より
たとえば、その一つは、客観的事実の正しさだけでは科学者も含めて人びとの信念や行動を変容させることは困難で、医療実践を変化させて感染症を減らすことはできない、という点だ。科学技術社会論で繰り返し論じられてきたとおり、観察された事実を受容する理論やパラダイムなどの認知の枠組みの変化とそれに伴う説明理論の入れ替わりが、事実そのものよりも重要であり得る。消毒法が社会に受け入れられたのは、感染予防に有効だったからというより、病原体説という思想がコンスティテューションのなかで支配的になったからだ。
美馬達哉(みま たつや、1966 - )氏は、日本の医学者、医師。立命館大学先端総合学術研究科教授。専門は、臨床脳生理学、医療社会学、生命倫理、現代思想。主要な著書に『リスク化される身体 現代医学と統治のテクノロジー』(青土社, 2012)、『生を治める術としての近代医療 フーコー『監獄の誕生』を読み直す』(現代書館, 2015)など。
本書は、パンデミックにおけるさまざまな事象を、ミシェル・フーコーの〈生政治〉の概念を鍵としつつ、主には医療社会学的観点から論じている。しかしながら、(医師らしい視点である)生物医学、公衆衛生学、ウイルス学的な観点も記述されており、それらを社会学的に相対化して論じているところが非常に興味深い。
引用したのは序章からの文章。ここで美馬氏は、医学史的には感染症(疫病)は、コンタギオ説(病原体説)とミアスマ説(瘴気説)の混合体として捉えられてきたことを明かす。ミアスマとは古代ギリシャにおいて、疫病がその一帯に淀む汚れた空気(ミアスマ)が原因となっていると考えられたことに由来する。例えば、コレラのパンデミックをきっかけにした19世紀のイギリスにおける衛生改革(上下水道の整備、都市の塵芥処理、換気の奨励)は、一種のミアスマ説とも言える。
また、フーコーが『臨床医学の誕生』において、一種のミアスマとして「コンスティテューション(constitution)」という概念を出していることにも注目する。コンスティテューションとは、構成・組成(ときには憲法や政体)を意味するが、近代医学においては感染拡大に関わる広い意味での社会・環境因子の複合した状況を指している。
美馬氏は「ミアスマ」が重要な役割を演じている例として、医学史的に有名なゼンメルヴァイスによる産褥熱対策の物語をここで持ち出す。ハンガリー出身の産科医イグナーツ・ゼンメルヴァイス(1818 - 1865)は、産褥熱の原因として医師たちが「手洗い」をしていないことに気づき、分娩管理や外科手術の前に手洗いの励行を促して産褥熱を激減させたことで有名だ。産褥熱は、抗生物質がまだ発明されていない当時、致死率が高く、産婦にとって恐ろしい病気だった。しかし、実際のところはゼンメルヴァイスの説は当時ほとんど受け入れられなかった。なぜなら、当時は感染症の原因として「ミアスマ説」が優勢だったからだ。彼は、面倒な手洗いを周囲に強制する狂信者とみなされ、他の産科医や医学界の重鎮に批判されて職を追われた。彼は頑迷な医学界からの迫害に絶望し、精神に障害をきたし、手術中のメスでできた小さな傷の化膿がもとになった敗血症で、47歳の生涯を終えた。彼の死後、病原菌の発見とともに病原体説が確立されて初めて、ゼンメルヴァイスの業績は正当に評価されたのである。
つまり、感染症を減らすことにおいて重要な事実の一つが「客観的事実の正しさだけでは科学者も含めて人びとの信念や行動を変容させることは困難」ということだ。そして、これは今でも変わっていない。美馬氏は、COVID-19パンデミックにおいても同様のことが起きており、広い意味でのミアスマ(コンスティテューション)の影響を考える必要があると説く。今回のパンデミックにおいては「一つのウイルスによる世界の均質化というにはあまりに複雑な事態が生じており、感染拡大や死亡率の国家間や地域間での差異の大きさのほうが私たちの目を引く」と言う。つまり、コロナ禍という現象の背後には、かなり複雑で多様な要因がコンスティテューションとして働いているわけだ。
私たちが留意すべきなのは、単に生物医学的・公衆衛生的にコロナ禍を捉えることではなく、コンスティテューションとしての個別的で複雑な局面状況を、細部に目を配りつつ複雑なままに取り扱うことなのではないか、そのように美馬氏は提唱するのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
