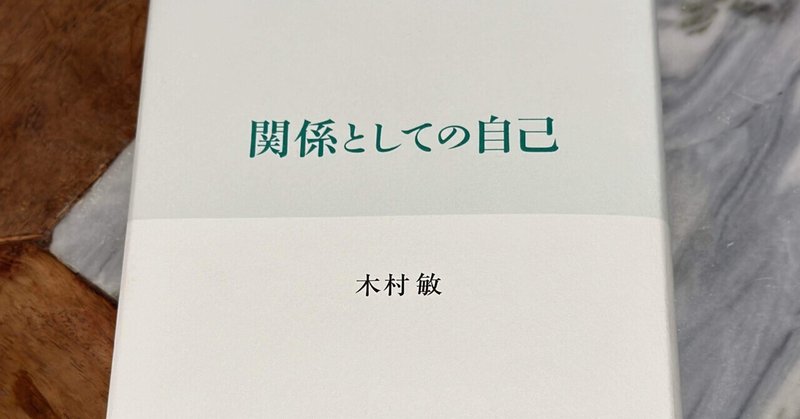
「私」とはなにか——木村敏の「関係としての自己」論
「私」とは、私自身のことである。自分自身のことを実感を込めて「私」という一人称で名指せる存在、それはこの私自身の他にはこの世界にだれもいないはずである。ところが、実際にはこの世界に生きているというすべての人が、それぞれの自分のことを「私」と言い、私自身も当然のこととしてそれに倣って自分のことを「私」と呼んでいる。これは考えてみればおかしなことではないのか。
これは人間にとっての根源的で普遍的な問いの一つではないだろうか。この種の問いを感じる人と感じない人がいると思うが、感じる種類の人が哲学をする者となるのだろう。とはいえ、この種の疑問を感じずとも日常生活を送ることはできる。というよりも、この種の疑問は感じないほうが人生を円滑に生きることができるのかもしれない。それでも、哲学者とは、生きることの根底に潜む問いに目を向け、考えざるを得ない人々のことである。
著者は精神科医・精神病理学者の木村敏(1931 - 2021)である。日本の精神病理学の第一人者であり、人間存在を探究し、独自の思想を発展させた知の巨人でもある。木村は「あいだ」を軸にした独自の自己論を展開して国内外に大きな影響を与えた。人間の心理的時間感覚を「祭りの前(アンテ・フェストゥム)」「祭りの後(ポスト・フェストゥム)」「祭りの最中(イントラ・フェストゥム)」の三つに分類し、現代思想界から注目された。 「祭りの前」が統合失調症的、「祭りの後」が躁うつ病的、「祭りの最中」がてんかん的と考察された。
本書『関係としての自己』は、木村の自己論に関する論文集であり、2005年に初刊、新装版が2018年に出ている。その豊富な臨床経験と、ハイデガーの存在論、ニーチェの永遠回帰、フロイトの「死の欲動」、西田幾多郎の「純粋経験」などとの思想的対話をとおして、私を、自己を生きるとはいかなることなのかを論じつくす、木村人間学の到達点である。
冒頭の引用は第一章『私的な「私」と公共的な「私」』の中にある。私が「私」であることの不思議について、木村は、そこで意味してる「私」とは、「「私」一般のうち、特定の時点に特定の場所を占めている特定の「私」であり、「自己」一般のうち、特定の他者(たち)に対して特定の関係を持つ特定の「自己」である」(p.22)と述べる。「私」には両義性があり、いわば私的な「私」と公共的な「私」の間に私たちは生きている。その二つが相剋ををきたし、病的な症状を生む状況として、木村は「対人恐怖症」の例を考察する。対人恐怖症とは、「つねに変動する私的内面と公共的外面との板挟みになって、両者の関係がもっとも不安定で相剋のもっとも激しい「中間的な顔見知り」という対人状況」(p.49)で発生するという。
本書では、キルケゴールの「自己とは関係が関係それ自身と関係するという関係である」(『死に至る病』岩波文庫, 1939, 20頁)という言葉が何度か引用される。木村が考える「私」とは、「自己と世界とのあいだ——現在の事物的な世界とのあいだだけでなく、当面の他者とのあいだ、所属集団とのあいだ、過去や未来の世界とのあいだなどを含む——の、そしてなによりも自己と自己とのあいだの関係そのもののこと」(p.99-100)だと述べる。
本書では、キルケゴール、ニーチェ、レヴィナス、西田幾多郎など哲学、また、フロイト、ヴァイツゼカーなど精神医学・神経医学、さらにはニューロサイエンスの知見(リベットの「主観的時間遡行」の実験)なども参照されながら、「私」とは何なのかが深く洞察される。さらには、精神科医としての臨床経験(対人恐怖症、統合失調症など)も踏まえて考察していことが、説得力と深みを増していると言えるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
