
競合他社より過去の自社製品と競う文化がある
本連載 “Challenger’s IDEA” は、各業界でチャレンジされている方をゲストとしてお迎えし、今後のブランドの在り方をディスカッションしながら、「チャレンジを続ける人たちの思想をシェアするスペース」です。
今回はDJI JAPAN株式会社マーケティング部 コンシューマー マーケティング ディレクター 川中さんと、ドローンをはじめとする撮影機器とクリエイティビティの可能性についてディスカッションしました。
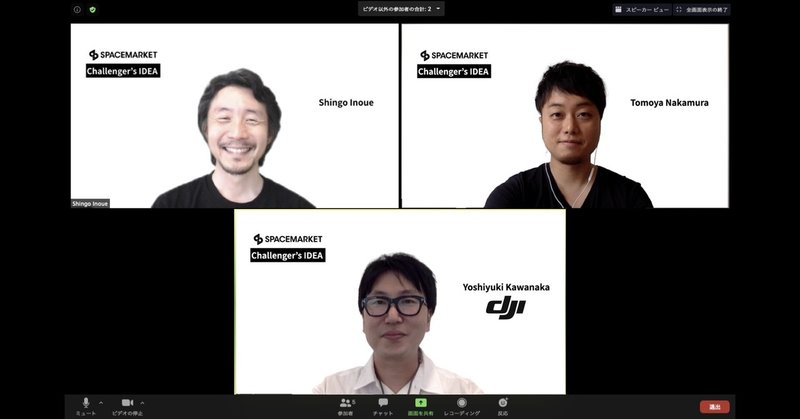
(下)DJI JAPAN株式会社 マーケティング部 コンシューマー マーケティング ディレクター 川中 良之 氏
(左上)株式会社スペースマーケット 井上 真吾
(右上)株式会社スペースマーケット 中村 友哉
中村:今日はよろしくお願いします!
川中:お願いいたします!
中村:僕、今日最初にこれを伝えたかったのですが、Osmo Action(手持ちアクションカメラ)のCM動画が大好きで。
クリスマスに子どもがサンタさんにプレゼントをお願いするという内容。途中でOsmo Actionが出てくると思いきや出てこなくて、最後に #視点を変えれば見えてくる というメッセージで締める、めちゃくちゃ感動しました。
中村:世の中の広告動画は製品をそのまま押し出すものが多い中、あえて製品を本編に出さずに、最後にストーリー全体の裏側はそういうことか!という気付きを与えて認知させる。めちゃくちゃ最高です。
川中:ありがとうございます!非常に難しい決断でした。メーカーなので通常であれば製品の魅力をそのまま説明するのが一番ストレートですが、他社製品もある中で我々の製品の見せ方をどうすべきか、工夫しました。
中村:とてもすてきでした。冒頭からすみません個人的な感想で。(笑)
川中:いえいえ、ありがとうございます!
個人向けOsmoシリーズから映画撮影機器のマーケティングに従事。
中村:まず川中さんの事業領域、またDJIとしてのミッションを簡単にご紹介ください!よろしくお願いします。
川中:はい。DJI自体は2006年に創業し、いわゆる空撮用や、様々な業務の現場、農業、測量・点検や防災目的で使うドローンまでトップシェアのラインナップを拡張しています。
私がDJI JAPANに入社したのは2015年12月です。当時は国内で改正航空法が施行され、市場が大きく変わり、日本法人として大きく拡大を図り始めた年でした。入社当初はソーシャルメディアの運用を担当し、その後2018年から現在にいたるまでは個人向けの製品や、映画制作のようなプロクリエーター向け製品のマーケティング全般を担当しています。
また地上で使うカメラやアクションカメラ、スマートフォンを載せてぶれない映像が撮れるジンバル技術を搭載するOsmoシリーズや、Roninという映画を撮るような映像機器もラインナップしており、それらの日本市場におけるマーケティング活動を行っています。
中村:なるほど。ありがとうございます。ここ数年Osmoシリーズが世界の中でも日本の売上が高いという話を聞いた事があるのですが、約5年間DJI JAPANに在籍される中で、国内ユーザーの変化として特に感じられている事などありますか?
ユーザー層をプロ意外にも裾野を広げる事に成功。
川中:私が入社した2015年当時、ドローン愛好家は一部のクリエイターや、もともとラジコンを飛ばすのが趣味だという方々に限られていたのですが、最近では「カメラ」という一つの趣味としてのポジションを得たというのが非常に大きいです。
その背景としては、そのカメラ性能が上がり、使いやすくなったことが挙げられます。「使いやすさ」とは高画質での撮影だけではなく、自動で飛んで撮影してくれるとか、それなりのスキルがないとできなかった撮り方も指でアプリをタップするだけで自動的に飛ぶとかを含めてです。同時に安全性能も高まってきていますので、初めて飛ばしたときから意外と使えてしまうという製品に進化してきました。
また我々をとりまく外部要因として、ここ約5年でソーシャルメディアが非常に活発に利用され、動画配信が広がってきたという点が大きいです。Instagramも当初はスマートフォンで写真を撮ろうというアプリだったのが、今では動画の活用も多くなりました。
あとはYouTuberの盛り上がりです。動画プラットフォームの進化と、投稿して共有していく流れの活性化もわれわれの追い風になりました。特に旅に出たときの思い出、さらには映像作品や写真も人と違うものを撮りたいという方々に非常に刺さって、「いつかやってみたい」という思いも含め、興味関心を持っていただく方が増えたのが、これまでの大きな変化です。
コロナ禍の外出自粛も未来志向の製品には影響せず。
ただ手持ち型製品のOsmoも含め、われわれの製品は外で使って初めてその価値を発揮するものが大半です。そのため2020年前半のコロナの問題を受けて在宅時間が多くなることで、大きな課題が生じると予想していました。
実際はビジネスとして好調で、ドローンも含めて特に大きく落ち込むというよりは、むしろ非常に伸びている状況です。
昨今の「何か1つの作品に力を入れて撮るだけではなく、今日は使えなくてもいつか使えるかもしれないとか、これさえあればこんなことができるかも」という未来志向の製品にしていった事が良い展開を作ったのだと考えています。コロナ自粛が明けたらこれを持って何か撮ろうとか、今というよりは未来志向でこれがあったらこんなことをしたいなという、ワクワクする製品が多いのかもしれません。
利用シーンはどう拡散されていったか。
井上:最初はクリエイターのような方々が独自の作品を作って発信していくと思うんです。彼らは他人と違う角度で「ここの視点から、こういう形でこう撮ったんだ」と自身の作品を投稿する。それを見たインフルエンサーが同じようなものを作る。今度はそのインフルエンサーのフォロワーがみんな同じものを作る。今のDJI製品のワクワクはそのフォロワーにだんだん広がっていっているし、それを助けているのがソーシャルという構図なのだと感じました。
川中:まさにそうですね。特に若いクリエーターさんの間で絶大なる影響を与えたSam Kolderという方がいます。YouTubeやInstagramで、その撮影スタイルや編集のエフェクトの付け方、色のレタッチ方法などを紹介し、世界的に影響を与えた人です。彼はいち早く新しい技術を取り入れていて、それをやってみたいというモチベーションがクリエイターに広まったと言って良いと思います。
井上:自分でやってみたときの体験が大事で、その体験を共有してみないと同じようなモチベーションや感情になれないですよね。
新しい製品の体験者をどう増やしていくか。
中村:DJIはドローンやOsmo Pocketなど市場にとって新しい製品が多いのですが、それらの経験者が少ない中で、まず触って体験を促すために、今までどんな取り組みをされてきましたか。
川中:一つは店舗での訴求ですね。Osmoは電源がつく状態で店舗に展開しているので、こんなものかと触りやすいのですが、ドローンに限っていうと体験してもらって初めて分かることも結構あります。そのため、DJIというより全国にいる代理店さんに協力いただいて講習会をやっています。飛ばし方だけではなくて飛行ルールの説明会も含めて、まずは知って体験していただく、という会をよくやっています(コロナ禍では休止中)。
井上:御社の中でアンケートはとられていますか?例えば「ドローンについてご存じですか?」というと結構な割合の方が知っていると思います。一方で「触ったことがありますか?」となるとグッとその割合が減って、「持っていますか?」となるとさらに減る。触ってみたいなと思っている人と触ったことがある人の間に結構な差があるような気がするのですが、そのあたりいかがでしょうか。
川中:まさにおっしゃった通りで、ドローンという言葉そのものは皆さんご存じですし、ああいうものが撮れるのだったらやってみたいなと思っていただく方も多いのですが、実際にアクションを取るまでの距離は結構遠いんです。体験会をやるといっても連日実施しているわけでもないですし、特に地方にお住まいの方々にとっては気軽に参加できる場所でやっているかというと、まだまだ少ないです。
そこを埋めるためには、自分ごとというか、自分でも使ってみようという気持ちに持っていくまでのチャレンジはあります。なので、やっぱり体験の場をつくっていかないといけないですし、より身近に感じられる疑問にお答えできるコンテンツの発信は継続していかないといけないなと思っています。
この先の情勢がどうなるかもありますが、ユーザーを増やしていくことは会社のミッションとしつつも、その活動を通じて使っている人が周りにいる人を1人でも増やすというのが、われわれの次の大きなステップです。心理的なハードルも事実ありますので、そこをいかに下げていくか。
当然ルールもあるのでそこの認知を高めながらですが、例えば、何かの集まりのときに誰かが持ってきたとか、あの人が空撮のコンテンツを出しているとか、そういうところからの広がりは大きいと思っています。昔ながらの表現でいうと、口コミも大切にしないといけないかなと。
DJI一社だけでは生み出せないコミュニティを作る。
井上:御社として空撮やOsmoで押しているクリエーターみたいな取り組みもされていますでしょうか。
川中:いわゆるインフルエンサーと呼ばれる方々もおられれば、その中で元々ユーザーだったという方も多いのですが、一緒にコンテンツを作って、企画に参加いただいています。
今まで我々と接点が全くない方に対して依頼するということは、実質ありませんでした。もともとのユーザーさんや、地上では活発で空撮を取り入れたら面白いという方とか、親和性のある方を使っていただいていて、そういう意味では結構いらっしゃいます。
井上:そういうところからクリエーターや趣味でやっている人たち同士が、コミュニティー内でいろいろ情報交換をしたり、自分の作ったものを交換して、それを影ながらDJIさんがサポートすることによって、実は結構間口は広いんだよという見せ方を作り勝手にユーザーが増えていくと一番いいなと思います。
川中:まさに、その動きをより具現化していかないといけないかなと。ずっと課題としては持っていて、いよいよ今年かなと思っていたら、この状況(コロナ自粛)になってしまったんですけれど。
あとわれわれが特定のどなたかに依頼するときは、必ずしも影響力一番ではないんです。よくSNSからも、「そのクリエーターになりたいんですけど、どうしたらいいですか」とお問い合わせいただくことがあるんですけれど、意外と数の足し算の世界ではないので、お答えが難しい部分があります。
やってみたいと思われる方が多いことも認識しているので、コミュニティーをより広げていかねばというのはあります。SNSにはドローンのコミュニティーがたくさんあるのですが、もうちょっと気軽に共有できる場所をつくっていかないといけないと思っています。
井上:技術的なことや中身の仕組みはプロダクトを提供しているDJIさん側が一番詳しいと思うのですが、実際の使われ方とか、こういうことをするとこんな風景を撮れるとか、ここでこうやっているとこんな体験ができるよというのは、ユーザーのほうが詳しい可能性が高いですよね。なので、もしかするとDJIのカスタマーサポートでは答えられない質問を、あまりDJIさんが中に入らずそれをユーザーさん同士で回答しあえると一番良いような気がします。
われわれスペースマーケットもそういう世界観を目指しています。CtoCのサービスなので、できるだけユーザーさん同士がネットワークを自然と広まげていく、というのをつくりたいです。
川中:われわれが語ることは、実際の利用の要素でいうと50%でしかなくて、物があっても使う人がいなければ成立しないのは一緒ですね。
井上:あまり会社側が答えちゃうと制限してしまうというか、ステレオタイプ的なものが確立してしまい、実はこんな使い方もできるみたいなのは、ユーザーさんのほうが詳しいような気がします。
川中:製品を提供する側のドローンのアクセサリーメーカーも今たくさんいて、われわれが推奨している、していないは関係なく、実はいろんなものもあります。例えば、360度カメラのメーカーが、ドローン搭載用のアクセサリーも販売しています。ただし、われわれは単体での使用を想定し機体バランスを取っているので、アクセサリー類を載せることは推奨していないんです。
とはいえ、360度カメラでいうとInsta360さんは、われわれのMavicを載せるキットみたいなドローン用のカメラという名目で出されいます。そこには360°映像を撮りたいニーズがあって、それをいろんなツールで実現しているという意味では、われわれ1社ではできないことも本当にたくさんあります。
ルールを広めていくこともそうですし、皆さんの希望である「どこなら飛ばしても良いのか」という場所を広げる方法もそうです。1社単独では、速度も遅いし力も及ばない。そういったコミュニティやドローン業界にもたくさんの団体があるので、みんなでこの業界を盛り上げていこうよという機運が、そろそろ大きくなるんじゃないかなと思っています。
クリエイティブの自動化と人によるアートと。
井上:今後の技術的な観点からの製品の成長や、増やしたいクリエイティブなどについてお話をお伺いできますか?
川中:われわれがテクノロジーの会社として、究極の目標にしているのは無人化です。人の手間を省略して撮りたかったものをいかに最短で撮れるかが大きな目標です。ドローン操作を自動化することもそうですし、編集用のアプリを開発していて、テンプレートで枠にはめていけば動画ができたり、Osmoだとカメラそのものが動いて短い動画を自動で作ってくれたりします。
これからは一般の方が動画を写真と同じレベルで撮影や編集ををいかに簡単にしていくかが大きなポイントで、そこにいち早く取り組んでいこうと思っています。
ただ当然、ある種、アートな部分もあって全部を自動化してしまうのも難しいので、ある程度はその人のアイデアを確実に具現化できるソリューションとしての立ち位置を持っておくことが、今後は大事かなと。DJIもそこに向かって着実に進んでいます。
井上:そこはめちゃくちゃ楽しみですね。多くの人にとって恐らく一番大変なのは編集で、良い動画を撮ったんだけれども放置されちゃうともったいない。そこでささっと編集して、パッとアップできるとなると、レイトマジョリティーというか、ユーザーの裾野を広げていくためには、とても効くような気がします。
川中:どれだけ技術が進歩していっても、例えば世界標準が電気自動車になってもガソリンのマニュアル車で走りたい人もきっといると思うんです。そういった趣味としてのドローンを楽しめる要素は、恐らく大切です。一方でわれわれの製品を使っていただく多くの方々は、DJIやOsmoを趣味にしたいわけではなくて、きっと旅行に行くからきれいに撮りたいとか、何かの目的の手段でしかないので、思ったことをいかに簡単にしてあげるかはポイントだと思います。
井上:今のお話、すごく僕にとって刺さりました。製品のファンを増やすというよりは、体験をするときに常に横にあるという状態を作るのが一番大切ですよね。良さをメーカーから一方的に伝えるというよりは、体験の素晴らしさを訴求していけば、自然と伝わっていくと思います。
川中:われわれDJI JAPANとしてもっとも親しまれているのは実はOsmo Pocketで、かばんの中に入っていて、いきなり取り出してすぐ撮影できる。なので皆さんからも「何それ」と聞かれるし、製品そのものが話題になるんです。やっぱり小さくて使いやすいという要素もありますが、物として持っていて楽しいという事も大事で、DJIという会社はどこまでいっても常にそういったワクワク感を提供したいと考えています。
DJIは競合他社というよりは自社製品の過去のものと競っている文化があります。価格にかかわらず最新製品に最新技術を載せるという思考が非常に強くて、驚きのある製品を作ることに全力を費やしている会社です。なので1~2年の間に全く想像できないレベルの何かが出ているんじゃないかなと。
時代に合わせて新しい提案をしかけていく。
中村:今お話に出たOsmo Pocketは特にシリーズとしては初代ながら、すごく普及しているなという印象があります。僕の周りの友だちでも使ったことのある人が意外と多いんです。
僕自身も2泊で北海道旅行に行った時にOsmo Pocketで撮影した動画を、帰りの飛行機の中でさくっと編集できて感動したのを覚えています。
そしてちょうど去年、スペースマーケットコラボの中で古民家やパーティールームに置かしてもらって体験できる施策をやりましたが、OsmoとDJI Mimoアプリという組み合わせが簡単に作品が作れるという意味では、すごくいいなと思いました。
川中:Osmo pocketは2018年後半に出した製品なのですが、いまだに好調で、DJIの製品といえばあの形みたいに未だ現役です。Osmoを初めて使っていただくケースのほうが多い気もします。去年からCMを見ればトヨタではずっと出ていますし、テレビロケの中など意外といろんなところに入っています。
何よりOsmo pocketの優れている点はカメラを向けられている気がしないことです。旅行で使ってみるとよく分かりますが、大きいカメラだと撮影してる感が出すぎるのですが、Osmo pocketはちっちゃいので片手で持つだけでいろいろ撮れます。そういう意味では、日本向けだったかなと思います。
特にコロナの状況下では、スマホをスタビライザーに装着する形状のOsmo Mobileも販売が伸びているので、手軽に動画を撮ってみようかなという方が非常に多かったんだと思います。スマートフォンなら皆さんお持ちですし、せっかくだったら手ブレのなくせるスタビライザーを手にして家の中を動いて撮ろうかなというニーズはありました。
さらに少し未来の話にはなりますが、もし今後5Gなどに通信速度が上がったときに、ポイントはいかにユーザーのみなさんが画質を落とさずに日常をオンラインで配信できるかだと考えています。解像度が上がれば上がるほどブレは目立つので、その様な時代に合わせて、われわれ側も新しい提案をしていかなければと考えています。
DJI JAPANの永遠のテーマとは。
川中:もともと空撮の面白さであり難しさは何が撮れるか飛行させてみないと分からないところです。熟練者は地上で空から撮れた絵が分かる方もいますが。なので「ここは空撮にお勧めですよ」とか、「ここはこういうルールを守っていただいたら飛ばしてもらってもいいですよ」という、撮れる作品としての推奨すべきポイントと、飛ばせる環境が整った場所を日本全国に広げていかないといけないと思っています。それはDJI JAPANがある限り永遠のテーマになるので、いろんなユーザーさんと共に広げていきたいです。
中村:ぜひスペースマーケットもそこで協力できるといいなと思っています!
川中:ユーザーの皆様にとって、ここって飛ばしていいのかな?という疑問や、実際に撮影許可を取ることも含め、複雑になりやすいこともあって。それであればスペースマーケットさんのスペースを時間で借りて、そこで飛ばしてみようというのは非常に大きなニーズがあります。
われわれとしても場所のオーナー様の立場である、施設管理者、自治体、地域の方々に対しても収益として落ちていくモデルを今後検討し推進したいのです。もちろん、無料で使える場所も広げていく一方で、一つ有料施設としてユーザーさんが占有して使えるという空間は大事なので、そこをスペースマーケットさんのスペースホストの皆さんと、ここは飛行OKというところをノミネートいただけるとうれしいです。
先ほどのお話のように2~3回飛ばしてから本番に臨みたいという練習ニーズがあるので、近所で練習できる場所を確保できるとすれば、都会ではそれだけで大きなニーズがありますし、実際にわれわれ自身も使いたいぐらいです。
井上:われわれは会社として「スペーシェアをあたりまえに」というミッションを掲げていますので、ぜひ力になりたいですね。
地上から見たら何の変哲もない場所が、上空に行ったらこんな凄い絵が見られますというのは、新たな価値の創造になるなと思います。
川中:そうですね。そういった発見もあるので、そこは一緒に見つけて行きたいです。
あとは、ちょっとトリッキーな話ですけれど、既に出ているフットサルコートも一部開いている天井をネットで覆っていたりするので、航空法のルールでは外であってもネットで屋根を作っていたら屋内扱いなんです。極端な言い方をするとゴルフの打ちっ放しは都会のど真ん中であっても、実はあそこだと屋内扱いになるんです。
あと今は空撮のお話でしたが、場合によっては動画撮影に推奨できるようなロケ地スペースが広がってくるだけでも業界全体としてはありがたいです。
中村:ありがとうございます。それこそ、この記事をホストの皆様にも展開して、キャンペーンに参加を希望される方を、どんどん増やしていきたいと思います!
川中:ありがたいです。
中村:いろいろと面白いお話をいただきまして、ありがとうございました!
井上:ありがとうございます!
川中:ありがとうございます!

