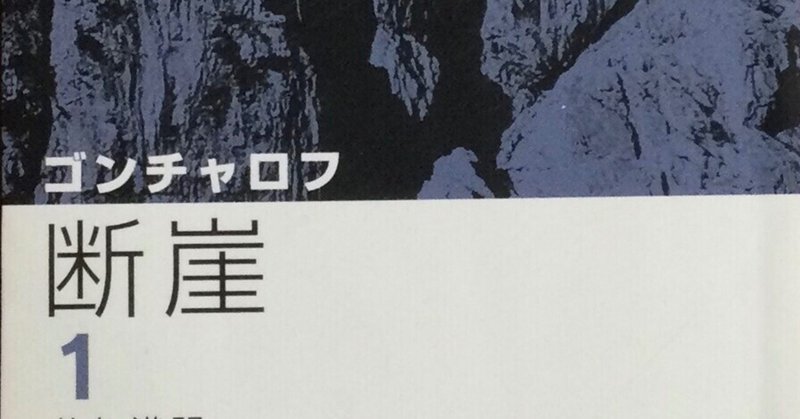
ゴンチャロフ『断崖』についての雑記
ロシアの小説家・ゴンチャロフの最後にして最大の長編『断崖』を読み終わった。これでゴンチャロフの小説は全て目を通したことになる(『平凡物語』『オブローモフ』『断崖』)。この作品、とにかく長い!ひたすらノロノロと進むのである。ゴンチャロフの作品に共通することは、筋というものがおおよそ存在しないということである。だから、粗筋なんかに目を通しても大して意味は無い。ゴンチャロフの才能は(ベリンスキーやドブロリューボフが指摘するように)形象の創造という点で大いに発揮される。彼は典型的人物を創造するのがとても上手なのである。そしてその形象たちが動くがままに筆を進める。これはゴンチャロフが自身の創作に関して述べてある通りである(『おそ蒔きながら』)。だから彼の小説は人物を中心に進み、その登場人物たちが外的な出来事に意味を与える。ゴンチャロフにあって重要なことは、登場人物たちの外界に対する態度、彼ら同士の会話にあらわれる。「筋が無い」とはこの意味においてである。
『断崖』の主人公・ライスキーは情熱を秘めた芸術家である。具体的に何をしているのか?何でもしている。小説も書くし、絵も描く。音楽もするし、彫刻にも手を出す。才能はあるが、その才能を何に向けて良いか分からないのである。そして何より怠惰である。やり通すことが出来ないのだ。『断崖』は彼を中心にして話が進み、そこに祖母のタチヤーナ、従妹のヴェーラとマルフィンカ、ならず者マルク、旧友のコズローフ、実業家のトゥーシンたちが加わって一大絵巻を展開する。
正直に言うと、私はこの『断崖』にあまり惹かれなかった。『平凡物語』ほどには、登場人物同士のやりとりの軽妙さも感じるところは無く、『オブローモフ』ほどには、形象に興味を抱かせるようなところも無かった。ライスキーは確かに面白い人物ではあるが、アレクサンドルとオブローモフ、つまり前二作品の主人公の混合物のような印象を受ける。主人公の形象に新鮮さを感じることが出来なかったのが、『断崖』に惹かれなかった一番の原因かと思う。
『断崖』の思想面については次のことを思った。「理念が形象を追い越している」というようなことを、ベリンスキーはゲルツェンの『誰の罪か』に関して言ったことがある。ゴンチャロフは『断崖』にあってゲルツェンの方向に近づいてしまったように思われる。つまり、作者の理念が前面に出過ぎたのである。このこと自体は全く問題では無い。トルストイもドストエフスキーも、偉大な小説家であると同時に偉大な思想家でもある。思想家・ゴンチャロフにはあまり魅力が無い。『断崖』はいわゆる「アンチ・ニヒリズム」であるが、その「ニヒリズム」にあたるマルクはあまりにも弱々しく一面的である。マルクにあるのは反骨心だけで、それ以上の何も無い。ゴンチャロフはニヒリズムに積極的な意味を一切与えなかった。同じ「アンチ・ニヒリズム」である『悪霊』がアンチ・ニヒリズムの枠を超えて「神と人間」という問題に至っているのに比べて、『断崖』は、「古き良き」を体現する祖母タチヤーナを持ち出してマルクを追い払ってしまう。
『断崖』について、なんだか色々と思うところあって書いてしまったが、たしかに面白いところもある作品である、と最後に言っておきたい。ライスキーとクリッツカヤのやりとりは噴飯ものだし、祖母タチヤーナにおける形象的積極性は、アクサーコフ『家族の記録』の老バグロフに通じるものがある。この点に置いて芸術家・ゴンチャロフの才能が遺憾なく発揮されていると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
