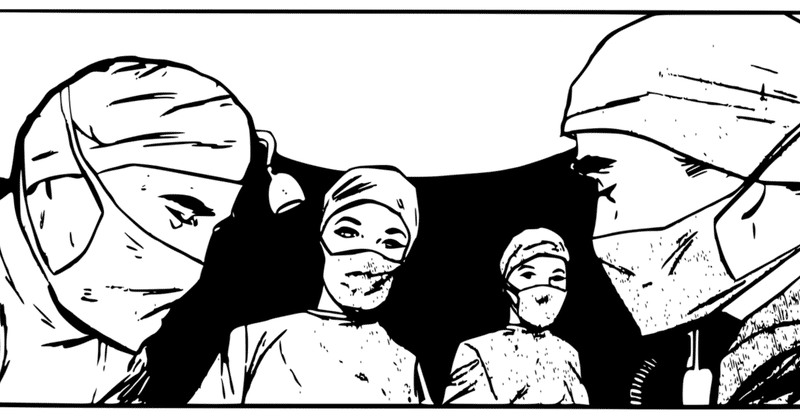
小説「移植医たち」:医師の視点で臓器移植を描く!モデルとなった医師と僕らのねがい!
日本の臓器移植の定着を遅らせたと言われる「和田移植」この事件がもたらした闇の真相を探れば探るほど、その疑惑は深まり、あってはならない思いは強まる。
しかし、臓器移植の是非を問われると、それは必ずしも否定できるものではない、移植医療の発展によって、助かる命がある限りそれを望む声があるのは当然である。
この問題は立ち位置やポリシーによって意見は異なるのだ。
果たして、移植医の立ち位置はどうあるべきなのだろうか?
医師の使命は患者の命を守ることである。しかし、彼らは常に、ドナー(臓器提供者)とレシピエント(臓器移植者)の命を秤にかけなければならない十字架を背負っている。
小説 移植医たち
「移植医たち」(著;谷村志穂)という医療小説は、移植専門の外科医たちが技術を磨き、様々な苦悩に立ち向かうといった内容である。
もちろん小説なので、フィクションなのだが、医者の目から見た臓器移植の現実を理解するには参考になる本だ。
多くの取材や調査を重ね、臓器移植の世界や現実をリアルに表現している、「和田事件」と思わせる内容や、今日の移植手術を日常化としたノーマン・シャムウェイスタンフォード大学名誉教授、教授とも接点があったろう、和田壽郎札幌医大教授をモデルにした登場人物も描かれている。
小説の登場人物のモデルとなった上記の二人は一体どのような人であったのだろうかを検証してみよう。
和田壽郎氏の疑惑

和田壽郎氏は1922年生まれ、北海道大学医学部を首席で卒業、28歳から4年間アメリカへ留学し、複数の大学で胸部外科医としての研鑽を積む。
この間、世界初の心臓移植手術を執刀した南アフリカのバナード氏や、今日の移植手術の礎を築いたとされるノーマン・シャムエイ氏などとも知己を得たと言われている。
帰国後は、新設された札幌医科大学の助教授となり、36歳の若さで院内に創設された胸部外科教授となる。
「ワダ弁」と呼ばれる心臓人工弁を開発、多くの心臓手術を行い豊富な経験と論文の多さで、我が国の胸部外科の第一人者となった。
46歳の時に我が国初の心臓移植手術を執刀し、時の人となるが、83日後にレシピエントの死を境に、ドナーへの仕組まれた脳死や、不適切なレシピエントへの移植ではなかったにかなど数々の疑惑が持ち上がった。刑事告訴もされ、社会は揺れ動いた。
不起訴とはなったものの、真相は藪の中で極めて灰色な状況は、その後日本の「脳死」や「臓器移植」に対するアレルギーを強め、これ以降30年以上我が国では臓器移植はタブーとされ、行われることはなかった。
我が国の臓器移植のパイオニアでありながら、臓器移植の是非はともかく、結果的には我が国の臓器移植の発展に歯止めをかけたことは皮肉でしたない。
医療の発展には、仕方がないとは言わないが結果として多くの犠牲や失敗はつきものである。しかし、疑惑を探れば探るほど、それは生命を軽視した行いである。
疑惑が事実ならば、独善的な驕りと、功名心があったのではないかと思わずにはいられない。
ノーマン・シャムエイ氏の功績
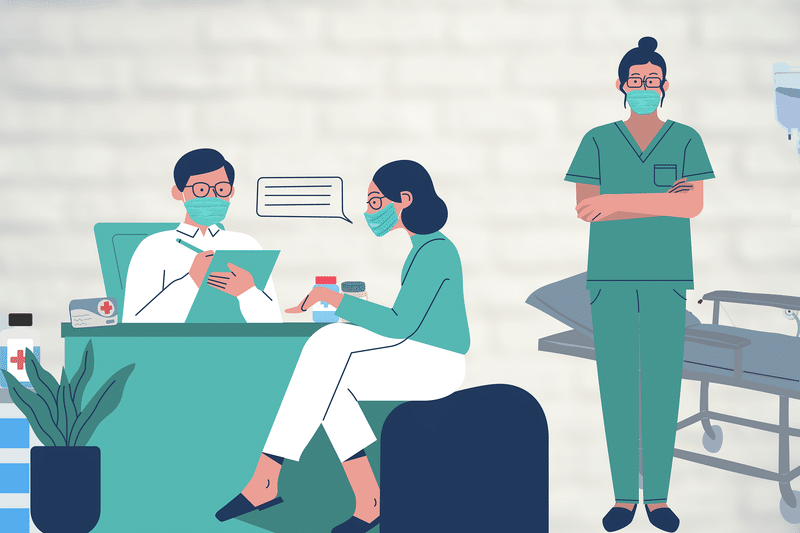
1923年ミシガン州で生まれた氏は、陸軍に徴兵されますが、適性検査で医学の道を希望するよう勧められ、医学訓練を含む陸軍プログラムに参加します。
27歳で医学博士を取得。その後軍隊勤務、外科訓練を経て、33歳で心臓血管外科の博士号を習得し、除隊後スタンフォード大学の講師となる。
そこで、心臓血管プログラムを立ち上げ、8年間にわたり犬を使った心臓移植の研究と実験を繰り返す。
十分な精度を上げるようになり、1968年アメリカでは初めての心臓移植を行なった。日本で和田移植が行われる半年前のことである。
1歳年下のシャムエイ氏の心臓移植手術は、日本の和田医師も意識をしていたことは十分に推察できる。
シャムエイ氏が行ったレシピエントは14日間生存後、亡くなりました。
この点で言えば、和田氏の場合レシピエントの生存は83日間でしたので、その長さにおいては差がある。
シャムエイ氏の心臓手術はアメリカでももちろん賛否はあったようだが、新たな医療の心臓外科での画期的な手術は熱狂を呼び、世界的に広がる兆しとなり、たちまち世界で100例もの移植が行われた。
「和田事件」となった移植もこの中の一つである。
しかし、そのブームは術後のレシピエントの死亡率があまりに高いため、次第に関心が薄れ、米国でも世界でも採用を控えるようになったのだ。
最大のリスクは、移植した臓器に対する免疫対抗によるもので、移植そのものが成功したとしても、多くの患者が新たな臓器への拒絶反応で命を落としてしまうのが原因であった。
この間、スタンフォード大学のシャムエイ教授グループだけが、逆風の中で根気よく研究と実践を続ける。
1980年代に活気的な免疫抑制剤が開発されるまでの10年以上は、スタンフォードが唯一無二の存在であったが、この間孤立無縁の中で継続はその後に与えた影響は大きい。
免疫抑制剤であるシクロスポリンが登場し、それを定着させることで成績が良好になったため再び臓器移植は世界で急速に進歩することになる。
1990年代半ばには世界で年間4400例まで増加している。その後も、1年間に4500-5000例が施行されているが、それに関わる多くの医師はスタンフォード大学のシャムエイ氏の影響を受けていると言わている。
苛烈なる正さ

「移植医たち」(著;谷村志穂)では、シャムエイ氏をモデルにした登場人物が重要な役割を果たすのだが、移植手術にかける情熱と、タフでクールな人物で描かれている。
10時間にも及ぶ手術のあとに、日本から留学した主人公である研修医を呼び出し、チャーターしたジェット機で、新たなドナーのいる病院に向かう。
到着するや否や、見事な手捌きで、ドナーの胸を開き、心臓を取り出す場面が描かれている。
胸の中の心臓はイキイキとしており、その生命の証を鮮やかに取り出す場面、主人公の研修医はドナーからの心臓摘出に初めて立ち会ったのだが、大きな衝撃を受ける。目の前で怒った殺人に、この道に進んだことに動揺し、後悔する。
取り出した心臓を手に、再びジエット機でレシピエントの待つ病院に戻り、手術室に消えていく姿に主人公は畏怖するのだ。
もちろん、これはフィクションなのだが、このくらいの割り切りがなければ移植医など務まらないのは確かだろう。
やがて、主人公は心臓移植のマイスターとなっていくのだ。
事実、スタンフォードのシャムエイのチームは1,000人以上の移植を行い、命を繋いでいる。繋がる命の影にはそれと同じだけのつなげる命があるということである
この小説の中では、札幌医科大学の和田氏をモデルとした人物も登場するが、「和田事件」の真実は語られない。
物語では、事件のあと、アメリカに逃れ医者を引退するが、その娘が医者となりシャムエイの門下生として移植技術を学び、日本に帰り父以来初めて、日本で心臓移植を行うといったストーリーになっている。
もちろん、事実は違う、
臓器移植の是非はともかく、繋がる可能性のある命と繋ぐ命があり、決断をしたならそれを粛々と行う移植医たちの存在があることは間違いない。
一つ言えることは、ドナーになるもの、レシピエントになるのも、その決断をするのは移植医ではなく自分であるべきだということだ。
当たり前のことではあるが、医師の視点で語られる物語から感じたのはそういうことだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
