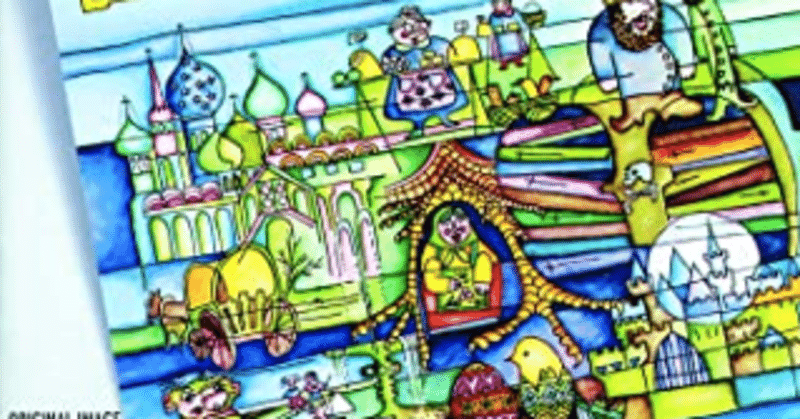
モーリス・ラベル:ボレロ
モーリス・ラヴェル作曲 ボレロ
演奏:WDR交響楽団
指揮:アロンドラ・デ・ラ・パーラ 演奏時間:14分53秒
収録:2022年1月27日 at ケルナー・フィルハーモニー
最初に、Wikipediaより、モーリス・ラベルという人のご紹介文を。
モーリス・ラヴェル(J. Maurice Ravel 1875年3月-1937年12月)は、
フランスの作曲家。バスク系フランス人。
「スペイン狂詩曲」やバレエ音楽「ダフニスとクロエ」・「ボレロ」の作曲、ムソルグスキー作曲の「展覧会の絵」のオーケストレーションで知られます。
オーケストレーションの天才、管弦楽の魔術師と言われる卓越した管弦楽法、スイスの時計職人と評された、精緻な書法、が特徴です。
入念な「完璧さへの腐心」と同時に「人間的豊かさを併せ持った表現力」は、知性のゲームを甚く刺激してくれると同時に、心の奥深く隠された領域に、沁み入ります。
さて、そーんなことは暫らくそこに置いといて、この曲の真ん中に立って
聴いてみましょう!
ご案内するのは、メキシコの指揮者アロンドラ・デ・ラ・パーラさん指揮によるWDR交響楽団による演奏です。
ラベルの曲らしいラテンの香りを存分にお楽しみいただきたいものです。
さて、この「ボレロ」という曲の解説文を書くのはとても難しいのです。そこで、
「OEKfan オーケストラ・アンサンブル金沢を応援するページ」様の中の「ラベルのボレロ」という解説文が、とても判り易く、且つ素晴らしい名文 ですので、今回は、それをご紹介いたしましょう(^▽^)/。
このような名解説をネットで探し出して読みこんでいくのも、クラシック
音楽の楽しみの一つ。
是非、この「ボレロ」の不思議な世界を楽しんでいただきたく思います。
では、ここから****************
20世紀前半以降のクラシック音楽は、一種の混迷の時代の中にあります。
バロック~古典派~ロマン派と流れて来た伝統的な西洋の音楽が行き着く所まで行き着き、どうやったら新しい機軸を打ち出せるだろう、というアイデア合戦のような様相を呈しています。
難解なものほど価値があるといった風潮も出てきたりもしたのですが、そういう風潮をあざ笑うかのような名曲がこの「ボレロ」です。
非常に斬新なアイデアを持った作品でありながら,全く難解な所のない作品で、「破綻無く演奏すれば必ず盛り上がる曲(ただしプロでないとなかなか破綻なく演奏できない曲でしょう)」となっています。
この斬新なアイデアというのは、「コロンブスの卵」的な発想です。
「リズムは一定、音量は漸増(クレッシェンド)、音色は多彩に変化させる」というのがこの曲の基本コンセプト。
西洋音楽の根本である「主題の展開」というものを使わずに、ひたすら繰り返すだけで盛り上げるという構造は、原始的な音楽に先祖帰りしたような所もあり、音楽の根源的迫力を感じさせてくれる曲です。
このボレロは、もともとはバレエ音楽で、中でいちばん有名なものはモーリス・ベジャールによる振り付けで、クロード・ルルーシュ監督の映画「愛と哀しみのボレロ」などにも採用されています。
スペインの民族舞踏「ボレロ」の基本リズム、「タンタタタ,タンタタタ,タンタン | タンタタタ,タンタタタ,タタタタタタ 」という2小節からなる3拍子の基本リズムが、小太鼓により、最初から最後まで、なんと169回も繰り返されます。
ただし、曲の最後の2小節だけはこのリズムが崩れます(ここが、ミソ!)
この主題が、まるで「オーケストラの楽器のデモンストレーション」のように、ソロ楽器を次々と変えて、繰り返し演奏されます。
いちばん最初、フルートで演奏された後、クラリネット・ファゴットと木管楽器を主体に主題が受け渡されていき、その後、オーボエ・ダモーレ、サクソフォーンなど古い楽器やら、金管楽器やら、様々な楽器が合奏に参加。
途中まで、合いの手を入れるようにピツィカートだけで参加していた 弦楽器は、中盤から”待ってました”という感じで、ゴージャスに加わり、全楽器による演奏となって、堂々と大きなウネリのように進みます。
そして、終結部。半音階的に下降する音型と各種打楽器の荒々しい音とが絡み合い、いままで積み上げてきたものが一気に崩れ落ちるかように、曲が終わるのです。
*************************ここまで。
繰り返しますね。
「この斬新な「コロンブスの卵」的な発想、「リズムは一定,音量は漸増(クレッシェンド),音色は多彩に変化させる」というのがこの曲の基本コンセプトです。」
「西洋音楽の根本である「主題の展開」というものを使わずに、ひたすら繰り返すだけで盛り上げるという構造は、原始的な音楽に先祖帰りしたような所もあります。」
「難解なものほど価値があるといった風潮も出てきたりもしたのですが、
そういう風潮をあざ笑うかのように、終結部では各種打楽器の荒々しい音とが絡み合い、いままで積み上げてきたものが一気に崩れ落ちるかように、曲が終わります。」
「音楽の根源的迫力を感じさせてくれる曲です。そういう点で、ストラヴィンスキーの「春の祭典」と並ぶ20世紀を代表する音楽と言えます。」
そして、最後の瞬間、大音量のドラの音が、ムソルグスキー「展覧会の絵」の終曲「キエフの大門」を彷彿とさせるように鳴り渡るのを、お聴き逃しのございませんように😎😎
如何でしょう!? お楽しみ頂けたら幸甚です(o^―^o)ニコ 😄😄😄
観客の、止むことのない拍手喝采が素晴らしい!
スピンも、この中に居たかった!と激しく思うのです(o^―^o)ニコ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
