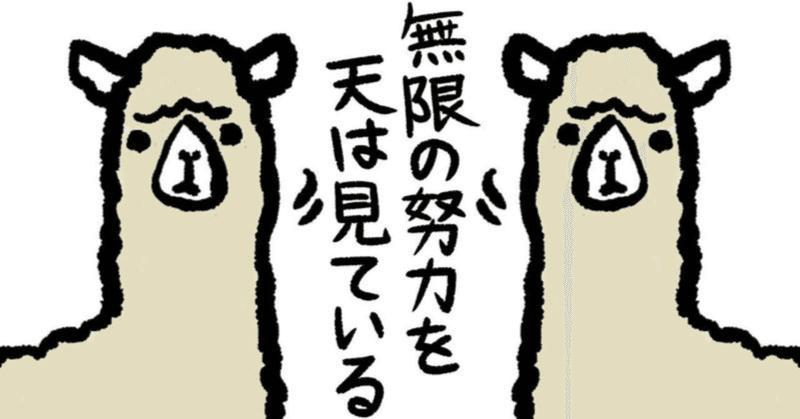
親がこどもにできること
よくよく考えると親が子どものためにできる事ってそんなに無いな、と思う今日この頃。
唐突ですが、子どもの権利条約をご存知でしょうか?
国際条例として発効されたのが1990年。
日本も1994年に条約に批准し発効され、
現在196の国と地域で締約されています。
対象は18歳未満の全てのひと。
(婚姻などで成人と認められる場合を除く)
子どもの権利条約で定める『子どもの権利』とは大きく分けて4つ。
・生きる権利
・育つ権利
・守られる権利
・参加する権利
生きる権利とは…
衣食住足りて医療が受けられる権利のこと
育つ権利とは…
勉強したり遊んだり、もって生まれた能力を充分に伸ばしながら成長できる権利のこと
守られる権利とは…
紛争に巻き込まれず保護され、暴力や搾取、危険な労働などから守られる権利のこと
参加する権利とは…
自由に意見したり、団体を作ったりできる権利のこと
親の私に紛争は防げないし、教育システムは国によってもう出来上がってる。
育つ権利で親に出来ることは
こどもが興味あるものに触れさせる機会を作るところまで。
あとは精々、習い事や塾の運転手と進学費用を稼ぐことくらいでしょうか。
ごはんを作って洗濯をして仕事に行く
当たり前の日常を繰り返して
気付けば娘も高校生。
持って生まれた能力を充分に伸ばすのも
こども本人の主体性がなければ、きっとうまくいかない。
主体性を持って取り組んだことの成功体験が自信につながり、次の一歩に繋がるから。
こども同士の遊びの計画や、
こどもがやりたいと言った習い事の教室や塾選びのシチュエーションでこどもの意見を尊重すること等…
『参加する権利』だけが親のさじ加減を試される『こどものために親ができること』なのかもしれません。
そして「自由に意見する」権利があっても、こどもの意見全てにOKを出せるわけではありません。幼い頃は尚更に。
こどもの守られる権利により
こどもの安全が最優先で危ないことはダメ
こどもの学ぶ権利により
宿題をやらずに遊びに行っちゃダメ
こどもの生きる権利により
予防接種のワクチン注射は受けましょうと
こどもの権利条約なのに義務教育中は
こどもの権利を制限したり、強制する事が
多くなってしまうジレンマ。
守られるとはそういう事かもしれない。
成長につれて自分で出来ることが増え、行動範囲が徐々に広がり
高校生になれば自分ルールを持ち、経済面を除いての身辺自立はほぼ完了している。
親の許可が必要な進学の手続き等は煩わしく思う事も多かったのではないかと思うけれど
新しい世界はまだ始まったばかり。
好奇心を失わず、興味あることを探して
少しずつ成功体験を積み重ねながら
『育つ権利』を存分に行使していただきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
