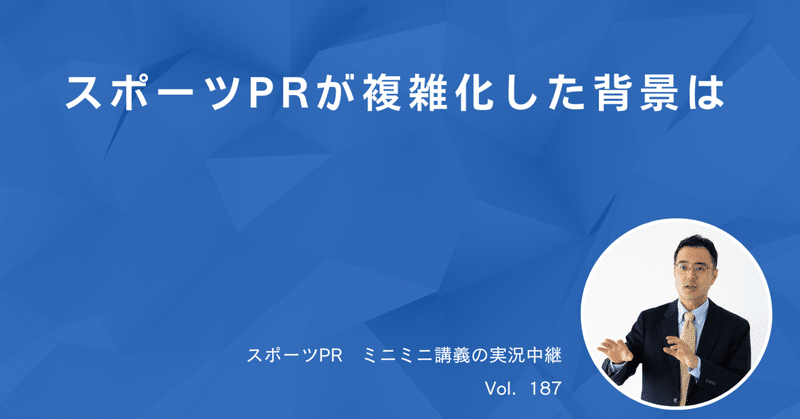
スポーツPRが複雑化した背景は
スポーツPRに大きな影響を及ぼすことの一つは、伝えられる内容の特性と範囲が時代を経て、変わってきたことです。
昔の新聞のスポーツ記事を見ると、今とは全然違います。
1980年代の新聞の縮刷版を図書館でチェックしたことがあります。今よりも1行あたりの字数が多いですし、行数も多いですが、その量で何が書かれているのかと言うと、競技中の選手の描写です。泳ぎ方、走り方、打ち方などに凝った表現が使われていますし、また、その時の表情や仕草の表現も非常に細かいです。
また、記者の目から見た評価にも行数を割いています。何が良かったから勝てたのかとか、強いはずの方が負けた場合は、その敗因を書いています。今だと、元選手や指導者の評論家にお願いしているような内容です。もう一つ付け加えると、選手当人のコメントが今よりもはるかに少ないです。
つまり、記者の現場を見る目、競技の理解力は今よりも高いレベルが求められていました。
しかし、テレビの影響力が増してくると、表情やプレーの様子は、それで見ればいいものになりました。中継には解説者がついています。即時性と描写力と評価はテレビに譲り、新聞はその翌朝に改めて読まれるものなので、描写にボリュームを割くことは読者のニーズに応えていません。それよりも、パッと見てはわからなかったことを掘り下げていることが大事になってきます。
そこで人間性の部分を取材して、ストーリーに取り入れていくことが主流になってきました。今、皆さんがマスメディアを見て楽しんでいるのは、ほとんどこのスタイルのコンテンツです。
大きなスポーツイベントの時には、新聞は、いわゆるヒューマンストーリーをどんと大きく載せるというのが、1990年代ぐらいから続いています。
またSNSが発達して、選手も取材に答えるだけではなく、自分のメディアで言いたいことを言ったり、写真載せたりすることが当たり前になりました。
メディアで働く人ももちろん、それをチェックしています。その前提で、さらに面白いものを出すには、本人の周りにいる人の取材をして、それを伝えることがそれまで以上に大事になってきます。本人が明かさないことだったり、近くにいる人だからこそ見えたことや感じたことだったり、思いがけず耳にした本音などを取材して伝えることが増えました。
また、今の時代は、その面白い話を、どこが早く出すのかという競争もハードになりました。即、SNSやネットにアップするのが当たり前になりました。また、オンライン上の情報は、放送時間やページ数のような上限はないので、情報量は指数関数的に増えています。その中で1本の記事や映像コンテンツに注目を集めることは、難しくなる一方です。
このように、伝えることの特性や取り上げられる範囲が変わってきたという歴史があります。
発信する側はマスメディアを通じて出していくことは何かを決め、自分たちのSNSで出していくのは、また別のこととして決める。そんな方針や戦略が必須になりました。組織のみならず、個人レベルでもその巧拙が問われています。スポーツPRはより複雑になり、情報を発信する側も大変になり、メディア関係者の仕事も変わるのは、避けられない変化だったのでしょう。
事例紹介など実践ノウハウを知りたい人は、月2回配信の無料メルマガにご登録を。
よろしければ、サポートをお願いします。新しいことを学んで、ここにまた書くために使わせていただきます。
