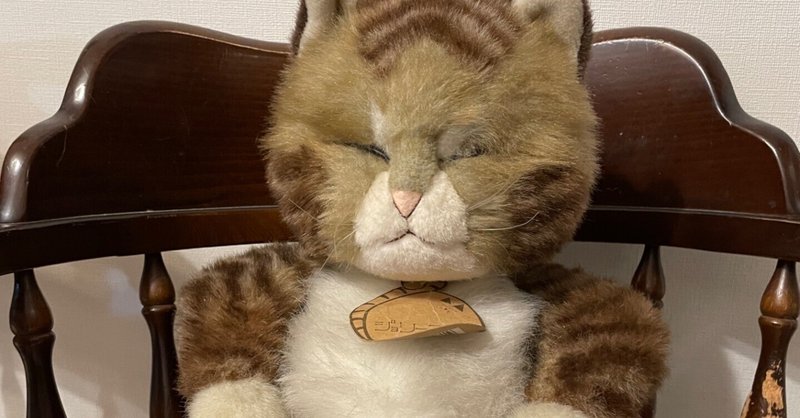
580在外投票憲法判断へ 投票権巡り最高裁弁論
裁判官の任免に国民(有権者)が関与するのが民主主義に合致するのか、それとも反するのか。これが今回の問題点。
海外在住の国民も国会議員の選挙に参加するが、最高裁裁判官の国民審査(憲法79条)では除外されている。これは憲法違反ではないかということで、裁判になっているわけだ。経緯を日経新聞記事でたどってみよう。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE123V50S2A410C2000000/
2019年5月の一審・東京地裁判決では、国民審査を「司法に対する民主的統制の方法として、憲法上認められた重要な権利」と位置づけ、海外の日本人の審査権の行使を認めないのは違憲と判断した。その上で国に原告1人あたり5千円の損害賠償を命じた。
2020年6月の二審・東京高裁判決は国の賠償責任は認めなかったものの、違憲との判断は維持。次回の審査時、海外在住を理由として投票ができなければ違法に当たるとした。
下級審の判断は、国民審査は民主主義に基づく国民の権利であるから、海外居住国民を除外することは許されないということだ。
三審制の最終結論を求めて、舞台が最高裁に移っている。4月20日に最終弁論が行われて審理は終結し、後は最高裁の判断を待つことになる。さてどういう結論になるか。

わが国は民主主義社会。投票の権利は最重要の要素の一つ。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(15条)。
ここでの国民とは、日本国籍を持つ人だから、現在居住地は問われない。
次に選挙で選任すべき公務員の範囲。裁判官についいては「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し」、「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」(79条)との規定がある。
原告側は、在外国民にも国民審査参加権があると主張している。
対する国の主張は、国民が選任した国会議員が総理大臣を選任し、そうして作られた内閣が最高裁裁判官を任命する。間接的が重なるけれど、裁判官を国民が選定することになっている。これで国民主権は確保されている。国民審査による罷免権は、例外的、補完的なものに過ぎないのであり、在外者が除外されていても枝葉末節的なことである。
これに関連して思うのは、裁判官国民審査の方法だ。罷免を可とする者に×印をしなさいと用紙に書かれている。罷免を求めない者は信任しているとみなすというのだ。でもよく考えれば、「罷免」「信任」のほかに「棄権」があるはずだ。正しくは棄権者を除いて、「罷免賛成票」と「罷免反対票」の多寡で決定するべきだろう。
議員の選任投票と対比すればわかりやすい。有権者には、「A候補の選任に賛成」と「B候補の選任に賛成」のほかに、「A候補、B候補いずれの選任にも反対」があり、その有権者は投票所に行かない(棄権)か、行って無記入で投票(白票)することになる。集計ではこれら棄権や白票はなかったものとして扱われ、A候補支持票とB候補支持票の多寡によって、当選者が決定される。
これと同じ論理に立つときは、裁判官国民審査においても、無投票(棄権や白票)を認めるべきであろう。方法は簡単で、まず衆議院議員選定投票と国民審査投票の入り口を別にして、一方だけの投票を可能にすることだ。次に用紙には対象裁判官ごとに「信任」と「罷免」を印刷しておき、そのいずれかに印を入れることにして、熟慮の結果としての白票を可能にする。
裁判は専門的要素があるが、だからといって一般国民には関知させないというのは間違っている。外国での陪審制はそうした考えの反映であろう。わが国でも一部とはいえ一般有権者による裁判員が制度化された。そうした傾向を裁判官の任免に適用するのは当然ではないのか。
理念と信念、それに正しい憲法観をもって仕事をしている裁判官が国民審査で罷免されるわけがない。むしろ政治的に偏った任命が行われないよう、国民による防波堤になる。裁判官の国民審査の方法についての見直し議論が望まれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
