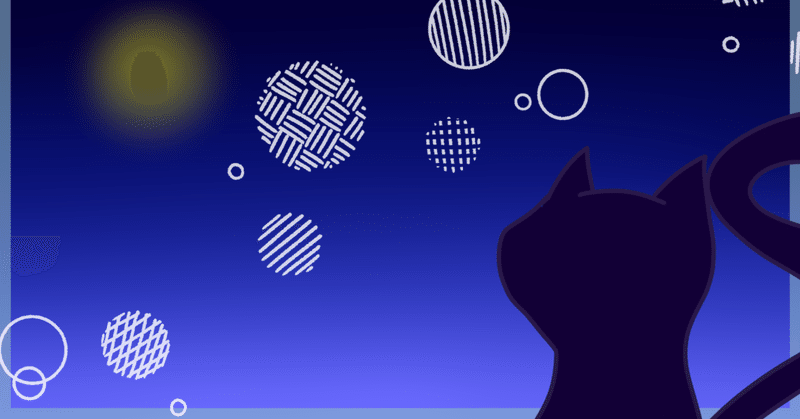
【おはなし】夜の町
この町はある時から、ずっと夜だ。
どうして夜が続いているのか、理由を知る人はいない。きっと誰かが『朝が来なければいい』と強く思ったんじゃないかと、僕の飼い主さんは言った。そんな話があるだろうかと思ったけど、まぁたまにある事だという。人間の世界のことは、猫の僕にはよく分からない。
夜が終わらないのだから当たり前なのだけれど、町の中は塗りつぶされたみたいに真っ黒だ。道も広場も建物も、月と星の控えめな光が少しだけ照らしている。
夜にほとんどの人が出歩かないように、町の人たちはあまり外に出ない。多くの人は家の中で過ごし、多くの人は寝ている。たまに気晴らしに夜風に当たる者や、夜に仕事をする者がいるにはいるけど、基本的には広場も通りも裏道もしんとしていて、聞こえるのはときどき吹く風の音と、ミミズクの鳴き声と、僕たち猫の足音だけだ。猫達だけは怪しく動き回るものも多い。
こうもずっと町が暗いと、だんだん人びとの気持ちまで暗くなってくる。大人はため息が増え、子供たちは部屋でじっとしているので、夢も見なくなってしまった。町は湿っていてどんよりしている。
この長い夜を終わらせるために、やらなければいけない事と、そのための条件があると飼い主さんは言った。
やらなければいけないことは、朝のタネを育てて花を咲かせること。朝のタネが花を咲かせると、夜の揮発性が高まり夜が正常に終わるのだという。
もうひとつの条件は、そのとき空が晴れていること。つまり、晴れた日に朝のタネの花が咲くと、夜が明けるということだ。
実は晴れた空というのを僕はあまり見たことがない。僕が生まれてすぐに夜が始まったからだ。飼い主さんが言うことには、ほんとうに晴れた日というのは、空はどこまでも高くて、空気は澄んで、見えるものすべての輪郭が濃くなるのだという。そんな日は特別で、人の心は例外なくうきうきするのだと飼い主さんは言った。猫の心はどうなんだろうなぁと、僕は思った。
さて、ミミズクがその日に最初に鳴くころに、飼い主さんは家を抜け出して町に出て行く。退屈な僕も、それについて行く。
町の端のほうの誰も行かないような裏道の先、そのさらに端のほうのごみ捨て場に、小さな花壇がある。花壇にはずっと前からひとつ芽が生えていた。
飼い主さんはここに来ると近くの木箱を椅子代わりにして腰かけ、しばらくぼうっとする。そして持ってきたじょうろで花壇に水をやると、そのあと本を読みだす。
ここはいい具合に月の光が差し込んでいてほんのり明るいので、手元はかろうじて見ることができる。暗い夜に本を読むのに、このゴミ捨て場はちょうどいい場所なのだという。
本を開くと飼い主さんは長い。僕は隣で丸くなって眠り、飽きたらそのまま帰る。いつもの流れはだいたいこうだけど、今日は違った。
いつも飼い主さんが座っている木箱の上にすでに今日は人影があった。年は同じくらいだろうか。飼い主さんはおそるおそる近づいていく。僕もそれに続く。
「そ、そこ」
飼い主さんが言った。
「き、気をつけて」
足元を指さしながらそう言った。ささやかな囲いがしてあるだけの花壇は、知らずに歩けば気づかず踏みつぶされてしまうだろう。
「ああ、ごめんよ」
小さな声でそいつが言った。深く帽子をかぶっていて顔がよく見えない。悪いやつではないようなので、飼い主さんが気にせずに花壇に水をやる。
「それは、もしかして朝のタネを育ててる?」
水をやり終わったあとにそいつがたずねてきた。飼い主さんはこくりとうなずいた。
「てことは、夜を終わらせるつもりかい?」
飼い主さんがまたうなずく。
「そっか」
低くて掠れた声だった。
朝のタネを飼い主さんが育て始めたのは、少し前からだ。みんなのためにそうしなければいけない気がするからと、彼女はそう言った。
夜を終わらせることは、この町のみんなが望んでることだと僕は思ってた。朝が来れば、みんな清々しい気持ちに違いないのだと。けどそいつの反応は、なんとなく思ってたものじゃなかった。
「驚かないでほしいんだけど」
そいつが頭へ手を置いた。そのままゆっくりと帽子をつかみ、外す。何をするのだろうと思った。月明かりに照らされてそいつの顔が明らかになる。言葉は出さなかったけど、飼い主さんが息をのむのがわかった。人間の容姿のことはよく分からないけれど、その姿は何というか、ほかの人間とは異なっていてかなり、いびつだった。
「僕には、居場所がないんだ」
そいつの裂けて歪んだ口が空気を震わせた。目玉は窪んでいて、左右で大きさが違っていた。
「この姿のせいで、昼間は誰も僕のことを気味悪がって近づいてこない。ずっと、こそこそ隠れて生きてきた」
鼻は曲がり、呼吸をするたびに煩わしい音が漏れる。そいつは深呼吸するみたいに続けて言った。
「でもこの暗闇の中では僕の顔は隠れて見えないだろ。堂々と外の空気が吸えるんだ。夜の中なら、町の広場を走り回ることもできる。だから、その」
そいつが帽子を被り直した。また、顔が見えなくなる。
「朝のタネを育てるのを、やめてほしいんだ」
この長い夜が明けるのが、逆に困る人もいるのだと初めて分かった。すがるようなそいつの声は暗い裏道に静かに吸い込まれていった。月の明かりが、うすく雲に隠れた。
僕は飼い主さんを見上げた。飼い主さんのずっと後ろのほうには夜空があって、今ではもう見慣れた星の粒が光っていた。
「あ、あなたはここに住んでるの?」
すこしの沈黙のあと、飼い主さんがたずねた。今までは埋もれていて気づかなかったけど、ごみ捨て場の横に小さな手作りの屋根がある。
「そうだよ」
誰も知らない町の端で、ごみと一緒に暮らす人間がいたなんて知らなかった。
「こ、ここはいい場所だよね」
「うん」
「つ、月の光がよく照らされるし、そ、空もよく見える。あ、朝のタネはこういう場所じゃないと、そ、育たないの」
飼い主さんが絞り出すような声で言った。そいつは俯きながら、帽子のつばを握りしめていた。
「それより、朝のタネを」
「わ、私の言葉は、ひ、人に、と、届かないことが多いのね」
そいつの言葉をさえぎって、飼い主さんがつぶやいた。
「き、きっと私の中に言葉が少ないから、だ、だからうまく、で、出てこないんだと思う」
彼女が人の話を止めて自分の話をするなんて、はじめてのことだった。
僕の飼い主さんは、他人と繋がるのがあまり上手じゃない。町で買い物をする時も、遊んでいる時も、近所で世間話をする時も、悪口を言われて笑われいても、ひどい事をされて傷ついても、にこにこして笑っているだけ。みんながなるべく不快にならないように、みんなに迷惑をかけないように、ただ佇んでいるだけだった。
「それなら君だって、夜のままのほうがいいじゃないか。他人と関わるのはつらいことも多いって知ってるだろう」
「わ、私だって、そ、そのほうが心地いいなって、お、思うこともあるよ」
「じゃあ、どうして朝のタネなんか」
「だ、だって、よ、夜の次は朝が来るのがほんとうのかたちでしょ。そ、そして昼間になって、ま、また次の夜が来る。い、いつまでも暗いところに、か、隠れてはいられないわ」
「君はどうなんだよ。ほんとうってなに?君自身は朝が来た時、ほんとうに笑えるのかい?」
そいつが泣きだしそうな声で言った。飼い主さんは困った様子でその窪んだ目玉を見つめ返す。
飼い主さんの中でうまれた言葉は、ほとんどの場合口から出てくる事はない。僕達が生理的に毛玉を吐き出すのと同じようにはいかない。飼い主さんがつくる言葉はきっと細くて薄くて、口の中で音もなく割れちゃうんだと、僕は思ってる。
だから飼い主さんは、ずっと孤独だった。
「ど、どんなに他人がこわくても、こ、言葉が届かなくても、わ、私にはこの子がいるから」
僕のことだ。なんだかくすぐったくて、僕は前足をなめる。
僕は知ってる。飼い主さんは、本当はきれいな言葉をたくさん持ってるのを。
空が青い日はいつもより気持ちがいい。きれいな形の葉っぱがあったこと。新しい靴で出かけるとうきうきする。同じ形の草はひとつもない。読んでいる本の感想。猫のお腹の毛はお日様と同じにおいがする。
そんなたくさんの言葉を少しずつ無理やり飲み下して、誰かに届けるのを諦めかけていたところにこの長い夜が始まったのだ。
「そ、それに、あ、明るい方が、み、みんな楽しそう。だ、だから私は、あ、朝のタネを育てるのを、や、やめないよ」
それが飼い主さんの答えだった。きっと飼い主さんはこのあとも朝のタネに水をやり続けるんだろう。自分を知らないこの町の人たちのために、朝のタネの花が咲くまでずっと。
そいつは花壇に目をやり、そのあと空を見上げた。帽子をかぶり直して、静かに息を吸う。
「そっか」
飼い主さんがその場を立ち去ろうとする。背中を向けて名残惜しそうに。僕はそれについていく。
「また居心地の悪い明日に、取り残されなくちゃいけないな」
そいつが自分の足元に視線を落としてつぶやいた。月の光にさらされた朝のタネの芽は、簡単にひっこぬけそうなほど小さかった。
本当に朝が来るのがいやなら、無理やりにでも芽を摘んでしまえばいいはずだった。なにも言わずに、さっさと花壇を踏みつけてしまえばよかったのに、なぜだかそいつはそうはしなかった。
「僕はどうしたらいいんだろう」
背中でそいつの声が聞こえた。夜の静けさが、その震えをいっそう際立たせた。
きっとそいつは少しずつ心をすり減らしていたのだと思う。その姿のせいで、好奇心や軽蔑や嫌悪感に晒されていたんだろう。そして悲しみを感じる気持ちさえなくなってきた頃に、この夜が来た。すこし、気の毒だった。『朝が来なければいい』と強く思ったのは、もしかしたらこいつなのかもしれない。
それでも人を怖がらせないように、町の端っこでありあわせの居場所を作って住むそいつは、ひどく優しくて臆病で小心者なのだと思う。
そういう人を、僕はもうひとり知っている。
飼い主さんが立ち止まり振り返った。僕は驚いて飛びのく。どうしたのかと思ったら、ばたばたとそいつの方にかけよっていく。
「こ、これ、か、かしてあげる」
飼い主さんが持ってきた本を差し出した。
「そ、それを読み終わったらまた、べ、別なのをかしてあげる。そ、それも読み終わったら、ま、また別なのを」
飼い主さんのこんな顔も、僕ははじめて見た。困ったような、それでもすごく嬉しそうな表情を。
「だ、だから、ま、またここに、き、来てもいいかな」
今まで飲み下していたものが、飼い主さんの内側からはっきりと形になって押し出されていく。今飼い主さんが話しかけているのは、そいつにだけじゃないのかもしれなかった。
「なんで、そんなこと」
そいつが驚いた顔をみせた。
「わ、私たちは、よ、よく似てるんだと思う」
飼い主さんが笑った。僕も二人のそばにかけよる。さわやかな夜風がふいて、月があらわれた。
飼い主さんとそいつが並んで空を見上げたので、その横で僕は前足をたたんでまどろむ。
目を閉じる。まぶたが視界を暗くする前に、朝のタネの芽が水をはじいて揺れるのが見えた。
あと何日かしたら、きっと朝のタネは花を咲かせるだろう。
夜が蒸発していき、あたりは少しずつ明るくなる。日の光が差し込んで、あたたかくなる。その日はもしかしたら朝焼けかもしれない。気温、湿度、風などによって、曇っていて暗いまだら模様の空かもしれない。まぁそうだとしても、そうじゃなかったとしても、そこからきっと何でもない一日が始まるだろう。そのあとは自由だ。明るい場所を見つけて、しっぽの毛を整えながら丸くなって眠るかもしれないし、小さな虫を追いかけまわすかもしれない。日が暮れて、夜が満ちたらご飯を食べて、のんびりしたあとにまた眠る。飼い主さんは本を読む。そんな明日を想像した。
あたりまえの、いつもの一日。
これから訪れる飼い主さんと、あとまぁそいつの一日に、ひとつでも多くのしあわせがあればいいなと僕は思う。
「あ、あなたは、ひ、ひとりじゃないよ」
そいつは月を見上げたままなにも言わなかった。
飼い主さんがひかえめに笑う声が聞こえた。
大きなあくびが出た。涙で視界がぼやけた。
晴れた夜になる予感がした。
おしまい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
